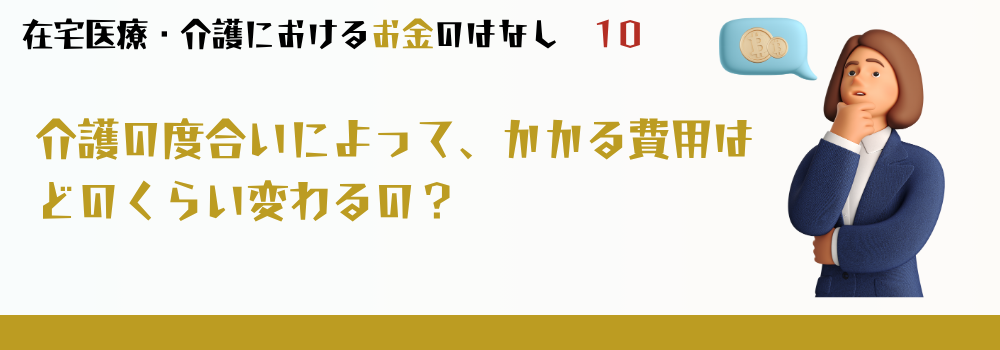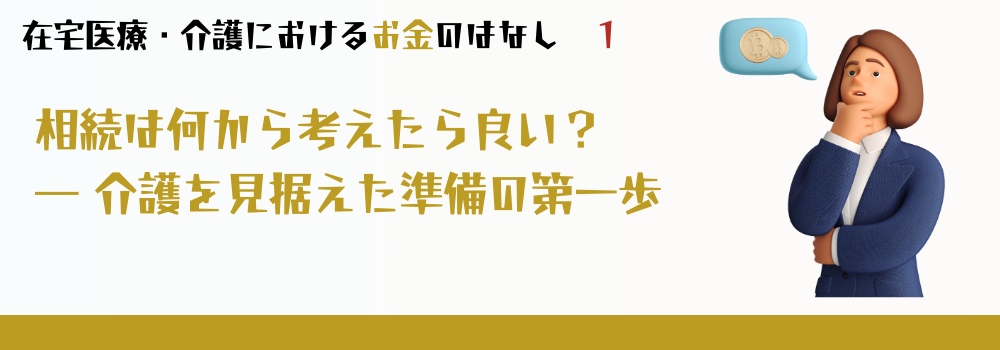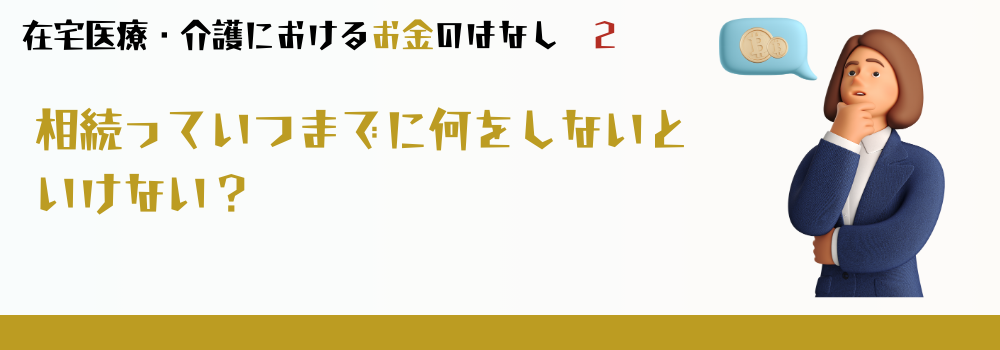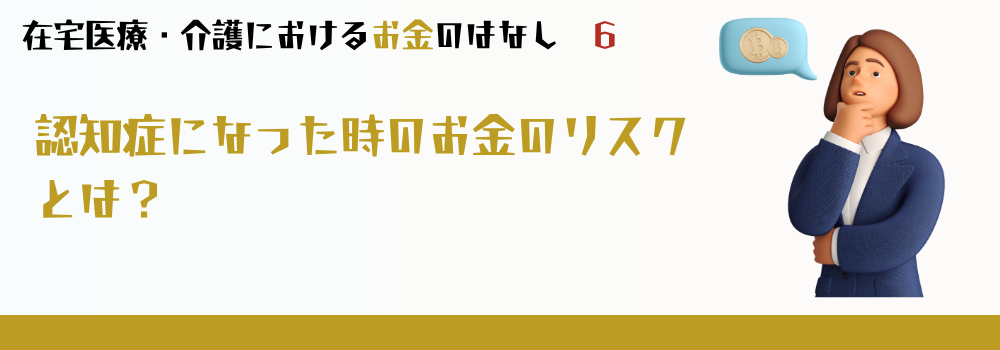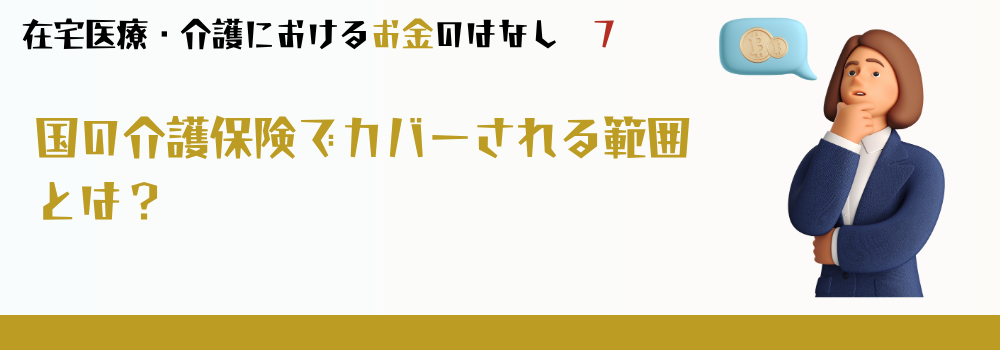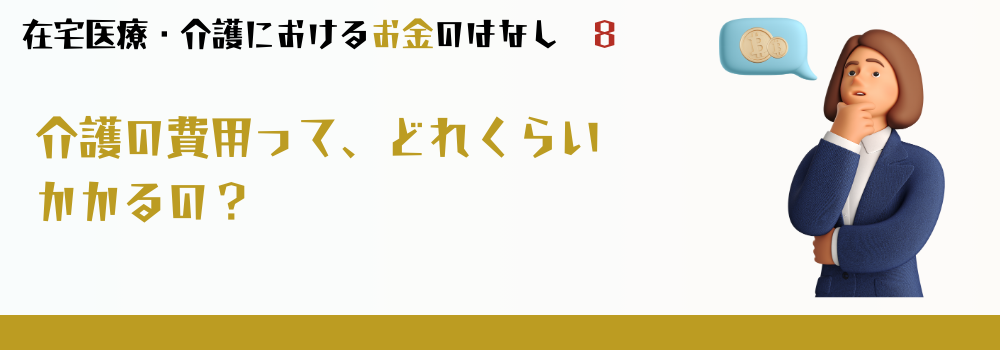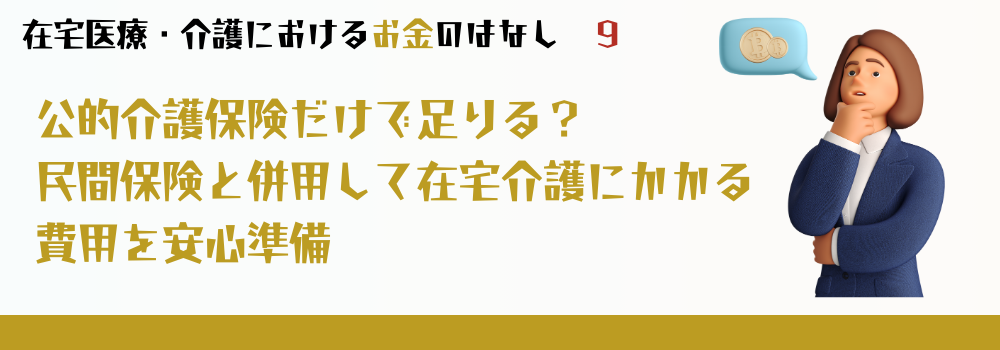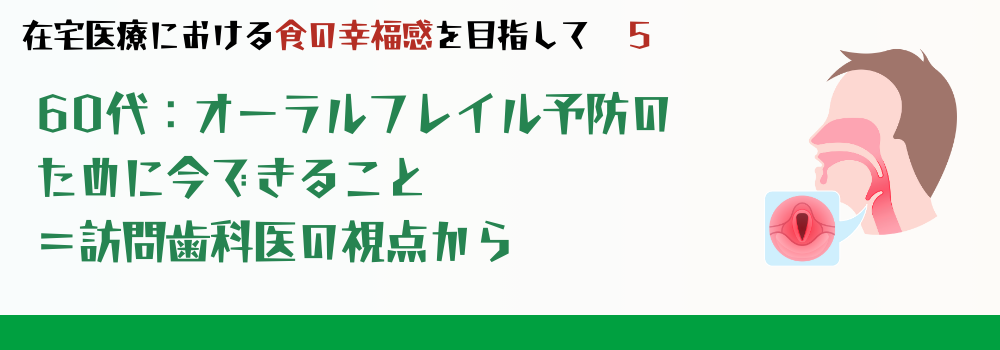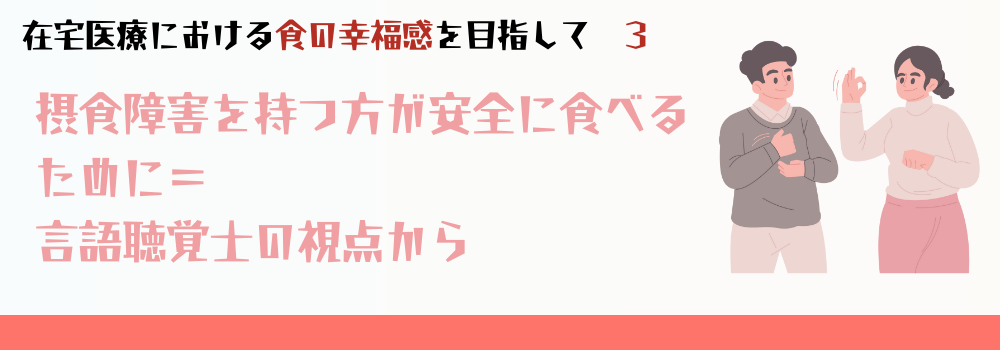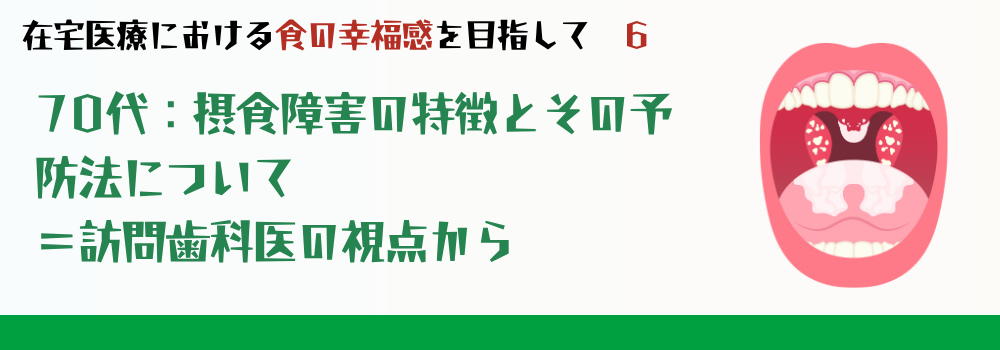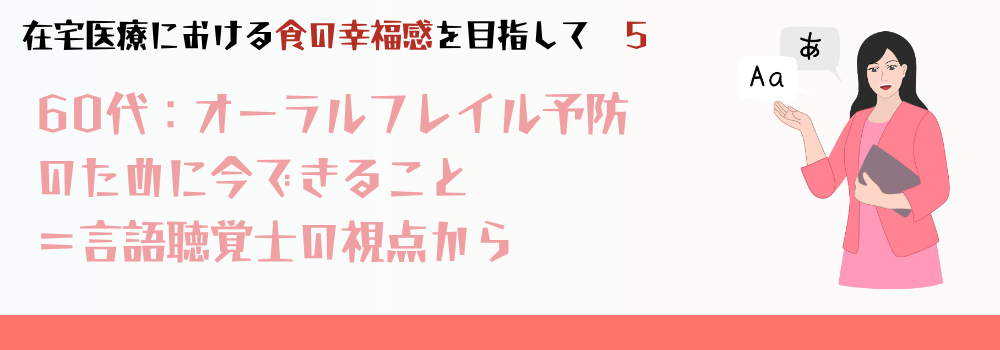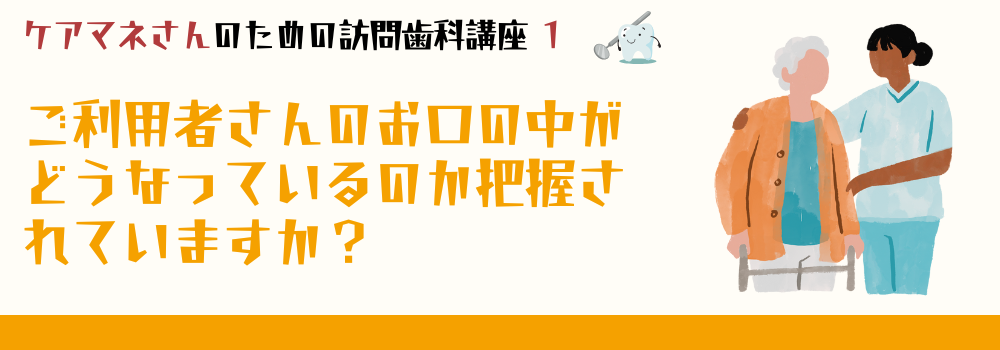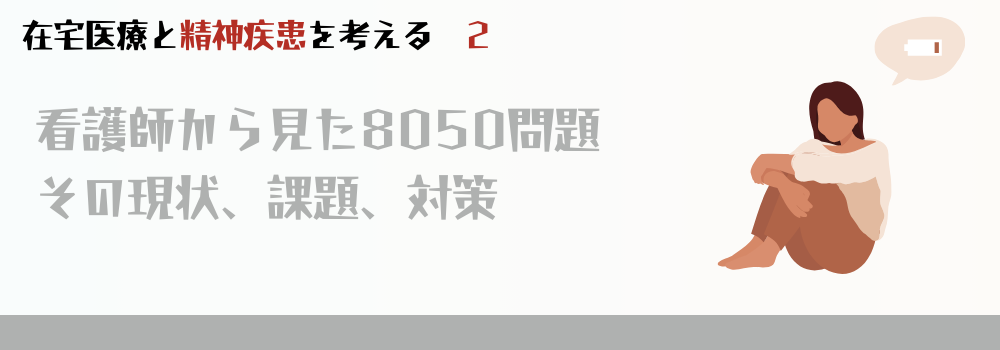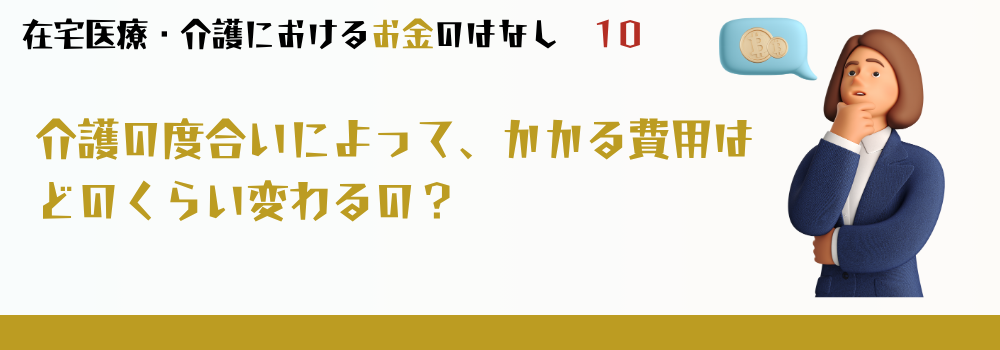
これまで、受ける介護サービスの違いによってどれくらい費用が掛かるかなどについてみてきましたが、実際、介護費用は“介護の度合い(要介護度)”によって大きく変わります。
軽い支援だけで済む場合もあれば、24時間の見守りや医療的なケアが必要になる場合もあります。
今回は、要介護度ごとにどのくらいの費用がかかるのか、在宅介護と施設介護の両面から見ていきましょう。
介護保険とは?制度の仕組みと自己負担の基本
まず知っておきたいのは、公的な介護保険を使うことで、介護にかかる費用の一部が公的に補助されるということです。
介護サービスを利用する際、かかる費用の1割〜3割を自己負担として支払います。
ただし、介護度に応じて「利用できる上限金額(支給限度額)」が決まっており、その範囲を超えると全額自己負担になります。
例えば、
・要支援1の上限は約5万円
・要支援2で約10万円
・要介護5では約36万円程度
この金額は「サービスを使える枠」を示しており、実際に支払うのはその1割〜3割です。つまり、要介護度が高くなるほど、利用できるサービスも増える一方で、自己負担も増えていく仕組みになっています。
介護度(要支援・要介護)ごとに“いくらかかる”? 在宅介護の費用目安
在宅介護は、自宅で暮らしながら必要な支援を受けるスタイルです。介護度が低い場合は比較的費用を抑えられますが、介護度が上がると利用回数や時間が増え、費用も膨らんでいきます。
【要支援1・2】
「自分のことはある程度できるけれど、少しサポートがほしい」という段階。
訪問介護で掃除や買い物の代行を頼んだり、デイサービスでリハビリや入浴支援を受けたりします。週1〜2回の利用で月に1〜3万円程度の自己負担が一般的です。この段階ではまだ外出もでき、介護予防としての側面が強いため、サービスの種類も軽めです。
ただし、交通の便が悪い地域では送迎費などが加わることもあり、地域差があります。
【要介護1・2】
一部の家事や身の回りのことが難しくなり、入浴・食事・排せつなどの介助が必要になる段階です。
週3〜4回の訪問介護やデイサービスを組み合わせるケースが多く、自己負担は月3万円〜6万円前後。
例えば、要介護2の人がデイサービスを週3回・訪問介護を週2回利用する場合、1割負担でも月5万円近くかかることもあります。また、この頃から福祉用具のレンタル(介護ベッド、手すり、歩行器など)が増え、月1,000〜2,000円程度が追加されることもあります。
【要介護3・4】
立ち上がりや歩行などに常時介助が必要になり、外出も難しくなってくる時期です。
介護サービスの利用頻度も増え、1日の大半をデイサービスやショートステイで過ごす方も少なくありません。
自己負担は月7万円〜10万円前後が目安。要介護3では限度額が約27万円、要介護4では約31万円と増え、サービスをフルに使うと1割負担でも3万円を超えます。
また、入浴介助や夜間の見守りなど、介護度が高くなるほど専門職の関わりが必要になり、その分費用が上がります。
介護する家族の負担も大きく、仕事との両立が難しくなってくる時期です。
【要介護5】
寝たきりや重度の認知症など、ほぼ24時間の介助が必要になる状態です。
訪問介護・訪問看護・リハビリ・夜間の見守りなど、複数のサービスを組み合わせるため、自己負担は月10万円を超えることもあります。さらに、介護用品(おむつ、食事介助用品、床ずれ防止マットなど)の購入費も毎月1〜2万円ほど発生します。
この段階では在宅での介護が限界に近づき、施設入居を検討する家庭も増えていきます。
「自宅で最期まで」と思っても、介護者の体力的・精神的負担は非常に大きく、費用と同じくらい現実的なサポート体制を整えることが重要です。
施設型ケア(老人ホームなど)では費用はどう変わる?種類別に見るいくらかかるか
要介護度が上がると、在宅介護が難しくなり、施設介護を選ぶ方も増えます。施設の種類によっても費用は大きく異なります。
【特別養護老人ホーム(特養)】
介護保険が使える公的施設で、費用は比較的抑えられています。自己負担は月8〜15万円程度。ただし入居には要介護3以上が必要で、人気が高く入居待ちが発生している地域もあります。
【介護付き有料老人ホーム】
24時間介護スタッフが常駐し、医療連携もしっかりしている民間施設です。手厚いサービスが受けられる一方で、費用は月15〜30万円前後。入居金が数百万円~数千万円かかる場合もあります。
【サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)】
自立に近い高齢者向けの住宅で、必要に応じて介護サービスを受けられます。家賃・共益費・生活支援サービス料などを合わせると、月10〜20万円前後が目安です。介護度が上がると、追加で外部の介護サービスを利用するため、結果的に費用が増える傾向にあります。
自己負担だけじゃない!介護度が上がると増える“見えないコスト”
介護度が上がると、単純に介護サービスの利用額が増えるだけでなく、それに付随する費用も増えていきます。
例えば、紙おむつや介護用消耗品、送迎時の交通費、食費、医療費など。これらは介護保険の対象外で、全額自己負担です。
また、在宅介護を続ける場合には、
・住宅の手すり設置(介護保険の住宅改修制度を利用しても上限20万円まで)
・冷暖房や光熱費の増加
・介護する家族が仕事をセーブすることによる収入減
といった「間接的なコスト」も発生します。
介護度が上がるほど、こうした支出が家計にじわじわと影響していきます。
介護保険を活用しても補えない分をどう備えるか?~いくらかかるかを知るからこそできること~
介護費用は、軽度のうちは月数万円で済む場合もありますが、重度になると年間100万円を超えることもあります。
そのため、「介護が始まってから考える」では遅く、早めに備えておくことが大切です。まずは、自分や家族が「どんな介護を望むのか」を整理しておきましょう。
在宅での生活を続けたいのか、あるいは施設でのケアを希望するのか。どちらを選ぶかによって、必要な金額も、準備の方法も大きく変わります。在宅介護を想定するなら、住宅改修や介護用品の購入資金を準備しておくこと。
また、介護度が上がったときに利用できる公的制度(高額介護サービス費制度、医療費控除、要介護者の税控除など)を確認しておくと安心です。施設介護を視野に入れるなら、入居金や月々の費用を踏まえて、「どのくらいの期間なら無理なく支払えるか」をシミュレーションしておくとよいでしょう。
まとめ:介護度×生活スタイルで変わる“いくらかかるか”を理解して備えよう
介護の費用は、要介護度によって大きく変わります。
軽度のうちは月1〜3万円ほどでも、重度になると月10万円を超えるケースも珍しくありません。また、在宅介護と施設介護では、年間で100万円以上の差が生まれることもあります。
大切なのは、「今の状態」だけでなく、「これからの変化」を見据えて準備しておくこと。介護は長期にわたることが多いため、無理なく続けられる仕組みを考えておくことが、本人と家族の安心につながります。
介護度が上がるほど、生活の支えが必要になります。その支えを“お金の準備”でも整えておくことが、「安心して介護を受ける」「安心して支える」ための第一歩です。
これまで10回にわたり、「相続」と「介護」をテーマに、人生の後半を安心して迎えるためのお金の知識や備え方をお届けしてきました。
相続では、「いつまでに」「何を」「どう進めるか」という手続きの流れから、財産の分け方、税金の考え方、生前贈与の活用まで。
介護では、「どんな施設やサービスがあるのか」「どのくらい費用がかかるのか」そして、「家族がどのように支え合えばよいのか」を見てきました。
どのテーマにも共通しているのは、“早めに知り、準備することで、選択肢を広げられる”ということ。相続も介護も、突然やってくる「いつか」に備えておくことが、自分や家族の「これから」を守る第一歩になります。
次回は、これまでの内容を一つにまとめ、「お金」と「心」の両面から“安心して最期まで暮らすための総まとめ”をお届けします。これまで読んできてくださった方にも、途中から読み始めた方にも、「今からできること」がきっと見つかる内容です。
どうぞお楽しみに。
知らなきゃ損する介護費用と自己負担のポイントQ&A
Q1. 介護保険を利用すると、自己負担はいくらになりますか?
A. 原則として、介護保険サービスの自己負担は1割から3割です。所得によって異なり、課税世帯では2割または3割負担となります。たとえば要介護3で月10万円分のサービスを受けた場合、1割負担なら1万円、3割負担なら3万円が自己負担となります。所得証明書や介護保険証に記載の負担割合を確認しましょう。
Q2. 介護度によって、かかる費用はどのくらい違いますか?
A. 要支援1〜要介護5までの区分で利用できるサービス量が異なります。たとえば在宅介護の場合、要介護1では月3万円前後の自己負担ですが、要介護5では10万円以上かかるケースもあります。重度になるほど必要なケアが増え、費用も上昇する傾向にあります。
Q3. 老人ホームに入ると、介護保険の自己負担以外にどんな費用がかかりますか?
A. 食費・居住費・管理費・光熱費などの実費が必要です。介護付き有料老人ホームでは、初期費用0〜数百万円、月額費用は15〜30万円が相場です。介護度が高い場合や個室を選ぶ場合はさらに高額になることもあります。
Q4. 自宅で介護する場合と老人ホームを利用する場合、どちらが費用を抑えられますか?
A. 一般的に在宅介護のほうが初期費用を抑えられますが、重度介護になると訪問介護・訪問看護などの回数が増え、月額が上昇します。老人ホームは一定額で生活支援を受けられるため、長期的な安心感を重視する方に選ばれています。
Q5. 介護費用が高くて支払いが難しい場合、利用できる公的支援はありますか?
A. 高額介護サービス費制度を活用できます。月の自己負担額が上限を超えた分は払い戻しが受けられます。また、自治体によっては独自の補助制度もあるため、地域包括支援センターへの相談がおすすめです。
関連リンク:
この記事を執筆したファイナンシャルプランナー

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。