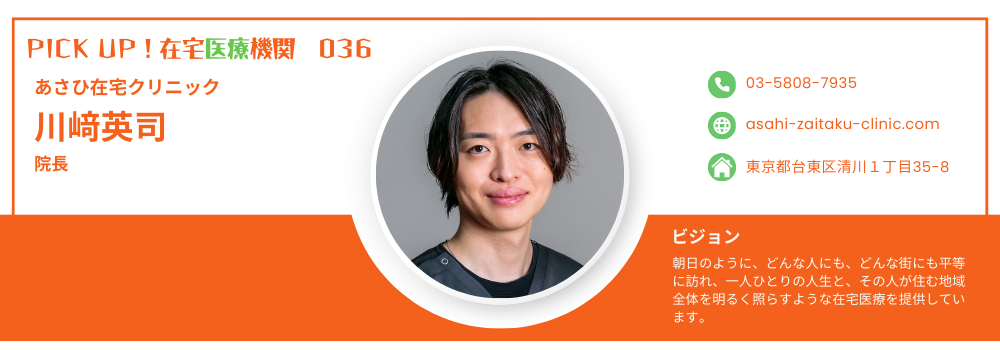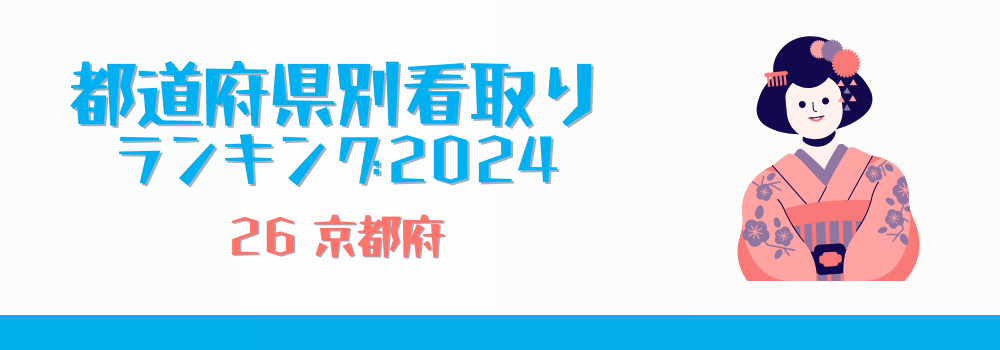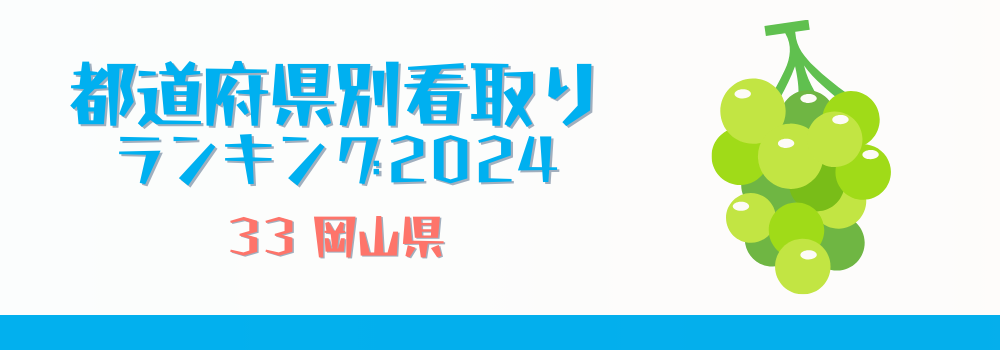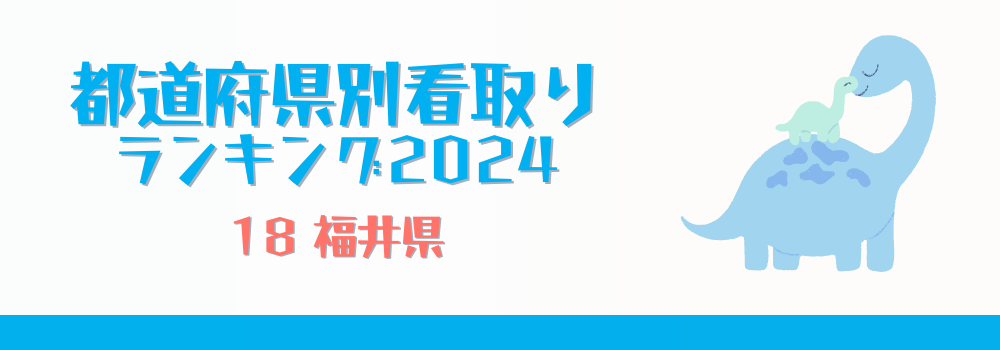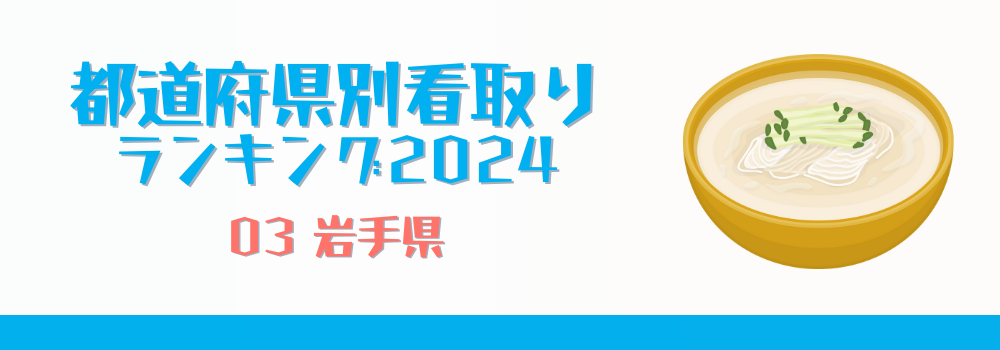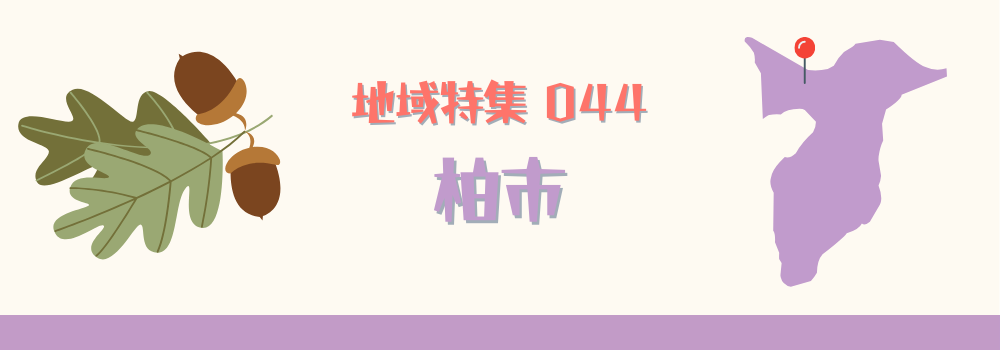静岡で在宅医療の仲間を募集|中之郷クリニックが語る医師採用と働きやすさ 最終更新日:2025/11/26

在宅医療専門の中之郷クリニック(静岡)では医師募集中。常勤医5名の24時間365日体制、緩和ケアに強い多職種連携とICT共有で質の高いチーム医療を実現。ゆとりある訪問スケジュールでワークライフバランス良好。外来併診可・見学歓迎—地域で患者と家族を支える仲間を求めています。

「人の最期」への違和感から始まった、理想の医療への道
— まず、齊藤さんが医療・介護の分野に関わるようになったきっかけからお聞かせください。
もともと人の心や成長に強い興味があり、「世界を知りたい」という思いもあってアメリカの大学に進学し、人間発達学を専攻しました。特に老年学に惹かれ、人が生涯を閉じていく過程について深く学びたいと考え、卒業後は高齢者の方々と密接に関われる介護施設で働くことを決めたのが、この道に進む第一歩です。

— 介護現場でのご経験を経て、クリニックの立ち上げという大きな挑戦に至ったのは、どのような経緯があったのでしょうか?
介護施設で働く中で、ある在宅医の先生と出会い、「静岡で初の在宅医療専門クリニックを立ち上げたい」という熱い想いに共感したのが直接のきっかけです。ただ、その根底には、二十歳の時に経験した祖父の介護で感じた強烈な違和感がありました。
— その「違和感」とは、具体的にどのようなものだったのでしょう?
祖父は7年間、胃ろうを含めたいわゆる「フルコース」の医療を受けながら在宅で療養していました。当時、介護保険制度が始まったばかりという背景もありましたが、娘である私の母は「1分1秒でも長く生きていてほしい」と願っていました。その気持ちは痛いほど分かる一方で、孫の私には、祖父自身がその最期を望んでいるとは思えませんでした。「本人の意思」と「家族の願い」、そして「医療ができること」の間に生まれる葛藤を目の当たりにし、もっとその人らしい最期を支えられる医療の形があるべきだと強く感じたのです。
— 13年前にクリニックを立ち上げた当初は、静岡初の在宅専門クリニックとして、ご苦労も多かったのではないでしょうか。
そうですね。2012年当時、外来はほとんど行っていなかったため、地域の方々からは「何のクリニックだろう?」と、なかなか理解されませんでしたね。アパートの一室から、医師1名という本当に手探りの状態でのスタートでした。
— そこから、どのようにして地域に信頼されるクリニックへと成長されたのですか?
2016年頃から常勤の医師が増え、がんの緩和ケアなど専門性の高い先生が加わってくれたことが大きな転機となりました。対応できる患者さんの層が広がり、個人宅への訪問依頼も急増しました。地道に一人ひとりの患者さんと向き合い続ける中で、少しずつですが、この地域の在宅医療を支えるインフラの一つとして認めていただけるようになったと感じています。

主役は患者さんと多職種。医師は「バックアップ」に徹する
— 齊藤さんが理想とする在宅医療の姿について、詳しくお聞かせください。
私たちが目指すのは、医師が主役にならない医療です。在宅の現場で患者さんと最も長く時間を共にするのは、ご家族や訪問看護師、ケアマネジャー、ヘルパーの方々です。医師が関わる時間は、実はごくわずかなんです。だからこそ、私たちは専門家としてチームを後方から支える「バックアップ」に徹するべきだと考えています。
— 「バックアップに徹する」という役割を、具体的に教えていただけますか?
現場の最前線にいる訪問看護師さんたちが、「何かあっても、あのクリニックの先生がいるから大丈夫」と心から安心してケアにあたれる環境を作ることです。彼らが自信を持って患者さんと向き合えて初めて、ご家族も家での療養を続けられます。主役はあくまで現場の多職種の皆さんと患者さん自身。この理念が、クリニックの核となっています。

— その理想を実現するために、地域全体で取り組むべき課題とは何でしょうか?
今後、高齢者救急はますます増加します。その中で、必ずしも入院が必要でないケースも多くあると思います。私たちが地域の多職種と連携することで、不要な救急受診や入院を減らし、患者さんが住み慣れた場所で穏やかに過ごせる時間を最大限に確保する。そのための「砦」となることが、私たちの使命だと考えています。
— チーム医療を円滑に進めるために、どのような医師を求めていますか?
医療スキルはもちろんですが、それ以上に「人間性」を重視しています。患者さんの人生のクライマックスという非常にデリケートな場にお邪魔するわけですから、相手の価値観を尊重し、真摯に向き合える人。そして、チームを組む看護師さんやケアマネジャーさんからも信頼され、時には「可愛がられる」ような人間的な魅力がある方が理想です。
— なぜ、専門的なスキル以上に「人間性」が重要なのでしょうか?
在宅医療は、医療を押し付ける場ではないからです。患者さんの生活に私たちがお邪魔し、その人らしい生き方を支えるのが仕事。そのためには、自分の意見を押し通すのではなく、多職種の意見に耳を傾け、チーム全体で最善の策を見つけ出そうとする柔軟な姿勢が不可欠なのです。

質の高いチーム医療を支えるクリニックの仕組み
— チーム医療を実践するために、クリニックではどのような工夫をされていますか?
徹底した情報共有が私たちの強みです。ICTツール「メディカルケアステーション(MCS)」を導入し、訪問看護師さんからの看護記録はもちろん、私たちのカルテもリアルタイムで共有しています。ケアマネジャーさんにも参加いただき、関係者全員が患者さんの最新情報を常に把握できる体制を整えています。
— カルテまで共有するのは珍しいですね。どのような効果がありますか?
日々膨大な情報が飛び交いますが、全員でそれを確認することで、チームの目線が揃います。医師は短い診察時間でも的確な判断ができますし、他の職種の方にとっても学びの機会になります。この密な連携こそが、医療の質の担保に直結していると思います。
— ツールだけでなく、アナログなコミュニケーションも重視されているとか。
はい。「電話のしやすさ」は非常に大切にしています。現場の看護師さんが判断に迷った時、「先生に聞きづらい」と感じてしまっては意味がありません。24時間、いつでも気兼ねなく相談できる心理的な安全性を確保すること。結局は、人と人との信頼関係がチーム医療の基盤です。

— 中之郷クリニックの体制の強みについて教えてください。
現在、常勤医5名を含む7名の医師で24時間365日の体制を敷いています。緊急の電話はまず担当医が受けますが、もちろん一人で抱え込む必要はありません。対応が難しい場合は他の医師がすぐにカバーに入ります。また、日々の訪問スケジュールも、緊急往診などに対応できる余白を常に意識して、ゆったりと組んでいます。これにより、一人の医師に過度な負担が集中することなく、心身ともに健康な状態で医療を提供できる、持続可能な働き方が可能になっています。安心してしっかりと休みを取れるのも、このチーム体制と余裕のある人員配置があるからです。
— 呼吸器、消化器、精神科など、専門性の高い医師が揃っているのも特長ですね。
そうですね。当院には、県立総合病院やがんセンター、済生会など、地域の中核病院で研鑽を積んできた経験豊富な医師が集まっています。専門も呼吸器外科、消化器外科、精神科と多岐にわたり、世代も30代から60代までとバランスが取れています。そのため、院内で気軽に専門的な相談をし合える文化が根付いています。複雑な症例でも、それぞれの知見を持ち寄り、チームとして多角的な視点からアプローチできるのは、患者さんにとっても、私たち医療者にとっても大きな強みです。
患者さんの想いを実現するチームを目指して
— 在宅医療の現場における立ち位置について、どうお考えでしょうか。
在宅医療の現場では、多様な職種が関わりますが、そのチームに明確なリーダーがいるわけではありません。あえて言うならば、リーダーは患者さん自身です。私たちは、その患者さんの想いを実現するために集まったチームの一員にすぎません。
— 医師の指示が絶対、というわけではないのですね。
時に、医療的な正しさよりも患者さんの生活や価値観を優先すべき場面があります。そうした時に、医師の顔色を伺うのではなく、専門職として「患者さんのためにはこうすべきだ」と臆せず意見を言える関係性が理想です。
— クリニックは、他の医療従事者にとってどのような存在でありたいですか?
私たちは、訪問看護師さんやケアマネジャーさんにとっての「安心材料」でありたいと思っています。「中之郷クリニックがついているから、私たちは目の前の患者さんに集中できる」そう思っていただけるような、頼れるバックアップであり続けることが目標です。

— そのために、日々のコミュニケーションで心がけていることはありますか?
どんな些細なことでも報告・相談してもらえるような雰囲気づくりを大切にしています。医療・介護制度は複雑で、知らないと損をしてしまうことも多い。そうした制度面の知識も含めて、私たちがチームの潤滑油となり、皆さんが専門性を最大限に発揮できる環境を整えていきたいです。
— 最後に、在宅医療に携わる医療従事者の方々へメッセージをお願いします。
人の生涯の最期という、非常に尊い時間に関わらせていただくのが私たちの仕事です。そこには大きな責任が伴いますが、他では決して得られない深いやりがいがあります。もし、あなたが患者さんの人生そのものに寄り添う医療をしたいと考えているなら、ぜひ一度、私たちの話を聞きに来てください。
外科医から在宅医へ。クリエイティブな医療を求めてたどり着いた場所
— ここからは高木先生にお話を伺います。先生が医師を目指されたきっかけは何ですか?
父が総合病院に勤務する医師で、その姿を見て育ったのが大きいですね。子どもの頃、家族の誰かが体調を崩した時に、父が「大丈夫だよ」と言うと不思議と安心できた。そんな父への憧れから、自然と医師の道を志していました。

— 医師になられてからは、どのようなキャリアを歩んでこられたのですか?
専門は外科で、主に消化器や乳腺のがん治療に携わり、外科専門医も取得しました。病院では手術から終末期の緩和ケアまで、一貫して患者さんを診る経験を積みました。
— 外科医として充実したキャリアを積まれていた中で、なぜ在宅医療の道に進まれたのでしょうか?
外科医として関わっていた緩和ケアがきっかけです。病院の中では、どうしても安全管理のために「あれはダメ、これもダメ」と患者さんの行動を制限せざるを得ない場面が多くあります。そのことに、ずっともどかしさを感じていました。患者さんがもっとその人らしく、自由に過ごせる場所で医療を提供したいという思いが強くなり、在宅医療の道を選びました。
— 実際に在宅医療の世界に飛び込んでみて、どのような印象を受けましたか?
「なんて面白い世界なんだ」と衝撃を受けました。病院が「ホーム」なら、在宅は完全に「アウェイ」。私たちのルールではなく、患者さんの生活のルールに合わせなければなりません。その中で何ができるかを考えるプロセスは、非常にクリエイティブだと感じています。
— 病院医療と在宅医療の「クリエイティビティ」の違いとは何でしょうか?
病院での医療は、病気というマイナスの状態をゼロに近づけることが主な目的でした。しかし在宅医療では、必ずしも病気を治すことだけがゴールではありません。患者さんが持つ独自の価値観や生活様式を尊重し、「こんな生き方もありますよ」と新しい価値観を一緒に作り上げていくことができる。それが在宅医療のクリエイティビティであり、最大の魅力だと感じています。

「出しゃばらない医療」医師が白衣を脱ぎ、患者の人生に寄り添う
— 高木先生から見た中之郷クリニックの特長を教えてください。
まず、非常に働きやすい環境です。事務スタッフがスケジュールを柔軟に組んでくれるので、一件一件の訪問にしっかり時間をかけられますし、緊急の往診にも対応できる余力が生まれます。子どもの学校行事などにも参加できており、ワークライフバランスは格段に向上しました。
— 在宅医療の現場で、高木先生が特に意識されていることは何ですか?
「自分が出しゃばらないこと」です。チーム医療において、医師の一言は非常に重みを持ちます。私が先に意見を言ってしまうと、他の職種の方が意見を言いにくくなってしまう。ですから、まずは看護師さんやご家族の話をじっくり聞き、チーム全体の意見を尊重することを常に心がけています。

— なぜ「医師が出しゃばらない」ことが重要なのでしょうか?
在宅医療の主役は、あくまで患者さんとその生活だからです。私たちの役目は、その生活がより豊かになるように、専門家として選択肢を提示し、サポートすること。医療的な正しさだけを押し付けるのではなく、患者さんの価値観と私たちの提案をすり合わせていくプロセスが不可欠です。
— チーム医療を実践する上で、大切にしていることはありますか?
齊藤さんも話していましたが、やはり情報共有とコミュニケーションです。多職種で一人の患者さんを支えるには、全員が同じ方向を向いている必要があります。そのためには、日々の細かな情報交換と、職種を超えた信頼関係の構築が欠かせません。
— 普段の患者さんとの関わりの中で、どのようなことを意識されていますか?
患者さんのお宅に上がらせていただくのですから、こちらも一人の人間として接することを大切にしています。病気の話だけでなく、世間話をしたり、時には一緒に笑ったり。そうした関わりの中で生まれる信頼関係が、より良い医療に繋がると信じています。白衣を着ていないのも、その表れかもしれません。

「家で過ごしたい」その想いを支える選択肢がクリニックにある
— 今後の中之郷クリニックの展望や、高木先生の夢についてお聞かせください。
クリニックとしては、現在のスタイルを継続していくことが第一です。個人的には、このフットワークの軽さをいつまで維持できるか、という挑戦もありますね。ただ、それ以上に、新しい仲間を増やし、私たちが培ってきた「中之郷クリニックの文化」を次の世代に繋いでいきたいという思いが強いです。
— どのような仲間と一緒に働きたいですか?
私が見学で感じたように、「なんだか楽しそうだな」と直感的に思ってくれる人がいいですね。そして、患者さんの家にすっと溶け込み、その人や家族の物語を一緒に紡いでいけるような、そんな温かさを持った方と一緒に働きたいです。
— 入職を決められる前に、クリニックを見学されたそうですが、その時の印象はいかがでしたか?
はい、1日同行させていただきました。その時に感じたのは、とにかく「楽しそう」だということでした。同行させていただいた先生が、患者さんのお宅にすっと自然に入っていき、一人の人間として世間話をしながら心の距離を縮めていく。その姿がとてもハートフルで、私が外科医として抱えていたもどかしさの答えがここにある、私がやりたかった医療はこれだと直感しました。その良い意味での「ゆるやかさ」と「温かさ」が入職の決め手になりましたね。

— 働きやすさの面では、病院時代と比べていかがですか?
格段に働きやすいです。先日も休みをもらって、家族で千葉や長野まで足を延ばしました。子どもの学校行事にも問題なく参加できます。これは外科医時代には考えられなかったことですね。オンとオフをしっかり切り替えられるからこそ、日々の診療に集中できるのだと思います。
— 最後に、在宅医療に興味を持つ医師や地域の方々へメッセージをお願いします。
もしあなたが今の働き方に疑問を感じていたり、もっと患者さんと深く関わる医療がしたいと思っているなら、ここは最高の場所だと思います。医師としての新しいやりがいを見つけ、人間らしく働き、プライベートも大切にできます。そして地域の方々には、「在宅医療」は特別なものではなく、皆さんの暮らしを支える身近な選択肢の一つだと知っていただきたいです。何か困ったことがあれば、いつでも気軽に私たちを頼ってください。
医療法人社団隆誠会 中之郷クリニック

診療科
内科・精神科・緩和ケア内科・外科
医師7名で24時間365日体制で患者様の健康を管理させていただいており、夜間・休日問わず、医師が往診への対応を致します。
医師7名で24時間365日体制で患者様の健康を管理させていただいており、夜間・休日問わず、医師が往診への対応を致します。
対応エリア
診療実績(直近1年間※)
・診療患者数合計 1,884
・看取り件数 356
・訪問診療等の合計回数 17,956
往診 1,174
訪問診療 16,023
訪問看護(緊急を含む) 759
・在宅医療を担当する常勤の医師数 9
・連携する保険医療機関数 4
❏ さらに詳しい診療内容・実績はこちら
❏ 静岡県の在宅看取り件数ランキング2024年版
・看取り件数 356
・訪問診療等の合計回数 17,956
往診 1,174
訪問診療 16,023
訪問看護(緊急を含む) 759
・在宅医療を担当する常勤の医師数 9
・連携する保険医療機関数 4
❏ さらに詳しい診療内容・実績はこちら
❏ 静岡県の在宅看取り件数ランキング2024年版
※在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書に基づく
お問い合わせ
齊藤祐希事務長のプロフィール
経歴:
2010年 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校卒業
2012年 中之郷クリニック開業(事務長)、現在に至る
2012年 中之郷クリニック開業(事務長)、現在に至る
資格・学会:
社会福祉士
日本緩和医療学会
日本緩和医療学会
高木航医師のプロフィール
経歴:
2009年 北海道大学医学部卒業
2009年 静岡県立総合病院初期研修
2011年 静岡県立総合病院外科(後期研修)
2014年 静岡県立がんセンター胃外科レジデント、緩和医療科レジデント
2017年 中之郷クリニック、現在に至る
2009年 静岡県立総合病院初期研修
2011年 静岡県立総合病院外科(後期研修)
2014年 静岡県立がんセンター胃外科レジデント、緩和医療科レジデント
2017年 中之郷クリニック、現在に至る
資格・学会:
日本外科学会 認定登録医
日本プライマリ・ケア連合学会
日本プライマリ・ケア連合学会
【専門家監修】訪問診療の採用に関するFAQ
Q1. 在宅医療の医師はどのような働き方になりますか?
A. 在宅医療では医師が患家や施設を訪問し、計画的な訪問診療と必要に応じた緊急往診を行います。1日の訪問件数は患家で8〜12件程度が一般的で、移動を含めたスケジュール管理が特徴です。多職種連携が前提となるため、訪問看護師・ケアマネジャー等とのコミュニケーションも重要な業務です。
Q2.在宅医療に向いている医師の特徴は何ですか?
A. 患者や家族の価値観を尊重し寄り添える姿勢、生活背景を踏まえる視点、他職種との協働ができる柔軟性が求められます。病院とは異なり「生活支援」や「意思決定支援」の比重が高いため、傾聴力やコミュニケーション力も重要です。
Q3.在宅医療の経験がなくても応募できますか?
A. 多くの在宅医療機関では未経験者も歓迎されています。訪問看護師や経験者の同行訪問による研修があるため、外来や病棟経験のみでも問題ありません。内科・総合診療の経験があるとよりスムーズに業務に適応できます。
Q4.在宅医療の業務で身につくスキルは何ですか?
A. 慢性疾患管理、緩和ケア、急変時対応、自宅での看取り支援など、多岐にわたるスキルが身につきます。また、患者の生活を軸にした「包括的な診療能力」が身につくため、総合診療領域のキャリア形成にも役立ちます。
Q5.在宅医療のやりがいは何ですか?
A. 患者が住み慣れた自宅や施設で安心して過ごす時間を支えられることが大きなやりがいです。病院とは違い、患者の生活背景まで理解し「人生全体」に寄り添うことができます。家族との関係性を含めた包括的なサポートができる点も魅力です。
Q6.当直やオンコール対応は必ずありますか?
A. 多くの在宅医療機関ではオンコール体制がありますが、医師複数名でシフト制を組む、訪問看護師と初期対応を分担するなど、無理のない体制が整えられています。最近はICTによる情報共有が進み、負担軽減に取り組む施設も増えています。
Q7.在宅医療の1日のスケジュールはどのような流れですか?
A. 予め計画された訪問診療に対応しつつ、診療の合間に訪問看護記録の確認や急変対応を行います。
Q8.在宅医療でのチーム医療はどのように行われていますか?
A. 医師・訪問看護師・ケアマネジャー・ヘルパー・薬剤師等が連携し、患者の生活を支える体制を取ります。定期的なカンファレンスやICTツールを使った情報共有が中心で、一人の患者に多職種で関わる「地域包括ケア」の実践となります。
Q9.在宅医療の医師にとって大変な点は何ですか?
A. 在宅では限られた医療資源と制度を遵守した対応をしなければならないため、病院とは異なる負荷があります。訪問看護師を主としたチームで支える体制があれば負担は大きく軽減されます。
Q10.在宅医療の医師採用で重視されるポイントはありますか?
A. 医療スキル以上に、人柄・コミュニケーション力・チームワーク・患者家族への姿勢が重視されます。「寄り添う医療」を実践できるか、生活の質を大切にした診療方針に共感できるかが、採用の重要な判断基準となっています。
関連リンク: