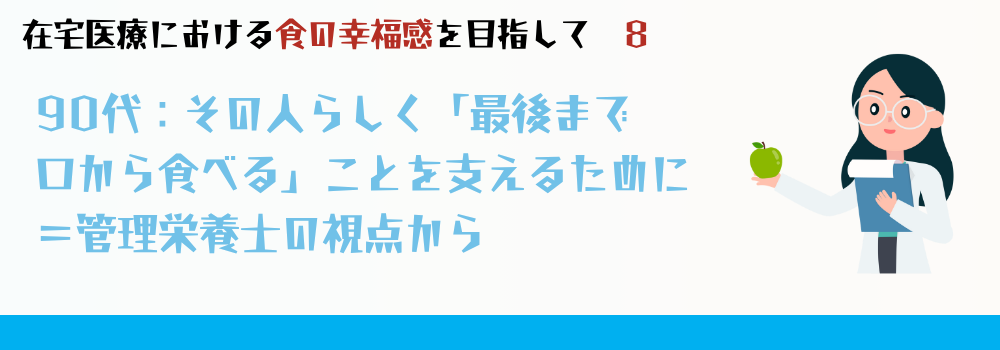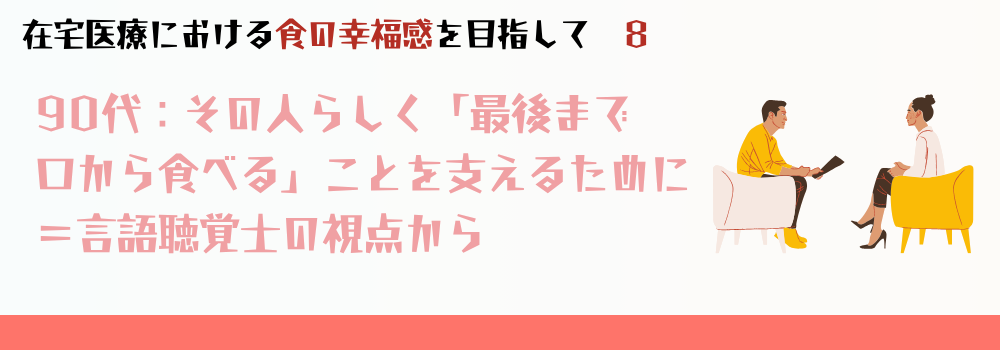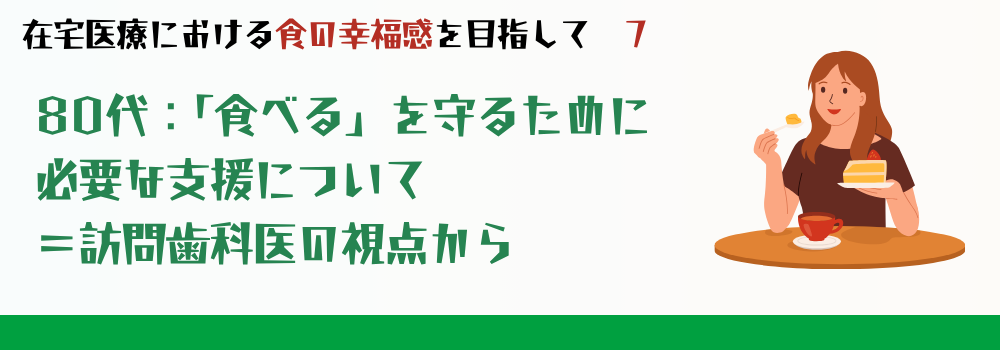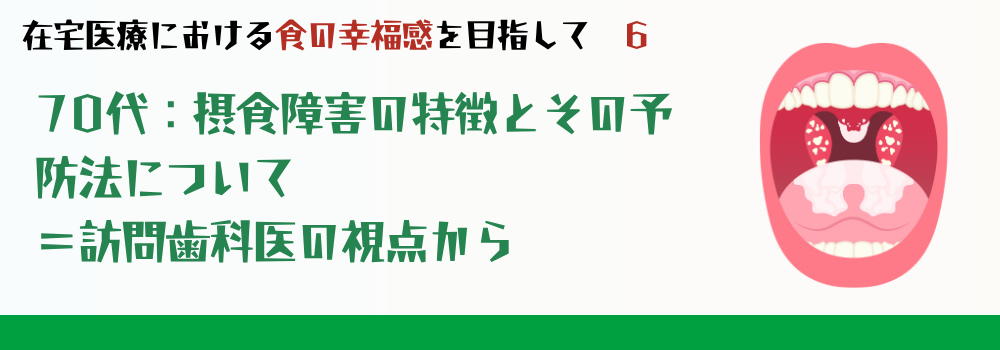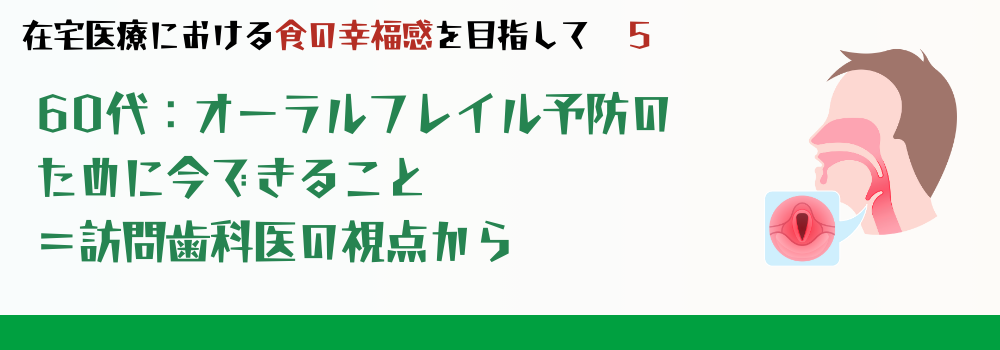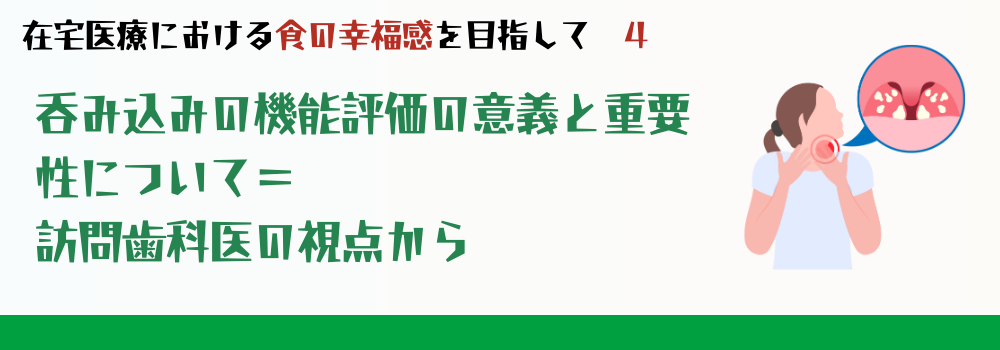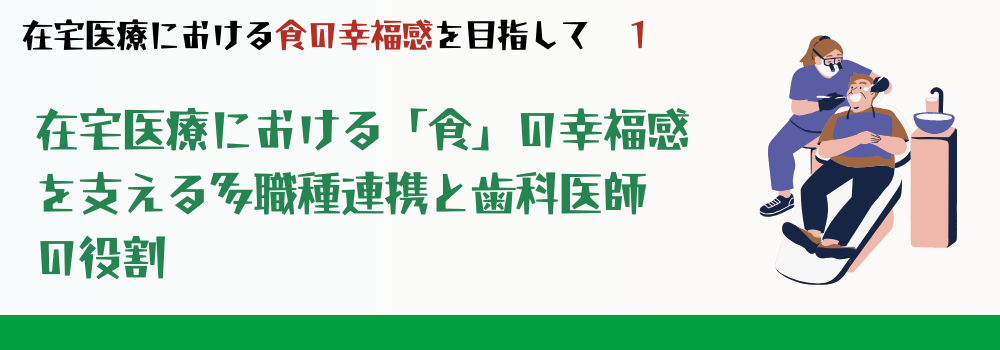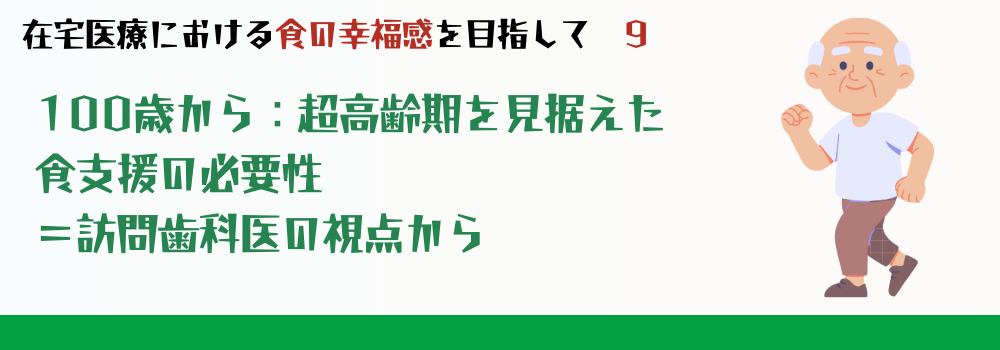【医師執筆】90代の摂食嚥下障害ーその人らしく「最後まで口から食べる」ことを支えるために 最終更新日:2025/10/21
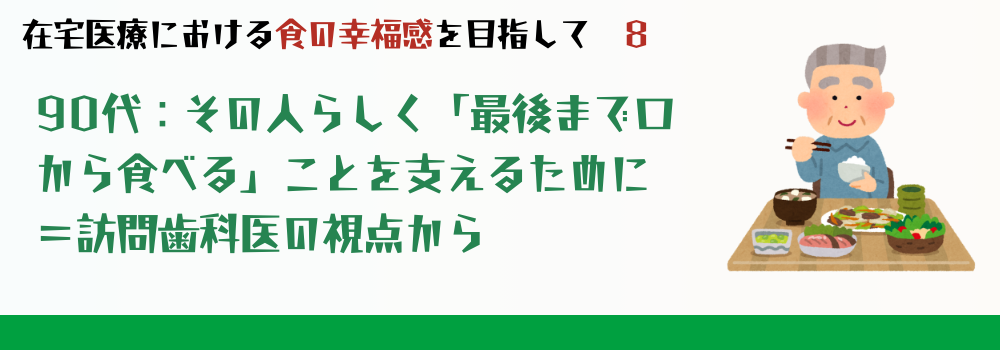
90代で多くみられる摂食嚥下障害を、訪問歯科医の視点から解説。92歳女性の実例をもとに、日常でできる食支援の工夫、看取り期における「最後まで口から食べる」ための選択肢、そして多職種連携の重要性を詳しく紹介します。
はじめに─90代の摂食嚥下障害と在宅での食支援の重要性
人生の最終章を迎える90代。
身体は細り、動作はゆるやかに、言葉は少なくなっても、食卓に座るその姿は、長い人生を歩んできた生き様そのものです。
90代になると多くの方が、今までの病気やその後遺障害をいくつか抱え、支援を受けながらの生活を送っています。そのなかでも重要なのが、「食べる力=摂食嚥下機能」をどう守るかという視点です。80代までとは異なり、機能の維持ではなく、“どのようにすれば安全に、穏やかに、最後まで口から食べられるか”という支援に焦点が移ります。
身体は細り、動作はゆるやかに、言葉は少なくなっても、食卓に座るその姿は、長い人生を歩んできた生き様そのものです。
90代になると多くの方が、今までの病気やその後遺障害をいくつか抱え、支援を受けながらの生活を送っています。そのなかでも重要なのが、「食べる力=摂食嚥下機能」をどう守るかという視点です。80代までとは異なり、機能の維持ではなく、“どのようにすれば安全に、穏やかに、最後まで口から食べられるか”という支援に焦点が移ります。
モデル患者:92歳中村つねさんに学ぶ摂食嚥下の現状
都内の自宅で長男夫婦と同居。要介護3。2年前に軽度の脳梗塞を起こして以来、歩行はほぼ困難。昼間はリクライニングチェア、夜は介護ベッドで過ごしている。軽度の認知症があり、日によって会話の調子や食事の意欲に波がある。現在は訪問看護と週1回の訪問歯科、訪問リハビリを利用中。
普段の食事は、やわらかめに調理した自宅の食事と市販のムース食が中心。自分の手でスプーンを持ち、家族と一緒に食卓を囲む時間を大切にしている。

90代女性に多い摂食嚥下の課題とリスク
・舌や咽頭の筋力が著しく低下し、粘度の低い水分ではむせやすくなっている。とろみをつけないと咳き込みやサイレントアスピレーションのリスクが高い。
・食事中の集中が続かず、時折うとうとしたり姿勢が崩れることでむせこみが起こる。
・「食べたい」と「怖い」の間で揺れる気持ちがあり、むせた後は不安そうな表情を見せることもある。
・家族は、「誤嚥させたくないけど、無理やり食べさせるのも怖い」と葛藤を抱えている。
・医師からは「経口摂取が限界なら経管栄養の検討も」と言われ、家族は悩んでいる。
「つねさんの声」にみる在宅療養と食べることへの想い
「私はね、やっぱり自分の口で食べたいのよ。スプーンで少しだけでもいいから、あったかい味噌汁の味を感じたいのよ。」
つねさんのように、90代の高齢者にとって「食べる」という行為は栄養摂取ではなく、記憶・誇り・喜び・尊厳の再確認そのものです。
この“ひとくち”が、今までの人生のすべてを語る瞬間でもあるのです。
訪問歯科が支える日常の工夫と食支援のポイント
・座位保持と環境調整:足を台に載せることで接地をさせ、顎が自然に引ける姿勢を取れるように介助。集中が途切れないようにテレビを消し、静かに声かけを行いながら落ち着いた環境を整える。
・口腔ケアと食前準備:乾燥している場合は保湿ジェルを塗布し、食前に唾液腺マッサージや深呼吸を行う。
・1口の質を上げる:量を減らしても、「懐かしい味」「好きな香り」など、感情を呼び覚ます味覚刺激を優先する。
・水分にとろみをつける:とくに就寝前や薬の服用時に注意が必要。本人の飲みやすい温度や器の形状にも配慮。
看取り期に選ぶ“口から食べる”ための選択肢とケア
つねさんのように、「少しでも食べたい」という想いを持ちつつ、飲み込む力が限界に近づいている人は多くいます。
その時、「もう食べさせない方がいいのでは」「栄養を維持するには経管栄養に切り替えるべきか」といった医療的・倫理的な判断が求められます。
大切なのは、“延命のための栄養”ではなく、“人生の質を支える食支援”という発想です。
本人が何を望んでいるのか、家族は何を大切にしたいのか、支えるチームで十分に話し合う必要があります。
たとえば、
・1日3食を目指さない
・“完食”をゴールにしない
・食べない日があったとしても受け入れる
こうした姿勢が、「食べることが本人の負担にならない」ように支える鍵になります。
多職種連携で支える92歳の“そのひとくち”
・歯科医師:義歯調整や口腔乾燥ケア、VEによる評価
・言語聴覚士(ST):嚥下機能訓練、食形態の提案
・栄養士:ムース食やゼリー食の工夫、嗜好への配慮
・看護師:体調管理、脱水や感染の早期察知
・介護者・家族:食事中の見守り、声かけ、励まし

一口の食事を実現するには、多くの手が必要です。けれどその手は、生きる力を支える温かい手でもあります。
おわりに─最後のスプーンに込める希望と在宅医療の未来
90代の食支援とは、回復を目指すものではなく、その人がその人らしく生ききるためのケアです。
つねさんが、ある日スプーンを止めたとしても、それは衰えではなく、「人生を静かに閉じていく選択」なのかもしれません。
それまでの日々、たとえ1口でも、
「おいしかったよ」
「食べられてよかった」
そう思える時間が積み重なれば、
それは、何よりも豊かな“食のエンディング”になるはずです。
つねさんが、ある日スプーンを止めたとしても、それは衰えではなく、「人生を静かに閉じていく選択」なのかもしれません。
それまでの日々、たとえ1口でも、
「おいしかったよ」
「食べられてよかった」
そう思える時間が積み重なれば、
それは、何よりも豊かな“食のエンディング”になるはずです。

90代の摂食嚥下と訪問歯科 Q&A
— Q1. 90代では摂食嚥下障害はなぜ起こりやすいのですか?
A. 筋力低下や慢性疾患の影響で舌・咽頭の動きが弱まり、水分や食物が気管に入りやすくなるためです。
— Q2. 摂食嚥下障害があっても口から食べ続けることは可能ですか?
A. 訪問歯科や多職種連携の支援、姿勢や食形態の工夫により、最後まで口から食べられるケースがあります。
— Q3. 訪問歯科ではどのような支援が受けられますか?
A. 口腔ケア、嚥下機能評価、食形態の提案、食事環境調整などを行い、安全な経口摂取を支えます。
— Q4. 看取り期でも食べることを選ぶメリットは?
A. 栄養補給だけでなく、本人の尊厳や生きる喜びを守る「QOLの向上」につながります。
— Q5. 家族はどのように支援すればよいですか?
A. 医療・介護チームと連携しながら、本人の希望を尊重し、無理のない食事環境を整えることが大切です。
関連リンク:
執筆: