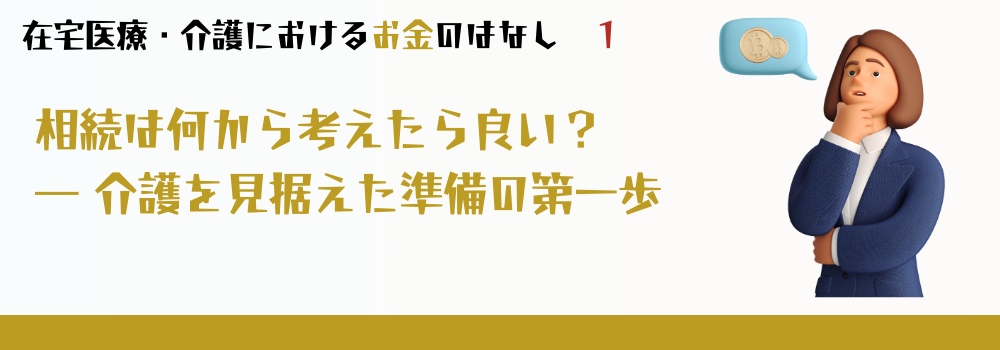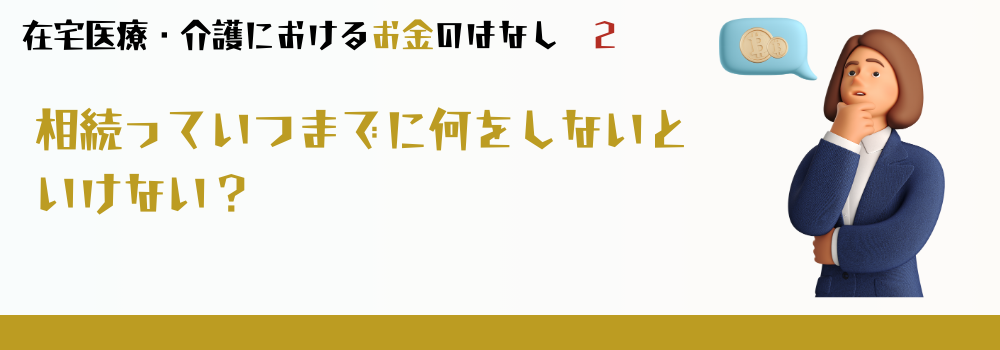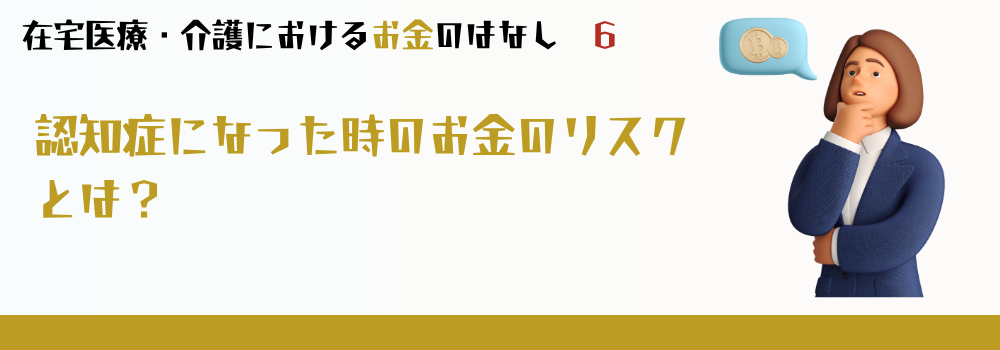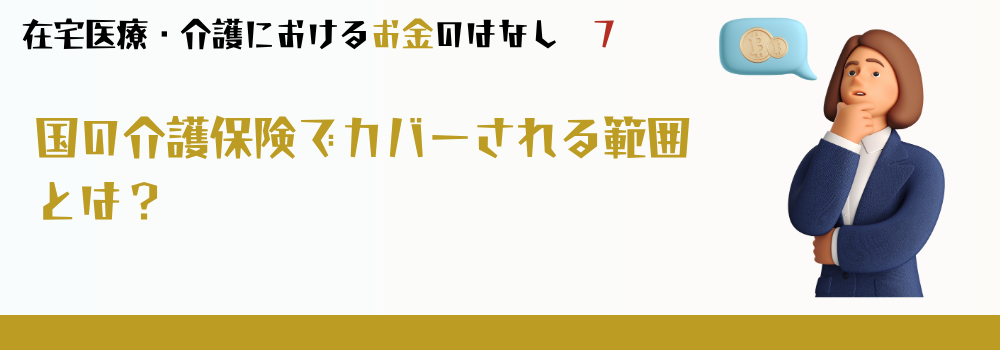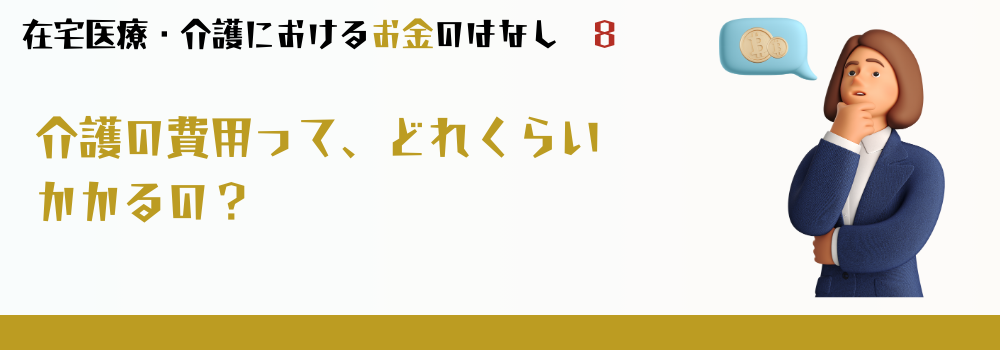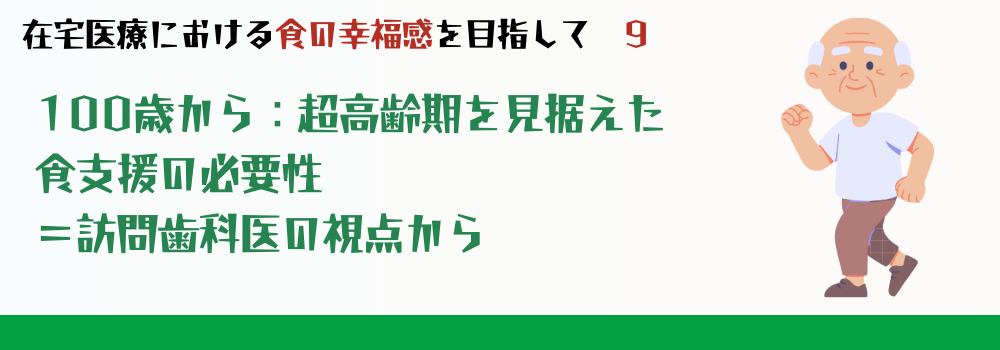公的介護保険だけで足りる?民間保険と併用して在宅介護にかかる費用を安心準備 最終更新日:2025/11/26
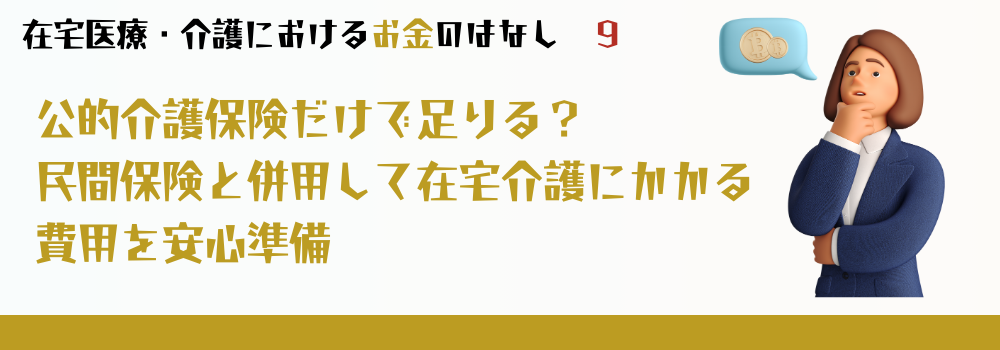
高齢化社会が進む中、「介護にかかる費用はいくらかかるのか」「公的な介護保険だけでは足りないのではないか」といった不安を抱える方が増えています。
本記事では、在宅介護を中心に、「公的介護保険の仕組み」「民間保険で備える方法」「そして介護にかかる実際のコスト」を詳しく解説します。
「民間保険」と「介護保険」をどう使い分けるか、「どれくらいお金がかかるか(いくらかかる)」という疑問にも数値の目安を示しながら、わかりやすくご案内します。
介護を将来に備えたい方、あるいはすでに介護が始まっているご家族がいる方にとって、この記事が制度理解と対策のヒントになれば幸いです。
本記事では、在宅介護を中心に、「公的介護保険の仕組み」「民間保険で備える方法」「そして介護にかかる実際のコスト」を詳しく解説します。
「民間保険」と「介護保険」をどう使い分けるか、「どれくらいお金がかかるか(いくらかかる)」という疑問にも数値の目安を示しながら、わかりやすくご案内します。
介護を将来に備えたい方、あるいはすでに介護が始まっているご家族がいる方にとって、この記事が制度理解と対策のヒントになれば幸いです。
民間保険 × 介護保険 × 在宅介護:費用はいくらかかるか
「介護が必要になったら、どれくらいお金がかかるのだろう?」
これは誰にとっても避けられない問いです。厚生労働省や生命保険文化センターの調査によれば、介護期間の平均は約4年7か月、介護にかかった自己負担額の総額は平均543万円。しかし、実際には10年以上続くケースもあり、その場合は1,000万円を超える負担になることもあります。
こうした背景から、公的介護保険に加えて、民間の「介護保険」で備える人が増えてきました。今回は、公的介護保険の仕組みを踏まえたうえで、民間保険にはどんな種類があるのか、そして「在宅介護」と「施設介護」の費用と合わせて整理していきたいと思います。
公的介護保険とは:制度の基本と給付の仕組み
日本の介護制度の基盤は、公的介護保険です。
加入と負担
・40歳以上の人が強制的に加入となります。
・介護保険料は健康保険や国民健康保険と一体で徴収されます。
・自治体ごとに保険料額が異なり、65歳以上は年金から天引きされるケースが多いです。
サービス利用の流れ
1.市町村に申請して「要介護認定」を受けます。
2.要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じてサービスの支給限度額が決定します。
3.サービス利用時の自己負担は原則1割(高所得者は2〜3割)となります。
利用できるサービス
・在宅:訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具レンタル、住宅改修費の一部補助
・施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなど
注意点
・食費・居住費は原則自己負担となります。
・個室や手厚い介護サービスは対象外です。
・利用できるサービス量には上限があり、必要な介護をすべて賄えないこともあります。
公的介護保険は「最低限の安心」を支える制度であり、「自分や家族が望む介護」までは保証してくれません。
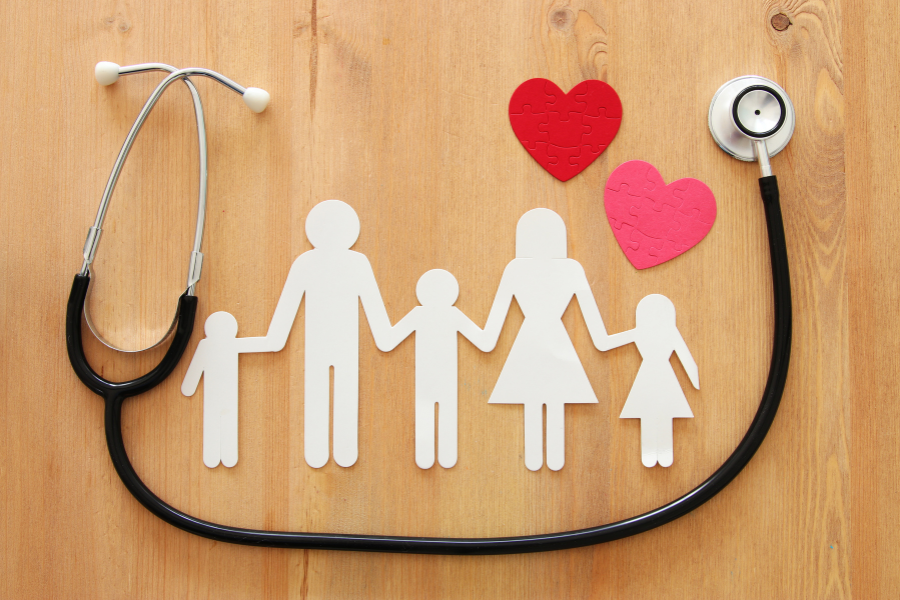
在宅介護 vs 施設介護:どちらがいくらかかる?費用比較
介護は「自宅で行うか」「施設に入るか」で費用が大きく異なります。
在宅介護
・訪問介護:1時間あたり自己負担600〜800円程度
・デイサービス:1日自己負担1,000〜1,500円程度
・福祉用具レンタル:ベッドや車いすは月数百〜数千円(自己負担分)
・月額合計:5〜8万円程度(自己負担)
メリット:住み慣れた家で過ごせ、家族の見守りができます。
デメリット:家族の負担が大きく、夜間や休日の対応が難しい。
デメリット:家族の負担が大きく、夜間や休日の対応が難しい。
施設介護
・特別養護老人ホーム(特養):月6〜15万円
・介護付き有料老人ホーム:月10〜35万円程度
・高級施設では月40万円以上かかることも
・年間200〜300万円以上の出費になるケースも
メリット:24時間介護スタッフが常駐して安心です。
デメリット:入居待ちが長く、費用も大きくなりがちです。
デメリット:入居待ちが長く、費用も大きくなりがちです。
費用が膨らむ要因
介護にかかるお金が平均額を大きく上回ってしまう理由はいくつかあります。まず挙げられるのが「長期化」です。要介護度が比較的軽くても、介護が10年以上続けば当然ながら総額は膨らんでいきます。
また「重度化」も大きな要因となります。要介護4や5になると、利用できるサービスの量が増え、自己負担も増えていきます。さらに「施設利用」も支出を押し上げる要素です。特別養護老人ホームなどの公的施設であれば費用は抑えられるものの、介護付き有料老人ホームなどを選べば毎月20万円から30万円程度かかることも珍しくありません。
加えて、「医療費の追加負担」も見逃せません。介護と同時に入院や治療が必要になれば、介護費用に医療費が上乗せされ、家計への負担はさらに大きくなってしまいます。

民間保険で備える介護:主な種類と特徴
こうした費用負担に備えるために、民間の介護保険があります。大きく分けて3つのタイプがあります。
(1)介護保険
介護に特化した保険で、要介護状態になると給付金が支払われます。
特徴
・給付条件は「要介護1以上や2以上」など
・一時金・年金形式・併用型など給付方法を選べる
・公的介護保険の認定を基準にする商品が多く、わかりやすい
メリット
・介護に特化しており保障内容が明確
・自分の希望に合わせた金額設定が可能
・介護資金を“確実に”用意できる
デメリット
・加入年齢が高くなると保険料が高額になりやすい
・要介護度の条件を満たさないと給付されない
向いている人
・平均的な介護費用(500万円程度)を丸ごとカバーしたい人
・「介護になったら必ず備えを使いたい」と考える人
(2)医療保険・生命保険に付ける介護特約
既に加入している保険に介護保障をオプションで追加するタイプです。
特徴
・医療保険や終身保険に数百円〜数千円の特約料を追加
・介護状態になったときに一時金や年金が支払われる
・主契約ではなく特約として不可するので、解約がしやすい
メリット
・手軽に介護保障を追加できる
・保険料負担を抑えやすい
・医療・死亡保障と一緒に管理できる
デメリット
・保障額が少なめで大きな介護資金はカバーできないケースも
・主契約を解約すると特約も消える
・特約だけを柔軟に変更できない保険会社も
向いている人
・「最低限の備えだけで十分」と考える人
・既に医療保険や終身保険に加入している人

(3)貯蓄性を持つ終身型(介護+死亡保障)
介護になれば介護給付金、ならなければ死亡保険金として家族に残せるタイプです。
貯蓄性があり、外貨建てや変額保険もあります。
貯蓄性があり、外貨建てや変額保険もあります。
特徴
・「介護」と「死亡」の両方をカバー
・一生涯保障が続く
・貯蓄性が高く、資産形成にも役立つ
メリット
・介護になっても、ならなくても“無駄にならない”
・老後資金や相続資金の役割も持つ
・家計に安心をプラスできる
デメリット
・保険料が高めで加入ハードルがある
・「介護資金だけでよい」という人には過剰になる可能性あり
・専用タイプに比べると効率はやや劣る
向いている人
・「介護にも相続にも備えたい」と考える人
・長期的に資産を保険で運用したい人
公的保険と民間保険の給付の違い:何がもらえて、何が足りないか
民間の介護保険は、同じ「介護給付」といっても、その受け取り方に違いがあります。まず「一時金型」は、介護が始まった時点でまとまったお金を受け取れる仕組みで、住宅改修や入居一時金といった初期費用に対応しやすいのが特徴です。
これに対して「年金型」は、介護が続く間、毎月一定額を受け取れる仕組みで、在宅サービスや施設利用にかかる月々の費用をまかなうのに適しています。
さらに「一時金と年金を組み合わせたタイプ」もあり、初期費用と継続的な費用の両方をバランスよく補うことができます。
一般的に、在宅介護では住宅改修と継続費用の両方が必要になるため一時金と年金の併用型が合いやすく、施設介護では毎月の支出が大きいため年金型が安心につながりやすいと言えるでしょう。
介護が家族に与える負担と対策:時間・費用・心身
介護はお金だけでなく、家族の時間・労力の負担も大きいものです。
・毎年約10万人が「介護離職」を余儀なくされている
・在宅介護では心身の疲労が重なりやすい
・施設に預けても費用面での負担や罪悪感に悩む人が多い
「経済的な安心」があれば、介護の選択肢が広がり、家族が無理なく支える体制をつくることにつながります。
民間保険と貯蓄、どちらで介護費用に備えるべきか
介護費用は「発生するかどうか分からないが、一度発生すると負担が大きい」典型的なリスクです。
十分な貯蓄がある家庭は保険に頼らない選択も可能な一方、貯蓄が少ない、あるいは将来の収入に不安がある家庭は、保険でリスク分散する方が安心です。
「我が家の場合、どちらが安心につながるか」を見極めることが大切です。

まとめ:民間保険・公的制度・在宅介護のコストを整理
介護費用は平均543万円。施設利用になれば年間200〜300万円の負担もあり得ます。公的介護保険は最低限を支える制度に過ぎず、希望する介護を実現するには自己資金や民間保険が欠かせません。
専用タイプ・特約タイプ・終身型、それぞれの特徴を理解し、自分のライフプランに合った備えを考えていくのが大事です。介護のお金の備えは「正解が一つ」ではありません。
在宅か施設か、家族の関わり方、どのくらいの生活水準を望むかによって必要資金は変わります。だからこそ、まずは家族で「どんな介護を望むか」を話し合うことが一番の備えです。そのうえで、公的保険+自己資金+民間保険をバランスよく組み合わせれば、安心はぐっと高まるでしょう。
次回のテーマは、「介護の度合いによって、かかる費用はどのくらい変わるの?」です。
要介護度によって、どれくらい負担として変わってくるのでしょうか。介護度合い別にみていきたいと思います。
要介護度によって、どれくらい負担として変わってくるのでしょうか。介護度合い別にみていきたいと思います。
FAQ:在宅介護はいくらかかる?保険と制度の疑問解消
— Q1. 在宅介護には月にどれくらい費用がかかりますか?
A. 利用サービスや要介護度によりますが、一般的には月額で 約4.8〜5.0万円程度(介護サービス費+消耗品・光熱費など含めて)という目安がよく挙げられています。
— Q2. 在宅介護で発生する初期費用(住宅改修・福祉用具など)はどれほどですか?
A. 初期費用として、住宅のバリアフリー改修や手すり、スロープ設置、介護用ベッド・車椅子などを整える場合、数十万円〜70万円前後になるケースもあります(平均的な目安では 74万円などの数字も報じられています)
— Q3. 民間の介護保険は本当に必要ですか?公的保険で足りますか?
A. 民間保険は、公的介護保険でカバーできない「足りない部分」や「上乗せ保障」を補う役割があります。公的制度には給付の上限や自己負担がありますので、将来のリスクに備えて 民間保険 を併用する人も増えています。
— Q4. 公的介護保険と民間介護保険の給付の違いは何ですか?
A. 公的介護保険は法律によって定められた給付制度で、要介護状態の認定に応じてサービス利用料の一部を支援する仕組みです。一方、民間介護保険は保険会社との契約に基づき、死亡・要介護・入院などの条件で給付金が支払われるタイプや年金支払い型など、多様な商品があります。給付条件、金額、支払い期間・保険料の違いがポイントです。
— Q5. 介護費用を保険ではなく貯蓄で賄うのは現実的でしょうか?
A. 貯蓄で備えることも可能ですが、数年に渡る介護費用を前もって蓄えておくには相当な金額が必要です。保険を利用すれば、少ない保険料で将来のリスクを分散できる利点があります。多くの方は「保険+貯蓄」の併用戦略を取るケースが多いです。
関連リンク:
執筆:

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。