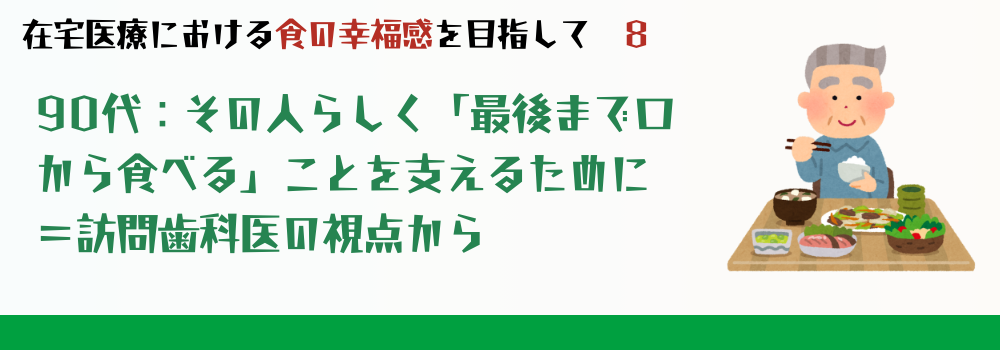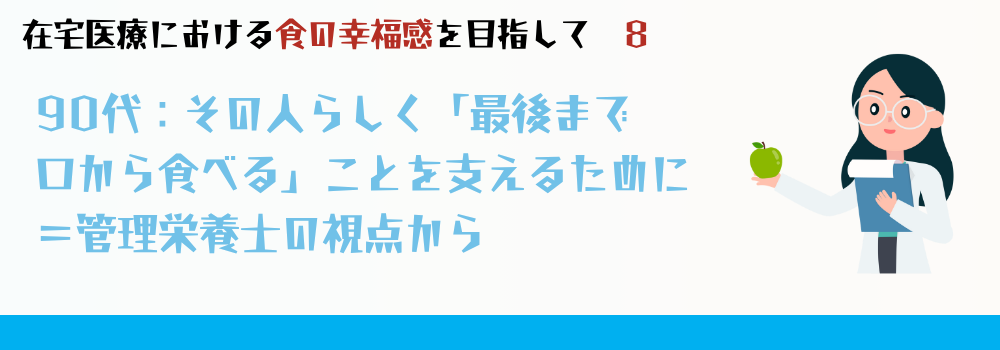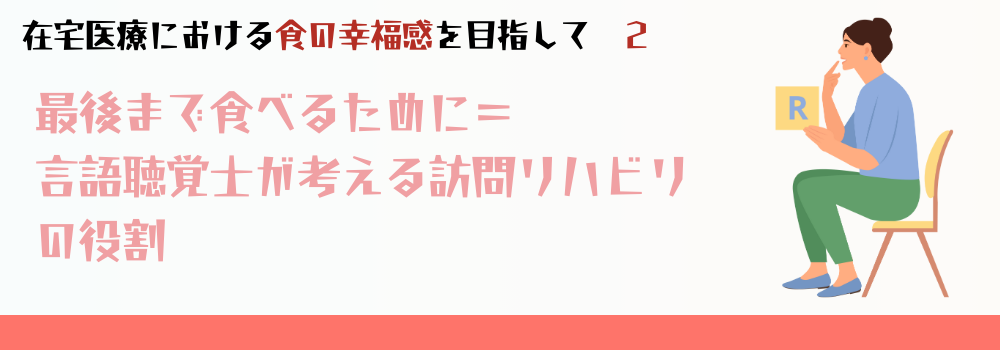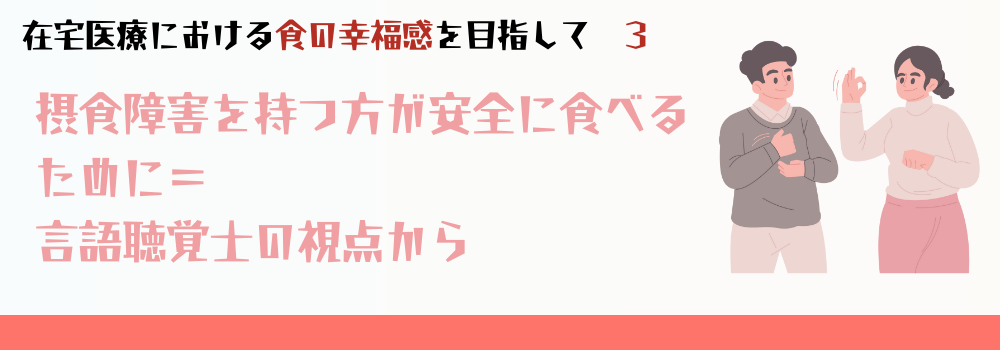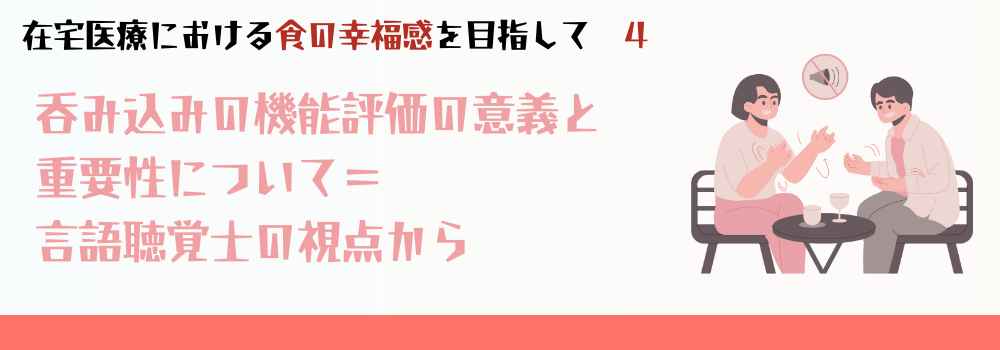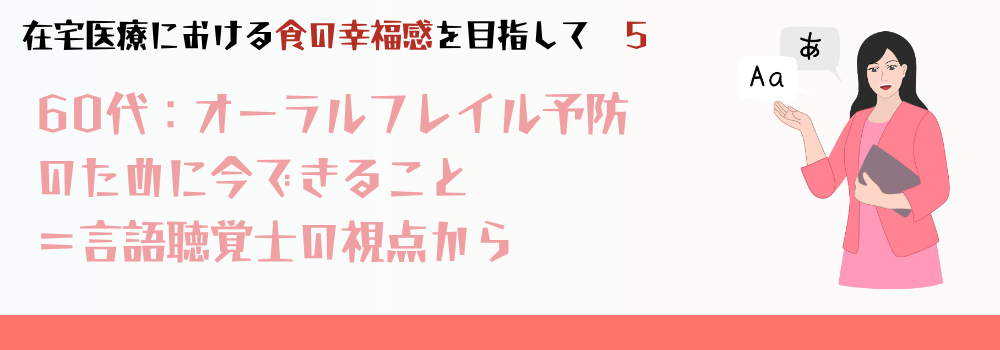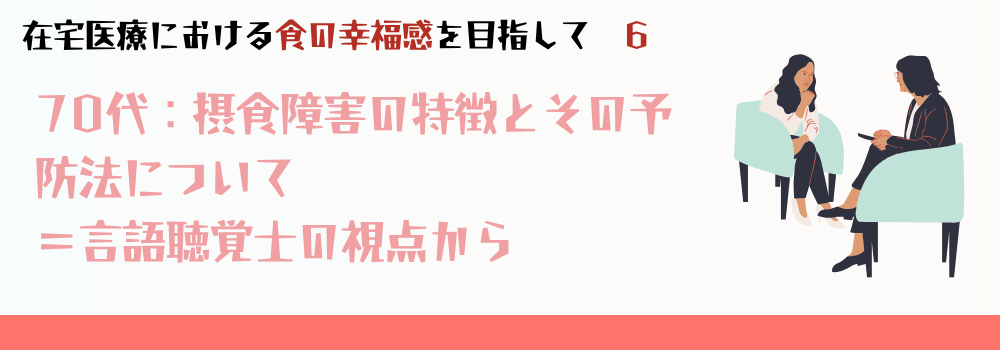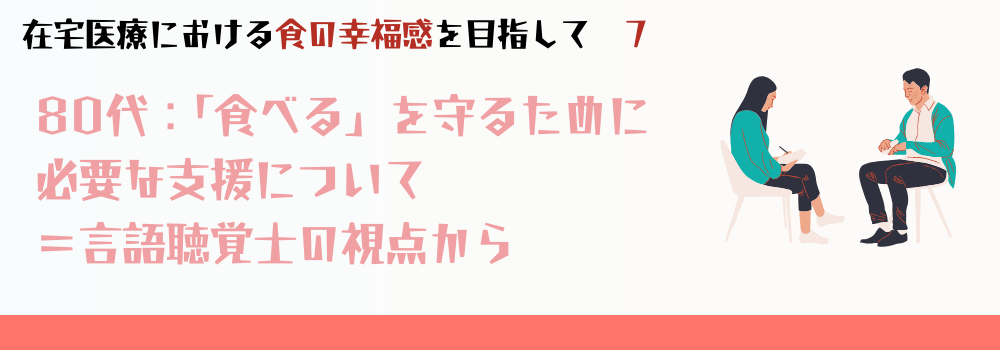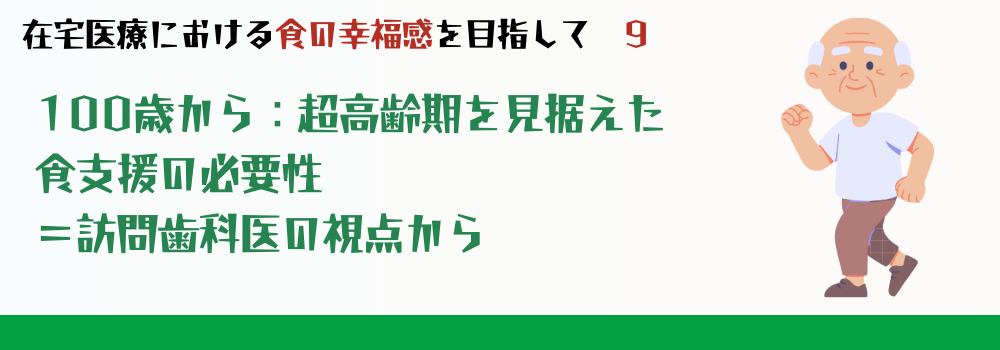【言語聴覚士執筆】90代の嚥下障害を支える言語聴覚士の役割|在宅で「最後まで口から食べる」ために 最終更新日:2025/11/26
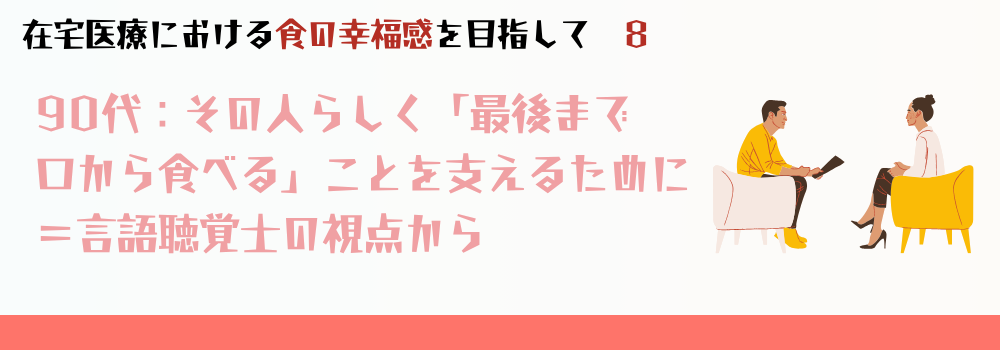
90代で増える摂食嚥下障害。その背景には筋力低下や認知機能の変化など、複数の要因が関わっています。本記事では言語聴覚士の視点から、在宅で「最後まで口から食べる」ための支援方法、評価のポイント、多職種連携の実践について詳しく解説します。
はじめに──90代の嚥下障害と「食べる幸福」を支える意義
90代という⻑い人生を歩んできたからこそ、「食べること」には栄養以上の意味が宿ります。 それは記憶であり、尊厳であり、人とのつながりを実感する時間でもあります。
しかし、この年代における摂食嚥下障害は、身体機能や心理的な面で⼤きな影響を及ぼし、最期まで「口から食べる」ことを支えるには、多面的な視点と丁寧な対応が求められます。
本稿では、90代に多くみられる摂食嚥下障害の特徴、言語聴覚士としての関わり、看取り期の支援、多職種連携、そして⼀つのモデル事例を通して、支援のあり方を整理します。

90代に多い摂食嚥下障害の特徴と原因
90代では、加齢による機能低下が⻑年蓄積された結果として、複数の摂食嚥下に関する問題が同時に現れやすくなります。以下に挙げるような要因が重なり合い、⼀人ひとりに異なる形で影響を及ぼします。
・筋力低下:⾆や喉頭、咽頭、頬筋といった嚥下に関わる筋群の筋力が全般的に低下し、咀嚼、食塊の送り込み、喉頭の挙上・閉鎖が不⼗分になることで、誤嚥や食べこぼしが生じやすくなります。また、咀嚼から嚥下への移行がスムーズにいかないことで、食事での疲労感を訴えることも少なくありません。
・サルコペニア:加齢による筋肉量の減少は、単に嚥下器官に限らず、体幹や四肢の安定性にも影響します。その結果、適切な姿勢を保持できず、姿勢が崩れることで嚥下時の安全性が損なわれるケースが多くみられます。⻑時間座ることが困難で、途中で食事を中断せざるを得ない方もいます。
・慢性疾患の影響:高齢者に多くみられる心疾患、脳血管障害、糖尿病、パーキンソン病などの基礎疾患は、神経や筋機能の障害を通じて嚥下動作に直接的・間接的な影響を及ぼします。たとえば脳血管障害後では、左右差のある咽頭収縮や感覚低下が背景にあることもあり、個別の評価と対応が必要となります。
・認知機能の低下:認知症の進行により、食事の手順や食べるという行為そのものがわからなくなるケースがあります。また、注意・集中の維持が難しく、口に物が入っていても飲み込まずに口腔内に⻑く溜めてしまうこともあります。食事の途中で立ち上がってしまう、食事に対して無関心な様子が見られる場合もあります。
・心理的側面:加齢に伴う繰り返しの誤嚥体験や、体調の波によって「食べること」への不安感が強まる方も少なくありません。「またむせたらどうしよう」「家族に迷惑をかけたくない」といった気持ちが先行し、意欲の低下や拒食傾向につながることもあります。
このように、90代の摂食嚥下障害は、身体・認知・心理の複数の側面が複雑に絡み合うことで、その日の状態や周囲の環境によって食行動が⼤きく左右される特徴があります。
そのため、日々の食支援においては⼀律の対応ではなく、個々の背景に応じた柔軟で多面的な支援が求められます。

言語聴覚士が行う嚥下評価と支援の実際
90代の方に対して言語聴覚士が行う支援は、単なる機能訓練だけでは不⼗分です。評価・助言・環境調整を含めて、生活そのものに寄り添う関わりが求められます。
・姿勢評価・調整:わずかな角度調整や足台の使用が嚥下動作に影響するため、座位の安定性を確保します。
・嚥下機能の評価:嚥下内視鏡検査(VE)や嚥下造影検査(VF)などの直接的評価が難しい在宅や施設の現場では、湿性嗄声、咳、嚥下後の残留感などの間接的な所見についても丁寧に観察し、変化を見逃さないようにします。
・食前の準備:唾液腺マッサージ、口腔内のケア、嚥下体操などで口腔・咽頭の感覚と意識を整えることで、嚥下反応を引き出しやすくします。
・食形態の調整:ムース食やゼリー食だけでなく、本人が「食べたい」と感じられる味・香り・温度の⼯夫が必要です。
・声かけ・環境設定:テレビを消す、周囲の物音を減らすなど、静かで落ち着いた環境づくりが基本です。加えてご本人が安心できる声かけや、場合によっては心地よい音楽を流すなど、過ごしやすい環境を整えることが支援に繋がります。
看取り期における“口から食べる”ための支援方法
状態が進行し、飲み込む力が限界に近づいたとき、医療的な判断とともに、「その人らしさ」をどう支えるかが問われます。
・食べない日があってもよい:体調が悪い日や意欲がない日は、無理に食べさせる必要はない。
・“完食”を目標にしない:数口でも、ご本人が納得して食べたならそれでよい。
・スプーン提⽰のみの支援:香りを感じる、口元に運ぶだけの時間も「食べること」に含まれる。
・ご本人の言葉・しぐさを尊重:わずかな表情や仕草から、「もう少し食べたい」「今日はやめておきたい」を読み取る。
この時期は、「どれだけ食べてもらえたか」よりも、「どのようにその時間をともに過ごしたか」が問われます。ご本人の⼩さな変化や、ご家族の揺れる気持ちにも丁寧に目を向けながら、言語聴覚士として「食事摂取量」ではなく、「そのひとときをどう支えたか」に重きを置いて関わっていきます。

事例紹介:94歳女性Aさんに学ぶ在宅での食支援
・プロフィール:軽度の認知症と脳梗塞の既往があり、要介護3。日中はリクライニングチェアで過ごし、訪問看護・歯科・リハビリを併用。会話の反応や食事の意欲に日々波がある。
・座位と環境の調整:食事中はクッションと足台で姿勢を整え、周囲を静かにしテレビを消すなど、集中できる環境を整えた。
・食前準備の⼯夫:食事前には唾液腺マッサージと口腔ケア、嚥下体操、声かけを行い、口腔嚥下器官への感覚刺激と嚥下への注意を促した
・食形態と嗜好への配慮:普段はムース食を基本としつつ、本人が好んでいた甘い系のメニューを中心に構成。食べる量より「食べたい気持ち」を優先。
・意欲が乏しいときの対応:食べたくない様子の日は、食事を無理に勧めず、味噌汁の香りを嗅いでもらうなど、食体験を香りや会話の時間として捉え直す支援を試みた。
実際に食べられた日よりも、「今日はいい匂いだったね」と穏やかに笑われたAさんの姿からは、たとえ経口摂取に⾄らなかったとしても、香りやその場の雰囲気が食への関心や情緒的な充足感につながっていることがうかがえました。
言語聴覚士としては、「食べる」という行為を摂取量だけで評価するのではなく、感覚刺激や心理的な満足感も含めて支援の⼀環と捉えることの重要性を再認識しました。
多職種連携で守る「食べる喜び」と安全なケア
90代の食支援は言語聴覚士だけで行うことは難しいです。
・歯科医師:義歯調整、口腔衛生管理、嚥下評価
・看護師:全身状態の変化、脱⽔や感染の早期察知
・栄養士:本人の嗜好と嚥下レベルに応じた食事設計
・介護職・家族:日々の観察や気づき、精神面の支え
言語聴覚士は、嚥下や食事場面における⼩さな変化を見逃さず、他職種と連携しながら支援内容を適宜調整していきます。
おわりに──その人らしい“ひとくち”を支えるために
90代の摂食嚥下障害を支えるということは、機能の維持や回復を第⼀に求めるのではなく、今このとき、その方にとって⼤切な⼀口をどのように守り、支えていけるかを問い続ける営みだと感じています。食べられた⼀口にも、食べなかった時間にも、それぞれに意味があり、価値があります。
ご本人の表情や言葉、ご家族の思いに静かに寄り添いながら、その時間が穏やかに重なっていくよう、これからも丁寧に関わっていきたいと思います。
90代の食支援・在宅ケア相談室
Q1. 90代ではどのような嚥下障害が多いですか?
A. 90代では、舌や喉の筋肉が弱まり、飲み込みの反射が遅れることで誤嚥しやすくなります。加齢による筋力低下やサルコペニアに加え、脳血管障害・パーキンソン病などの疾患、義歯の不適合、姿勢保持の難しさも影響します。さらに、認知症による判断力低下や「むせるのが怖い」という心理的要因も食欲を減退させる要素です。これらが重なり、口から食べることを諦めてしまう方もいますが、正しい支援によって再び安心して食事を楽しめるケースも多くあります。
Q2. 言語聴覚士はどんなサポートをしてくれますか?
A. 言語聴覚士は、嚥下機能を評価し、飲み込みやすい姿勢や食形態を整える専門家です。例えば、椅子の高さや顎の角度を調整したり、口腔マッサージや嚥下体操で筋力を維持したりします。食事中は静かな環境をつくり、焦らず食べられるよう声かけを行うことも大切です。また、家族へのアドバイスを通じて「安全に、楽しく食べる」時間を支えます。誤嚥を防ぐだけでなく、“食べる喜び”を守ることがSTの役割です。
Q3. 嚥下訓練はどのくらい効果がありますか?
A. 嚥下訓練は、継続すれば高齢者でも改善や維持が見込めます。訓練内容は、嚥下体操や姿勢調整、食形態の工夫など多岐にわたります。大切なのは、専門職が実施する訓練に加え、日常生活の中で安全に食べられる環境を維持することです。家族や介護者が正しい方法を継続することで、誤嚥や食事中の疲労を防ぎ、口から食べる期間を延ばすことができます。環境・習慣・意欲の三要素を整えることが成果を左右します。
Q4. 看取り期でも「口から食べる」ことは可能ですか?
A. 看取り期でも、嚥下機能や体調に配慮すれば、少量でも「口から食べる」ことは可能です。無理に栄養を摂るよりも、本人が望む味や温度、香りを楽しむことを優先します。医療職と相談しながら、ゼリー状やとろみ食など安全な形態を選び、“食べる行為”を本人の満足や尊厳として支えることが大切です。たとえ一口でも、味覚や感情を呼び起こす「生きる時間」としての価値があります。
Q5. 家族として何を意識すればよいですか?
A. 家族は「食べる時間を穏やかに過ごす」ことを意識しましょう。食事中は静かな環境を整え、姿勢を安定させる工夫が誤嚥を防ぎます。疲れやむせが出た場合は無理せず休憩を入れることも大切です。また、訪問リハビリや栄養士と連携し、日々の変化を共有するとより安全な支援につながります。介護を抱え込まず、専門職と協力して“安心して食べられる時間”を一緒に守ることが理想的です。
関連リンク:
執筆:

國谷侑岐(くにたにゆうき)
言語聴覚士
経歴:
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
資格:
言語聴覚士
言語聴覚士