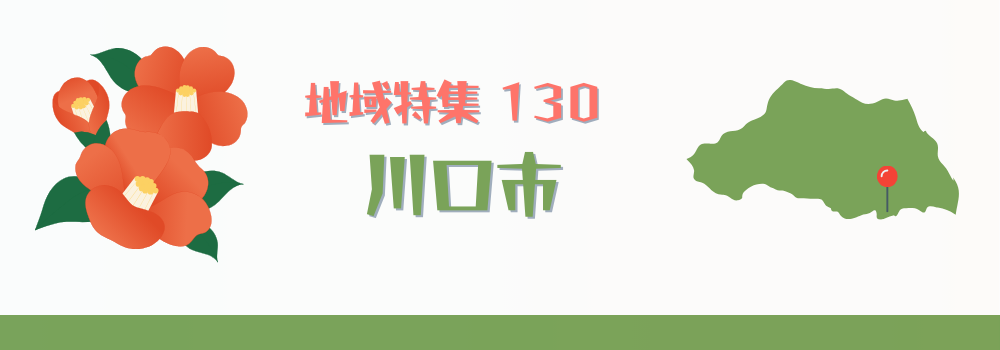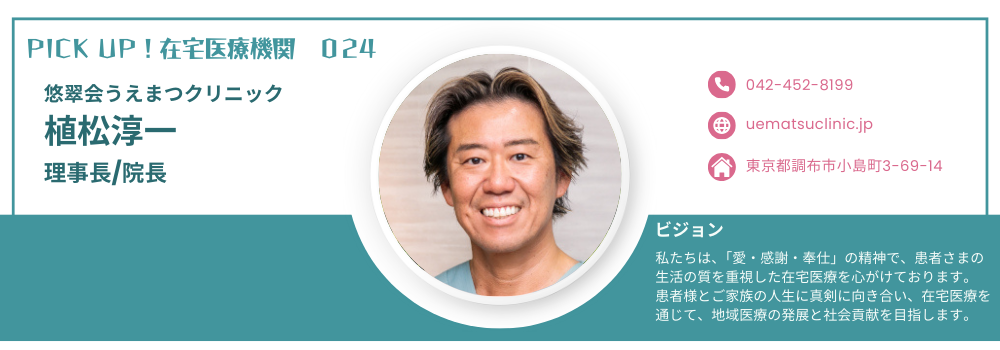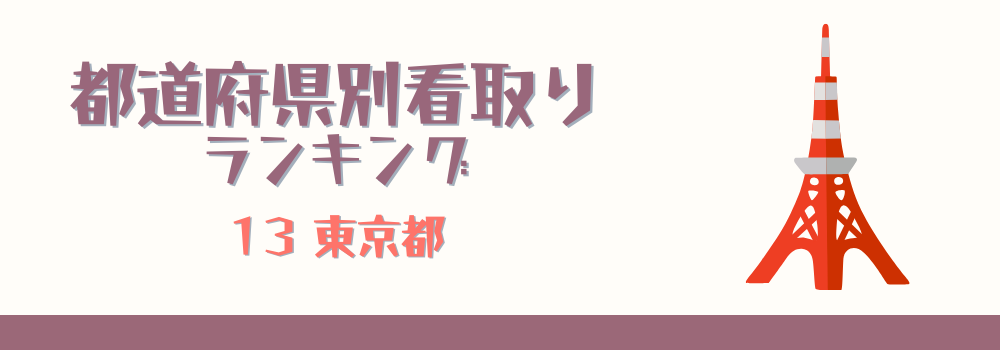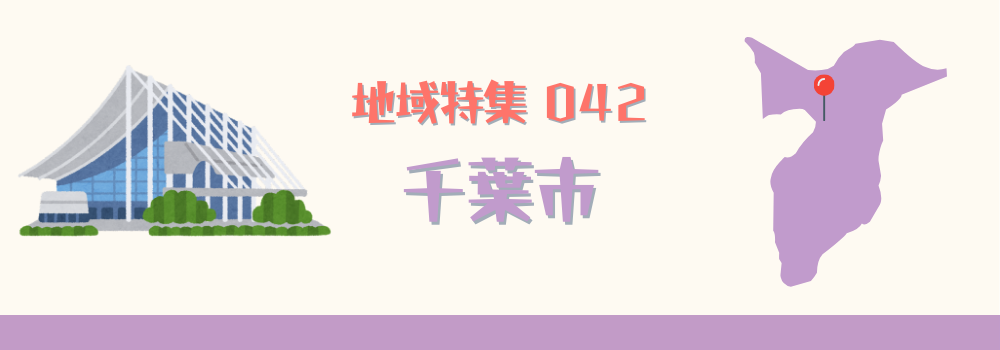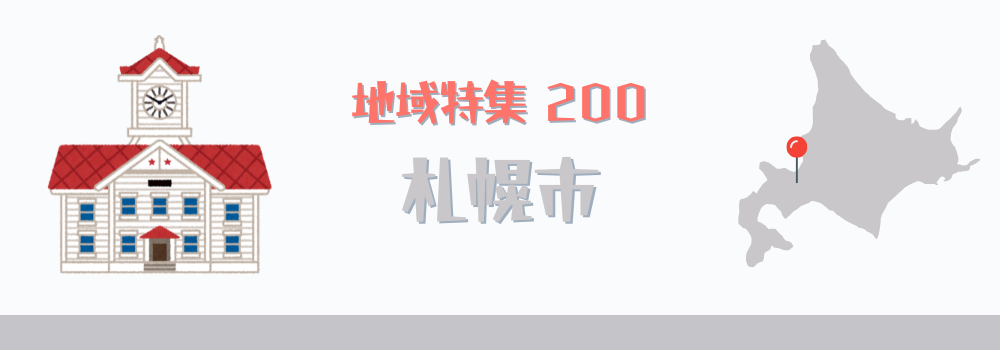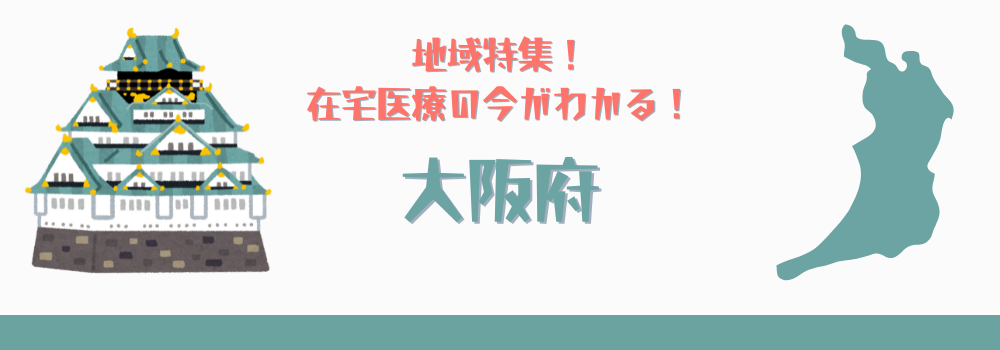【PICK UP!在宅医療機関 015】医療法人 真成会 屋宜亮兵理事長 最終更新日:2025/03/04

注目の在宅医療機関へのインタビュー取材「PICK UP!在宅医療機関」の第15回目は沖縄県那覇市にて「医療法人 真成会」を運営されている屋宜亮兵理事長です。医療法人 真成会の特長、患者さんや訪問診療にかける思いを熱く語っていただきました。
地元沖縄に貢献したいという思いから医師を志す
— 医師を目指されたきっかけについて教えてください。
地元である沖縄県に貢献するような仕事をしたいと思ったことが、一番の動機です。沖縄が大好きなんです。中学生の時、進学のために一度県外で暮らしたことがあるのですが、やっぱり沖縄が自分にとって住みやすい場所だなと感じまして。将来は沖縄で働いて、地元の役に立てたらいいなと思い、医師を目指しました。

— 医師になられてからは一旦、救急の分野へ進まれたのですね。
はい。沖縄県立南部医療センターで、救急専従医として勤務しました。救急科であれば様々な経験が積めると思ったのです。それは思った通りで、搬送されてきた患者さんを一番に診るのは救急科であり、どんな患者さんでも初期治療は救急科がやるといった感じでした。夜勤も多くて大変でしたが、こちらでの経験が医師としての力をつけてくれたと思っています。
救急医療の現場で在宅医療の必要性を感じた
— 救急医療の現場での経験が、今に生きているんですね。訪問診療に興味を持ったのも、この時でしょうか。
この頃はまだ、訪問診療の制度について詳しくは知らなかったです。ただ、患者さんを最初から最後まで診てあげたいという思いは、初期研修医の頃からありました。救急医療で携わるのは初期治療の段階だけだったので、患者さんのその後はカルテで追うぐらいしかできなかったんです。
また、医師がもっと外に出て行くべきだということも感じていました。救急の現場では、かなり症状が悪化した状態の患者さんを診ることも少なくありませんでした。例えば、重度の精神疾患の方を病院に連れて行くとなると、家族の負担が大きいため、ギリギリの状況まで我慢してしまう場合が多いんですね。
病院に行きたいけれど、いろいろな事情で行けない人がいる。そういったところに手を差しのべていく必要があるのではないかと感じていました。
転機となったのが、浦添総合病院への転職でした。転職時に、訪問診療をやってみたいということを病院に伝えると、「救急の仕事に支障が出なければ、やってもいいよ」と言ってもらえました。さらに、浦添総合病院には、実際に訪問診療を行っている先生がいたんです。その先生に色々と教えてもらいながら、訪問診療のキャリアをスタートさせました。
ただ、最初から訪問診療をメインでやっていこうと思っていたわけではないです。あくまでもメインはプレホスピタル・救急・集中治療でした。当時は、自宅まで診に来てほしい患者さんがいれば、訪問診療をするというスタイルでやっていこうと思っていました。

訪問診療所の立ち上げ、奔走する日々
— そうなんですね。その後、訪問診療をメインでやっていこうという思いになったのは、なぜですか。
医師である友人がとある理由で急性期病院で働くことが難しくなってしまいまして、何とかしてその友人が医師として働き続けられるようにしてあげたいと思い、訪問診療だったらできるかもしれないということで、このゆずりは訪問診療所を立ち上げたんです。

— 立ち上げのきっかけは、ご友人だったのですね。それが今となっては先生の専門になったということですか。
友人のためというのもありましたが、ちょうど私自身も訪問診療の必要性を感じていたところだったので、診療所の開設は本望ではありました。
患者さんに「今後の治療どうしたいですか」と尋ねた時に、「家でできるなら、家がいい」という患者さんは多くいました。でも、当時は訪問診療もそこまで普及していなかったので、在宅医療を望んでいる患者さんも、病院に搬送されてしまうという現状がありました。私には、そのような状況を変えたいという思いがあったんです。
— 診療所を立ち上げられた当時の状況について、聞かせていただけますか。
すごく大変でした。私がたった一人で開設したようなものなので、最初の頃は電話対応なども全部自分で行っていました。立ち上げから1か月ぐらい経過後に事務員さんが来てくれて、訪問診療や在宅医療の点数やレセプトについても、事務員さんと一緒に一から勉強しました。そのようにして徐々に体制ができていった感じでした。
でも、本当に24時間365日休みなく働いていたので、寝る時間も食べる時間も正直足りていなかったです。当時の私を知る人に聞くと、「どんどん痩せていくから心配だった」と言うんですよ。自分では全然気がつかなかったんですけどね。今思えば、相当業務にのめり込んでいたんだと思います。
— 今は組織の基盤などもしっかり出来上がっている状態でしょうか。
そうですね。組織としてはだいぶ形になってきたかなと思います。ただ、最初の頃は組織づくりについても試行錯誤していました。私、何でも自分でやってしまう性分なんですよ。スタッフには定時の17時半で帰宅してもらって、自分は21時ぐらいまで働いてそのままオンコールに突入ということをしばらくやっていました。
これは少し違うなと思いまして。もちろんスタッフのことは第一に考えています。でも、トップの私だけが何でも引き受けて、個人プレーみたいになってしまうのは、組織のあり方としてどうなのかなと、疑問に思うようになりました。そこから少しずつ体制を整えていき、今ではスタッフに安心して現場を任せられるようになっています。

地域医療において患者さんをトータルで支援
— 「切れ目のない医療」というワードをホームページなどにも掲げられていますが、その思いへ至った経緯について聞かせてください。
私たちの法人では、訪問診療と訪問看護だけでなく、定期巡回や介護支援の事業も行っています。これは、患者さんを医療以外の分野からもトータルでサポートしていきたい、切れ目のない支援をしていきたいという思いから始めたことです。多職種で連携することで、患者さんの生活全般を見守っていくことを目指しています。
特に介護分野における定期巡回を実施していることは、私たち法人の特色の一つでもあります。訪問介護には利用間隔や利用時間に制限があります。一方、定期巡回の場合はそのような制限がないので、夜間対応など、利用者さんに合わせた柔軟なサービスの提供が可能となっています。

また、患者さんをトータルでサポートするという意味では、できる限り病院と同じレベルの医療を提供できるよう心がけています。ただ、「在宅医療って何ができるの?」と聞かれることも時々あります。在宅輸血や腹膜透析などにも対応していますし、多分皆さんが想像している以上に色々なことを行っていると思います。
他にも、骨密度測定を実施して、骨粗しょう症の早期治療に繋げていく取り組みなどもやっています。今後は歯科医と連携して、食に関する支援も実施していく予定です。在宅医療の枠組みにとらわれず、地域の方々のために色々なことをやっていきたいですね。
— 色々な取り組みをされていることで、在宅医療へのイメージも変わっていきそうですね。先生は、在宅医療の「セカンドキャリア」というイメージも刷新していきたいということでしたね。
はい。‟訪問診療はお医者さんのセカンドキャリア”といった世間のイメージを変えていきたいという思いがありました。今や訪問診療は、地域医療を支える重要な基盤となる分野となってきましたが、私たちの活動を通じて、人々の在宅医療への関心がもっと高まっていけばいいなと思いますね。
幅広い診療地域と診療科目
— 地域医療を支えるという点で、診療地域はどの辺りをカバーされているのでしょうか。
診療所から16㎞という制度の範囲内であれば、基本的には遠くの患者さんも診に行きます。わざわざ遠い所からでも私たちに依頼してくれるということは、私たちでないといけないそれなりの理由があってのことだと思うので。患者さんの希望にはできるだけ応えてあげたいと思っています。

— ひと月にどのくらいの患者さんを診られているのでしょうか。
約600名の患者さんを診療しています。私たちの法人の特徴として、施設の患者さんを多く診ているという点も挙げられると思います。施設に関しては、以前は診療報酬の関係で「1つの施設につき何名まで」といった制限を設けていましたが、施設側から、訪問診療の受け入れ先がなくて困っているという声があったんです。そこで、現在は人数に制限を設けずに診療させていただいています。
— 多くの患者さんを診られていますが、医師はどのくらいいらっしゃるんですか。また、診療科目はどのような感じでしょうか。
常勤の医師が6名、非常勤の医師が19名という体制でやっています。診療科目は一般内科から循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、神経内科など全部で15の診療科目に対応しています。
基本的に診れない疾患はないという姿勢で診療をさせていただいています。特殊な症例の場合は、病院と連携しながらできる限り対応できるよう努めています。
— 診療において重視されている指標(KPI)などはありますか。
具体的な数値目標を持っているわけではないですが、定期訪問と往診の比率については意識するようにしています。突発的な往診が増えるということは、日頃の診療で患者さんの症状をコントロールできていないということだと思いますが、それをできるだけ少ない定期訪問でコントロールできているかどうかは、質の高い医療を提供できているかどうかの指標だと考えています。
ただ、私たちが一番重視していることは、いかに患者さんの想いを汲み取れているかどうかですね。患者さんの意思を尊重し、時にはご家族やケアマネさんとの間に入って、調整役をしたりもする。そういったところが一番大事なのではないでしょうか。

在宅医療で地域のために尽力したい
— 今後、先生が目指されている在宅医療の姿はどのようなものでしょうか。
在宅医療を通じて、地域の課題を解決していけたらと思っています。「地域のために」というのは、私たちの企業理念の一つでもあります。
昨今、国の政策として急性期医療の適正化が推し進められていますが、その結果、地域医療において重要な要素である急性期医療が縮小している状況です。私たちは、地域医療において足りない部分をカバーしていく存在でありたいと思っています。
病院での治療、在宅での治療、どちらを選ぶかは患者さんの意思によりますが、その前提となる選択肢を広げることが、私たちの役目だと考えています。

— より良い在宅医療を実現していくためには、何が必要だと思われますか。
在宅医療に関わる医師やスタッフが、患者さんのためを想って働いていくことではないでしょうか。地域に貢献することが、在宅医療の真の目的ですから。地域のため、患者さんのためを思って動ける人材が必要とされていると思いますし、今後もそういった熱意のある仲間が増えていけばいいなと思います。
— 最後に、地域住民の方へのメッセージをお願いします。
私たちは医療、看護、介護などを通じて、地域の方々の生活をより良くしていきたいという思いで、日々活動しています。何か困りごとや課題があれば、いつでも気軽にお声がけください。
また、健康に関するイベントや健康相談、地域住民の方同士が交流できるような行事なども随時開催しています。地域の皆さんで集まって、楽しい時間を過ごしていけたらと思いながらやっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。

医療法人 真成会

〒903-0815
沖縄県那覇市首里金城町三丁目32番地
TEL:098-885-7001/FAX:098-885-7002
・ゆずりは訪問診療所
・ゆずりは訪問看護ステーション
・まつりか定期巡回ステーション
・ひまわり居宅介護支援センター
沖縄県那覇市首里金城町三丁目32番地
TEL:098-885-7001/FAX:098-885-7002
・ゆずりは訪問診療所
・ゆずりは訪問看護ステーション
・まつりか定期巡回ステーション
・ひまわり居宅介護支援センター
屋宜亮兵理事長のプロフィール
経歴:
2006年 国立大学法人 琉球大学 医学部医学科 卒業
2006年 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 臨床研修
2008年 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 救急専従医
2012年 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 救急総合診療部
2016年 ゆずりは訪問診療所 開設
2018年 医療法人真成会 理事長就任
2022年 医療法人育泉会 理事長就任
2006年 国立大学法人 琉球大学 医学部医学科 卒業
2006年 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 臨床研修
2008年 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 救急専従医
2012年 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 救急総合診療部
2016年 ゆずりは訪問診療所 開設
2018年 医療法人真成会 理事長就任
2022年 医療法人育泉会 理事長就任
資格・役職等:
日本救急医学会 救急専門医
日本内科学会 認定内科医
日本在宅医療連合学会 在宅医療専門医・認定指導医
日本救急医学会 救急専門医
日本内科学会 認定内科医
日本在宅医療連合学会 在宅医療専門医・認定指導医
関連リンク: