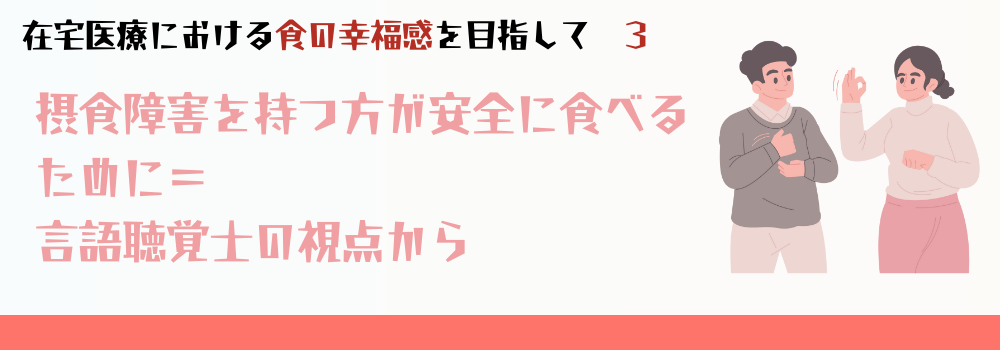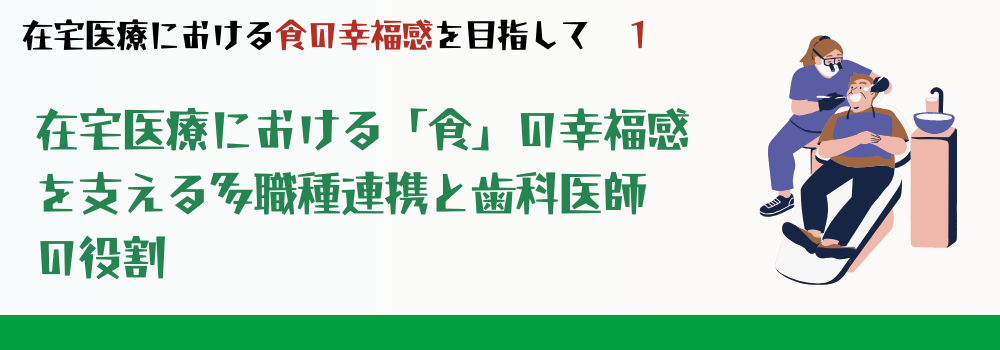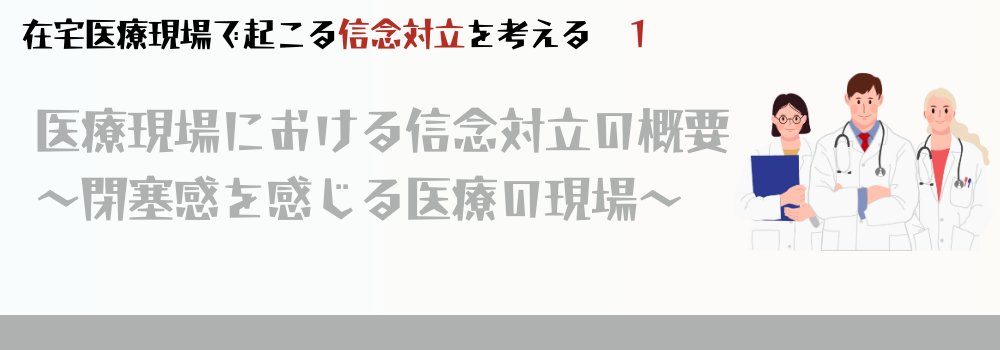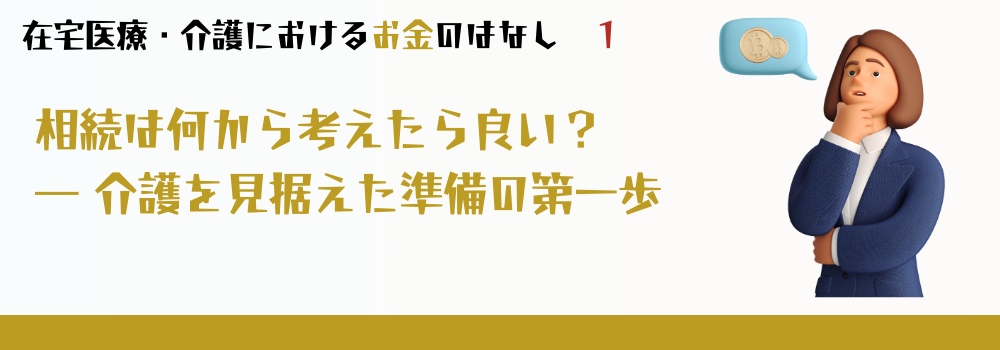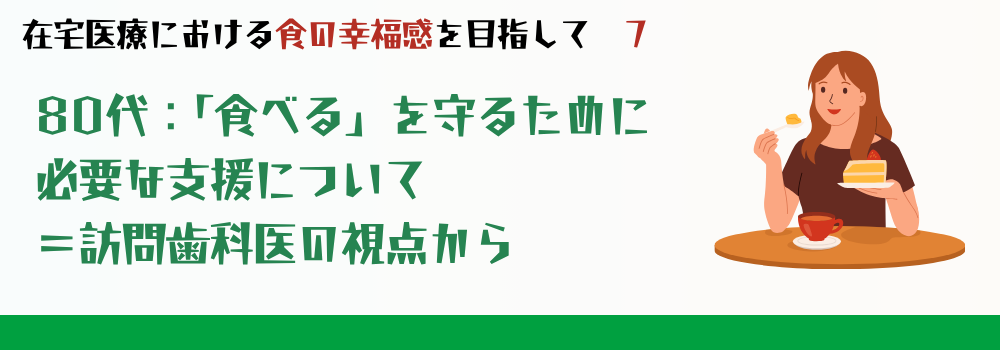摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために=訪問歯科医の視点から 最終更新日:2025/03/20

「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
3つ目のテーマとして「摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
3つ目のテーマとして「摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
はじめに
一般に摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるためにはポイントがいくつかあります。
1. 食事環境の工夫
2. 食事内容の工夫
3. 食べる動作の補助
4. 誤嚥を防ぐために行う対処法
以上の項目を常に嚥下機能、運動機能の評価を行い得られたアセスメントを基にした個別の配慮や援助が重要です。
認知症の方が食事を楽しむための注意点と工夫
認知症の方が食事を楽しむためには、摂食嚥下(せっしょくえんげ)障害の有無や進行具合に応じた工夫が必要です。以下のようなポイントを押さえることで、安全で楽しい食事を支援できます。

1. 食事環境の工夫
・落ち着いた環境を整える
テレビや大きな音を避け、食事に集中できるようにする。
テレビや大きな音を避け、食事に集中できるようにする。
・視認しやすい食器を使用
白い皿にカラフルな料理を盛るなど、視認しやすい配色にする。
白い皿にカラフルな料理を盛るなど、視認しやすい配色にする。
・食事のリズムを守る
毎日同じ時間・同じ場所で食事をとる習慣をつける。
毎日同じ時間・同じ場所で食事をとる習慣をつける。
2. 食事内容の工夫
・食べやすい形態にする
嚥下機能に合わせて「きざみ食」「ペースト食」「ソフト食」などを選択。
嚥下機能に合わせて「きざみ食」「ペースト食」「ソフト食」などを選択。
・適度な水分を含ませる
ぱさつく食品はとろみをつけたり、汁物を活用する。
ぱさつく食品はとろみをつけたり、汁物を活用する。
・温度・香りを活かす
温かさや香りを意識し、食欲を刺激する。
温かさや香りを意識し、食欲を刺激する。

3. 食べる動作を助ける
・一口量を意識する
スプーンの大きさを調整し、適量をとれるようにする。
スプーンの大きさを調整し、適量をとれるようにする。
・ゆっくり食べるよう促す
急がせず、嚥下を確認しながら進める。
急がせず、嚥下を確認しながら進める。
・声かけと視線の工夫
正面から優しく話しかけ、「一緒に食べる」ことで安心感を与える。
正面から優しく話しかけ、「一緒に食べる」ことで安心感を与える。
4. 誤嚥(ごえん)を防ぐための注意点
・姿勢を整える
椅子に座り、背筋を伸ばして食べるのが理想的(嚥下しやすい姿勢)。
椅子に座り、背筋を伸ばして食べるのが理想的(嚥下しやすい姿勢)。
・食後もすぐに横にならない
30分程度は上半身を起こしておく。
30分程度は上半身を起こしておく。
・「むせ」や「食べ残し」をチェック
口腔ケアを徹底し、食後の残留物を確認する。
口腔ケアを徹底し、食後の残留物を確認する。
5. 「食べる楽しみ」を維持する
・好きな食べ物を取り入れる
本人の好みを尊重し、可能な範囲で食べられる形態に工夫。
本人の好みを尊重し、可能な範囲で食べられる形態に工夫。
・食事を楽しい時間にする
家族や介護者と会話をしながら、安心できる雰囲気を作る。
家族や介護者と会話をしながら、安心できる雰囲気を作る。
・五感を刺激する
見た目や香り、食感を大切にし、「食べたい」と思わせる工夫をする。
見た目や香り、食感を大切にし、「食べたい」と思わせる工夫をする。
まとめ
認知症の方にとって「食事」は生活の大切な一部です。ただ栄養を摂るだけでなく、「楽しみ」や「安心感」を提供することが重要です。そのために、環境づくり・食事形態・食べる動作のサポートを総合的に考えることが必要です。
食べる喜びを保ちながら、安全に食事ができるよう、ぜひ工夫してみてください!
食べる喜びを保ちながら、安全に食事ができるよう、ぜひ工夫してみてください!
医療的ケア児が食事を楽しむための注意点と工夫
医療的ケア児(人工呼吸器装着、経管栄養、気管切開、嚥下障害などを抱えるお子さん)が食事を楽しむためには、安全を最優先しつつ、「食べる喜び」を感じられる工夫が必要です。
1. 食事環境の工夫
・落ち着いた空間を作る
音や光の刺激を調整し、リラックスできる環境を整える。
音や光の刺激を調整し、リラックスできる環境を整える。
・姿勢の工夫
嚥下しやすい姿勢(基本は背筋を伸ばし、やや前傾)を確保する。
胃食道逆流を防ぐため、食後30分は上半身を起こしておく。
嚥下しやすい姿勢(基本は背筋を伸ばし、やや前傾)を確保する。
胃食道逆流を防ぐため、食後30分は上半身を起こしておく。
・食事時間をゆったり確保
急がせず、一口ごとに嚥下を確認しながら進める。
急がせず、一口ごとに嚥下を確認しながら進める。

2. 食事内容の工夫
・嚥下機能に応じた形態に調整
「きざみ食」「ミキサー食」「ゼリー状」「とろみ付き液体」など、医療チームと相談しながら選択。
「きざみ食」「ミキサー食」「ゼリー状」「とろみ付き液体」など、医療チームと相談しながら選択。
・水分管理を徹底
とろみをつける、ジェル状にするなどして誤嚥を防ぐ。
とろみをつける、ジェル状にするなどして誤嚥を防ぐ。
・温度や香りを意識
適温にすることで食欲を刺激し、食べる意欲を引き出す。
適温にすることで食欲を刺激し、食べる意欲を引き出す。
3. 食べる動作をサポート
・一口の量を調整
小さめのスプーンや専用の食具を使用し、適量を確保。
小さめのスプーンや専用の食具を使用し、適量を確保。
・食事介助のタイミングに注意
口腔内の残留物を確認しながら、次の一口を提供する。
口腔内の残留物を確認しながら、次の一口を提供する。
・「食べる楽しみ」を引き出す声かけ
笑顔や優しい声で「おいしいね」と伝え、安心感を持たせる。
笑顔や優しい声で「おいしいね」と伝え、安心感を持たせる。
4. 誤嚥・窒息を防ぐポイント
・食事前に口腔ケアを行う
口腔内の汚れを除去し、感覚を刺激することで嚥下しやすくする。
口腔内の汚れを除去し、感覚を刺激することで嚥下しやすくする。
・むせやすい食品を避ける
パサパサしたもの、べたつくもの、細かい粒状のものは工夫する。
パサパサしたもの、べたつくもの、細かい粒状のものは工夫する。
・誤嚥のサインを見逃さない
「むせる」「咳き込む」「声がガラガラする」などがあれば中断する。
「むせる」「咳き込む」「声がガラガラする」などがあれば中断する。
5. 経管栄養の子どもへの「食の楽しみ」の提供
経管栄養を行っている場合でも、食事の楽しみを感じられる工夫が可能です。
・食べ物の香りをかがせる
食卓に座り、料理の香りを感じることで「食べる体験」を共有。
食卓に座り、料理の香りを感じることで「食べる体験」を共有。
・口腔内の刺激を行う
口に触れる、綿棒で舌をなぞるなどして食べる感覚を維持。
口に触れる、綿棒で舌をなぞるなどして食べる感覚を維持。
・好きな味を少量味わう(医師と相談の上)
口の中でなめる・味を感じる程度で「食べる楽しみ」を提供。
口の中でなめる・味を感じる程度で「食べる楽しみ」を提供。
6. 「食べる喜び」を大切にする
・本人の好みを尊重
食べられる形態で、できるだけ好きな味や香りを取り入れる。
食べられる形態で、できるだけ好きな味や香りを取り入れる。
・家族と一緒に食事の時間を過ごす
たとえ経管栄養でも「家族と同じ食卓を囲む」ことが重要。
たとえ経管栄養でも「家族と同じ食卓を囲む」ことが重要。
・五感を活用して楽しむ
見る・香る・触れる体験を通じて、食の楽しみを共有する。
見る・香る・触れる体験を通じて、食の楽しみを共有する。

まとめ
医療的ケア児にとって「食事」は栄養補給だけでなく、「生きる喜び」に直結する大切な時間です。
安全を確保しながら、無理なく食べる楽しみを支える工夫を取り入れましょう。
安全を確保しながら、無理なく食べる楽しみを支える工夫を取り入れましょう。
医療チーム・家族と連携し、食べることをポジティブな体験にすることが重要です!
終末期の方が食事を楽しむための注意点と工夫
終末期の方にとって、食事は「栄養を摂るため」だけでなく、「人生の楽しみ」や「心の安らぎ」としての大切な時間です。
身体の状態や嚥下機能の低下に配慮しながら、無理なく「食べる喜び」を支えることが重要です。
身体の状態や嚥下機能の低下に配慮しながら、無理なく「食べる喜び」を支えることが重要です。
1. 食事の目的を「楽しみ」にシフトする
終末期では、「栄養管理」よりも「食べる楽しみ」を優先する考え方が大切です。
・「好きなものを、食べられる範囲で」
・「本人の気持ちを尊重し、無理に食べさせない」
・「食べる量や頻度ではなく、食事の時間を心地よく過ごすことを大切にする」
2. 食事環境の工夫
・リラックスできる空間を作る
照明や音、周囲の雰囲気を穏やかに整え、落ち着いた環境にする。
照明や音、周囲の雰囲気を穏やかに整え、落ち着いた環境にする。
・食事の時間を柔軟に
体調に合わせて、無理のないタイミングで食べる。
体調に合わせて、無理のないタイミングで食べる。
・食べることにプレッシャーを感じさせない
介助する側もリラックスし、「一緒に楽しむ」姿勢を大切にする。
介助する側もリラックスし、「一緒に楽しむ」姿勢を大切にする。
3. 食べやすい食事の工夫
(1)形態の工夫
・嚥下機能に合わせた食事形態
普通食 きざみ食 ムース・ペースト食 ゼリー・とろみ食 など、医療チームと相談しながら調整。
普通食 きざみ食 ムース・ペースト食 ゼリー・とろみ食 など、医療チームと相談しながら調整。
・口に残りにくい食材を選ぶ
パサパサしたものや繊維が多いものは避け、なめらかな食感のものを選ぶ。
パサパサしたものや繊維が多いものは避け、なめらかな食感のものを選ぶ。
・水分管理を徹底
とろみをつける・ゼリー状にするなどして誤嚥を防ぐ。
とろみをつける・ゼリー状にするなどして誤嚥を防ぐ。
(2)味や温度の工夫
・本人の好きな味を優先
栄養価よりも「本人が食べたいもの」を選び、満足感を重視。
栄養価よりも「本人が食べたいもの」を選び、満足感を重視。
・香りや見た目を大切に
食欲を刺激するために、温かい料理や好きな香りのものを取り入れる。
食欲を刺激するために、温かい料理や好きな香りのものを取り入れる。
4. 食べる動作のサポート
・無理なく食べられる姿勢を確保
できるだけ上半身を起こし、前傾姿勢を意識する。
できるだけ上半身を起こし、前傾姿勢を意識する。
・ゆっくり食べる
一口の量を少なくし、嚥下を確認しながら食事を進める。
一口の量を少なくし、嚥下を確認しながら食事を進める。
・口腔ケアを徹底
口の中の清潔を保つことで、味覚を保ち、誤嚥リスクを軽減。
口の中の清潔を保つことで、味覚を保ち、誤嚥リスクを軽減。
5. 「食べられない時」の対応
終末期では、「食べること自体が負担」になることもあります。
・無理に食べさせない
本人が嫌がる場合は、「食べない選択肢」も尊重する。
本人が嫌がる場合は、「食べない選択肢」も尊重する。
・「食べる楽しみ」を別の形で提供
香りを楽しむ、口に少し含ませるだけ、食事の場を一緒に過ごすなどの工夫をする。
香りを楽しむ、口に少し含ませるだけ、食事の場を一緒に過ごすなどの工夫をする。
・経口摂取が難しくなった場合のケア
経管栄養や点滴に移行するかは、本人や家族の意向を尊重しながら決定する。
経管栄養や点滴に移行するかは、本人や家族の意向を尊重しながら決定する。
6. 「食べる喜び」を最後まで大切にする
・家族や大切な人と一緒に食べる時間を作る
たとえ少量でも、楽しい雰囲気で食事をすることで心が満たされる。
たとえ少量でも、楽しい雰囲気で食事をすることで心が満たされる。
・五感を活かした食の楽しみを提供
「大好きだったコーヒーの香りをかぐ」「好きな果物のジュースを口に含む」など、食の記憶を刺激する体験を大切にする。
「大好きだったコーヒーの香りをかぐ」「好きな果物のジュースを口に含む」など、食の記憶を刺激する体験を大切にする。
まとめ
終末期における食事は、「生きるための栄養補給」ではなく、「人生を楽しむためのひととき」として捉えることが大切です。
安全を確保しながら、可能な範囲で「食べる喜び」を最後まで支えることを心がけましょう。
安全を確保しながら、可能な範囲で「食べる喜び」を最後まで支えることを心がけましょう。

次に年代別の食の楽しみ方
80代の方が食を楽しむためには
各自治体では高齢者歯科健診という名称の80歳あたりの方の口の健康に対する啓発事業が行われています。その中のスクリーニングの質問で、「硬いものが噛めなくなってきましたか?」「口が乾燥しますか?」「水分がむせますか?」というものがあります。
これは年齢とともに口周りの機能が衰えてくるオーラルフレイルの状態にあるかどうかをスクリーニングすることでもあります。
オーラルフレイルの定義は口腔のリハビリや食事の工夫などでカバーすることのできる可逆的な状態です。
オーラルフレイルの定義は口腔のリハビリや食事の工夫などでカバーすることのできる可逆的な状態です。
毎日の食事を安全に食べる、食べたいものを長く楽しむためには歯が抜けてしまったところを放置しないで治療を行う、定期的な歯科でのメンテナンスを行うなどの積極的な対処法が必要です。
そのうえで食事の安全を高めるための工夫、水分を摂りながら窒息に注意するなどの対処法を考えていくとよいでしょう。
90代の方が食を楽しむためには
90歳にもなると、強い身体を作っていくために食べるというよりは基礎代謝量も必須エネルギー量も減少してきているので、食べたいものをいかに安全に食べるか?ということを常に念頭に置いて無理をしない食べ方が必要となってくるでしょう。
たくさんの量を食べる必要もないでしょうから、眼で見て美しい、多様な食材を食べられるなどの心への栄養という視点も必要ではないでしょうか?
もちろん窒息を起こさないような食形態への調製も必要とされてきます。
100歳の方が食を楽しむためには
100歳の方にお会いすることも珍しくなくなってきた昨今、そのような超高齢者はどのような食べ方が必要とされるのでしょうか?
ここまでの長寿の方は、健康上の良い習慣、生活の中での窒息や誤嚥の危険性などを全てクリヤしてきた結果のご長寿なので、もしかしたらフィジカルも含めたスーパーエリートなのかもしれません。
ここまでの長寿の方は、健康上の良い習慣、生活の中での窒息や誤嚥の危険性などを全てクリヤしてきた結果のご長寿なので、もしかしたらフィジカルも含めたスーパーエリートなのかもしれません。
その境地の方の食の楽しみとは、食べたいものを、たべたい量だけ、好きな時に食べる、ことが一番の幸せなのかもしれません。
いずれにしても高齢者から超高齢者まで食の楽しみを最後まで支援するためには常に嚥下機能と評価と配慮を行い、その時の機能にあった支援、介助をすることはどの年代においても必要とされるでしょう。

関連リンク:
執筆: