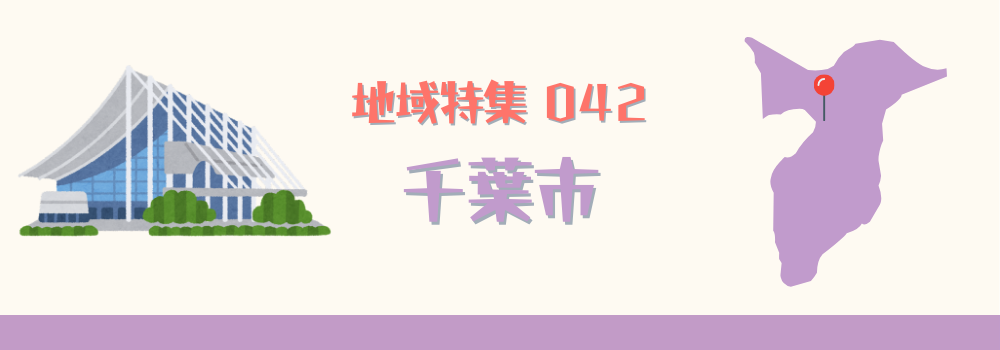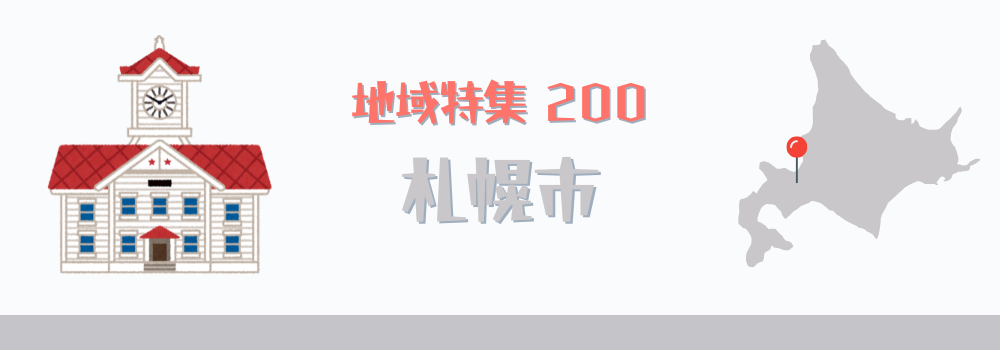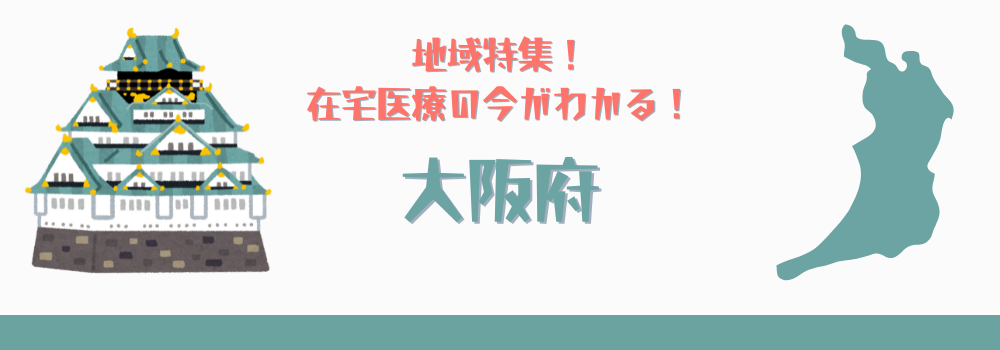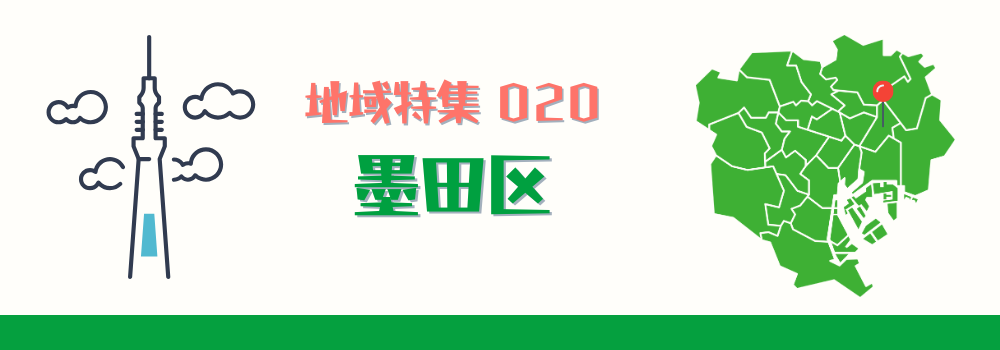【PICK UP!在宅医療機関 014】澁谷歯科医院 澁谷英介 院長 最終更新日:2025/02/24

注目の在宅医療機関へのインタビュー取材「PICK UP!在宅医療機関」の第14回目は東京都板橋区にて「渋谷歯科医院」を運営されている歯科医師渋谷英介院長です。これまでの歩み、訪問歯科やこれからの歯科医師像について熱く語っていただきました。
歯科医師の家系に生まれて
— 歯科医師を目指したきっかけを教えてください。
祖父、父と同じ歯医者ということもあり、進路選択にあたっては家業を引き継ぐというのが、よく理解している職業ということもあり自然に選びました。
しかし教員として教育に携わるということにも憧れていました。親族には歯医者も何人かいましたが、教員もまた多く、身近であったからです。
高校卒業後、東京歯科大学に進学し、千葉の稲毛のキャンパスで学びました。卒業後は基礎系の大学院へ進学しました。解剖学は専門基礎教育が始まると最初に学ぶ教科です。専門教育を受け始める学生さんに丁寧に教えてあげたいと思っていました。
大学院の4年間は研究に没頭しました。私が卒業した当時は歯科医師臨床研修義務化の前でしたので、国家試験に合格するとすぐに保険医の登録が行えたので、臨床でも働きながら研究を進めることが可能でした。
— 渋谷先生の専門領域や疾患を教えてください。
大学院時代の研究テーマが開発した実験用のマイクロCTを用いた顎口腔領域の硬組織の内部構造、具体的には顎骨の内部構造と根管系を中心とした歯牙内部構造の観察でした。今でこそ診療室に歯科用CTを備えているところも増えてきましたが、当時はまだパノラマX線写真だけで骨の状態を判断してインプラント治療を行うことも珍しくはありませんでした。
マイクロCTを使用した高精細な顎骨内部構造や歯牙内部構造の観察は解像度に劣るデンタルX線写真やパノラマX線写真より得られる情報を補完する役割を果たすことが示され、正確な骨の評価が可能になり、インプラント治療の精度向上に繋がることを示しました。この経験を通して基礎医学の知識や研究手法を習得できたことは貴重な経験でした。
大学院卒業後は、開業医に就職しましたが同時に歯科衛生士養成校や技工士養成校で解剖を教えていました。 授業を行うためには膨大な準備が必要でしたが、そのおかげで解剖学的な知識が整理されました。
大学院時代の研究がインプラントの基礎的な知識でしたので、ご縁のあったインプラントの専門の先生のところで勤務していました。
自身が術者として埋入する経験はあまりありませんでしたが、インプラントの診療の周りのすべての作業、術前の診断から、ステントの作製、骨造成の際のPRPの調製など多くのことを学べました。
現在、自身のクリニックではインプラントの埋入は行わず、補綴のみ対応していますが、修業時代の経験が大いに役立っています。また、在宅診療において要介護高齢者のインプラントが破損した際には、アバットメントの除去や暫間補綴など、対処の選択肢が広がっています。また、インプラントのフルマウス症例の治癒のための免荷期間に使用してもらう総義歯が破損してくるのを毎日のように修理していました。当時は自分の患者の診療の他に余分な仕事が増えたと憂鬱でしたが、限られた時間の中で修理する経験のおかげか、義歯の修理は今では得意というか、確実に行うことができるので、在宅診療の場などでも早期の咬合回復を可能にすることができます。
こういった外での修業期間を経て、自宅で父とともに診療をする準備を進めてきました。
板橋区で100年を超える歴史の歩みとともに
— 医院の歴史を教えてください。
大正8年に祖父渋谷常三郎が現在地の板橋区で開業して100年以上、地域に根ざした診療を続けています。父の歯科医院を手伝う形で、平成19年から関わっていました。ただ、本格的に医院を継承したのは平成23年で、そこから訪問診療を始めました。
— 診療内容について教えてください。
いわゆるGP(一般歯科医)と呼ばれるような一般的な診療を行っています。場所柄子供の患者さんも多いです。診療時間は月曜日から土曜日の9:00〜13:00と14:30〜20:00です。クリニックの周りはオフィス街というわけではなくて住宅地なので、昼の仕事の合間に診療にくる患者さんはほとんどいません、そのため昼前後から毎日訪問診療を行っています。自転車で行ける範囲ならばほぼどこにでも行くようにしています。
当院の特徴として建て直した際に旧ハートビル法に基づいて車いすで自走できる勾配のスロープを設置し、診療室内はフルフラットのため車いすからユニットに移乗しなくても診療が受けられます。駐車場が1台分あるため足が不自由な方でも利用しやすいと思います。予約制ですが、急患も随時受け付けています。一休みしていく軽い気持ちでご来院ください。
高齢者施設を中心に訪問歯科診療へ邁進
— 訪問歯科医としての活動について教えてください。
父と一緒に診療を始めた頃、近隣で介護老人保健施設を経営している歯科医師の先輩から、「入所者の歯科診療を手伝ってくれないか」と誘われました。
その施設には約100人の入所者がおり、義歯の修理や口腔ケアの人手が足りていなかったため、週に1回、歯科治療を行うことになりました。介護老人保健施設は在宅復帰のためのリハビリを目的とした施設であり、多くのリハビリ職が在籍しています。そのため、歯科診療の目的である「痛みを取る」「失われた歯牙の形態を回復する」だけでなく、その先の機能回復をリハビリを通じて獲得していくという考え方を間近で学ぶことができました。
施設での診療は、きちんとした診療スペースが確保されていたため、訪問診療のように診療環境で悩むことはありませんでした。特に工夫が必要だったのは、車いすからユニットへの移乗の介助技術で、基礎からしっかりと教わりました。
この頃はまだ在宅往診を始めておらず、患者の自宅での診療には多くの制約があり、難しいのではないかと感じていました。
在宅訪問診療は、診療室で行う治療とは異なる点が多々あります。例えば、機材の持ち運びや、患者さんの状態把握など、様々な面で工夫が必要です。また、訪問先での感染症対策も徹底しなければなりません。
そんな時、新宿の五島先生の勉強会に参加し、様々なことを学ばせていただきました。他の勉強会で知り合った方とも情報交換をしながら、少しずつ訪問診療のノウハウを学んでいきました。
現在は、1日に2〜3件の在宅の患者さんを訪問しています。在宅の患者さんは在宅主治医の先生からご紹介いただくことがほとんどです。在宅で人工呼吸器を使っている方で歯牙が多い方などはVAPと呼ばれる口腔内の細菌が直接気管を通じて肺に行ってしまうことで起こりやすい肺炎を防止するために定期的に口腔ケアを行うことが多いです。
— 高齢者施設でのエピソードを教えてください。
近隣に200床の特別養護老人ホームができた際に歯科医師会に入所者の診療をしてほしいという依頼がありました。当時の歯科医師会は、会員全員が当番制で施設を訪れる方法を採用していました。しかし、この方法では、意欲のない歯科医師も診療にあたることになり、十分な診療が行われないケースが多かったのです。
そこで、私は、近くの特別養護老人ホームなら私がメインで診療できると思い、歯科医師会に、当番制ではなく、少数のチームを作ってほしいと提案しました。その結果、特別養護老人ホームの診療は私がほぼ一人で担当することになり、そのまま10年以上が経過しています。
そのような状況の中、高齢者の入れ歯治療の経験を積んでいきました。特別養護老人ホームの入所者は、入れ歯を作れば良いというわけではなく、嚥下障害などの様々な問題を抱えています。嚥下障害といっても、急性期の脳血管障害で麻痺が残った患者さんの場合の嚥下障害とは違い、特別養護老人ホームの入所者はほとんどが認知症高齢者なので、リハビリによる改善というよりは衰えていく昨日の維持のための環境調整がメインです。特別養護老人ホームは介護老人保健施設と違いリハ職が配置されていないためにそのあたりの説明をしても理解してもらえないことが多く苦労しました。
一般的な特別養護老人ホーム(特養)ではリハビリを実施しておらず、身体機能の評価も行われていないため、嚥下障害のある患者への十分な対応ができていないという問題があります。例えば、「むせたから食事を控える」「飲み物に過剰にとろみをつける」といった対応が見られますが、これらは安全性を重視した措置であるものの、必ずしも適切な解決策とは言えません。
やがて施設内では「誤嚥性肺炎の発生を抑えよう」という目標が掲げられるようになりました。この目標を達成するには、口腔内のセルフケアや介助者による仕上げ磨きの徹底、食事時の安全確保など、多方面からのアプローチが必要です。私は診療の合間に個別の相談に応じ、適宜アドバイスを行ってきました。
そんな中、事務方から「関連施設で経口維持加算を算定することで介護報酬を追加で得られる」との情報が伝えられ、当施設でも取り組みが可能かと問い合わせがありました。私はすぐにその取り組みを開始しました。経口維持加算とは、多職種が一堂に会し、食事の安全について検討する仕組みで、栄養科、介護職員、ケアマネージャー、歯科が参加し、ミールラウンド(観察とカンファレンス)を実施します。
私はその場で即座に改善できるよう、食事時の姿勢や嚥下機能に適した食形態の判定・変更を行うようにしています。現在は月に8回、昼食時に訪問し、経口維持加算対象者の嚥下評価とミールラウンドを実施。それ以外にも、臨時で食事形態の変更を伴う嚥下評価を行っています。
この取り組みの背景には、入所高齢者が不意の発熱で入院し、CT検査で肺炎が否定されたにもかかわらず「とりあえず禁食」とされ、退院時サマリーに「誤嚥性肺炎のため経口摂取不可」と記載されるケースが多いという現状があります。実際には嚥下機能に問題がないのに、誤った評価や、場合によっては評価すら行われずに禁食やミキサー食での再入所となることがあります。その結果、嚥下機能と食形態のミスマッチが起こり、食事摂取量の低下や栄養状態の悪化につながります。こうした状況を防ぐため、早期の再評価を行い、適切な食べ方や食事形態の見直しを進めています。
また、施設内では月に一度、口腔ケア委員会が開催され、口腔ケアの方針について話し合いを行っています。私は第二回から欠かさず参加し、ミールラウンドの意義、日常の口腔ケアの実践的手技、伝達講習などを担当しています。さらに、職員が口腔内の変化に気づけるよう、自身も歯科治療を受けることを推奨。そのため、自院では職員が受診しやすい時間帯に診療を行う取り組みを実施しています。
— 訪問診療時のエピソードを教えてください。
訪問診療は基本的に1人で行っています。その理由はいくつかあります。在宅療養中の患者は、何らかの制限を抱えている方がほとんどで、中にはベッドから離れられない方もいます。そのような状況で、大勢のスタッフや大掛かりな機材を持ち込むと、かえって危険を伴うことがあります。
また、診療室と同じレベルの治療を行おうとすると無理が生じるため、安全性を確保するためにも、1人で対応できる範囲の治療に限定しています。どうしても水を使用する削合処置やブリッジの作成が必要な場合は、診療室に一度来院してもらい、集中的に処置を行います。
一方で、訪問診療のスタイルにはさまざまな形があり、歯科医師や歯科衛生士に加え、多数のスタッフを伴うチーム医療を実践する歯科もあります。しかし、高齢者が一人暮らしをしているところに4~5人ものスタッフが訪問すると、かえって負担を感じる方も少なくありません。そのため、「一人で診療してくれる方が良い」という理由で、ケアマネージャーを通じて私への診療交代を希望されるケースも決して少なくありません。
検診や勉強会など地域住民へのサービスに注力
— 地域住民への啓蒙活動について教えてください。
歯科医師会は、行政から委託されたさまざまな事業を担っています。代表的なものの一つが歯科検診です。
板橋区では、成人歯科検診が40歳以降5年ごとに実施されており、近年では後期高齢者歯科検診や妊産婦歯科検診など、国民総歯科検診の流れを受けて対象が拡大しています。子どもの検診についても、1歳半や3歳時に実施されています。
また、介護予防教室の開催をはじめ、地域住民への健康増進に関する啓発活動や情報発信など、多岐にわたる取り組みを行っています。
シームレスな診療の実現を目指して
— 今後の歯科診療の課題・提言はありますか?
よく「2050年問題」と言われますが、それは一時的なものだと考えています。私が歯科医になった30年ほど前と現在では状況が大きく変わっています。今は超高齢者でも元気な方が多いですが、その下の世代、例えば私の親も80歳ですが、85歳や90歳まで生きるかと考えると、やや疑問に感じます。年齢構造も変化し続けているため、高齢者の増加に伴う若年層の負担増加といった単純な問題ではないのではないかと思います。
最も大きな課題は、在宅で歯科診療を受けられない人が多いことです。現在、訪問診療が提供されている割合はわずか4%程度と言われています。そのため、より多くの人が訪問診療を受けられる環境を整えることが必要です。
また、訪問診療について「診療室と同じレベルの治療を提供しなければならない」と思い込んでいる歯科医が多いのも問題です。例えば、割れた入れ歯を修理して「これでまた食べられますよ」と伝えるだけの処置に、大人数のスタッフは本当に必要でしょうか? まずは、自分が患者に何をしてあげられるかを見極める視点を持って診療にあたるべきです。
訪問診療を始めたいという歯科医から「機材を揃えるのが大変では?」と相談を受けることがありますが、まずは自分が提供できる診療から始めることが大切です。訪問診療は必ずしも大掛かりなものではなく、身近な治療から始めることが可能なのです。
— 今後、先生が目指していることは何ですか?
診療をシームレスにしたいと考えています。
例えば、ある75歳の患者さんが、急に通院しなくなったと思ったら、久しぶりに来院された際に「実は3年前に脳梗塞を起こし、病院で治療とリハビリを受けた後、自宅に戻っていた」と話されました。その後、コロナ禍の影響もあり、外出を控えていたとのことでした。
先日、ようやく意を決して電話をくださり、第一声が「脳梗塞になったんですが、診てもらえますか?やっと歩けるようになりました。また通院してもいいですか?」というものでした。その時、私は「それならもっと早く電話してくれたら、すぐに訪問したのに」と感じました。こうした機会を逃してしまうのは、非常にもったいないと思います。
だからこそ、私は「どこにでも行く」というスタンスを大切にしています。ただし、どこで診療しても全く同じクオリティを提供するとなると、負担が大きくなり現実的ではありません。そのため、一律の対応を目指すのではなく、状況に応じて柔軟に対応していきたいと考えています。
— 訪問歯科医として注意していることはありますか?
在宅診療では、他職種が協力して患者を支えている中で、歯科医が呼ばれるのはたいてい最後になります。では、その状況で歯科医に何ができるのか、何を求められているのかが重要になります。
例えば、それまで訪問看護師(Ns)や言語聴覚士(ST)が口腔ケアの一環として歯磨きを行い、特に問題がなかったケースでも、大きなブリッジが脱落した途端に食事が摂れなくなり、対応に困ることがあります。こうしたケースのリカバリーは難しいことが多いですが、せっかく呼ばれた以上、できる限りの対応をしたいという気持ちになります。
しかし、訪問歯科診療では「ほぼ全ての患者に嚥下障害があるから内視鏡で診よう」といった流れになりがちです。しかし、それよりもまず、歯科医にしかできないこと—例えば、歯石の除去、抜歯、義歯の修理など—を優先すべきです。他職種が歯科医に期待しているのは、歯科医にしかできない処置を行うことです。それを後回しにしたり避けたりしていると、次第に誰からも相手にされなくなってしまいます。その点は十分に意識しておくべきだと思います。
— かかりつけ医として地域住民へのメッセージをどうぞ。
新しい歯科医院ができたからって、そこに浮気しないでくださいね(笑)。冗談はさておき、かかりつけ医として、家族全員で来てくれてもいいかなと思っています。「子供は小児歯科に連れていかなくてはいけない」という真面目な患者さんのご家族が多いです。「ここは小児歯科と書いてないから、子供を連れてったら、うるさくて迷惑だろうみたいな。」そういう気遣いをしなくても大丈夫です。家族みんなで来てください。気軽に相談できる「かかりつけ医」として、今後も地域医療に貢献していきたいと思っています。
渋谷歯科医院

〒173-0013
東京都板橋区氷川町11-8
TEL:03-3961-0205
東京都板橋区氷川町11-8
TEL:03-3961-0205
渋谷英介院長のプロフィール
経歴:
1997年 東京歯科大学卒業
2001年 東京歯科大学大学院卒業 歯学博士 解剖学専攻
2008年 渋谷歯科医院
2012年 渋谷歯科医院開設管理者
1997年 東京歯科大学卒業
2001年 東京歯科大学大学院卒業 歯学博士 解剖学専攻
2008年 渋谷歯科医院
2012年 渋谷歯科医院開設管理者