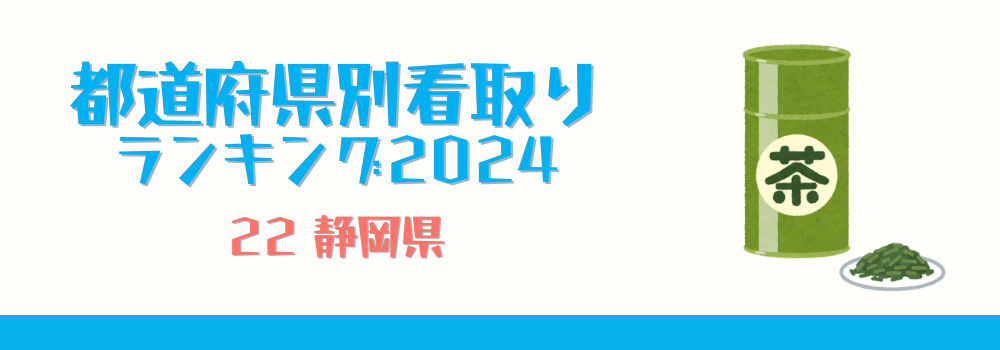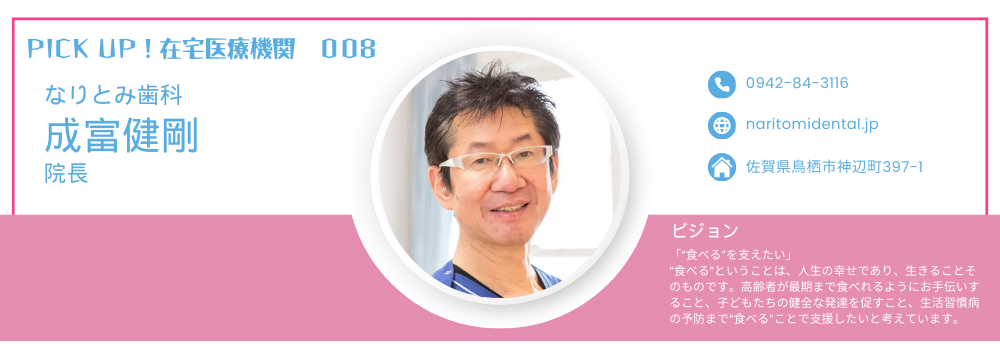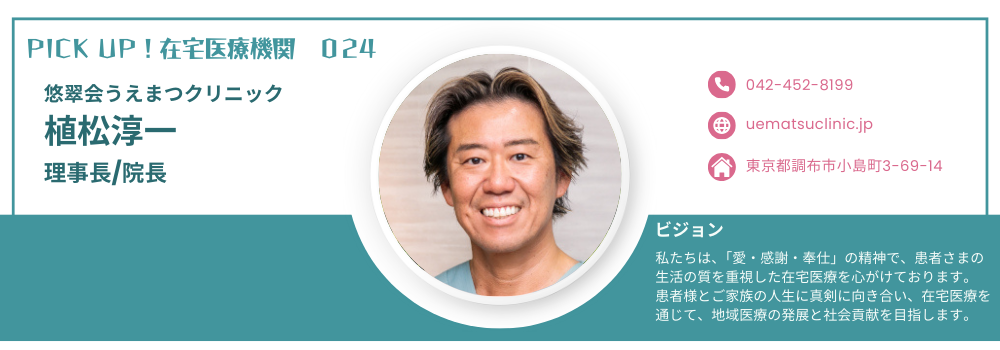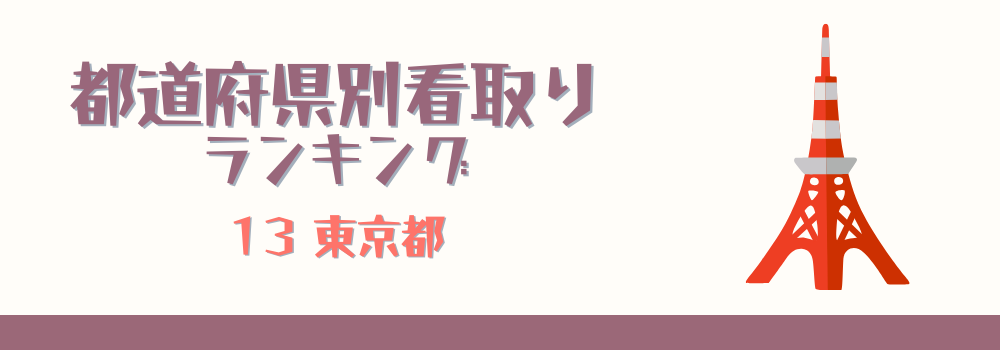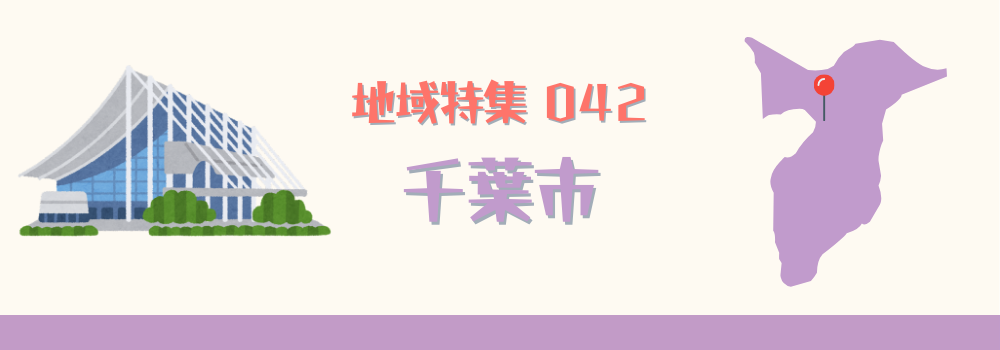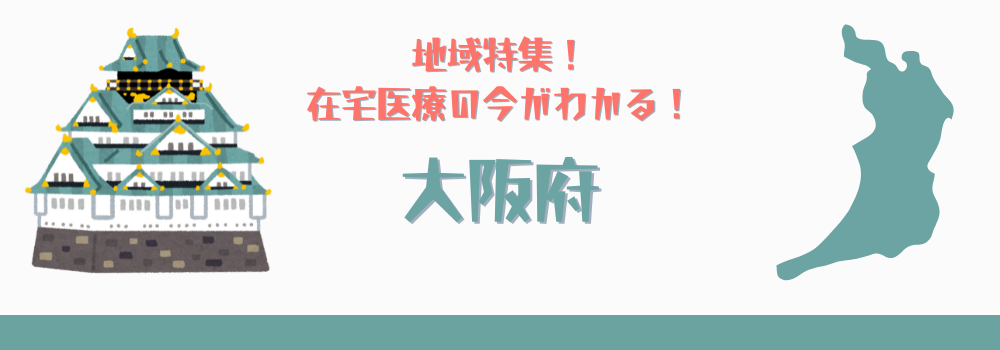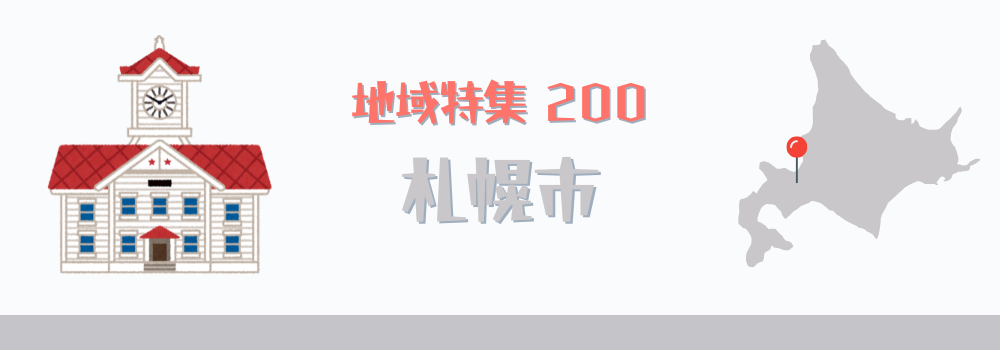中央区・江東区・港区の在宅医療/訪問診療|石川島記念病院 下山直人在宅事業部長インタビュー 最終更新日:2025/09/27

中央区・江東区・港区を中心に在宅医療・訪問診療を展開する石川島記念病院。緩和ケアの経験を活かし、「絶対に断らない」チーム体制で地域を支える下山直人在宅事業部長が、医師としての歩みから在宅医療に取り組む理由、診療・看護・リハビリの一体的ケア、地域医療の未来までを語ります。
医師を志した原点と下山直人の歩み
— 先生が医師を目指されたきっかけを教えてください。
もともと文学少年で、野口英世の伝記を読んで大変感動して、人のために自分の命を犠牲にする姿に「自分も医師になる!」って決めたんです。小学校5年生になると脳外科医が主人公の海外ドラマ「ベン・ケーシー」に熱中し、「脳外科医になる!」って診療科まで決めてましたね。
私の実家は代々続く農家だったのですが、医師を目指して一直線でした。この時の「人の役に立ちたい」という気持ちは今も大切にしています。
— 大学時代で印象に残っている出来事はありますか。
千葉大学医学部へ進学し、大学時代は勉強よりも部活動に熱心になっていました。卓球を大学からはじめたんですけど、もともと凝り性なのでずっと練習ばかりして。でもそのおかげで、インターハイ出場経験者と一緒にレギュラーに選ばれ、東医体(東日本医科学生総合体育大会)で6連覇することができました。
私らの時代は「医師はまず体を鍛えろ」っていう風潮もあって、その教え通りに過ごしたっていう感じですね。
— 大学卒業後に脳神経外科ではなく麻酔科を選ばれたのは、気持ちの変化があったのでしょうか。
私は脳神経外科か消化器外科に入るつもりでしたが、麻酔科の教授から食事会に誘われまして。ステーキを食べさせてもらったんですが、なぜか教授にはステーキがないんですよ。後から聞くと、どうやら私が教授の分のステーキを食べてしまっていたみたいで…。
麻酔科を選ぶ学生も少なかったので、教授に恩返しできればと麻酔科を選びましたね。気持ちの変化というより、義理と人情で進むことに決めました。
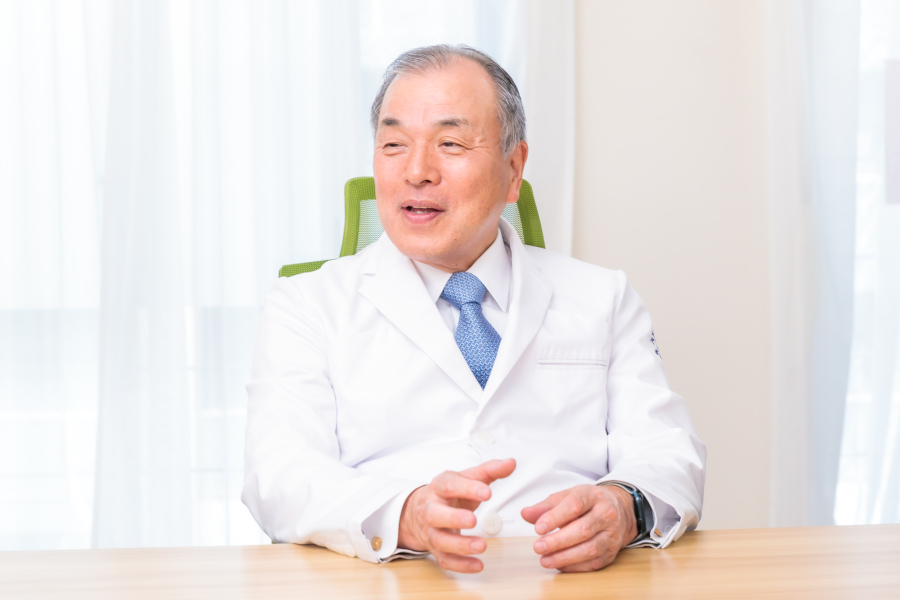
麻酔科から緩和ケアへ:包括的支援を実現するチーム医療
— 麻酔科に進まれてからはいかがでしたか。
就職先の選択肢には国立病院などの公立系の病院や私立病院などがあるのですが、他と比べて忙しいのに給料が低い、バイトもできないなど、国立病院系は人気がなくて、誰も行きたがらないんですよ。そうなると私はお金よりも人助けがしたいから「私がいきますよ」って、卒業後の就職先に国立の千葉大学病院を選びました。
困っている人は患者さんだけじゃなくても、助けたくなっちゃうんですよね。時には、麻酔科医として働いている妻から「私が働いている病院に心臓麻酔に詳しい医師がいない」って相談をうけて、手助けに行ったりしたこともあります。手術前から手術後の麻酔管理を徹底し、死亡率の減少につなげることができたので、患者さんに貢献できて良かったと思っています。
— 麻酔科医として経験と実績を積まれている中で、緩和ケアをはじめられたきっかけを教えてください。
研修医を終えて千葉大学病院に戻ってきた時に、ちょうど教授が変わりましてね。その教授は緩和ケアをしている先生だったんです。
1980年代の話なので、緩和ケアなんて誰もやりたがらないような時代だったから、「じゃあ私がやります」と弟子入りをして緩和ケアをはじめました。
1980年代の話なので、緩和ケアなんて誰もやりたがらないような時代だったから、「じゃあ私がやります」と弟子入りをして緩和ケアをはじめました。
その時に、医師、看護師、メディカルソーシャルワーカー、薬剤師でチームを作って、「緩和ケアチーム」として運営をはじめました。当時の日本では新たな取り組みでしたね。慈恵医大の時はお坊さんともチームを組んで、スピリチュアルペインもはじめたりして。もちろん痛みへの治療や副作用の対応は私たち医師が行いますが、心のケアっていう視点も含めて、包括的に患者さんを支えるという緩和ケアは私が注力してきたものです。
— まさに日本の緩和ケアのパイオニアですね。そこから、緩和ケアに注力されたのでしょうか。
1990年に千葉大学病院で緩和ケアチームを立ち上げて、1995年から1997年の2年間は緩和ケアを学ぶためにアメリカのメモリアルスローン・ケタリンがんセンターとコーネル大学薬理学教室へ研究員として留学しました。留学といっても様々な留学方法があって、私はお給料はいらないからとにかく勉強させてほしいと希望しましたね。最新の緩和ケアプログラムの指導を受けつつ、研究論文などもたくさん執筆したんですよ。
そうこうして日本に戻ると、国立がん研究センターで緩和ケアチームを立ち上げるから手伝ってほしいということで。国立がん研究センターは、当初は麻酔科医をしつつ緩和ケアを担当していましたが、どんどん緩和ケアの患者さんが増えてきて、最終的には緩和ケア医として働きました。
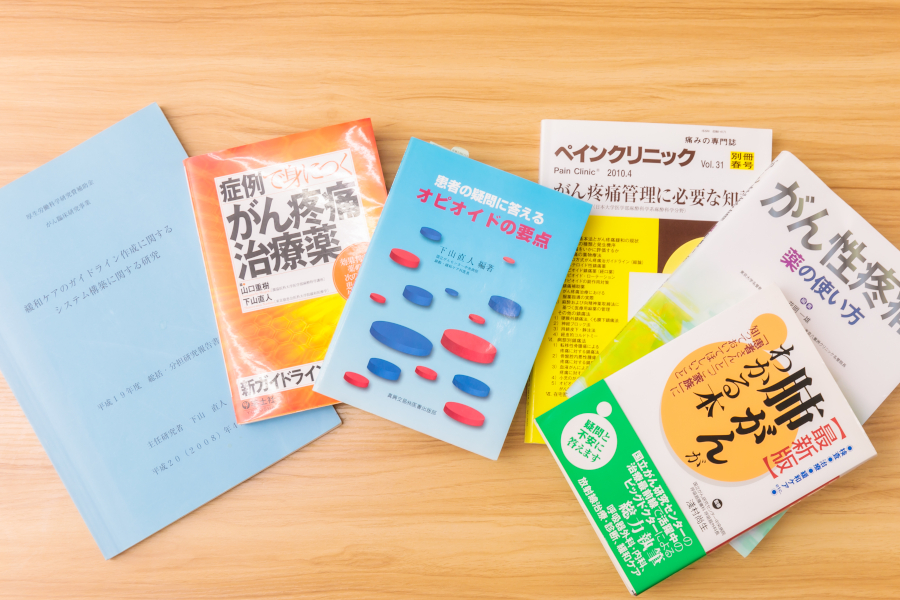
緩和ケアから在宅医療への転機:患者を自宅に帰すための挑戦
— 緩和ケア医として邁進される日々で、在宅医療にはどのような思いがあったのでしょうか。
大学病院や基幹病院で緩和ケアをしてきたのですが、どうしても家に帰してあげられなかった患者さんがいるんですね。千葉県には在宅医療がなかなかなくて、申し訳ない気持ちがずっとありました。
私が国立がんセンターの手術部長で麻酔・緩和科推進対策室長をしている時に、「国立がんセンターはがん難民量産工場だ」っていう言葉が使われました。「国立がんセンターでの治療後の患者さんは受入先がない、フォローがない」という意見から“がん難民量産工場”と呼ばれたんです。
その時に、病院と地域の連携、つまり地域で注力してくれている医師やコメディカルの方々との連携が必要と考え、「国立がんセンター緩和ケアチームと在宅医療合同検討会」をはじめました。
— 日本の在宅医療の流れや仕組みづくりにつながる検討会ですね。
当時は在宅医療がまだまだ浸透していなかったので、日本の在宅医療のはしりをされている先生方とたくさん意見を交わさせていただきました。国立がんセンターでがん治療をしても、「患者さんのサポート方法が分からない、治療方針が共有できない」と在宅医療の先生やスタッフの方々は困っていらっしゃる。
その中でどう連携をとっていくか、患者さんやご家族が困らないようにするにはどうすればいいか、そういったことを話し合いました。地域との連携を深めるため、国立がんセンターの緩和ケアチーム担当者が、退院後の患者さんを担当してくれている医院のカンファレンスに参加するような取り組みもしましたね。
— そして、在宅医療へ進まれたんですね。
2022年に地域で生活する患者さんの緩和ケアを担ってほしいと浦安病院から声をかけてもらって、在宅医療をはじめました。これまで基幹病院や民間病院も経験していて、残るは在宅医療だと思っていましたね。
自分の医師としての経験を、在宅で過ごす患者さんに最大限に活かして、よりよい生活を送ってもらいたいと。大学病院や国立がんセンター、民間病院で働く中で、地域で働く医師や看護師、行政の方々と関わってきたので、連携の重要性っていうところでも経験が活かせると思いましたね。

絶対に断らない在宅医療:石川島記念病院 訪問診療部のチーム体制
— 石川島記念病院の訪問診療部の特徴を教えてください。
石川島記念病院はもともと循環器・回復期リハビリテーション専門の病院だったのですが、地域のみなさまからのニーズもあり、2024年に地域包括ケア病棟へ転換しました。その際に新しく訪問診療部を立ち上げるということでお声がかかり、「絶対に断らない」を方針に、チームプレーを重視しています。このチームプレーとは訪問診療部のスタッフ間だけではなく、当院の地域包括ケア病棟や他院などとの連携も含めています。
例えば、熱が出た患者さんがいた場合には、石川島記念病院の地域包括ケア病棟と連携を図り入院していただくこともできます。
また、輸血は対応できない病院が多いのですが、うちは濃厚赤血球であれば対応できるので、他院からご依頼があったりもするんですよ。
また、輸血は対応できない病院が多いのですが、うちは濃厚赤血球であれば対応できるので、他院からご依頼があったりもするんですよ。
あと特化していることでいえば、私が麻酔科や緩和ケアをやってきてますので、がんやがん以外の痛みに苦しんでる方の疼痛管理ですね。科学的根拠に基づいた疼痛管理や、心のケアなど総合的視点でサポートする在宅医療を提供しています。

— 訪問診療の対象地域や利用者の疾患などを教えてください。
訪問対象は中央区がメインで、利用者の方は40人程、がんの患者さんは1割ほどですね。老人ホームの健康管理なども行っており、高血圧や糖尿病など生活習慣を抱える方にも対応してます。
あと、私達は訪問診療時に男女ペアで対応するようにしていますね。例えば、私が訪問する時は必ず女性の看護師さんについてもらうような感じです。これは診療を円滑にするためだけでなく、患者さんに安心感をもってもらうための配慮だと考えています。
特に女性の患者さんは、男性からの医療処置などは抵抗があるはずですし、女性スタッフがいるからこそ話せることもあったりね。こういった日々の診療場面でも、チームプレーを発揮して患者さんに寄り添える在宅医療を提供しています。
— みなさんとても良い雰囲気で、まさにチームプレーといった感じがします。
ここには、医師、看護師、理学療法士、作業療法士やメディカルソーシャルワーカーがいます。私だけの判断で何かを決めることはまずないですね。もちろん責任をとるのは私だけど、みんなの意見を必ず聞くようにしています。スタッフのみんなが笑顔で話しているのとか見るのも大好きなんですよ。
仕事での連携はもちろん、休憩時間もみんなでひとつの部屋に集まって、和気あいあいとしてたりね。情に厚いスタッフを集めてるから、患者さんのことで涙流したりすることもあったりします。
私も医師として色々な経験をしてきたけれど、本当に最後を飾るには素晴らしい場所だと思っています。

— 本当に素敵な職場ですね。下山先生やスタッフの方々で話題になるような、患者さんとのエピソードはありますか。
鳥を飼っている患者さんがいるんだけど、リハビリで訪問したスタッフが鳥から攻撃されたことがあって、頭にフンもされたみたいで。みんなで「運がついたね」って笑い合ったりしてますね。でもこれって在宅医療でとても重要なことで、鳥も患者さんにとっては大切な家族。
私たちは気兼ねなく生活できる空間をサポートするのが役割っていうことは忘れちゃいけないって思ってます。
私たちは気兼ねなく生活できる空間をサポートするのが役割っていうことは忘れちゃいけないって思ってます。
患者さんの中には、タバコは控えるようにって言われているのにタバコを吸う人だっている。もちろん声はかけるけれど「タバコ吸ってなにかあっても本望」って言われちゃうとね。医療とのバランスは難しいけど「その人らしく」って大切で、家族の一員のように寄り添える在宅医療が大切だと思ってます。
「帰りたい人を家へ」診療・看護・リハビリが連携する在宅医療の実践
— 在宅医療の課題はどのようなことだと考えていらっしゃいますか。
やっぱり認知度が低いことですね。在宅医療の存在を知らなかったために「家に帰りたいけど、帰れなかった」という人は多い。知っていたとしても利用方法が分からない、金額的に不安があるなど課題は山積みです。
特に、在宅医療をはじめて利用する時に「どれくらいお金がかかるか」はよく聞かれる質問なんですよ。色々なサービスもありますし、制度を使うことでそんなに高額にならないケースも多いです。在宅医療は家に帰りたい人やその家族を支えるためにあるので、ぜひ知ってほしいですし、在宅医療を広める役割も担っていきたいですね。
— 目指している在宅医療を教えてください。
「帰りたい人が家で自分らしく生活できる」これをサポートできるのが私たちの目指している在宅医療です。そのためには、私たちの訪問診療部だけでなく、石川島記念病院、行政、そして他の医療機関との連携が必要になります。私がこれまで大切にしてきたチームプレーで、情報共有をしていきながら、地域のみなさんを支えるようにしていきたいですね。
訪問診療部としては訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションの3チームで構成しているので、そこを最大限活用して、心不全や腎不全、呼吸不全などの管理や看取りでお困りの方を支援していきたいっていうのはありますね。ただ知ってもらわないとはじまらないから、まずは在宅医療を広めよう、石川島記念病院の訪問診療部を知ってもらおうということで勉強会や研究会を予定しています。
— 勉強会も開催予定とのことですが、対象はどのような方でしょうか?
まずは医療従事者を中心とした勉強会と一般の方向けに市民公開講座を予定しています。在宅医療を知らない人が多いから、「こんなことができますよ」っていうのを伝えて、自宅で最後まで自分らしく過ごすっていうのを伝えたいですね。
医療従事者の方も交流の機会になるので、私ができる地域の皆様への貢献ということで積極的にやっていきたいです。
— 最後に地域住民のみなさんへメッセージをお願いします。
「家に帰りたい」をお手伝いするのが在宅医療です。私たちは医師、看護師、理学療法士、作業療法士やメディカルソーシャルワーカーのチームプレーで、患者さんやご家族を支えることができるようサポートさせていただきます。必要時には入院も可能ですし、検査も充実しています。
1人でも多くの方の「家に帰りたい」という願いを叶えるためのお手伝いをいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

医療法人社団 健育会 石川島記念病院
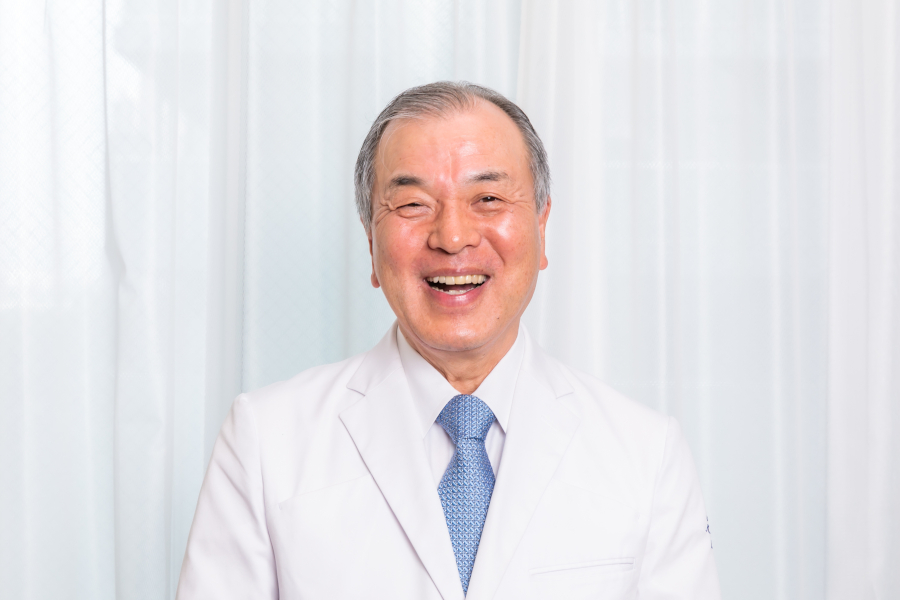
診療科
・内科/緩和ケア内科
診療時間
平日:9:00~17:30
※在宅診療は24時間365日対応しております。
休診日 土曜・日曜・祝日
※在宅診療は24時間365日対応しております。
休診日 土曜・日曜・祝日
対応エリア
診療内容
[当事業部の訪問診療でできる処置]
1. 膀胱カテ留置、管理
2. 褥瘡管理
3. 在宅酸素療法
4. 在宅中心静脈栄養
5. 在宅自己注射
6. 経管栄養(胃瘻、腸瘻から)管理
7. エコーガイド下腹水、胸水穿刺除去
※ 内視鏡下、胃瘻チューブ交換は当院入院で施行可能
[自宅で受けられる検査]
1. 血液検査(生化学、血算、細菌検査)
2. 超音波検査(エコー)
3. 尿検査
[病院で受けられる検査]
1. レントゲン検査
2. 心電図検査
3. CT
4. MRI
❏ さらに詳しい診療内容はこちら
1. 膀胱カテ留置、管理
2. 褥瘡管理
3. 在宅酸素療法
4. 在宅中心静脈栄養
5. 在宅自己注射
6. 経管栄養(胃瘻、腸瘻から)管理
7. エコーガイド下腹水、胸水穿刺除去
※ 内視鏡下、胃瘻チューブ交換は当院入院で施行可能
[自宅で受けられる検査]
1. 血液検査(生化学、血算、細菌検査)
2. 超音波検査(エコー)
3. 尿検査
[病院で受けられる検査]
1. レントゲン検査
2. 心電図検査
3. CT
4. MRI
❏ さらに詳しい診療内容はこちら
訪問診療のご相談・お問い合わせ
〒104-0051
東京都中央区佃 2-5-2
[在宅事業部]
担当窓口へ電話にてお問い合わせください。
ご利用者様情報の確認と在宅事業部の概要をご説明いたします。
TEL:03-3532-3205
お問い合わせはこちら
https://ishikawajima.gr.jp/inquiry/
東京都中央区佃 2-5-2
[在宅事業部]
担当窓口へ電話にてお問い合わせください。
ご利用者様情報の確認と在宅事業部の概要をご説明いたします。
TEL:03-3532-3205
お問い合わせはこちら
https://ishikawajima.gr.jp/inquiry/
下山直人在宅事業部長のプロフィール
経歴:
1982年 千葉大学医学部卒業
1982年 千葉大学麻酔科入局
1986年 麻酔科助手・ペインクリニック外来医長
1995年~1997年 米国メモリアルスローン・ケタリンがんセンター緩和ケア科客員研究員
1996年~1997年 米国コーネル大学薬理学教室客員研究員
1997年 千葉大学麻酔科復職・外来病棟医長
1999年 国立がん研究センター手術・緩和ケア部長
2010年 東京医科大学緩和医療学初代教授
2012年 東京慈恵医科大学大学院緩和医療学教授
2019年 千葉大学医学部附属浦安リハビリセンター特任教授
2021年 君津中央病院 PCU部長、科長
2023年 蒲田クリニック院長、理事長
2024年 石川島記念病院在宅事業部長
1982年 千葉大学麻酔科入局
1986年 麻酔科助手・ペインクリニック外来医長
1995年~1997年 米国メモリアルスローン・ケタリンがんセンター緩和ケア科客員研究員
1996年~1997年 米国コーネル大学薬理学教室客員研究員
1997年 千葉大学麻酔科復職・外来病棟医長
1999年 国立がん研究センター手術・緩和ケア部長
2010年 東京医科大学緩和医療学初代教授
2012年 東京慈恵医科大学大学院緩和医療学教授
2019年 千葉大学医学部附属浦安リハビリセンター特任教授
2021年 君津中央病院 PCU部長、科長
2023年 蒲田クリニック院長、理事長
2024年 石川島記念病院在宅事業部長
資格・役職等:
日本専門医機構麻酔科専門医
日本認定医機構がん治療認定医
日本緩和医療学会認定医
日本ペインクリニック学会専門医
日本麻酔科学会認定医・指導医
日本認定医機構がん治療認定医
日本緩和医療学会認定医
日本ペインクリニック学会専門医
日本麻酔科学会認定医・指導医