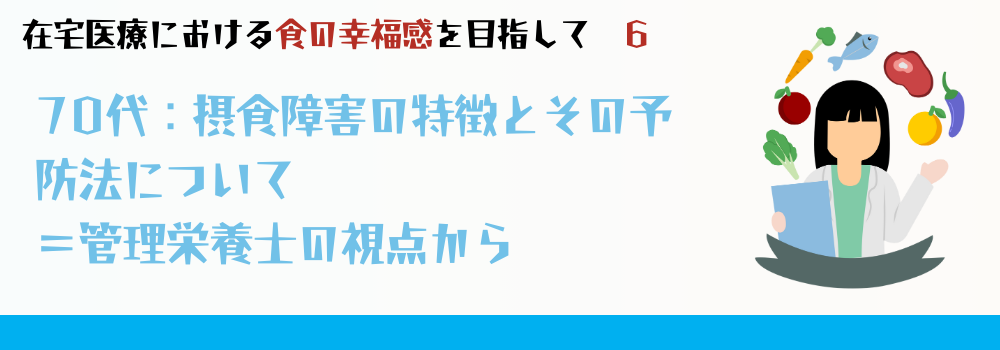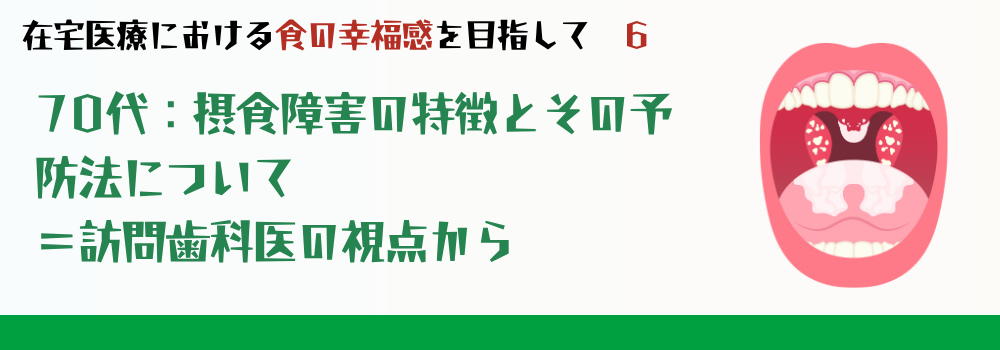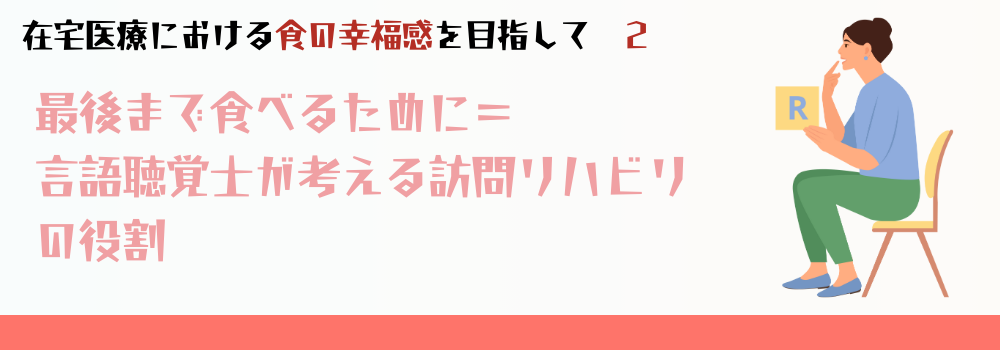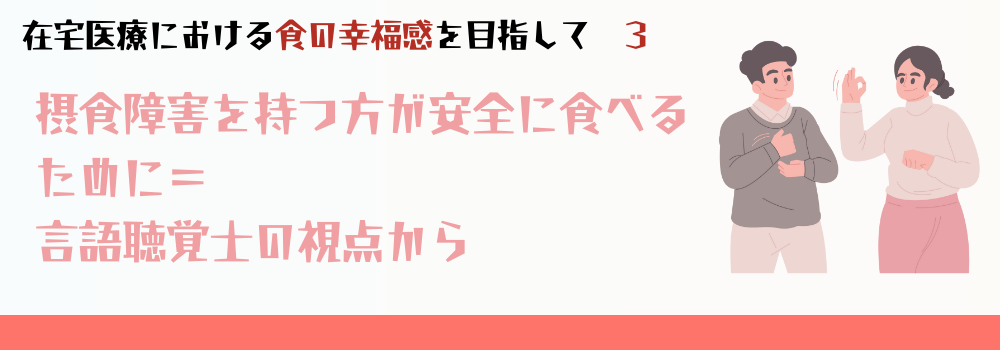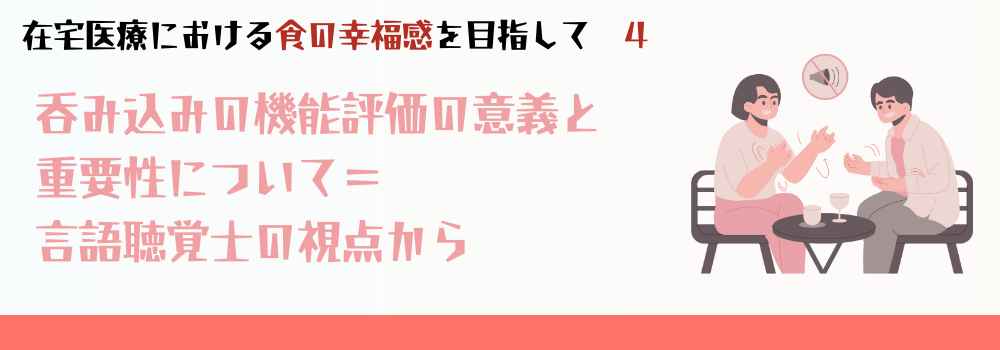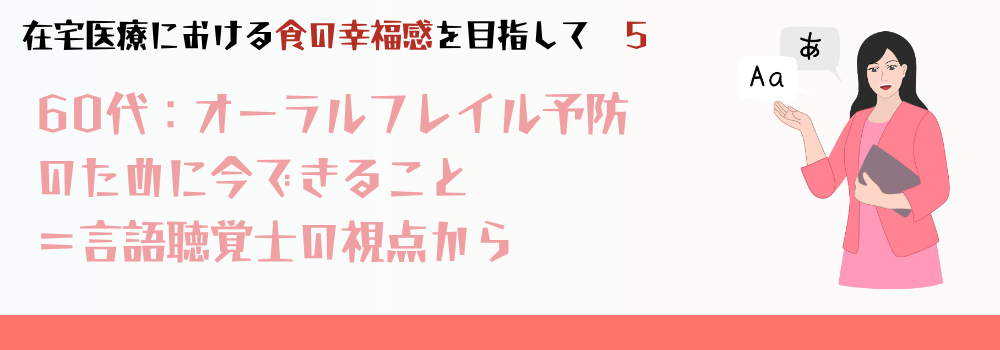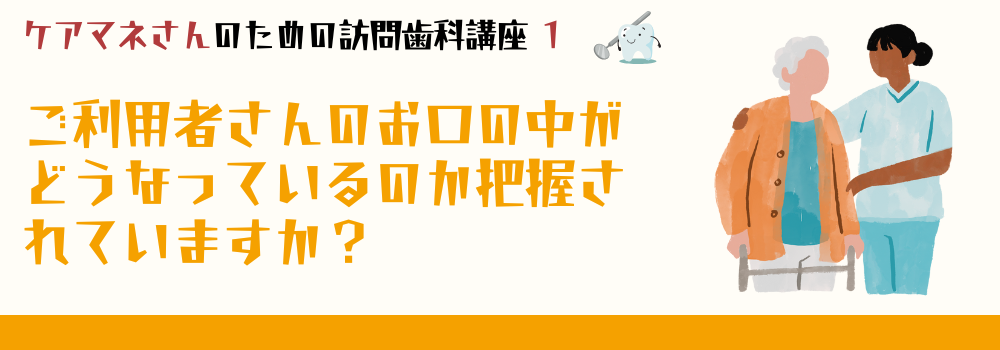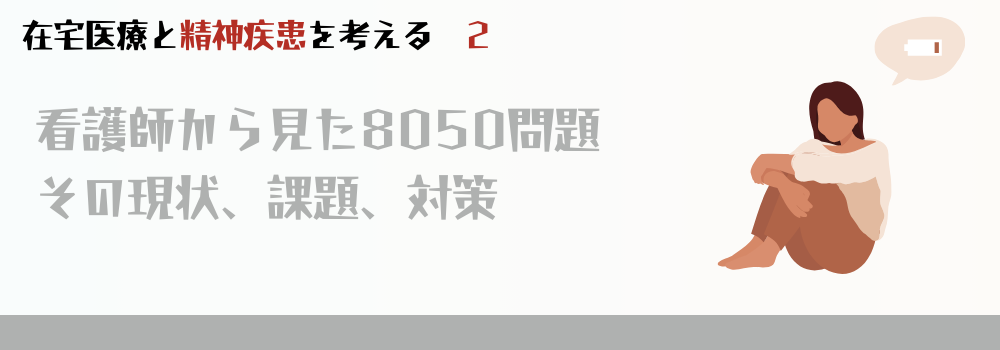「ちょっと食が細くなった」は老化のせい? 70代からの“口の老い”に向き合う=言語聴覚士の視点から 最終更新日:2025/07/12
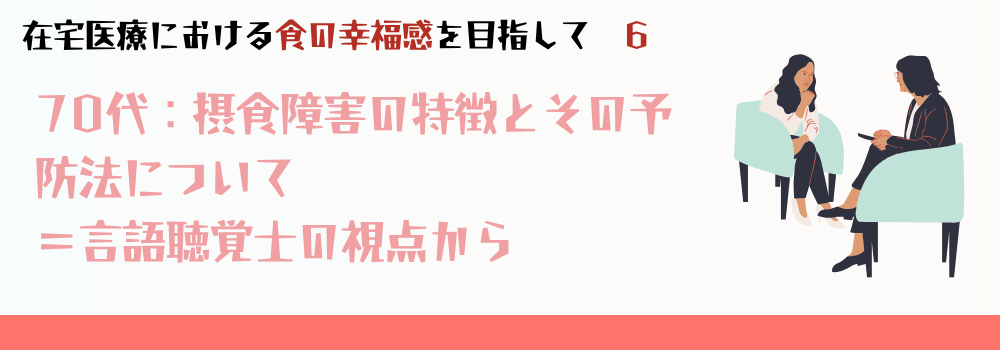
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
前回から年代別の予防について配信、6回目の今回は70代を対象に「70代からの“口の老い”に向き合う」と題して、言語聴覚士の立場として、國谷侑岐言語聴覚士(株式会社サンショー)により解説いただきました。
前回から年代別の予防について配信、6回目の今回は70代を対象に「70代からの“口の老い”に向き合う」と題して、言語聴覚士の立場として、國谷侑岐言語聴覚士(株式会社サンショー)により解説いただきました。
はじめに
70代を迎えると「ちょっと食が細くなったかも」「最近むせることが増えた」と感じる方が増えてきます。それでも多くの方は、「年を取ったから仕方ない」とやり過ごしてしまうのではないでしょうか。けれど、そうした小さな変化の裏に、「飲み込む力(嚥下機能)」の低下が隠れていることがあります。
この嚥下機能の衰えは、誤嚥性肺炎や低栄養といった命に関わるリスクにもつながるため、見過ごさずに向き合うことが大切です。この記事では、言語聴覚士(ST)の視点から、70代に見られやすい嚥下障害の特徴と、日常生活でできる予防法についてご紹介します。

摂食嚥下障害とは
摂食嚥下障害とは、食べ物を口に入れてから噛み、飲み込み、胃へ送り届ける一連の動作に支障が出ている状態を指します。高齢になると、舌や喉の筋力の低下、感覚の鈍化、咳反射の低下などが重なり、嚥下機能のバランスが崩れやすくなります。
高齢期に見られる嚥下機能の変化
70代になると、以下のような変化が現れやすくなります。
食事中や水分摂取時のむせ:嚥下タイミングのずれや筋力低下により、誤って気道に入りやすくなるため、注意が必要です。
食後の声のかすれ:食後の声のかすれや湿った声は、「のど風邪」や加齢と見られがちですが、実は誤嚥のサインであることもあります。特に声帯がうまく閉じないと、飲み込んだものが気道に入りやすくなるため注意が必要です。
食欲の低下や食事の億劫感:むせや飲み込みにくさが不安となり、食事を避ける傾向が強まります。
食後の咳や疲労感:飲み込む動作自体が負担となっているケースもあります。
不顕性誤嚥(silent aspiration)に注意
誤嚥には、むせによって気づけるものばかりではありません。高齢者では、誤って気道に入ってもむせが起きない「不顕性誤嚥」が増えてきます。
これは、咳反射や感覚の低下により、誤嚥に気づけない状態で、誤嚥性肺炎の主な原因となります。症状としては、慢性的な微熱、食欲低下、体重減少、繰り返す肺炎などが見られることがあります。本人や家族が気づきにくいため、早めの専門的評価が重要です。
日常生活でできる予防法
嚥下機能の衰えは自然な変化ですが、日常の工夫で進行を遅らせることができます。
1. 食事前の準備運動
・深呼吸、首回し、肩の上下運動
・「あ・い・う・べー体操」や「パタカラ体操」で舌や口周りの筋肉を刺激

2. 姿勢と食べ方の工夫
・背筋を伸ばし、軽く顎を引いた正しい姿勢で食べる
・一口量は少なめにし、よく噛んでから飲み込む
3. 唾液の活用
・耳下腺・顎下腺・舌下腺のマッサージ
・こまめな水分摂取(1日1.5Lを目安)
・室内の湿度を保ち、口腔の乾燥を防ぐ
4. 発声を習慣に
・声を出すことは声帯のトレーニングになり、咳反射の維持にも効果的
・会話や歌、音読などを積極的に取り入れる
家族が気づきやすい“ささいな変化”とは?
嚥下機能の低下は、本人が自覚しにくいケースも多くあります。特に不顕性誤嚥のようにむせが起きない場合、周囲の気づきが予防の第一歩になります。
ご家族や周囲の方が次のような変化に気づいたときは、嚥下機能の評価を検討するサインです:
・食事中、食後に声がかすれる・湿った感じになる
・食べる量が減り、食事に時間がかかるようになった
・食後に咳をすることが増えた
・なんとなく疲れやすく、食事を避けるようになった
・体重が減ってきた、微熱が続く
・以前より話す声が小さくなった、滑舌が悪くなった
こうした変化は、必ずしも大きな異常ではありませんが、飲み込む力の衰えのサインであることがあります。
「気のせいかな」と思っても、迷ったときは早めに専門職へ相談することが、結果的に重症化を防ぐことにつながります。
「気のせいかな」と思っても、迷ったときは早めに専門職へ相談することが、結果的に重症化を防ぐことにつながります。
モデル患者事例
Nさん(76歳・女性)——食事の「なんとなくの不安」の背景にあったもの
こうした変化が見られた方の一例として、76歳女性・Nさんの事例をご紹介します。Nさんは一人暮らしで、週2回デイサービスを利用。趣味は短歌と新聞の切り抜きで、生活はおおむね自立していました。ここ数ヶ月、食事中にむせることが増え、「お茶がのどに引っかかる感じがする」「最近、食べるのがしんどい」と話していました。

デイサービスの職員がその変化に気づき、言語聴覚士(ST)による訪問評価につながりました。VE(嚥下内視鏡検査)では、喉頭挙上の遅れ、咽頭残留、液体による軽度の不顕性誤嚥が確認されました。Nさん自身も「飲み込むのが怖い」と話しており、体重も1ヶ月で1.5kg減少していました。支援では次のような介入を実施しました:
・食事前にパタカラ体操や首・肩の運動で嚥下筋を活性化
・背筋を伸ばし、あごを軽く引く食事姿勢と、ひと口量の調整
・汁物やお茶にとろみを付ける
・新聞の音読(1日5分)による声帯閉鎖の強化
3週間後には「むせが減ってきた」「食べるのが楽になった」と本人の表情も明るくなり、体重も安定しました。
このように、「なんとなくの不安」やささいな違和感の段階でも、早期の評価と介入によって生活の質は大きく改善します。70代の“まだ大丈夫”を見逃さずに対処することが、誤嚥性肺炎や低栄養の予防につながります。
専門的評価を受けることの重要性
「むせが増えた」「声が変わった」「なんとなく食べづらい」と感じたら、嚥下機能の評価を受けてみるのも一つの選択肢です。言語聴覚士による評価では、次のような段階的かつ多角的な視点からアセスメントを行います。

1. スクリーニング検査(簡易テスト)
医療現場では、安全かつ短時間で評価できる方法として、以下のような簡易テストが用いられます。
・RSST(反復唾液嚥下テスト):30秒間に唾液を何回飲み込めるかを数える
・MWST(改訂水飲みテスト):少量の水を飲んでもらい、むせや呼吸変化を確認
・フードテスト(ゼリーなど):半固形物を用いて、嚥下反応の安全性をみる
2. 質問紙による主観的評価
・EAT-10(嚥下スクリーニング質問票):10項目から日常の嚥下困難を点数化。ご本人の主観的なつまずきに気づくことができます。
3. 食事・口腔機能の観察
実際の食事場面で、一口の量や噛み方、飲み込みのタイミング、姿勢の安定性などを確認。舌や口唇の動き、口腔清掃状態、声の変化なども評価の対象になります。
4. 認知・注意機能の確認
嚥下動作には集中力や理解力が関係するため、必要に応じて簡易的な認知評価を行うこともあります。
5. 専門的検査
・VF(嚥下造影検査):X線で嚥下の動きを視覚的に確認する
・VE(嚥下内視鏡検査):内視鏡を用いて咽頭・喉頭を直接観察する
これらの結果をもとに、食事形態の調整や口腔・嚥下リハビリなど、個別に適した支援が提案されます。評価は検査だけでなく、その人らしい食べ方・暮らし方を見つける手がかりでもあります。
まとめ:食べる力を守るということ
「食べる」という行為は、栄養をとるだけではなく、人との会話や楽しみ、生きる喜びにもつながっています。そしてこの力は、年齢とともに衰えるからこそ、意識的に守っていく必要があります。
特に70代は、「まだ大丈夫」と感じていても、実は嚥下機能がゆるやかに変化し始めている大切な時期です。ほんの少しの気づきと、日々のちょっとした習慣の積み重ねが、10年後の健康を大きく左右します。

言語聴覚士は、皆さんの「飲み込む力」「話す力」を支える専門家です。いつも通りに食べられることは、健康を支える力です。そしてその力は、その人らしい暮らしを守る土台にもなります。
気になる症状がある方は、どうぞ一度、言語聴覚士にご相談ください。
関連リンク:
執筆:

國谷侑岐(くにたにゆうき)
言語聴覚士
経歴:
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
資格:
言語聴覚士
言語聴覚士