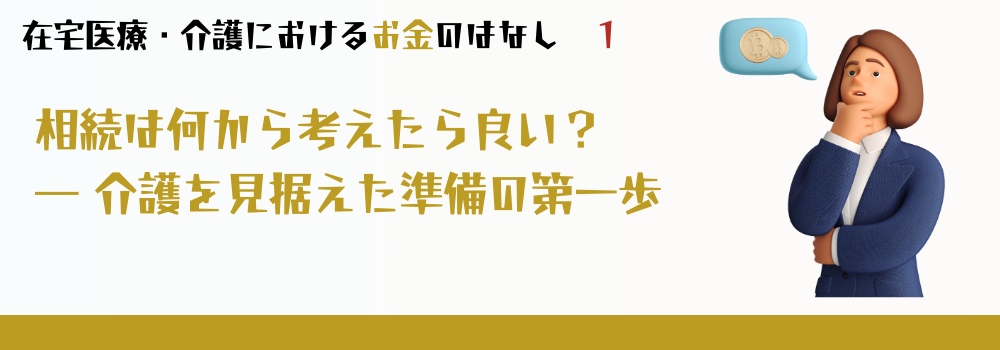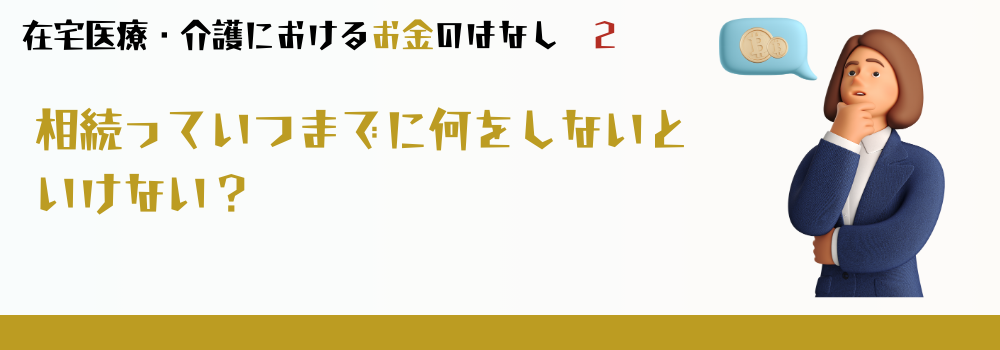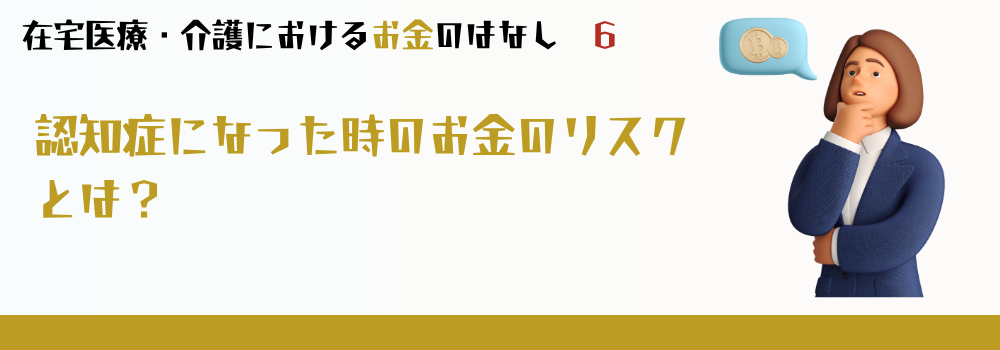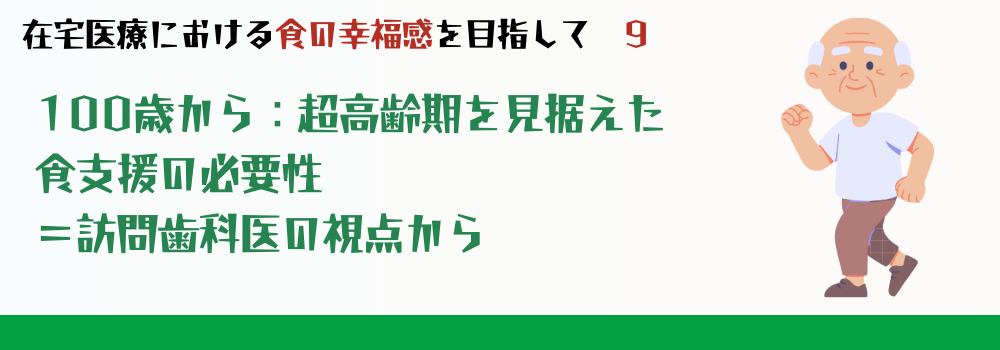国の介護保険でカバーされる範囲とは?~制度の正しい理解が、将来の安心につながる~ 最終更新日:2025/08/04
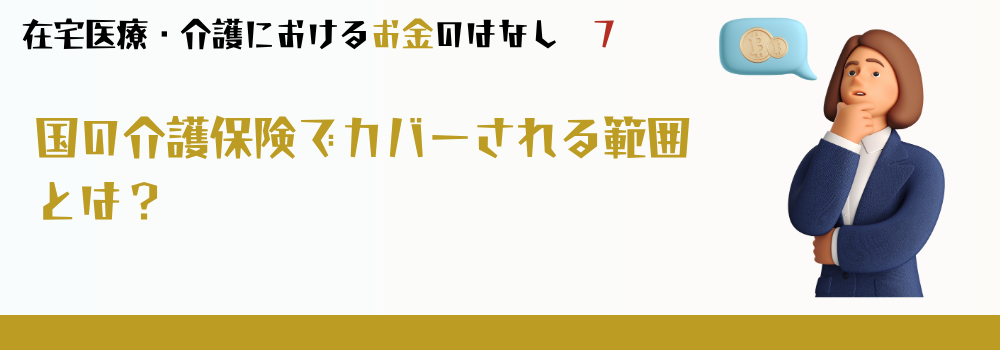
「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けする新企画「在宅医療・介護におけるお金のはなし」。
全10回シリーズの第7回は、「国の介護保険でカバーされる範囲とは?」です。
「もし、家族に介護が必要になったらどうしよう」
在宅介護や施設入所など、介護に関する悩みや不安は誰にでも訪れ得るテーマです。そうしたときに支えとなるのが「介護保険制度」です。でも、「実際にはどこまでサポートしてもらえるの?」「自己負担はどのくらい?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は、介護が必要になったときに国の制度として利用できる「介護保険」について、そのカバー範囲や利用方法、注意点をわかりやすく整理していきます。
「もし、家族に介護が必要になったらどうしよう」
在宅介護や施設入所など、介護に関する悩みや不安は誰にでも訪れ得るテーマです。そうしたときに支えとなるのが「介護保険制度」です。でも、「実際にはどこまでサポートしてもらえるの?」「自己負担はどのくらい?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は、介護が必要になったときに国の制度として利用できる「介護保険」について、そのカバー範囲や利用方法、注意点をわかりやすく整理していきます。
介護保険制度とは?
介護保険制度は、2000年にスタートした国の社会保障制度のひとつで、要介護や要支援状態になった高齢者が、できるだけ自立した生活を送れるように支援する仕組みです。
主なポイントは以下のとおりです。
主なポイントは以下のとおりです。
・対象者:原則65歳以上(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の特定疾病に該当する方(第2号被保険者)
・利用条件:要介護または要支援の認定を受けることが必要
・サービスの内容:在宅介護サービス、施設サービス、地域密着型サービスなど多岐にわたる
・費用負担:原則1割〜3割の自己負担(所得に応じて異なる)

カバーされる主なサービス内容
介護保険で利用できるサービスは大きく3つに分かれており、それぞれに適した「利用者の状態」や「希望する生活スタイル」があります。ここでは代表的なサービスの特徴と、どのような方に向いているかを詳しく見ていきましょう。
1. 在宅サービス(自宅での生活を維持したい方に)
「住み慣れた自宅で過ごし続けたい」と希望する方や、家族の介護力が一定ある方にとって、在宅サービスは非常に有効です。
● 訪問介護(ホームヘルプ)
・対象者:要支援〜要介護の方で、日常生活動作(ADL)が一部制限されている人など
・提供内容:身体介助(入浴・排せつ・食事など)や生活援助(掃除・調理・洗濯など)
・向いている人:ひとり暮らしや老老介護の家庭で、日常生活に一部だけ手助けが必要な方。プライバシーを大切にしたい人にも適しています。
● 訪問看護
・対象者:医療的ケアが必要な方(人工呼吸器、インスリン注射、褥瘡ケアなど)
・提供内容:看護師による健康管理、点滴、服薬管理、緊急時対応
・向いている人:慢性疾患や医療ニーズがありつつも、病院ではなく自宅での療養を希望する方。医療と介護の両立が求められるケースに有効です。
● 訪問入浴介護
・対象者:自力での入浴が困難で、寝たきりや車椅子の方
・提供内容:入浴車による訪問、簡易浴槽の設置、3人1組での介助付き入浴
・向いている人:清潔を保ちたいが入浴に不安がある方や、寝たきりでも安全に入浴したいという強い希望がある方に最適です。
● 通所介護(デイサービス)
・対象者:要支援〜要介護の方で、ある程度の移動や会話が可能な人など
・提供内容:送迎、食事、入浴、機能訓練、レクリエーション
・向いている人:日中ひとりで過ごす時間が長い高齢者や、家族の介護負担軽減を図りたい家庭。社会とのつながりを持ちたい方にもおすすめです。
● 短期入所生活介護(ショートステイ)
・対象者:要支援〜要介護の方
・提供内容:数日〜数週間の施設利用(食事・入浴・介助・見守り)
・向いている人:家族が旅行や入院などで一時的に介護ができない場合や、在宅介護のリフレッシュ(レスパイト)目的での利用に適しています。
2. 施設サービス(自宅介護が困難な方向け)
日常生活全般にわたって介助が必要で、自宅での介護が難しくなった方には、施設への入所という選択肢があります。
● 特別養護老人ホーム(特養)
・対象者:原則、要介護3以上の高齢者で常時介護が必要な人
・提供内容:生活全般の介助、看護、機能訓練など
・向いている人:家族の支援が受けにくく、24時間体制でのケアが必要な方。入居希望者が多く、申し込みから入所まで時間がかかる場合もあります。
● 介護老人保健施設(老健)
・対象者:病院での治療は終えたが、在宅生活に戻るにはリハビリが必要な人
・提供内容:医師・看護師・リハビリ専門職による短期的な機能回復支援
・向いている人:「在宅復帰」を目標とする人や、退院後のリハビリを経て自立を目指す方。施設は原則3〜6か月の滞在が想定されています。
● 介護医療院(旧:介護療養型医療施設)
・対象者:長期的な医療的管理が必要な人
・提供内容:医療と介護の両方を提供する長期入所施設
・向いている人:人工呼吸器、経管栄養などの医療処置が継続的に必要で、かつ家庭での生活が困難な高齢者。

3. 地域密着型サービス(「地域のつながり」を大切にする方に)
可能な限り自宅で生活したい人や、地域との結びつきを維持したい方に向けて、地域に根ざした小規模なサービスも整備されています。
● 小規模多機能型居宅介護
・対象者:要支援・要介護の方
・提供内容:「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できる柔軟なサービス
・向いている人:施設ではなく自宅で暮らし続けたいが、家族だけでは不安という方。サービス提供者との信頼関係を築きながら、必要なときに柔軟な支援を受けたい人にぴったりです。
● 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・対象者:認知症の診断を受けた要支援2以上の方
・提供内容:少人数での共同生活を通じた、家庭的なケアと認知症の進行抑制支援
・向いている人:症状が進行してきたが、大規模施設では混乱してしまうという方。落ち着いた環境で、自分らしい暮らしを続けたい方に適しています。
● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・対象者:要介護度が高く、頻繁な支援が必要な方
・提供内容:24時間体制での定期的な訪問と、必要時の緊急対応
・向いている人:自宅で最期まで過ごしたいが、重度の介護や医療が必要な人。夜間の対応も含めて、安心して在宅生活を続けたい方に効果的です。
こんなふうに、同じ「介護サービス」といっても、サービスごとに目的や対象者が異なり、生活スタイルや希望する暮らし方によって選ぶべき支援は変わってきます。
ケアマネジャーと相談しながら、「自分に合った介護のかたち」を見つけることが、将来の安心につながります。
介護保険の利用には「要介護認定」が必要
介護保険サービスを使うには、まず市区町村の窓口に「要介護認定」の申請を行うことが必要です。
申請後、以下の流れで認定されます。
申請後、以下の流れで認定されます。
1.訪問調査:市の調査員が自宅を訪れ、本人の状態を確認
2.主治医意見書:かかりつけ医が心身の状態を記載
3.審査会による判定:専門家による審査で、要支援1〜2、要介護1〜5のいずれかに認定
この認定結果によって、利用できるサービスの内容や限度額が決まります。
介護保険で「すべて」まかなえるわけではない
ここで気をつけたいのは、「介護保険でできることには限りがある」という点です。
介護保険のサービスには「支給限度額(1か月あたり)」があり、その枠内でサービスを受ける分には自己負担は原則1〜3割です。ただし、この限度額を超えた分は全額自己負担になります。
介護保険のサービスには「支給限度額(1か月あたり)」があり、その枠内でサービスを受ける分には自己負担は原則1〜3割です。ただし、この限度額を超えた分は全額自己負担になります。
さらに、以下のようなものは介護保険の対象外です。
・病院への通院や通院介助
・掃除・洗濯・買い物などの家事代行(本人以外のためのもの)
・生活のための住居費・食費・光熱費
・住宅リフォームの全額(介護リフォームの一部に限り対象)
つまり、介護保険はあくまで「介護が必要になったときの一部を補助する制度」であり、全ての費用をまかなえるものではありません。

利用者負担はどれくらい?
原則、介護保険サービスの利用者負担は1割ですが、所得に応じて2割や3割になる場合があります。また、サービス内容によっては別途費用が必要となることもあります。
さらに、要介護度によって1か月あたりの支給限度額も異なります(例:要介護1で約17万円程度、要介護5では約36万円程度)。この枠を超えたサービスを利用したい場合は、超過分を全額負担しなければなりません。
在宅介護を希望するなら、制度の理解がカギ
「できれば住み慣れた自宅で過ごしたい」という思いは、多くの人に共通しています。その希望を実現するためには、介護保険制度の内容を正しく理解し、早めに情報収集を行うことが大切です。
地域包括支援センターやケアマネジャーとの連携もポイントになります。いざというときに慌てず、自分や家族に合ったサービスを上手に選べるよう、早めの準備をしておきましょう。
まとめ
介護保険制度はとても心強い制度ですが、制度の枠内だけですべてをカバーすることはできません。実際に介護が始まると、想像以上に費用がかかるケースも多く、特に「食費・居住費」や「介護用の住宅改修費」「家族の通院・交通費」などは介護保険の対象外となります。
介護が始まってから慌てることのないよう、日頃から将来の資金計画に介護費用を組み込んでおくことが大切です。また、家計の負担を軽減するために、「介護保険外サービス」や「高額介護サービス費制度」などの活用も視野に入れておくと、経済的にも精神的にも余裕を持って介護に向き合えるようになります。
次回のテーマは、「介護の費用ってどのくらいかかるの?」です。公的な介護保険を踏まえて、実際に掛かる費用を具体的にみていきながら、万が一に備えていきましょう。

関連リンク:
執筆:

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。