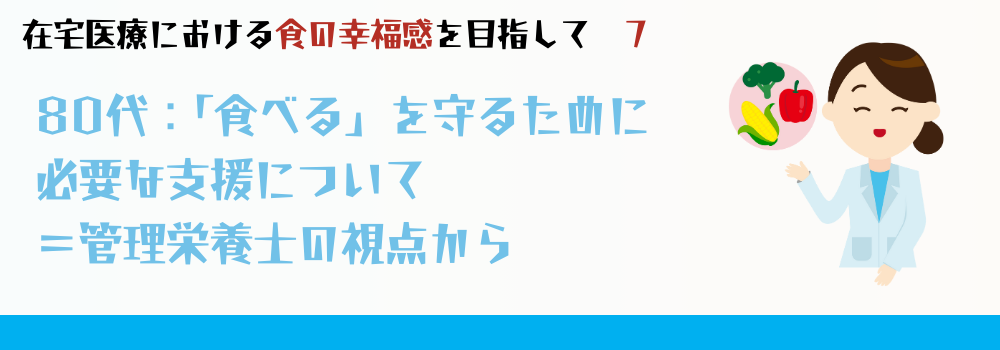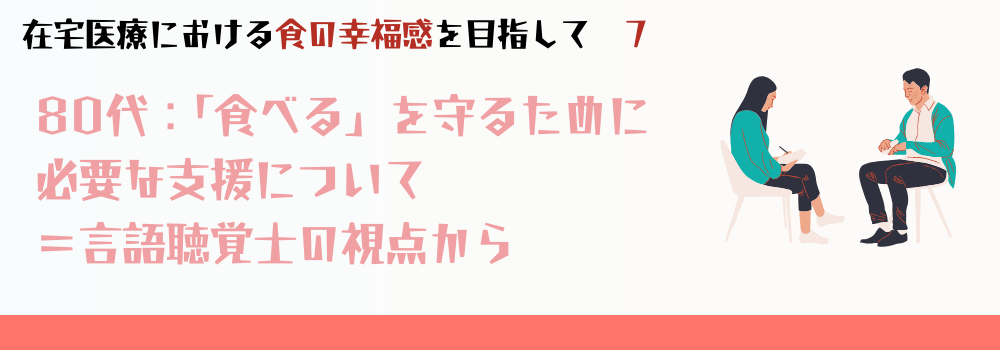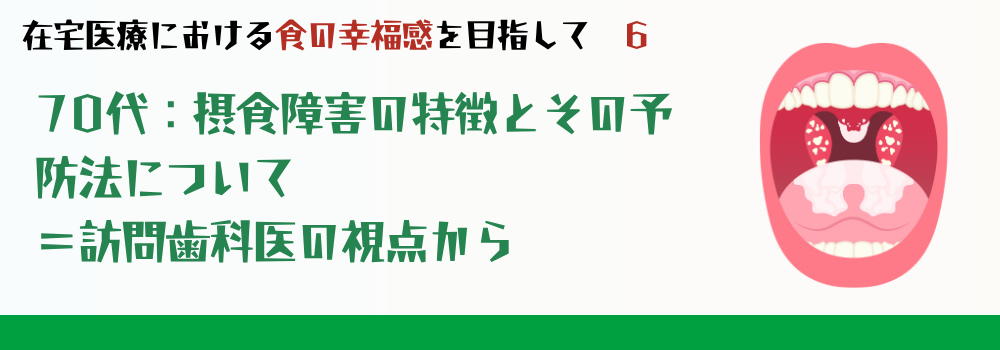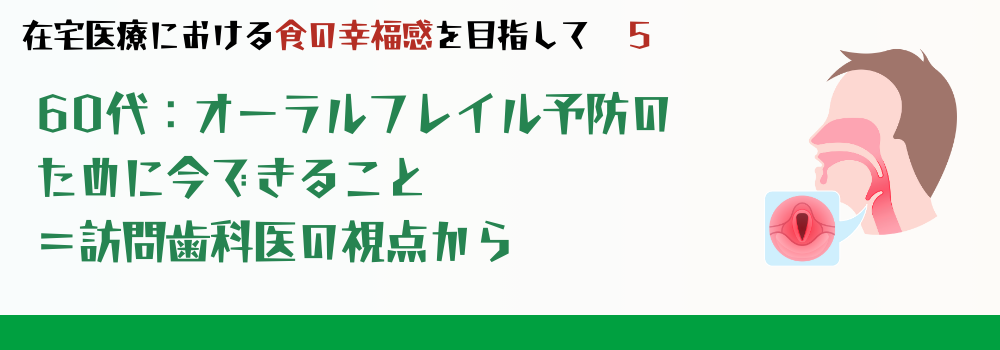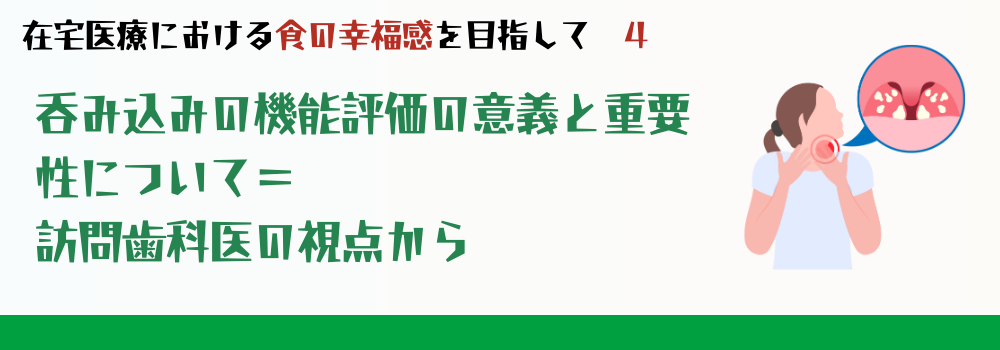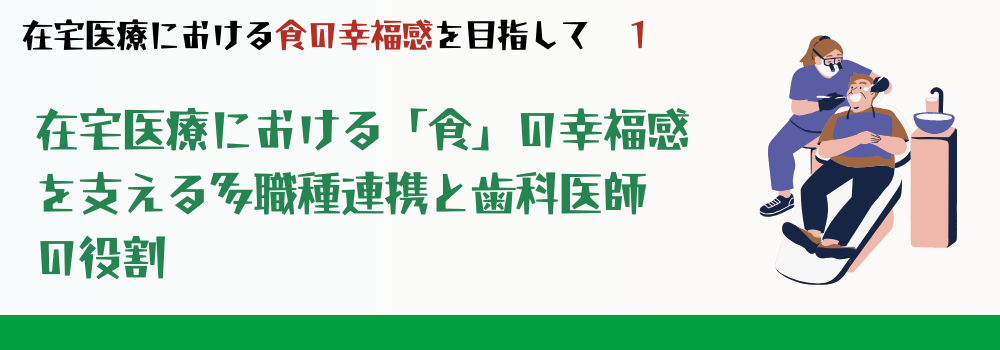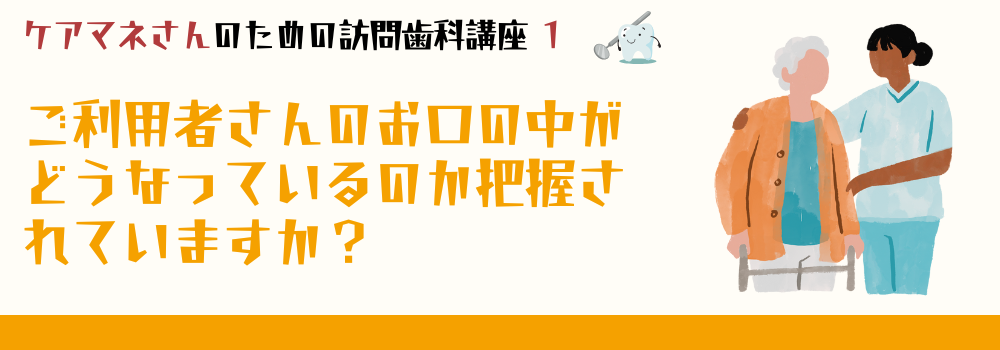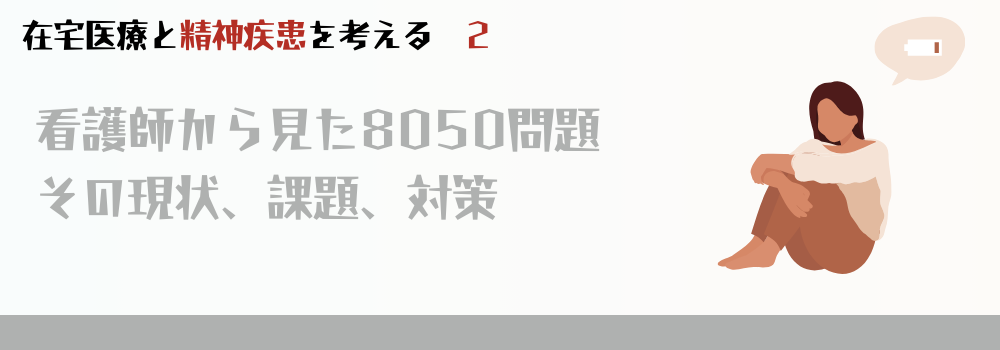「食べる」がこんなにつらいとは思わなかった—80代からの口の支え方=訪問歯科医の視点から 最終更新日:2025/08/17
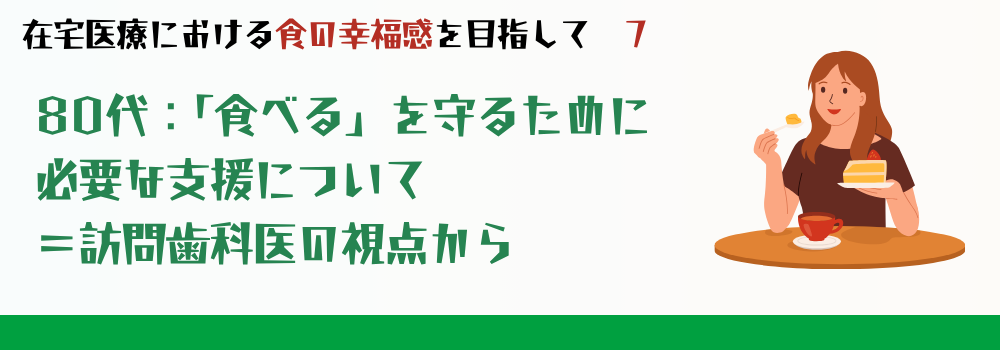
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
7回目の今回は80代を対象に「80代からの口の支え方」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
7回目の今回は80代を対象に「80代からの口の支え方」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
はじめに
80代。それは人生100年時代の「後半戦」ともいえる時期です。現役で地域の活動に関わる方もいれば、入退院を繰り返している方、介護が必要になった方もおり、生活スタイルも健康状態も千差万別です。ただ、そんな多様性の中で共通して語られるのが、「いよいよ食べることが難しくなってきた」という声です。
「むせるのが怖くて食べるのが億劫になった」
「疲れて食事が進まない」
「水を飲むだけでも咳き込むようになった」
これらは、80代によく見られる摂食嚥下機能の低下=“口の老化”の現れです。食事は生命を支えるだけでなく、楽しみや尊厳にもつながる大切な行為。ここでは、80代の口と飲み込みの変化、そしてその人らしい「食べる」を守るために必要な支援について考えていきます。
「むせるのが怖くて食べるのが億劫になった」
「疲れて食事が進まない」
「水を飲むだけでも咳き込むようになった」
これらは、80代によく見られる摂食嚥下機能の低下=“口の老化”の現れです。食事は生命を支えるだけでなく、楽しみや尊厳にもつながる大切な行為。ここでは、80代の口と飲み込みの変化、そしてその人らしい「食べる」を守るために必要な支援について考えていきます。

「飲み込めない」のは体力だけの問題ではない
80代では、加齢による身体の変化が、より複雑に、より顕著に現れてきます。
嚥下筋群の著しい低下
70代まではゆるやかに進んでいた嚥下に関連する筋肉の筋力低下が、80代になると急激に現れます。舌の動きが遅くなる、咽頭の収縮が不十分になる、喉頭の挙上が遅れる——これらの変化により、飲み込みにかかる時間が長くなり、誤嚥や咽頭残留が起こりやすくなります。
呼吸・姿勢・意識レベルの影響
飲み込む動作は、呼吸や姿勢、集中力とも密接に関連しています。高齢者では呼吸機能の低下や体感を維持する筋力の低下による前傾姿勢、眠気・注意力の低下が重なり、「飲み込む」という本来無意識に、自動的に行っていた行為が難しくなっていきます。
「むせても気づかない」サイレントアスピレーション
80代で特に注意すべきは、むせない誤嚥(サイレントアスピレーション)です。咽頭感覚の低下に伴う咳反射の低下により、気道に食物や唾液が入っても咳き込まず、気づかないうちに肺炎を起こしてしまうことがあります。
複数の要因が絡み合う
80代の嚥下障害は、単なる「老化」だけではありません。
それまでの既往歴(脳梗塞・パーキンソン病・認知症)、薬の副作用、義歯の不調、食環境など、多因子が重層的に関与してきます。
それまでの既往歴(脳梗塞・パーキンソン病・認知症)、薬の副作用、義歯の不調、食環境など、多因子が重層的に関与してきます。
「予防」から「支援」へ——80代からの嚥下ケアの考え方
80代では、「鍛えて維持する」という視点に加えて、「支えて補う」という考え方が重要になってきます。無理をせず、安全に、快適に食べるための日常生活での工夫が、生活の質を大きく左右します。
1. 無理に形のある食形態にこだわらない
もちろん、「噛んで飲み込む力」が残っていれば、しっかりした食事を続けることが理想です。しかし、嚥下機能が明らかに低下しているのに、これまで通りの食形態に固執するのは、誤嚥や窒息の危険を高めることにもなります。
・刻み食=安全ではありません。細かく刻んだ食材はばらけて咽頭に残りやすく、誤嚥を助長することがあります。
・飲み込む能力に合わせて、とろみ食・ゼリー食・ムース食など、形を保ちつつ飲み込みやすい食品を選びましょう。
・食形態の変更は、医師・歯科医師・ST(言語聴覚士)・管理栄養士の評価をもとに、根拠のある調整を行うことが大切です。
2. 「食べられる環境」を整える
高齢者の嚥下障害には、環境要因も大きく影響します。
・姿勢:車椅子やベッドでの食事は、頭が後ろに倒れがち。やや前傾で顎を引く姿勢が飲み込みを助けます。
・ペース配分:1口の量を減らし、食間にしっかり呼吸を整える。早食いは禁物です。
・集中力:テレビを見ながら、話しながらの“ながら食べ”は注意力を削ぎます。静かな環境で、1対1で向き合って食事をしましょう。
3. 嚥下に適した口腔ケアを徹底する
80代では、誤嚥性肺炎のリスクが高まるため、食べる前後の口腔内清掃が特に重要です。食べカスや細菌が残った状態で誤嚥が起きると、重篤な肺炎につながることがあります。
・歯磨きが困難な場合は、スポンジブラシや口腔湿潤剤を活用
・うがいが難しい方には、ワイプタイプの清拭ケアも有効
・専門的口腔ケア(歯科専門職によるプロフェッショナルケア)を月1回以上取り入れましょう
4. 「食べること」そのものをあきらめない
嚥下障害が進行しても、口から食べたい、味わいたいという思いは、最後まで残ります。たとえ1口、ひとさじでも、「口に入れて味わう」ことは、栄養以上の意味を持ちます。
・食事が難しい場合でも、嚥下評価用のゼリーや氷片・風味水などで刺激を与える
・口腔ケア+間接嚥下訓練を組み合わせ、状態を少しでも回復させる
・「口から食べる」という本人の希望を、周囲が考えることはその後の継続的な支援体制を構築する基礎になります。
5. 多職種チームで「食べる」を支える
80代では、医療的な配慮や介護支援が欠かせません。歯科医師・言語聴覚士・医師・看護師・栄養士・介護職員が連携し、個別の評価・計画・支援を行うことが重要です。
・在宅であれば訪問歯科・訪問リハ・訪問栄養指導の活用を
・施設であれば経口維持加算の活用を通じて、計画的に支援
「この人はもう食べられない」と決めつける前に、「どのような支援で、安全に食べられるか」を考える視点が求められます。
モデル患者事例
田中静子さん(84歳・女性)
要介護1。5年前に夫を亡くし、現在は一人暮らし。娘が週に数回訪問し、買い物や通院の付き添いをしている。軽度の認知症があり、曜日感覚や食事の記憶にやや混乱がみられる。日中はほとんどテレビの前で過ごし、1日1〜2回の宅配弁当が食事の中心。咀嚼や飲み込みが苦手になり、最近は食後に咳き込んだり、食欲が落ちてきた。

【起こっている困りごと】
1. 食事中にむせたり、咳が止まらない
→ 特にお茶や汁物でむせやすく、「喉に貼りつく感じ」がある。1人のときに起こると、不安感が強くなる。
2. 食事量の減少と栄養の偏り
→ 食事に時間がかかるため途中で残すことが多く、主菜を避けて柔らかいごはんや果物ばかり食べてしまう。
3. 孤食による意欲の低下
→ 一人で食べることが多く、食事への興味や喜びが薄れている。「食べてもおいしく感じない」と話すこともある。
【日常の対処法】
1. 姿勢と環境の工夫
→ テーブルと椅子での食事を基本とし、やや前屈姿勢で顎を引くよう意識する。テレビは消して、静かな環境で集中して食べる。
2. 飲み込みやすい食事の提供
→ 柔らかさとまとまりを保った食事(例:ムース食やゼリー食)に切り替える。汁物にはとろみをつけ、誤嚥を予防する。
3. 少量ずつ、ゆっくり食べる支援
→ 1口の量をスプーン1/2杯程度にし、「食べる・飲み込む・休む」のリズムをつくる。見守りや声かけが有効。
4. 口腔ケアと嚥下体操
→ 食前の歯磨きや唾液腺マッサージ、簡単な嚥下体操(あいうべ体操など)を娘と一緒に行うことで、飲み込みの準備を整える。
静子さんのように、心身の変化と生活環境が複雑に絡む80代の嚥下障害では、「無理なく、でもあきらめずに食べる」支援が鍵となります。生活の中でできる小さな工夫の積み重ねが、誤嚥や低栄養、孤立感を防ぐ大きな支えになります。
おわりに:そのひとくちが、人生を照らす
80代の摂食嚥下障害は、人生の終盤に直面する大きな課題のひとつです。しかしそれは、単に「食べられるかどうか」ではありません。
食べることは、生きること。
口から食べるという行為が、人の心や尊厳を支えています。
だからこそ、80代からは「予防」だけでなく、「希望をかなえる支援」が必要なのです。
だからこそ、80代からは「予防」だけでなく、「希望をかなえる支援」が必要なのです。
1口でも、1品でも、その人が「食べられてよかった」と思えるように。
その瞬間を支えることが、私たち医療者・支援者の使命です。
その瞬間を支えることが、私たち医療者・支援者の使命です。

関連リンク:
執筆: