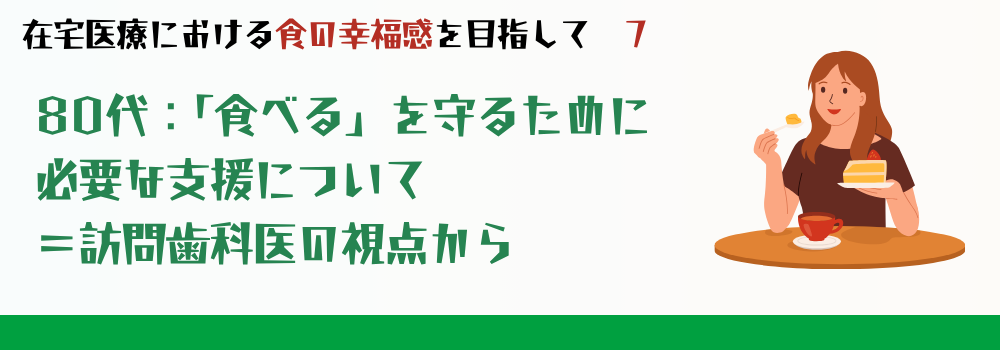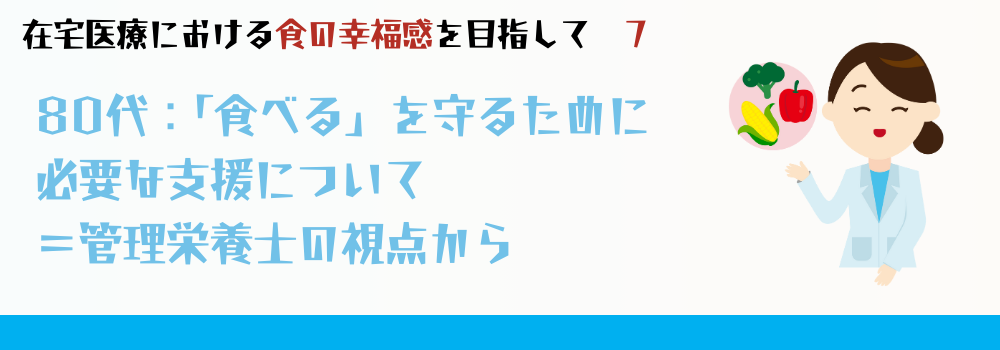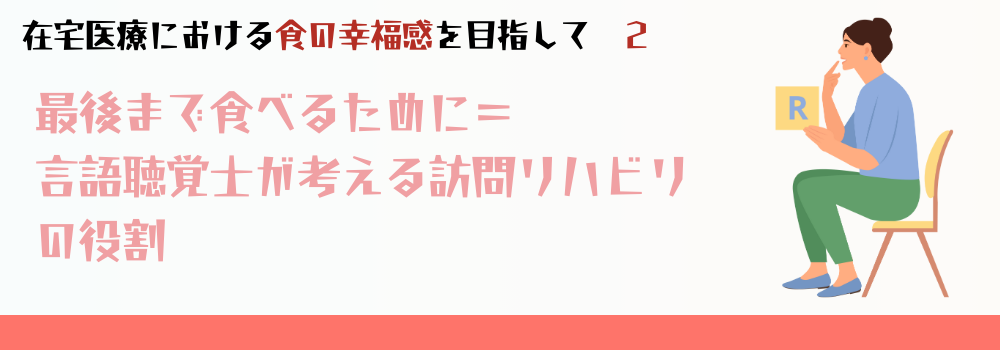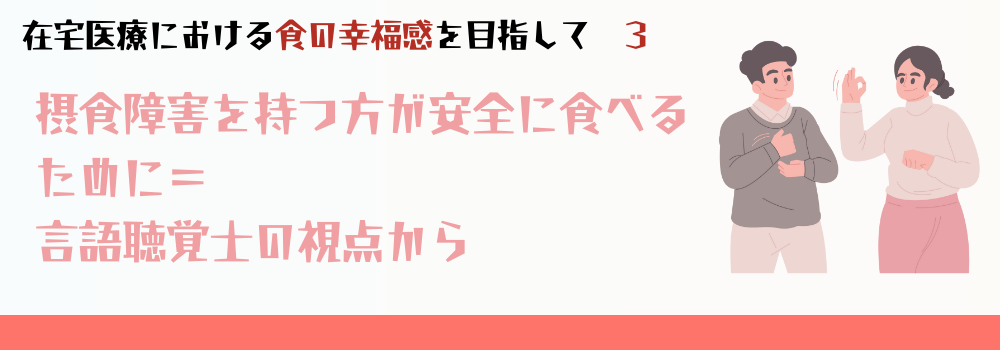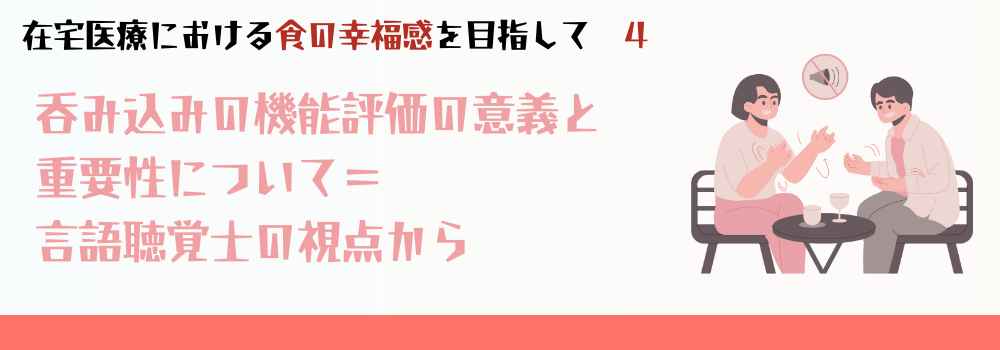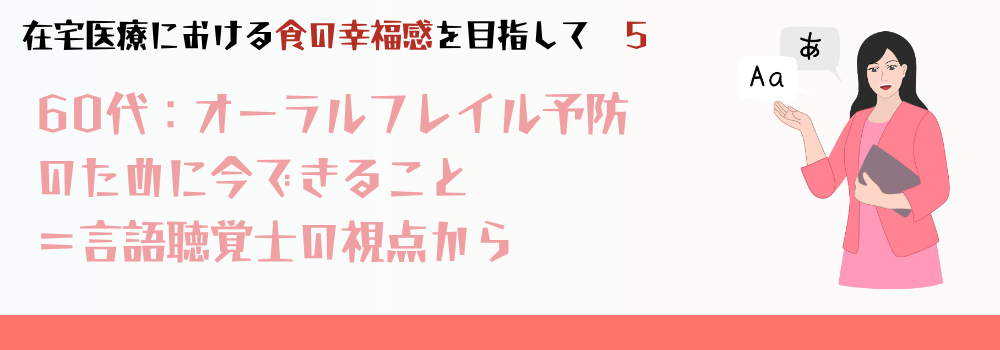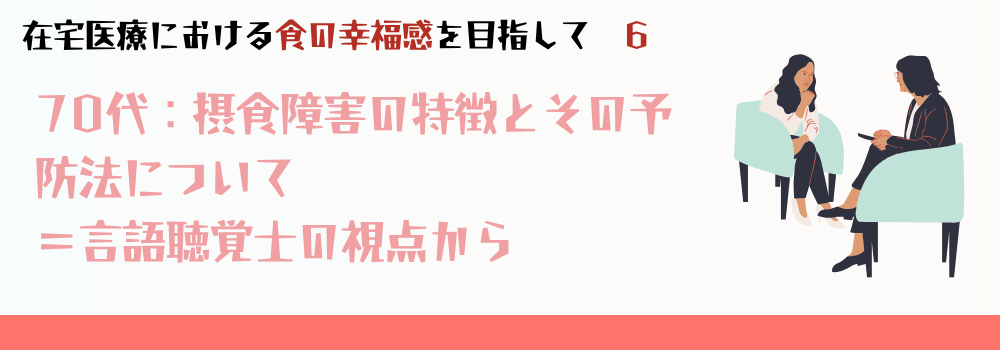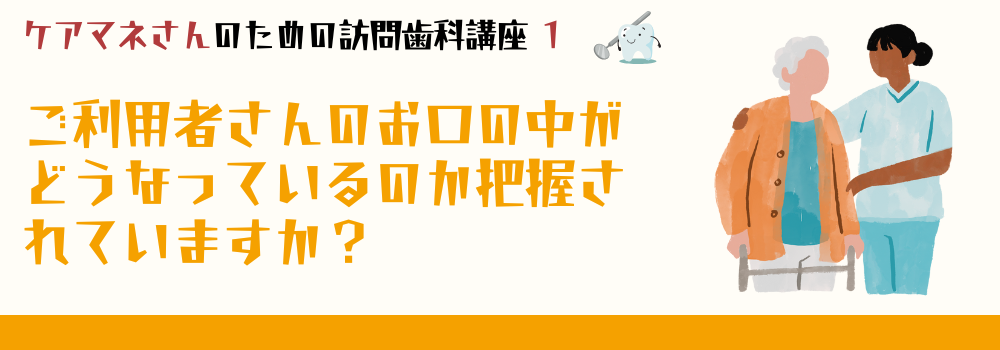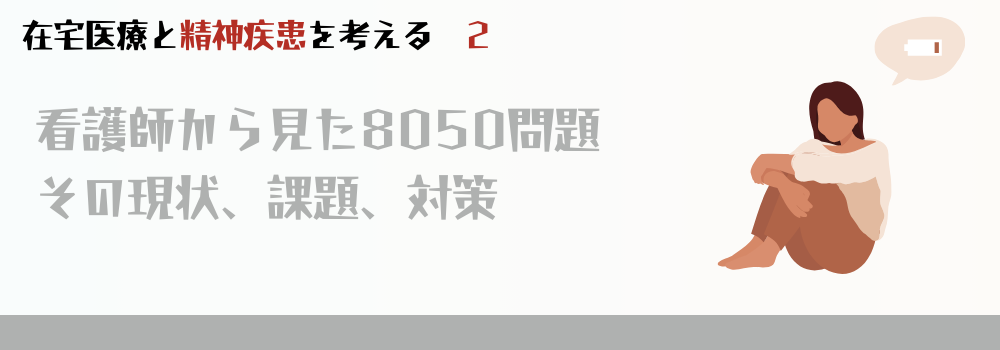「食べる」がこんなにつらいとは思わなかった—80代からの口の支え方=言語聴覚士の視点から 最終更新日:2025/08/17
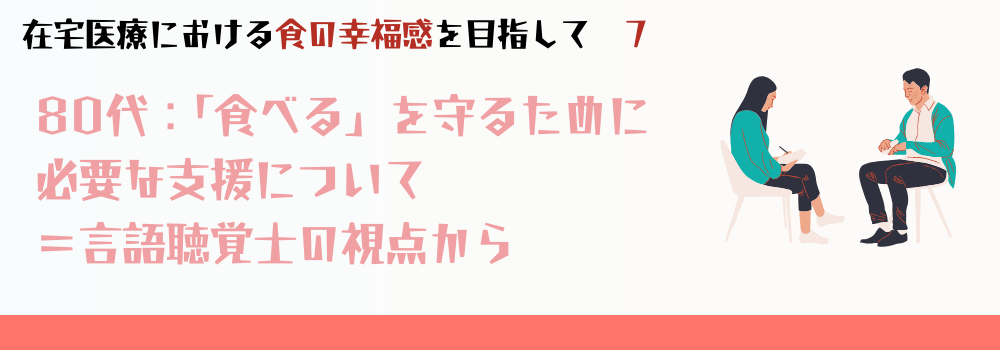
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
7回目の今回は80代を対象に「80代からの口の支え方」と題して、言語聴覚士の立場として、後藤茉利奈言語聴覚士(株式会社サンショー)により解説いただきました。
7回目の今回は80代を対象に「80代からの口の支え方」と題して、言語聴覚士の立場として、後藤茉利奈言語聴覚士(株式会社サンショー)により解説いただきました。
加齢に伴う嚥下機能の変化とは?
嚥下(飲み込み)機能は、加齢そのものでも変化します。厚生労働省の報告(2019年「高齢者の低栄養対策に関する検討会」)によれば、高齢者の約6割以上に、何らかの咀嚼・嚥下機能の低下がみられるとされています。

80代になると、加齢に伴って嚥下機能に様々な変化が生じます。主な原因と特徴は以下の通りです。
1. 筋力の低下(サルコペニア)
全身の筋力が落ちると、嚥下に使う筋肉も弱くなります。特に舌や喉の筋力が低下すると、食べ物を喉の奥に送る力が弱くなり、誤嚥や咽頭残留(食べ物が喉に残る)につながります。
2. 嚥下反射の遅れ
通常、食べ物が喉に触れると反射的に飲み込む動作が起きますが、高齢になるとこの「嚥下反射」が遅れ、誤って気道に入ってしまうリスクが高まります。
3. 唾液分泌の減少
唾液には食べ物をまとめたり、喉を滑らかに通す働きがあります。唾液が減ると、食塊がうまく形成されず、スムーズな嚥下が難しくなります。
4. 病気による影響
脳梗塞、パーキンソン病、認知症など、神経に影響を及ぼす病気は嚥下機能にも大きく関わります。特に脳卒中後の嚥下障害はよく見られ、リハビリや食事の工夫が必要になります。
こうした変化に気づかず、以前と同じように食事を続けていると、「むせる」「食欲が落ちる」「体重が減る」「誤嚥性肺炎を起こす」などの問題が起こることがあります。
「むせる=老化だから仕方ない」ではない
「最近、ごはんでむせることが増えたのよ」「水を飲んだらゴホゴホして…」
──そんな声を80代の方からよく耳にします。でも、それを「年だから仕方ない」と見過ごしてしまうのはとても危険です。
──そんな声を80代の方からよく耳にします。でも、それを「年だから仕方ない」と見過ごしてしまうのはとても危険です。
「むせる」ことが増えてきた場合、誤嚥(ごえん)が起きている可能性があります。誤嚥とは、本来食道に入るはずの食べ物や飲み物、唾液が誤って気管(空気の通り道)に入ってしまうことです。
これが何度も起こると、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)という病気になってしまうことがあります。これは、食べ物や飲み物、唾液などが誤って気道(肺につながる通り道)に入ってしまい、そこで細菌が増えて炎症を起こすものです。
誤嚥性肺炎は、高齢者の命を脅かす病気の一つです。実際、日本の死亡原因の第5位が「肺炎」であり、さらにその多くが高齢者の「誤嚥性肺炎」だと考えられています(❏ 厚生労働省 令和5年人口動態統計より)。
「年のせいでむせやすくなった」
「水を飲んだだけで咳き込む」
「水を飲んだだけで咳き込む」
こうした変化を、「仕方ない」と済ませてしまうのはとても危険です。むせることは、体が「今、うまく飲み込めていませんよ」と教えてくれる大事なサイン。
放っておかず、早めに対策することで、命を守ることにもつながります。
ここで、Aさんのケースをご紹介します。
ケース紹介:Aさん(80代女性)とおにぎりの話
Aさん(80代・女性)は、毎朝「梅干し入りのおにぎりと味噌汁」を楽しみにして暮らしていました。長年続いてきたその習慣は、Aさんにとって“1日のはじまりの喜び”だったのです。
ところが最近、食事中にむせることが増え、病院では「ミキサー食への移行」を勧められるようになりました。
しかし、見た目も味も大きく変わってしまったミキサー食を目にしたAさんはがっかり。「もうおにぎりは無理なのね…」と、落ち込んでしまいます。食欲も次第に落ちていきました。
そこで、ご家族と相談のうえ、訪問リハビリで言語聴覚士(ST)による嚥下評価を行いました。
しかし、見た目も味も大きく変わってしまったミキサー食を目にしたAさんはがっかり。「もうおにぎりは無理なのね…」と、落ち込んでしまいます。食欲も次第に落ちていきました。
そこで、ご家族と相談のうえ、訪問リハビリで言語聴覚士(ST)による嚥下評価を行いました。

評価の結果、Aさんにはまだ十分な咀嚼力(噛む力)と嚥下反射(飲み込みのタイミング)が保たれていることがわかりました。むせの原因は「食べる姿勢」や「一口の量」「食べ方のクセ」にあると判断され、以下のような支援を実施しました。
① 小さめで柔らかく握ったおにぎりに変更
喉に詰まりにくく、まとまりやすいサイズでおにぎりを準備。ごはんの水分量にも配慮し、硬すぎず柔らかすぎない食感に。具材の梅干しは細かく刻み、塩分や酸味にも注意を払いました。
② 一口量を減らし、ゆっくりよく噛むよう声かけ
食事中は「小さくして、よく噛んでからごっくんしようね」と優しく声かけ。一口量が多かったことがむせの一因だったため、無理なく食べられる量を調整し、ペースのコントロールを意識しました。
③ 顎を軽く引いた正しい姿勢を意識
食事の際は椅子に深く腰掛け、やや前傾姿勢で顎を軽く引くように調整。足裏が床につくよう高さも整え、誤嚥を防ぐ「安定した姿勢」を確保しました。
④ 食前の口・喉の体操を導入
食事前に「あいうえお体操」や舌・首のストレッチなどを行い、口周りや喉の筋肉をしっかり動かすことで、嚥下機能を活性化。
体操は1〜2分ほどで終わる簡単なもので、Aさんも無理なく続けられました。
体操は1〜2分ほどで終わる簡単なもので、Aさんも無理なく続けられました。
その結果、Aさんは「おにぎりがまた食べられるようになってうれしい」と笑顔を取り戻し、食欲も回復。ご家族も「やっぱり好物を楽しめるのは大きいですね」と安心されていました。
むせの原因は姿勢・一口量・食材の選び方など、調整で改善できることもあります。言語聴覚士は、飲み込み機能だけでなく、その人の「食べたい気持ち」や「日々の楽しみ」も大切にしながら支援を行います。完全に元の食事に戻すことが難しくても、「できる範囲」で好みに近づけることで、日常の質は大きく変わります。
「その人らしさ」を守る食支援
言語聴覚士が食支援を行う際に大切にしているのは、「安全」と「楽しみ」の両立です。
「安全に食べるため」といって、全てをゼリーやペーストにしてしまえばいいわけではありません。その人にとって大切な「味」「食感」「食べる楽しみ」をできる限り残すことが、生活の満足度や生きがいにつながるからです。
例えば、お誕生日に大好きだったお寿司を一貫でも食べられるよう工夫する。そんな小さな達成が、「また頑張ろう」という意欲につながることも多くあります。
家族や介護者とチームで支えること
在宅や施設では、言語聴覚士だけでなく、ご家族や介護職、看護師、栄養士など多職種が関わって「食べる」を支えます。言語聴覚士はその中で、「どうすれば安全に、そして楽しく食べられるか」を専門的に提案し、チーム全体をつなぐ役割も担っています。
ときには「これは無理だろう」と思われていた食事が、ちょっとした姿勢の調整や一口量の工夫で、可能になることもあります。諦めずに、皆で考えていくことがとても大切です。

最後に:80代だからこそ、“その人らしく”
「もう年だから」「仕方ないよね」――
そんな何気ない言葉が、知らないうちにその人の「好きなこと」や「楽しみ」を遠ざけてしまうことがあります。
そんな何気ない言葉が、知らないうちにその人の「好きなこと」や「楽しみ」を遠ざけてしまうことがあります。
でも、80代はただ年をとるだけの時期ではありません。
長い年月で培ってきた暮らしの知恵や習慣、好みやこだわりは、年を重ねるほどに味わい深くなっていきます。
だからこそ、高齢者への支援は「その人らしく生きること」を大切にするべきです。
言語聴覚士は、食べにくさやむせの原因をじっくりと見きわめ、「どうすればまた安心して“あの味”を楽しめるか」を一緒に考え、支える存在です。
「おにぎりがまた食べられた」
その一言には、日々の喜びを取り戻した証が込められています。
その一言には、日々の喜びを取り戻した証が込められています。
年齢にかかわらず、その人の「好き」や「日課」「楽しみ」を守ることが、生きる力につながります。
「できない」を前提にするのではなく、「どうすればできるか」をともに探す支援――それが言語聴覚士の役割であり、私たちが大切にしたいケアの形です。

関連リンク:
執筆:

後藤茉利奈(ごとうまりな)
言語聴覚士
経歴:
北里大学医療衛生学部言語聴覚療法学専攻を卒業後、回復期・慢性期病院、老人健康保健施設で言語聴覚士として勤務。
出産、育児をきっかけに小児分野へ転向。
児童発達支援での経験を経て、現在は訪問看護リハビリステーションさんぽに所属。
北里大学医療衛生学部言語聴覚療法学専攻を卒業後、回復期・慢性期病院、老人健康保健施設で言語聴覚士として勤務。
出産、育児をきっかけに小児分野へ転向。
児童発達支援での経験を経て、現在は訪問看護リハビリステーションさんぽに所属。