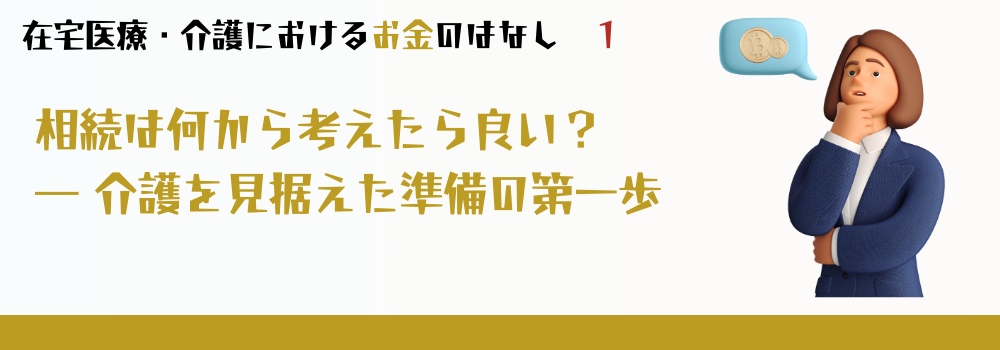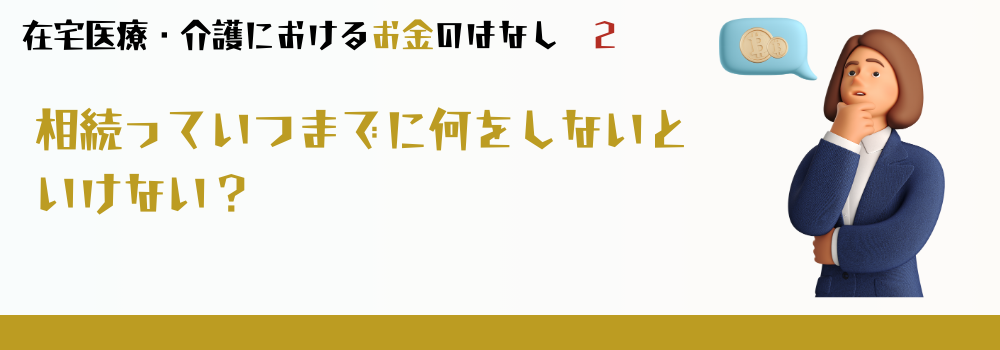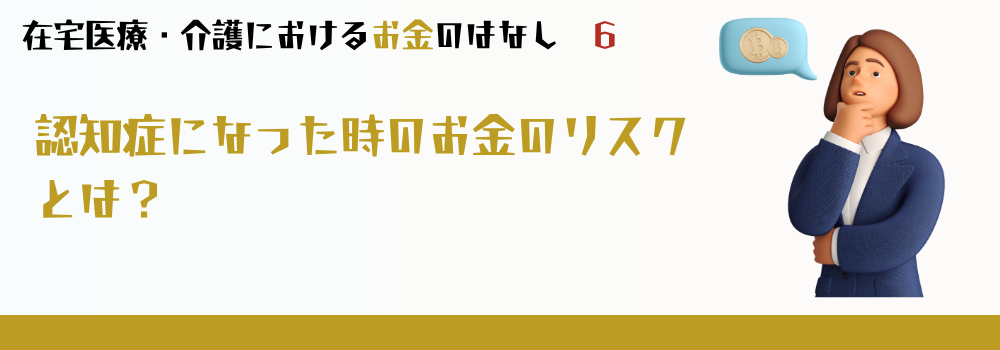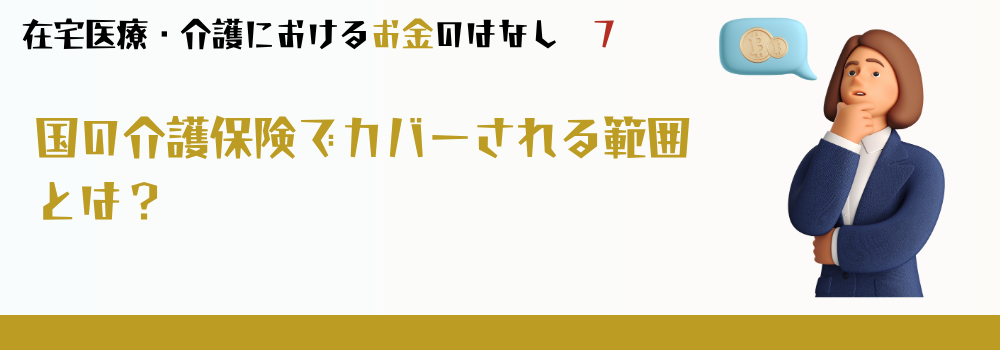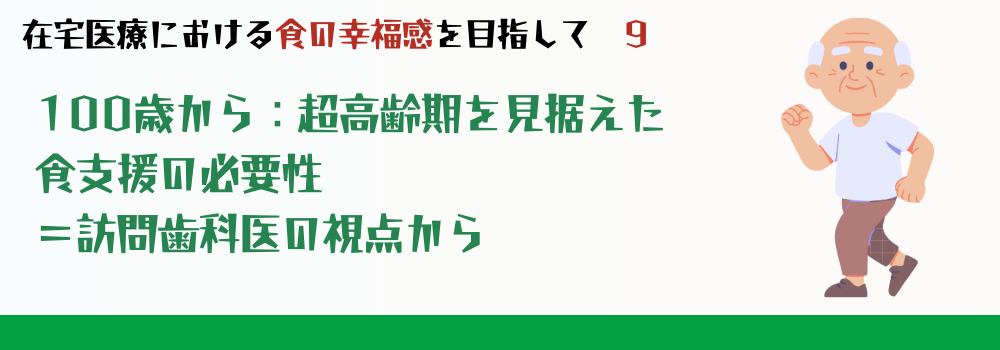介護の費用って、どのくらいかかるの? 最終更新日:2025/09/01
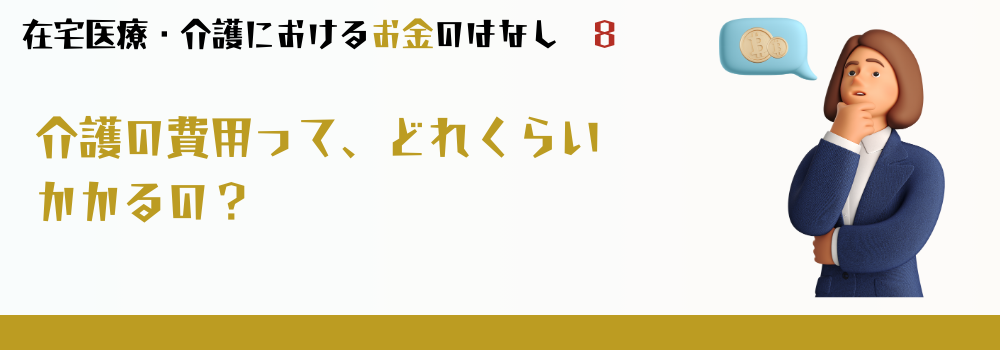
「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けする新企画「在宅医療・介護におけるお金のはなし」。
全10回シリーズの第8回は、「介護の費用って、どのくらいかかるの?」です。
私たちや家族が年齢を重ねる中で、介護が必要になる場面は少なからず訪れます。その際に、多くの方が最初に思うことのひとつが「介護にはどのくらい費用がかかるのか」ということです。介護費用は、利用するサービスの種類や利用時間、要介護度、そして地域や加算の有無などによって大きく異なります。そのため、具体的にどのくらいかかるのかを把握しておくことは、家計の計画を立てたり、介護サービスを検討したりするうえで非常に重要です。
今回は、代表的な介護サービスである「訪問介護」「デイサービス(通所介護)」「ショートステイ(短期入所生活介護)」「小規模多機能型居宅介護」「オムツ・介護用品」に焦点をあて、それぞれの費用目安や特徴、注意点を整理してみましょう。
私たちや家族が年齢を重ねる中で、介護が必要になる場面は少なからず訪れます。その際に、多くの方が最初に思うことのひとつが「介護にはどのくらい費用がかかるのか」ということです。介護費用は、利用するサービスの種類や利用時間、要介護度、そして地域や加算の有無などによって大きく異なります。そのため、具体的にどのくらいかかるのかを把握しておくことは、家計の計画を立てたり、介護サービスを検討したりするうえで非常に重要です。
今回は、代表的な介護サービスである「訪問介護」「デイサービス(通所介護)」「ショートステイ(短期入所生活介護)」「小規模多機能型居宅介護」「オムツ・介護用品」に焦点をあて、それぞれの費用目安や特徴、注意点を整理してみましょう。
訪問介護(身体介護・生活援助)
訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅に訪問して、生活全般の支援や身体に直接関わる介護を行うサービスです。訪問介護には大きく分けて「身体介護」と「生活援助」の2種類があります。
<身体介護>
身体介護とは、入浴や排泄、食事の介助など、利用者の体に直接関わるサポートです。例えば、入浴介助を行う場合は、体を支えながらの作業となるため、負担が大きく、その分単価も高くなります。60分程度の利用を目安にした場合、全国平均で自己負担1割は約230円〜580円が目安です。数字に幅があるのは、要介護度や行う内容、地域加算の有無によって変動するためです。要介護度が高い場合や、複数の身体介護を同時に行う場合は金額が上がる傾向にあります。
<生活援助>
生活援助は、掃除や洗濯、買い物代行など、生活全般のサポートを行うサービスです。身体介護に比べて身体的な負担は少ないため、45分以上の利用で自己負担1割は約150円~250円前後が目安です。生活援助は身体介護が不要な方でも利用でき、家の中の日常生活を支えるうえで非常に重要な役割を果たします。
訪問介護の特徴は、必要な時間だけサービスを受けられる柔軟性にあります。たとえば、毎日の入浴介助だけをお願いする、週数回の掃除や洗濯だけを依頼する、といった使い方が可能です。費用は利用内容や要介護度によって変動しますので、ホームヘルパーとの相談やケアマネジャーのアドバイスをもとに計画的に利用することが大切です。

デイサービス(通所介護)
デイサービスは、利用者が日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練、レクリエーションなどを受けるサービスです。家庭での介護負担を軽減するだけでなく、他の利用者との交流や日常生活の維持、体力や認知機能の維持・向上も期待できるサービスです。
1日あたりの自己負担は、要介護度や提供されるサービス内容によって変わりますが、全国平均で約1,000円〜1,500円が目安です。例えば、入浴と機能訓練を組み合わせた標準的な1日利用でこの範囲となります。デイサービスの料金には、送迎サービスや食事代も含まれる場合がありますが、施設ごとに差があるため、利用前に確認しておくことが大切です。
また、デイサービスは利用者の自立支援を目的とするサービスであり、単に日中の見守りだけではなく、生活リハビリや体力維持、趣味活動の支援なども行われます。介護費用の目安だけでなく、どのようなサポートを受けられるかを理解することで、より適切に利用できます。
ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイは、家庭での介護が一時的に困難な場合に、施設に短期間宿泊し、食事や入浴、生活支援を受けるサービスです。利用目的としては、家族が旅行や仕事で介護できない期間の代替や、介護者の休息(レスパイトケア)などが挙げられます。
自己負担1割の場合、1泊あたり全国平均で約3,000円〜8,000円程度です。利用日数や介護度、行われる介護内容によって変動します。例えば、要介護度が高く入浴介助や排泄介助が必要な場合は費用がやや高くなる傾向があります。また、夜間加算や食費の一部自己負担が加わる場合もあるため、施設に事前確認することが重要です。
ショートステイを利用することで、家庭での介護負担を軽減し、家族が安心して休息や用事を済ませることができます。利用回数や期間は家族の状況や利用者の体調に応じて柔軟に設定可能です。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「宿泊」の3つのサービスを組み合わせて利用できる施設型サービスです。必要に応じて通いと訪問を併用したり、急に宿泊が必要になった場合に対応したりすることができます。
費用は利用形態や日数によって異なりますが、全国平均で自己負担1割の場合、ひと月あたり約10,000円〜100,000円程度です。通い中心で利用する場合は費用が低めになり、宿泊を伴う場合や身体介護の割合が増えると高くなる傾向があります。小規模多機能型の特徴は、利用者や家族のニーズに応じて柔軟にサービスを組み合わせられる点です。生活スタイルに合わせて適切なサービスを受けることで、家庭での介護負担を大きく軽減できます。

オムツや介護用品
介護に必要な消耗品としては、オムツやパッド、介護用衣類などがあります。これらは介護保険の対象外で、実費負担となります。1か月あたりの全国平均費用は、利用量によりますが、約3,000円〜5,000円程度です。介護度が高くなるほど使用量が増える傾向があります。
また、介護用品は施設や訪問介護サービスと併用することも多く、必要な用品の種類や数量をあらかじめ把握しておくと、費用管理がしやすくなります。
介護費用を理解するポイント
ここまで、代表的な介護サービスの費用目安を紹介しました。重要なのは、費用の数字だけに目を向けるのではなく、サービス内容や利用者の状況を理解して、自分や家族に必要なサポートを見極めることです。
・訪問介護は、身体介護と生活援助で費用もサポート内容も大きく変わります
・デイサービスは日中の見守りだけでなく、機能訓練や交流なども行われます
・ショートステイは家庭での介護が一時的に困難な場合に便利です
・小規模多機能型は、通い・訪問・宿泊を組み合わせて柔軟に利用可能です
・オムツや介護用品は介護度が高くなるほどコストが増えます
それぞれのサービスにはメリットとデメリットがあり、費用の目安を理解することで、家族の負担を減らし、安心して介護を受ける環境を整えることができます。
まとめ
介護費用は、サービスの種類や利用時間、要介護度、加算の有無によって変動します。数字だけを見ると複雑に感じますが、目安として把握しておくことで、家族の介護計画を立てる際や、介護サービスの選択に役立ちます。
最も大切なのは、自分や家族に必要なサポートを見極め、サービス内容と費用のバランスを考えることです。これによって、家庭での介護負担を軽減し、安心して日々の生活を送ることができます。また、介護サービスや費用に関する情報は随時更新されるため、ケアマネジャーや市区町村の窓口などを活用して、最新の情報を確認することも忘れずに行いましょう。

次回のテーマは、「介護をカバーする保険ってどんなものがあるの?」です。受けたいサービスを気持ちよく選択できるようになるためには、お金も必要です。いつなるか分からない介護に備えて、ご自身での貯蓄で準備するだけでなく、保険を活用するのが効果的です。介護をカバーする代表的な保険について把握しましょう。
関連リンク:
執筆:

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。