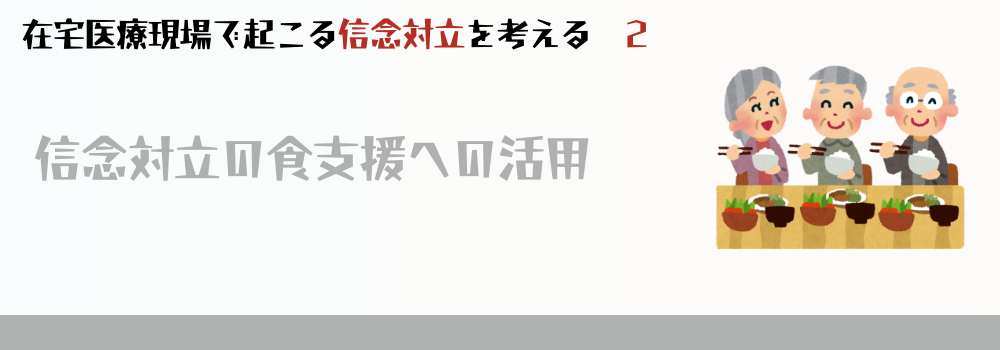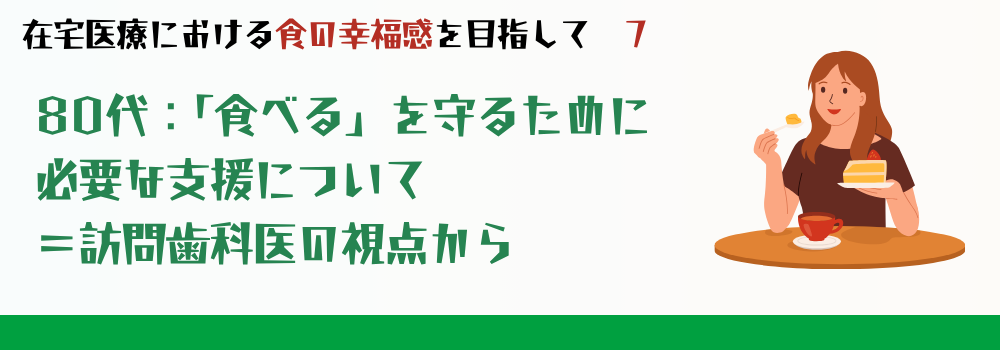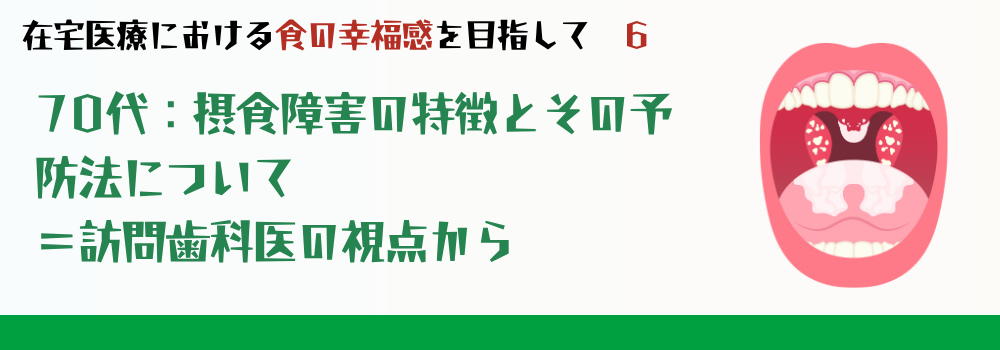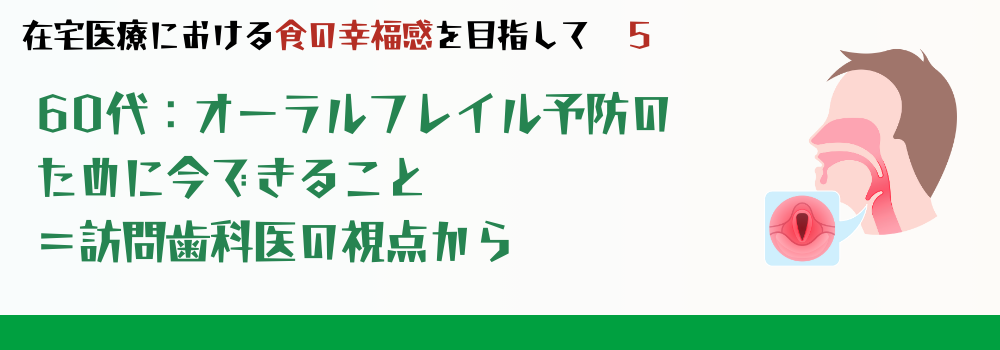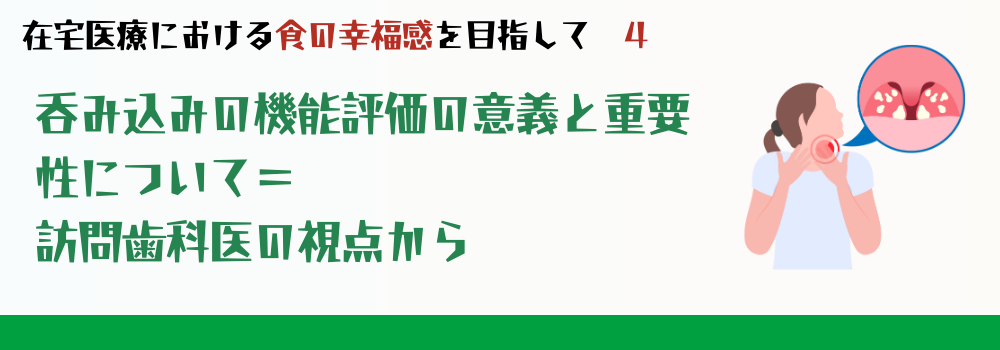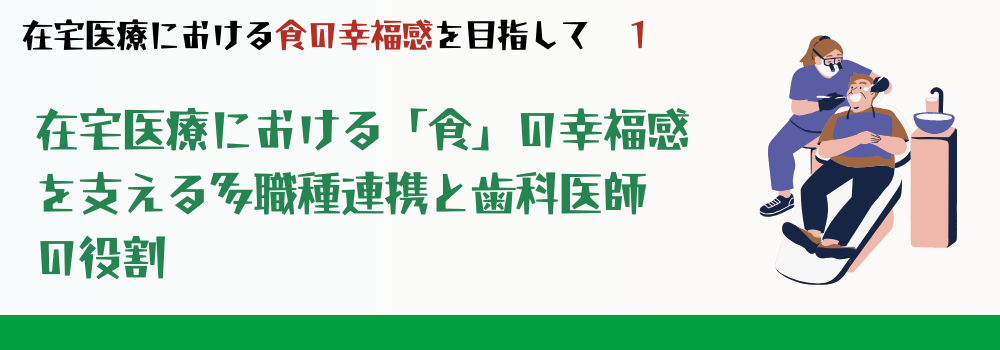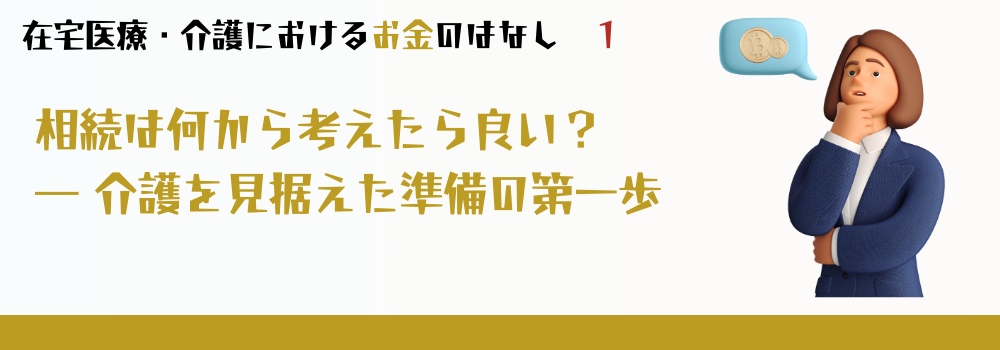医療現場における信念対立とは?原因・事例・解決法を解説|閉塞感を打開するヒント 最終更新日:2025/11/26
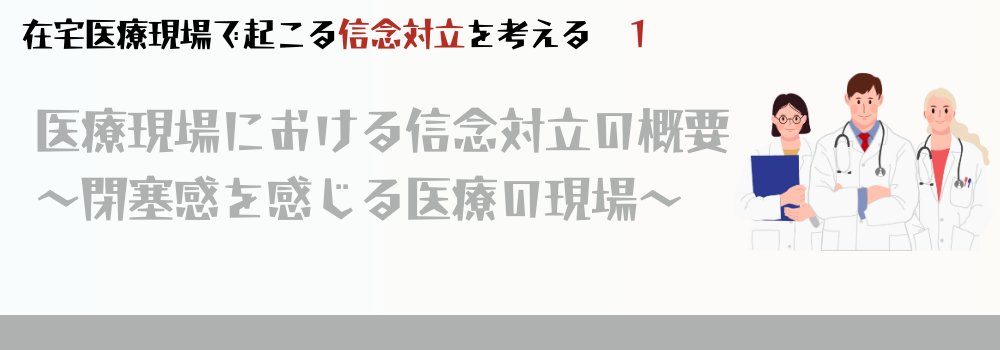
現在の医療は高度化、多様化し、また患者自身や家族は容易に様々な情報を入手可能ですが、事前にそれを理解しておくことが患者自身が自らの行動に責任を持ち主体的に治療に参加するということにつながっていきます。
しかし、逆に情報が過多なことにより最善策を選びにくくなってしまっていたり、「自分はたくさん情報や知識を持っているのに医療者から行われる情報の提示が不十分である」と物足りなく感じてしまうことも見受けられ、それが不安へと変わってしまうこともあります。
このような状態はなぜ生じてしまうのか、回避するにはどのような心構えが必要かを本稿では「信念対立」という概念を紹介することで考えてみたいと思います。
しかし、逆に情報が過多なことにより最善策を選びにくくなってしまっていたり、「自分はたくさん情報や知識を持っているのに医療者から行われる情報の提示が不十分である」と物足りなく感じてしまうことも見受けられ、それが不安へと変わってしまうこともあります。
このような状態はなぜ生じてしまうのか、回避するにはどのような心構えが必要かを本稿では「信念対立」という概念を紹介することで考えてみたいと思います。
1. 信念対立とは何か
医療における信念対立とは、患者・家族・医療者・介護職など、医療に関わる多様な主体がそれぞれの価値観や世界観に基づいて「何がよい医療か」を追求した結果、意見や判断が衝突し、結論を導きにくい状態を指します。
例えば
例えば
・「今後も治療を継続することで延命するべきか、それとも自然な経過を見守るべきか」
・「積極的治療を優先するか、苦痛緩和を優先するか」
・「自宅療養と施設療養のどちらが望ましいか」
このような場面では、正しい答えが一つではなく、関係者の価値観や状況によって結論が異なるため、調整が難航します。
2. 信念対立が生じやすい背景
(1) 医療の高度化と専門分化
近年の医療は専門分化が進み、診断・治療・ケアなどを多職種で分担する体制が一般的になりました。
医師、看護師、薬剤師、リハ職、臨床工学技士、栄養士、ソーシャルワーカーなど、それぞれが独自の専門知識と評価基準を持っています。
同じ患者を見ても、何を最優先すべきかの判断基準が異なるため、方針が食い違いやすいのです。
例として:職種によって何を最優先するかを考えてみると
医師、看護師、薬剤師、リハ職、臨床工学技士、栄養士、ソーシャルワーカーなど、それぞれが独自の専門知識と評価基準を持っています。
同じ患者を見ても、何を最優先すべきかの判断基準が異なるため、方針が食い違いやすいのです。
例として:職種によって何を最優先するかを考えてみると
・医師 → 生存率・合併症リスクを重視
・看護師 → 安全性・患者の苦痛・ケア負担を重視
・ソーシャルワーカー → 社会資源の利用や家族の生活再建を重視
このように「どの視点を優先するか」が異なることで、信念対立は起こりやすくなります。
(2) 多様な価値観と社会背景
現代社会では価値観が多様化し、患者・家族・医療者それぞれが人生観・死生観・宗教観に基づいたそれぞれが心に抱く「よい医療」の定義を持っています。
・「可能な限り延命してほしい」と願う家族
・「自然に任せたい」と望む本人
・「医療資源の限界」を意識する医療者
こうした価値観が交錯すると、対立が深刻化しやすくなります。
(3) 制度・資源・責任構造の複雑化
医療現場では、制度上の制約や社会的責任も意思決定に影響します。
・医療保険や介護保険によるサービス制限
・医療事故時の責任所在
・限られたスタッフ・病床・設備といった資源問題
たとえ関係者が同じ価値観を共有していても、「現実的に実施できるかどうか」という条件が対立を引き起こす要因になります。
3. 信念対立が発生しやすい典型場面
(1) 治療方針の決定
・延命治療を行うか否か
・化学療法の継続か中止か
・移植・高度先進医療の適応可否
ここでは「生命予後」「生活の質」「本人の意思」などが交錯します。
(2) 生活の場や療養形態の選択
・自宅療養か、施設療養か
・医療機関での治療継続か、在宅緩和ケアか
本人・家族・医療者間で「何を優先するか」の違いが表面化しやすいです。
(3) 多職種チームでの方針不一致
・医師と看護師で「侵襲的治療の適否」に関する考え方が異なる
・リハ職と主治医で「活動範囲の設定」に意見の乖離がある
専門性を発揮するほど視点が異なり、「誰の判断を優先すべきか」という問題になります。
4. 信念対立の構造的特徴
(1) 事実と価値の混同
・「この治療は危険だ」という発言が、医学的データに基づく指摘なのか、それとも価値観に基づく懸念なのかが不明確だと、議論は平行線になりやすいです。
(2) 時間軸のずれ
・短期的リスク(今の安全)を重視する立場と、長期的利益(回復や自立)を重視する立場で、優先順位が異なります。
(3) 責任と権限の不均衡
・最終判断を下すのは医師であっても、実際のケアは看護師が担い、家族が支えるという役割分担の不均衡が、意見対立を複雑化させます。
5. 信念対立を悪化させる要因
・立場の固定化:「自分の意見を曲げると専門性を否定された気がする」
・感情の高ぶり:怒り・不安・罪悪感などが判断を曇らせる
・情報共有の不足:医学的データ・制度・リスクが曖昧だと、誤解から不信感が増幅する
・意思決定の時間不足:緊急時ほど十分な対話が困難で、摩擦が深まります。
6. 信念対立へのアプローチの基本
(1) 事実と価値を分ける
・医学的データや予後などの事実情報と、本人・家族・医療者の価値観や希望を区別して整理します。
(2) 共通ゴールの明確化
・「延命をするかしないか」ではなく、「本人が望む生活の質を最大化するにはどうするか」という視点でゴールを再定義します。
(3) 対話と調整のプロセス
・多職種カンファレンスや家族面談を通じ、関係者が価値観を共有し合う場を設定することが有効です。
(4) 一時的合意と柔軟な再評価
・すべてを一度に解決しようとせず、時間限定の試行や再評価の機会を設けると、対立が緩和されやすくなります。
7. まとめ
・医療現場では、専門性の高まりと価値観の多様化により、信念対立は避けられない現象となっている。
・対立は「事実」と「価値」の混線から生じやすく、短期・長期の優先順位や役割分担の不均衡がさらに複雑さを増す。
・解決には、事実と価値を切り分けたうえで共通ゴールを再定義し、柔軟な調整プロセスを組み込むことが重要。
・信念対立は「悪いこと」ではなく、多職種の視点を統合しよりよい医療を設計するための出発点と捉える視点が求められる。
このように信念対立は患者も含めた各職種がベストを尽くそうと努力をすると起こりやすくなるという側面もあります。次回は私が食支援の現場で感じる信念対立、「食べられないけど食べさせたい」が生じてしまうジレンマについて解説したいと思います。
よくある質問(信念対立に関して):
Q1. 医療現場でいう「信念対立」とは何ですか?
A. 患者・家族・医療者・介護職など多様な立場が、それぞれの価値観や世界観に基づいて「何がよい医療か」を追求した結果、意見や判断が衝突し、結論を導きにくい状態を指します。延命治療の継続や在宅療養と施設療養の選択など、正解が一つに定めにくい場面で起こりやすい現象です。
Q2. 信念対立が生じやすい背景にはどのようなものがありますか?
A. 医療の専門分化による多職種間の視点の違い、価値観の多様化、医療制度や資源・責任構造の複雑化が主な要因です。たとえば医師は生存率を、看護師は患者の苦痛軽減を重視するなど、立場ごとの優先順位の違いが対立を生みます。
Q3. 具体的にはどんな場面で信念対立が起こりますか?
A. 治療方針の決定(延命治療を続けるか否か)、療養場所の選択(自宅療養か施設療養か)、多職種チーム内の方針不一致などが典型例です。短期的リスクを優先するか、長期的利益を優先するかなど、判断軸の違いが顕在化します。
Q4. 信念対立がこじれる原因は何ですか?
A. 事実と価値観が混同されたまま議論が進む、感情が高ぶる、情報共有が不足する、意思決定の時間が不足するなどが挙げられます。これらが重なると、不信感や対立が深まり、合意形成が難しくなります。
Q5. 信念対立を和らげるために有効な方法はありますか?
A. 事実と価値を切り分けて整理し、本人が望む生活の質を最大化するなど共通ゴールを再定義することが重要です。さらに多職種カンファレンスや家族面談など対話の場を設け、一時的な合意や柔軟な再評価を重ねながら調整することで、対立が緩和しやすくなります。
関連リンク:
執筆:

本シリーズは全3回で、医療現場で起こる「信念対立」を多角的に解説します。
第1回では、多職種が協働する中で意見が衝突しやすい背景やメカニズムを整理し、対話の出発点となる基本構造を学びます。
第2回では、治療方針の決定や療養形態の選択、多職種カンファレンスなど、実際の医療現場で信念対立がどのように発生し、どのような影響を及ぼすかを具体的に掘り下げます。
最終回となる第3回では、事実と価値を切り分け、共通ゴールを再定義し、柔軟な合意形成を実現するための対話技法やツールを紹介。より良いチーム医療の実践を支援します。
第1回では、多職種が協働する中で意見が衝突しやすい背景やメカニズムを整理し、対話の出発点となる基本構造を学びます。
第2回では、治療方針の決定や療養形態の選択、多職種カンファレンスなど、実際の医療現場で信念対立がどのように発生し、どのような影響を及ぼすかを具体的に掘り下げます。
最終回となる第3回では、事実と価値を切り分け、共通ゴールを再定義し、柔軟な合意形成を実現するための対話技法やツールを紹介。より良いチーム医療の実践を支援します。