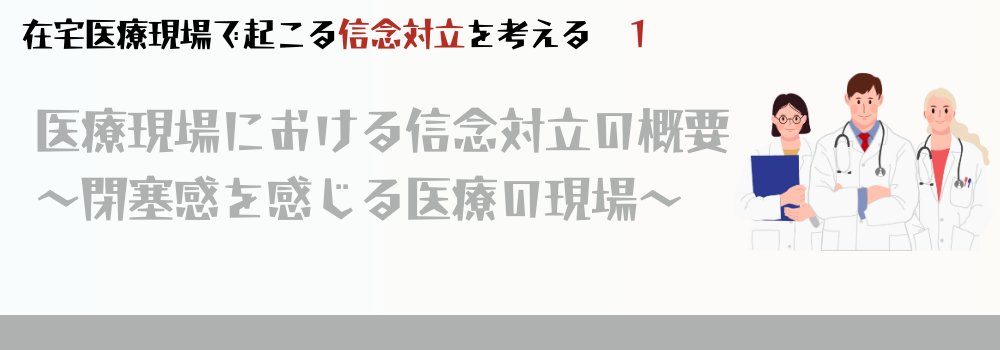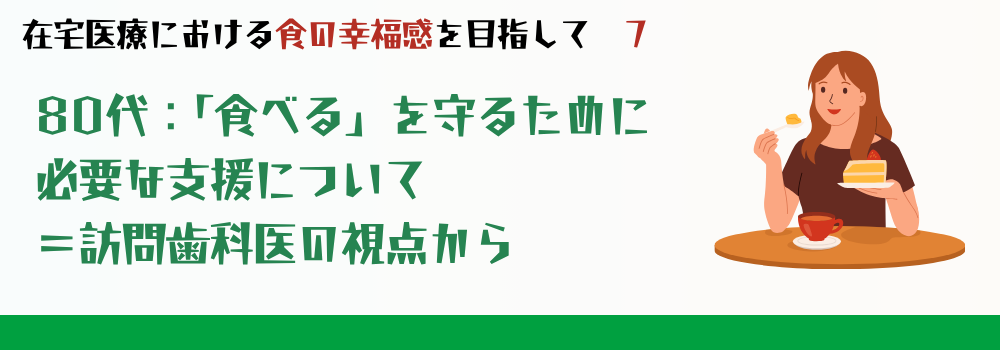相続は何から考えたら良い? ― 介護を見据えた準備の第一歩 最終更新日:2025/03/22
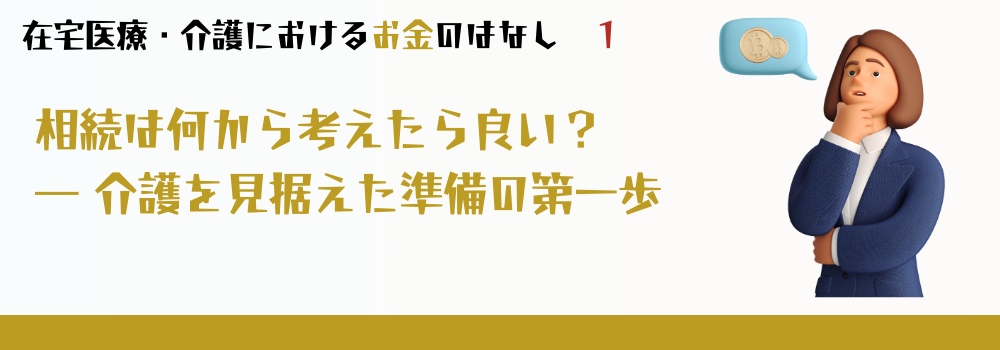
「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けする新企画「在宅医療・介護におけるお金のはなし」。
全10回シリーズの第1回は、介護を前提とした相続をどのように考え、準備を進めるべきかについてです。
相続と聞くと、「遺産の分け方」や「相続税」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、家族の介護を見据えた場合、相続は家族の生活そのものに直結する重要なテーマとなります。まずは相続準備の第一歩についてみていきましょう。
全10回シリーズの第1回は、介護を前提とした相続をどのように考え、準備を進めるべきかについてです。
相続と聞くと、「遺産の分け方」や「相続税」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、家族の介護を見据えた場合、相続は家族の生活そのものに直結する重要なテーマとなります。まずは相続準備の第一歩についてみていきましょう。
1. なぜ相続の準備が重要なのか
介護を支えるためには、金銭的な余裕や家族間の協力が必要不可欠です。しかし、相続について準備が整っていないと、次のような問題が発生する可能性があります。
・家族間のトラブル:相続の話し合いは、家族にとってデリケートな問題です。「公平」に分けるつもりでも、それぞれの立場や考え方によって「公平」の意味が異なることがあります。例えば、不動産を誰が相続するか、金額では均等に見えても、住む場所や思い入れの差で不満が生じるケースがよくあります。相続人間で話し合いがこじれ、関係が悪化してしまうことも少なくありません。
・介護費用の確保が難しい:介護が必要になったとき、施設利用料や在宅介護のためのリフォーム、ヘルパーさんの費用など、さまざまな形でお金がかかります。しかし、相続する財産が不動産や有価証券のように現金以外の資産ばかりの場合、それらを現金化しないと必要な介護費用をまかなえないケースも出てきます。
・税金負担の増加:相続財産に家や土地が含まれる場合、それらが大切な思い出や家族のつながりを象徴するものであれば、簡単には手放したくないという思いがあるでしょう。しかし、現金資産が十分にない場合、相続税の納税資金を準備するのが難しく、結果的にその家や土地を売却せざるを得ない状況に陥ることもあります。
これらのリスクを避けるためには、早めの計画と家族全員での話し合いが必要です。

2. 最初に確認すべきこと
(1) 財産の全体像を把握する
まず、遺産となる財産の全体像を明確にすることが大切です。主に以下の項目をリストアップしましょう:
・金融資産:預貯金、株式、投資信託など
・不動産:家や土地の評価額、所在地、用途(居住用・投資用など)
・負債:住宅ローンや借入金の残高
・その他:車、保険金、美術品など
これにより、相続対象の財産がどれくらいあるのかが具体的に分かります。

(2) 家族の意向を確認する
介護を見据えた場合、特に「誰がどのように介護を担うのか」を話し合うことが最も大切です。最低限、以下については話し合っておきましょう。
・誰が介護を中心に行うのか?
・他の家族はどのようにサポートするのか?
・介護中の住まいや費用の負担についてどう考えるか?
こうした話し合いは、どうしても後回しにしがちですが、後々のトラブルを避けるためにも、早めの確認をおススメします。相続計画を具体化する土台となります。

(3) 法律や税金の基本を知る
相続に関する基本的な法律や税金の知識も最低限必要です。特に以下の点は押さえておきましょう。
・法定相続分:各相続人が法律上どれだけの割合を受け取れるか
・相続税の基礎控除:現行制度では、「3,000万円 + 法定相続人1人あたり600万円」が控除額
・遺言書の有無:被相続人の意思が反映される重要な文書
3. 介護を見据えた相続計画の進め方
(1) 遺言書の作成
介護を前提とした場合、遺言書を作成しておくことが非常に有効です。遺言書には、以下のような内容を記載すると良いでしょう。
・誰が自宅を相続するか
・自宅の維持費やリフォーム費用の負担方法
・介護を担う人への特別な配慮(例:現金や他の資産の配分)
遺言書を公正証書として残すことで、トラブルを防ぐ効果が高まります
(2) 生前贈与を活用する
生前贈与は、財産を計画的に分割する方法として有効です。相続財産によって、相続税が掛かりそうな方は、相続税軽減対策や分割対策にもなります。贈与する資金の目的や種類によって、非課税となる制度もあるので把握しておきましょう。知らないと、思わぬ額の贈与税を支払わなくてはいけなくなるケースもあります。
・贈与税の非課税枠:年間110万円まで非課税
・教育資金の一括贈与:1,500万円まで非課税(条件あり)
・住宅取得資金の贈与:最大1,000万円まで非課税(適用条件あり)
生前贈与を行うことで、相続時の負担を軽減でき、家族の負担を減らせます。相続財産の大きさによって、対策が変わってくるので、盲目的な生前贈与には注意しましょう。

(3) 介護費用のシミュレーション
ひとことで介護と言っても、利用するサービスやケアの内容によって掛かる費用は大きく異なります。
在宅介護:月3万~10万円程度
ヘルパーや訪問看護を利用する際の費用は、利用するサービスの内容や頻度によって変わります。夜間サービスや特別なケアを追加すると、さらに費用が上がることもあります。在宅介護を継続するには、計画的なサービス選びが必要です。
ヘルパーや訪問看護を利用する際の費用は、利用するサービスの内容や頻度によって変わります。夜間サービスや特別なケアを追加すると、さらに費用が上がることもあります。在宅介護を継続するには、計画的なサービス選びが必要です。
デイサービス:1回あたり約5,000円前後
介護保険適用後の自己負担額で、週1回なら月2万円程度、週3~5回の利用で月6万~10万円になることもあります。送迎費や特別なリハビリなどのオプション料金が追加される場合もあるため、事前確認が重要です。
介護保険適用後の自己負担額で、週1回なら月2万円程度、週3~5回の利用で月6万~10万円になることもあります。送迎費や特別なリハビリなどのオプション料金が追加される場合もあるため、事前確認が重要です。
施設介護:月10万~50万円程度
特別養護老人ホーム(特養)は月10万~15万円と費用を抑えられますが、入所待ちが長くなることがあります。民間の有料老人ホームや介護付き住宅は月20万~50万円と幅広く、医療ケアや個室対応を希望する場合はさらに高額になる可能性があります。
特別養護老人ホーム(特養)は月10万~15万円と費用を抑えられますが、入所待ちが長くなることがあります。民間の有料老人ホームや介護付き住宅は月20万~50万円と幅広く、医療ケアや個室対応を希望する場合はさらに高額になる可能性があります。
医療費やリハビリ費用:月1万~数万円程度
慢性疾患やリハビリの必要性に応じて、介護費用に加えて医療費が発生します。訪問リハビリや定期的な通院が必要な場合、月1万~数万円程度かかることが一般的です。薬代や医療器具の費用も負担増の要因となります。
慢性疾患やリハビリの必要性に応じて、介護費用に加えて医療費が発生します。訪問リハビリや定期的な通院が必要な場合、月1万~数万円程度かかることが一般的です。薬代や医療器具の費用も負担増の要因となります。
これらの費用は、介護が長期化するほど大きな負担になります。介護を受けながらどのような生活をしたいのか、家族の意向や被介護者の希望に合わせたシミュレーションを行い、必要な資金を明確にしておくことが大切です。
それぞれの特徴や費用についての詳細は、今後のコラムでも触れていきたいと思います。
4. 専門家の力を借りる
効果的な相続計画を立てる為には、専門家の力も必要です。
・税理士:相続税の計算や税務対策をサポート
・司法書士:遺言書の作成や不動産の名義変更手続き
・ファイナンシャルプランナー:介護費用を含めた総合的な資金計画をサポート
相談が後手に回ることで、効果的な対策が立てられなくなることもあります。早めに相談することで選択肢が広がるので、必要に応じて、早めのご相談をおススメします。

おわりに
相続は、「お金」の問題だけでなく、「家族の絆」とも深く関わるテーマです。特に介護を見据えている場合、相続の準備は家族全員の安心につながります。
ぜひ、家族での話し合いや専門家への相談を始めてみてください。準備を重ねることで、未来への不安を減らし、より良い暮らしを実現することに繋がります。
次回のテーマは、「相続っていつまでに何をしなければいけない?」です。相続が起こってから焦って調べるのではなく、事前に知っておくことで、気持ちにゆとりを持った対応を目指しましょう。
関連リンク:
執筆:

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。