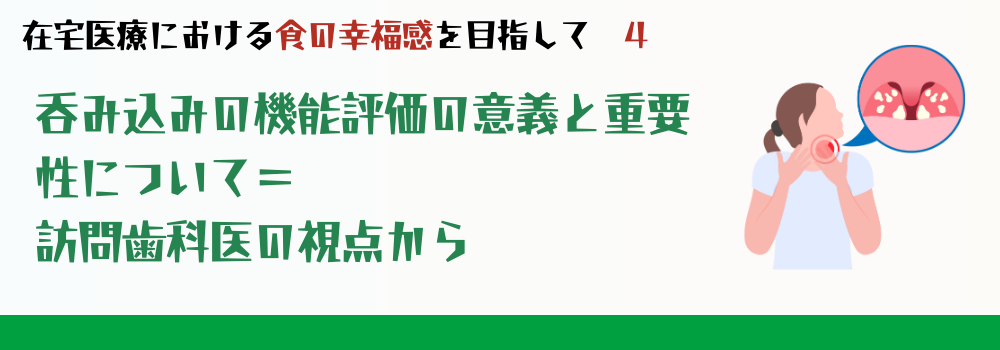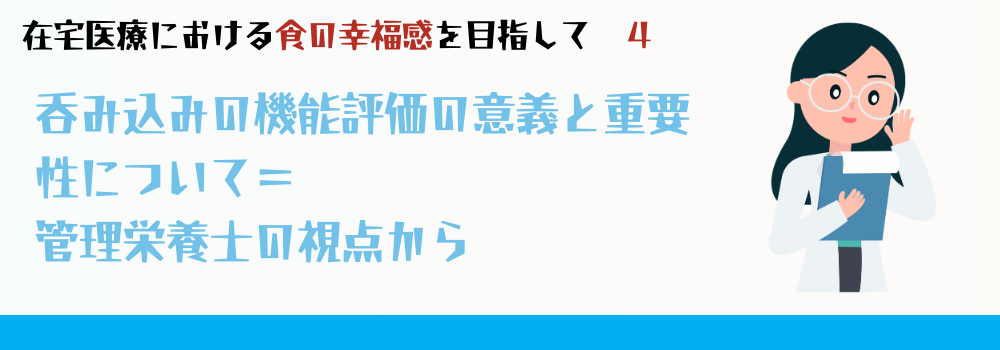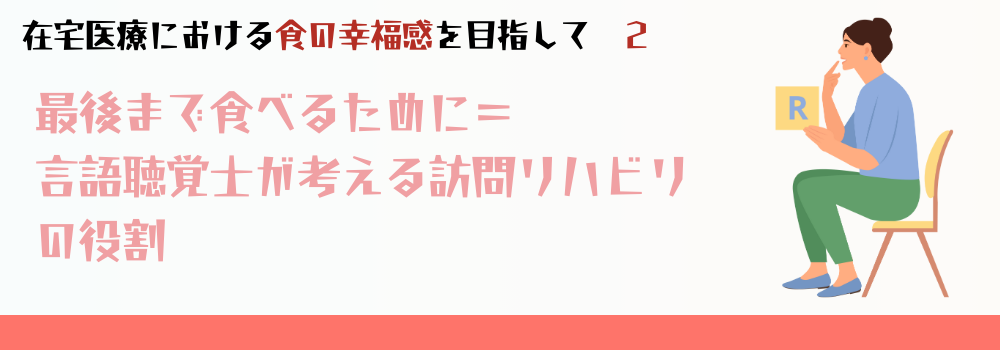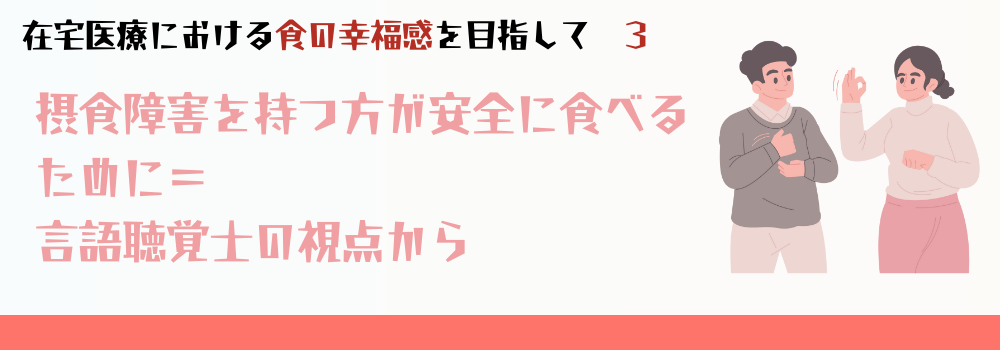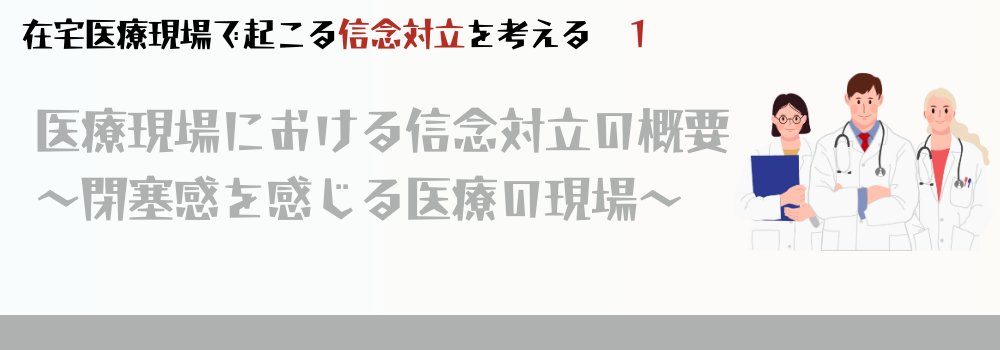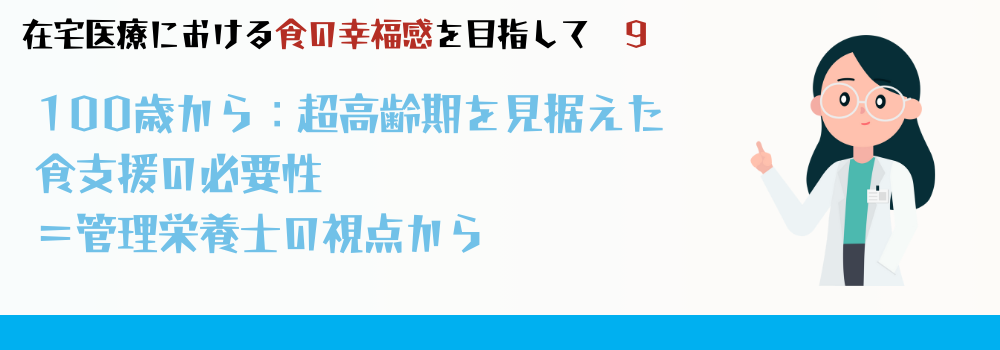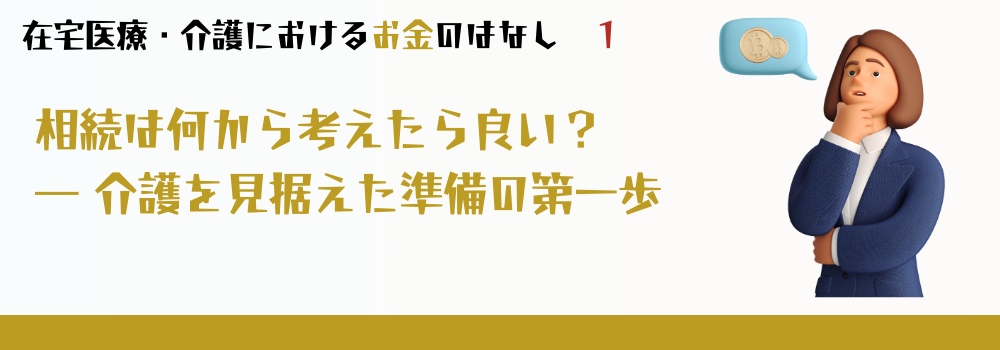嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について=言語聴覚士の視点から 最終更新日:2025/04/27
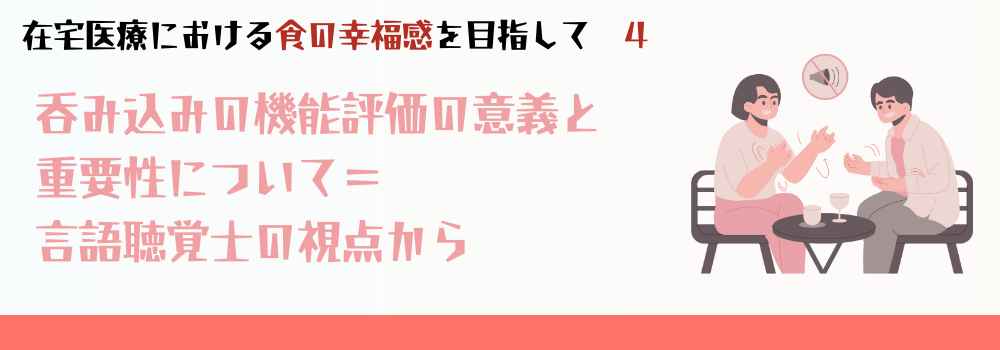
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
4つ目のテーマは「嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について=言語聴覚士の視点から」と題して、言語聴覚士の立場として、國谷侑岐言語聴覚士(株式会社サンショー)により解説いただきました。
4つ目のテーマは「嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について=言語聴覚士の視点から」と題して、言語聴覚士の立場として、國谷侑岐言語聴覚士(株式会社サンショー)により解説いただきました。
1. 「食べる力」を守るため-嚥下機能評価の意義とは
「食べること」は、命を支える営みであると同時に、人間らしい生活の象徴でもあります。高齢や疾患によって嚥下機能(飲み込みの力)が低下することは珍しくありませんが、嚥下機能の低下は誤嚥性肺炎や栄養不良・脱水、窒息といった深刻な健康リスクや社会的孤立・QOL(生活の質)の低下を招く恐れがあります。
こうしたリスクを予防し、口から安全に食べ続けるために欠かせないのが、「嚥下機能評価」です。言語聴覚士は、嚥下障害の専門職として、日々の臨床のなかでその支援に取り組んでいます。
嚥下機能評価と聞くと、「結果が悪かったら食べられなくなるのでは」と不安を抱く方もいます。しかし、私たちが目指しているのは、「食の安全と楽しみを両立させることを目的とした支援」です。

2. 安全と楽しみを両立させる-嚥下機能評価の3つの目的
嚥下機能評価の主な目的は3つあります。1つ目は安全確保(誤嚥や窒息を防ぐこと)、2つ目は生活の質(QOL)の向上(口から食べる楽しみを支えること)、3つ目は支援方針の明確化(リハビリや食事形態の調整など)です。「もう食べることができない」ではなく、「どうすれば食べられるか」を探る評価が、私たちの目指す姿です。
80代:女性・Bさんは、脳梗塞後に誤嚥性肺炎を繰り返しており、「もう口からは食べられないだろう」と医療スタッフの間でも経口摂取の中止が検討されていました。しかし、ご本人は「少しでもいいから、家族と一緒に食卓を囲みたい」と強く希望されていました。
そこで私たちは嚥下評価を丁寧に行い、嚥下内視鏡検査(VE)によってとろみの調整や姿勢、タイミングの工夫をすれば安全に嚥下できる場面があることが分かりました。結果として、1日1回のゼリー摂取から少しずつ経口摂取が再開され、ご本人の笑顔が増えていく姿を私たちは間近で見ることができました。
このように、嚥下機能評価は「危ないから止める」ためだけのものではなく、「どうすれば実現できるか」を探るための希望のツールです。嚥下異能評価を通じて見えてくる可能性が、人生の質を大きく左右することもあるのです。
3. 言語聴覚士が行う嚥下機能評価の実際
嚥下機能の評価は問診から始まります。既往歴や内服状況、むせや咳込み、体重変化、食事時間、声の変化(嗄声)などを本人と介護者から聴取し、嚥下機能低下が疑われないか確認します。視診・触診では姿勢や口腔運動、舌・喉の動きや筋力、口腔内では清潔が保たれているか、義歯が適合しているかなどを確認します。さらに、RSST(反復唾液嚥下テスト)、MWST(改訂水飲みテスト)、フードテスト、頸部聴診といった嚥下機能のスクリーニング検査も併用し、安全性を多角的に見ていきます。
また、必要に応じて嚥下内視鏡検査(VE)や嚥下造影検査(VF)も実施し、詳細な機能評価とリハビリ計画の立案につなげます。
VEは、鼻から細い内視鏡を挿入し、咽頭や喉頭の様子をリアルタイムで観察できる検査です。ベッドサイドでも実施可能な検査で、繰り返し評価がしやすく、食物の通過状況や誤嚥の有無、喉頭の動きなどを視覚的に確認できる点が大きなメリットです。一方で、嚥下の瞬間(いわゆる“ホワイトアウト”)は観察できないため、全体のタイミング把握には限界があります。
VFは、バリウムを混ぜた食物をX線透視下で摂取し、口腔から食道への一連の動きを動画として記録できる検査です。嚥下の流れを詳細に把握でき、食塊の通過や誤嚥のタイミング、喉頭の閉鎖機能、咽頭残留などの評価に非常に優れています。ただし、X線室での実施が必要で、ベッド上での対応が難しい方や移動が困難な方には負担が大きくなることがあります。
このように、VEとVFはいずれも嚥下評価において重要な役割を果たし、それぞれの特性に応じて使い分けられています。言語聴覚士はこれらの情報を総合的に判断し、主治医やご家族と連携しながら個別性の高い支援計画を立てていきます。
4. 食べる力を支えるために‐嚥下支援の工夫と視点について
嚥下機能評価時にはいくつかの注意点があります。姿勢は基本的に前傾座位をとり、体調や嚥下機能に応じて半座位や側臥位も検討します。評価に使う食品や液体は誤嚥リスクを考慮し、とろみ水やゼリーなど段階的に用いて評価を行います。そして何よりも、無理に進めず、本人の体調や心理面、症状の日内変動にも配慮しながら、継続的に再評価を行うことが嚥下評価時の際には重要となります。
嚥下機能評価を行う際、私たち言語聴覚士が大切にしているのは、単なる「嚥下機能の評価」ではなく、「その人の生活の一部としての食」として嚥下機能を評価する姿勢です。たとえば、普段どのような時間帯に食事をしているのか、誰と食べているのか、どのような味が好きなのか。どのような姿勢・食器を用いているか、なども嚥下機能を評価する上で重要な情報です。
また、評価だけで終わらせるのではなく、その結果をもとにどう介入するかまで一体として考えることが求められます。言語聴覚士は嚥下訓練だけでなく、食形態の提案、姿勢調整、口腔ケアの指導、食環境の調整にも関わり、医師や看護師、管理栄養士、介護職、薬剤師ご家族など多職種と協働して支援を行います。
たとえば、脳卒中後の片麻痺がある方であれば、非麻痺側での食事誘導や食具の選定、頭部・体幹のポジショニングなどに工夫を加えることで、安全性が大きく向上することがあります。また、認知症がある方では、視覚的にわかりやすい配膳や、食事を促す声かけのタイミングによっても嚥下の安定性が変化します。
こうした「小さな工夫」の積み重ねが、「もう無理かもしれない」と感じていた方の「まだできるかもしれない」につながる瞬間を、私たちは数多く見てきました。STの評価と支援は、ただ危険を見つけて止めるためのものではなく、「できる方法を見つけるための希望のツール」なのです。

5. 人生を豊かにする嚥下支援‐一人ひとりの「食べたい」を叶えるために
訪問リハビリの現場では、家の中というその人にとって最も自然な生活空間で評価を行えるという利点があります。病院や施設では見えにくかった「本来の食事風景」を確認できるため、より実生活に即した評価と支援が可能になります。たとえば、椅子やテーブルの高さが合ってない場合や、食器の滑り止めがないためにスムーズに食事ができていないケースなど、ちょっとした調整で大きな変化が生まれる場面も多くあります。
また、摂食嚥下障害は加齢だけでなく、病状の進行や体調変化によっても状態が変わりやすい特徴があります。そのため一度の評価で結論を出すのではなく、定期的なフォローアップと再評価が重要です。時には状態が良くなり、食形態を上げられることもありますし、反対に一時的な低下が見られる場合もあります。その変化を的確に捉え、柔軟に対応していくことが、言語聴覚士に求められる専門性です。
最終的には、「この人はどのように生きたいのか」「食べることで何を感じたいのか」といった価値観にまで寄り添える支援が、私たち言語聴覚士の理想です。食は単なる栄養摂取の手段ではなく、「その人らしさ」の象徴であり、人生の楽しみそのものです。言語聴覚士の嚥下評価は、その人生を豊かにするための一つのツールとして、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。
これからも私たち言語聴覚士は、一人ひとりの「食べたい」という思いに寄り添いながら、安全かつ豊かな食支援を届けていきたいと考えています。嚥下機能評価は、医療の枠を超えて「人生を支える支援」であることを、これからも伝え続けていきたいと思います。その一歩が、笑顔あふれる食卓の実現につながります。

関連リンク:
執筆:

國谷侑岐(くにたにゆうき)
言語聴覚士
経歴:
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
資格:
言語聴覚士
言語聴覚士