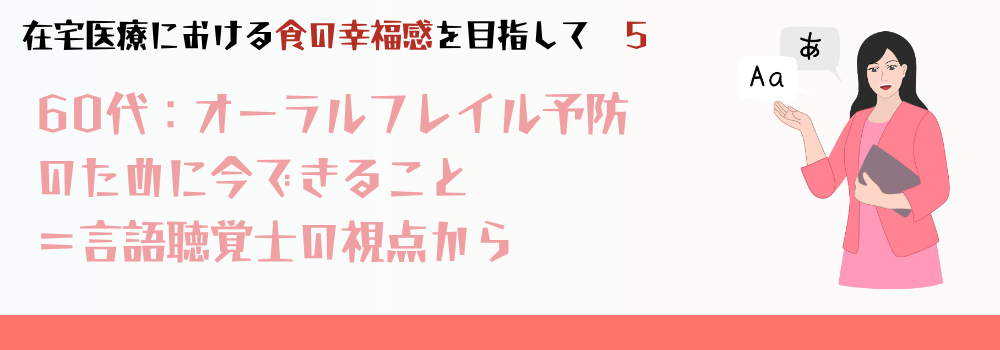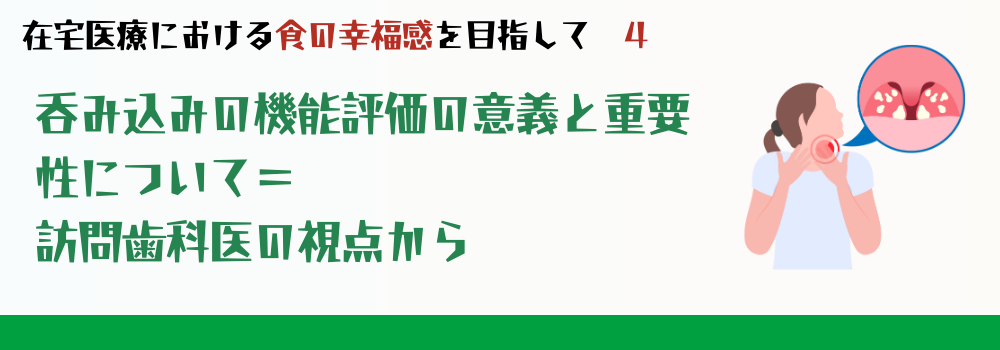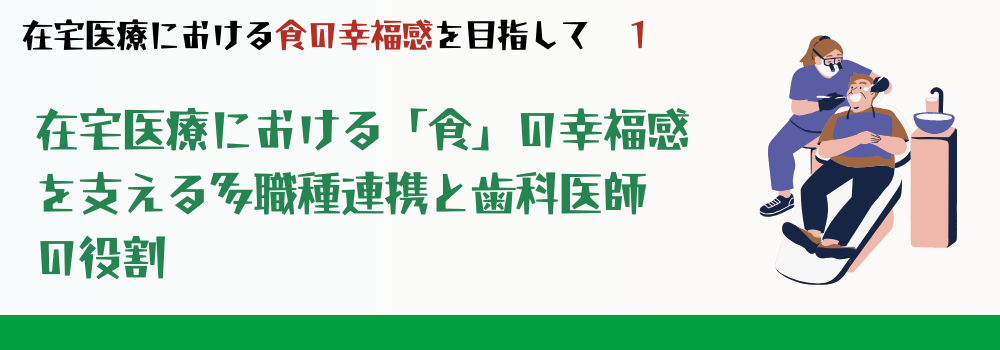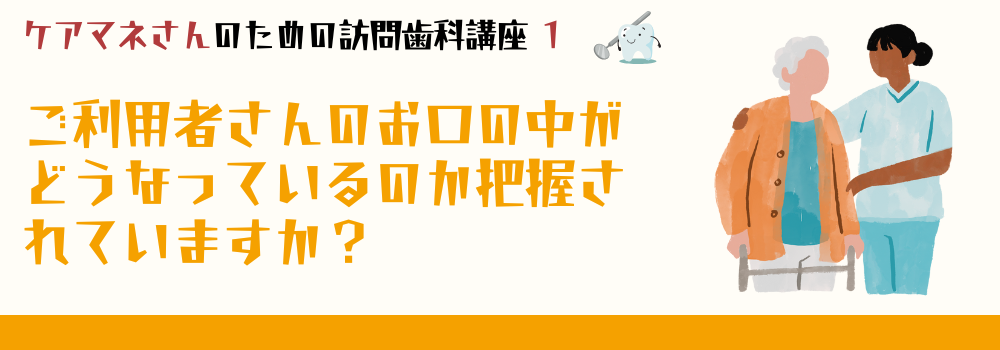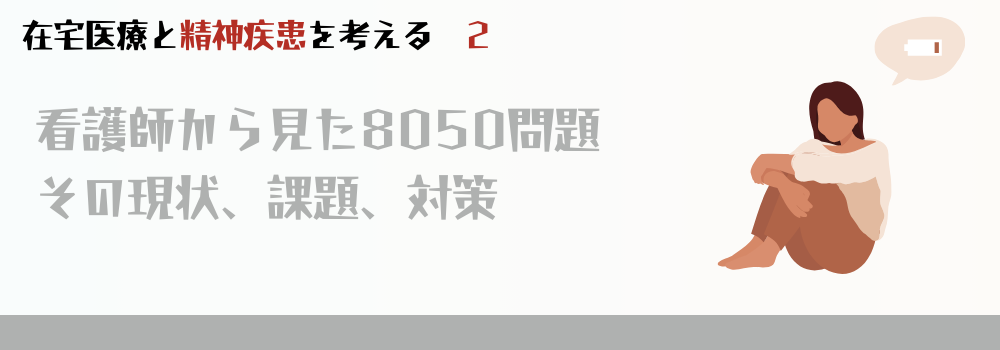60代から始まる機能低下と嚥下障害 ~オーラルフレイル予防のために今できること=訪問歯科医の視点から 最終更新日:2025/06/01
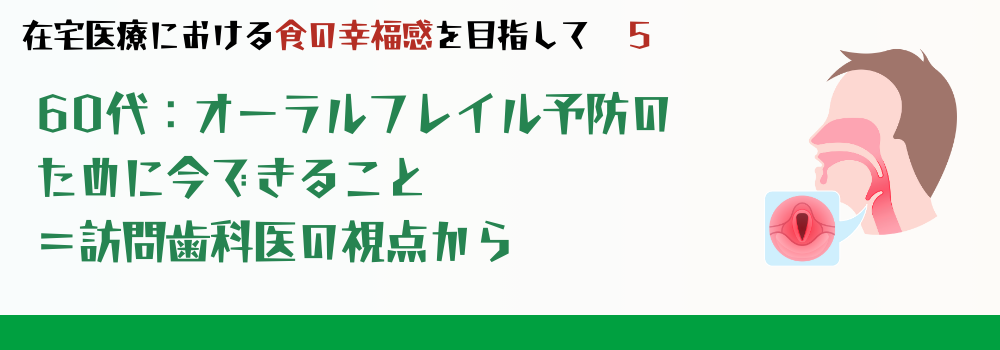
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
5回目の今回から年代別の予防について配信していきます。まずは60代を対象に「オーラルフレイル予防のために今できること」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
5回目の今回から年代別の予防について配信していきます。まずは60代を対象に「オーラルフレイル予防のために今できること」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
はじめに
「年を取っても元気でいたい」ーこれは誰しもが望むことです。しかし現実には、60代に差し掛かる頃から私たちの身体は少しずつ確実に変化し始めます。とくに口腔機能、すなわち「噛む・飲み込む・話す・感じる」などの機能は、加齢によって早期から影響を受けやすく、放置すればやがて“食べられない”という深刻な問題に直結します。
今回は、60代における加齢変化と、それによって起こりうる嚥下障害(のみこみの障害)について、またその予防のために私たちが日々の生活で意識すべきことについて考えてみたいと思います。

60代に始まる「口」の加齢変化とは?
60代になったとは言っても、見た目はまだ若々しい方が多く、「老い」をそうすぐには実感しにくいかもしれません。しかし、身体の内部、特に筋肉や神経機能には確実に変化が現れています。
1. 筋力の低下(サルコペニア)
全身の筋肉量は30代をピークに少しずつ減少し、60代になるとその減少スピードが加速します。とくに速筋(瞬発的に力を出す筋肉)が衰えやすく、これが口腔機能に及ぶと、舌・頬・のどの筋肉が衰え、「食塊の形成」「咽頭への送り込み」「咽頭収縮による駆出」などがスムーズに行えなくなります。
2. 唾液の分泌量の減少
唾液には、食塊をまとめて飲み込みやすくしたり、口腔内を清潔に保つ働きがあります。加齢により唾液腺の機能が低下したり、持病や服薬の影響で唾液量が減少すると、飲み込みづらさや口腔乾燥(ドライマウス)を訴える方が増えてきます。
3. 感覚の鈍化
味覚や触覚、温度の感知などの感覚も徐々に衰えてきます。舌で感じ取る力が低下すると、異物感や誤嚥に気づきにくくなり、サイレントアスピレーション(むせずに誤嚥する)につながる危険も出てきます。
4. 咀嚼力の低下
虫歯や歯周病によって歯の本数が減ったり、義歯の不具合、咬合力の低下などが進行すると、「よく噛んで食べる」という行動が困難になります。結果として、咀嚼回数や時間が減り、十分に咀嚼されないまま食塊が咽頭に到達してしまうと、さらに嚥下障害のリスクが高まります。

オーラルフレイルとは?‐口の虚弱が全身の虚弱へ
こうした口腔機能の軽度の衰えは、かつて見逃されがちでした。しかし、現在ではこの段階を「オーラルフレイル」と呼び、全身のフレイル(虚弱)の入口であると認識されています。
オーラルフレイルの段階では、自覚症状があまり強くないため、「まだ大丈夫」と思われがちです。けれどもこのタイミングで気づき少しずつ介入しなければ、将来的に「誤嚥性肺炎」「低栄養」「ADL(日常生活動作)の低下」などの重大な健康問題につながってしまいます。
60代から始める、オーラルフレイル予防の具体策
では、オーラルフレイルや嚥下障害を予防するために、60代からどのような対策を取ればよいのでしょうか?以下に、具体的な方法を5つ紹介します。
1. 定期的な歯科受診と口腔ケアの徹底
口腔機能を守る第一歩は、まず歯科医院での定期的なチェックです。虫歯や歯周病を予防するだけでなく、義歯の状態の確認、口腔乾燥の評価、舌の動きや咬合の状態など、口の中の“機能”全体を評価します。
また、毎日のセルフケアでは、歯磨きだけでなく舌・頬粘膜の清掃や、唾液腺マッサージなどを習慣にしましょう。

2. 噛む・話す・飲み込む「運動」を生活に取り入れる
咀嚼・発声・嚥下は、筋肉の活動そのものです。意識的に口腔まわりを動かす機会をつくりましょう。たとえば、
・「あ・い・う・べ体操」などの口腔体操
・硬めの食材(レンコン、ごぼう、こんにゃくなど)を意識的に日々の食事に取り入れる
・食事中は「よく噛む」を意識(1口30回以上を目安に)
・カラオケや会話ではっきりと声を出す
など、日常生活の中で“口を使う”ことが大切です。
3. 姿勢と呼吸の見直し
嚥下に関わる筋肉は、姿勢や呼吸とも密接に関係しています。前かがみや猫背では舌や喉の筋肉が使いにくくなり、誤嚥のリスクが高まります。座る姿勢、特に食事中の座位姿勢を見直すことも嚥下障害予防の一環です。
また、鼻呼吸を意識し、睡眠時無呼吸やいびきがある場合は耳鼻科での相談をお勧めします。
4. 栄養・水分の確保
低栄養は筋力低下を助長し、口腔・嚥下機能にも悪影響を与えます。たんぱく質を中心に、ビタミンや亜鉛などもバランスよく摂取し、「体を作る栄養」を普段から意識することが大切です。
さらに、口腔乾燥を防ぐためにも水分摂取は重要です。1日1.5〜2Lの水分を目安に、こまめな水分補給を行いましょう。
5. 自分の“食べ方”を知るー嚥下機能のセルフチェック
最近では簡易的なセルフチェック項目が多く開発されており、自宅で嚥下機能のリスクに気づける機会が増えています。たとえば、
・食事中によくむせる
・飲み込みにくい
・食事に時間がかかる
・声がかすれる、食後に痰がからむ
などの症状があれば、早めに歯科や医科の専門機関に相談することをおすすめします。
おわりに:口から食べる喜びを一生続けるために
「口は命の入口」とよく言われます。食べることは単なる栄養補給だけでなく、人生の楽しみや大切な人とのつながりを作る、かけがえのない行為です。だからこそ、60代から起こりうる“わずかな変化”に目を向け、今からできるケアを積み重ねていくことが将来の健康寿命の長さを大きく左右します。
口を守ることは、全身を守ること。人生100年時代の折り返しを迎えたこの時期だからこそ、「まだまだ自分は大丈夫」ではなく「今から始めよう」という意識を持つことが、将来の誤嚥や寝たきりを防ぐ最短にして最善の手段なのです。

関連リンク:
執筆: