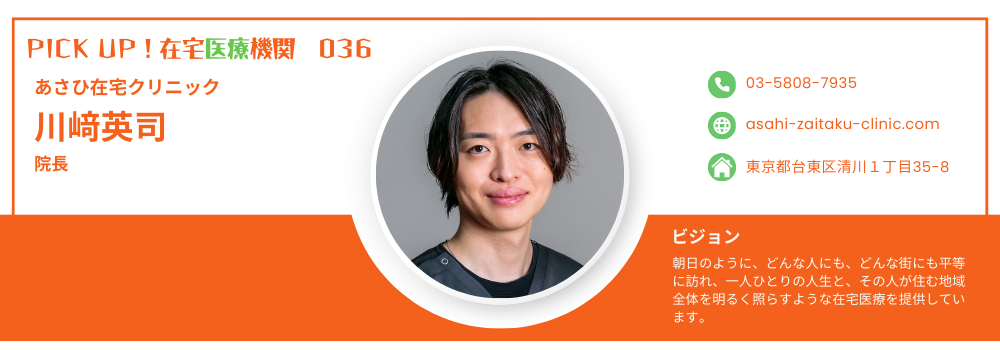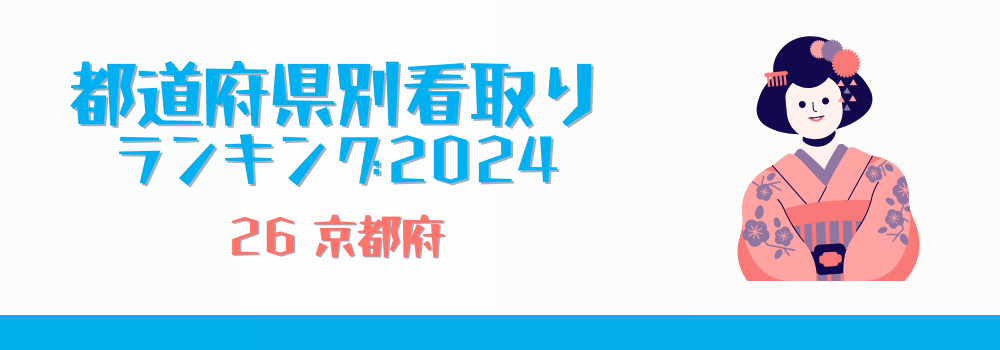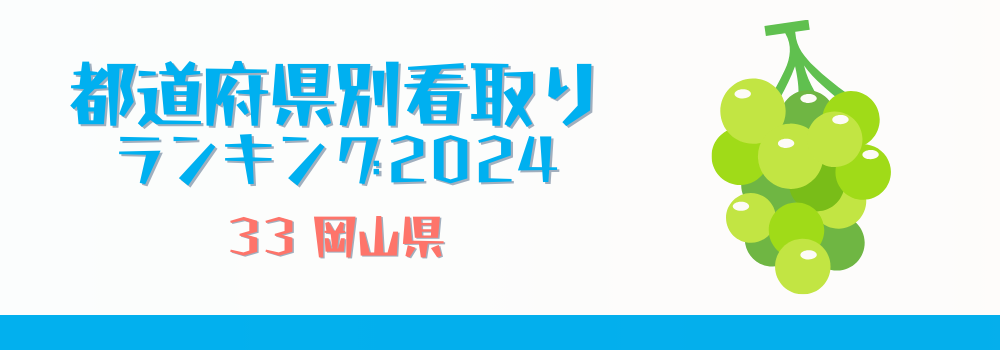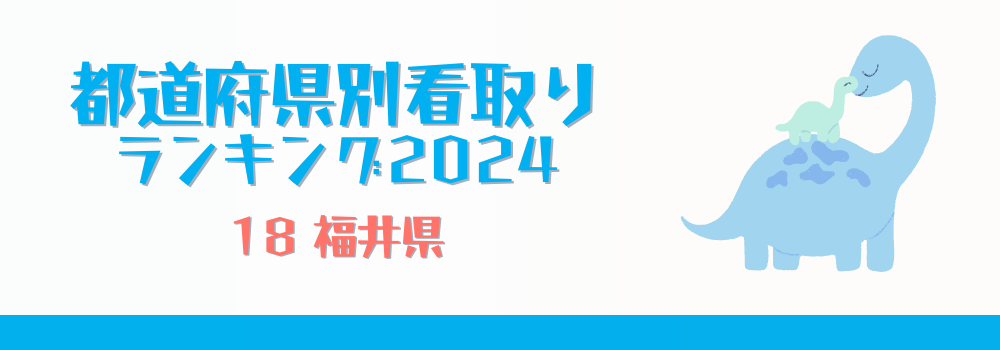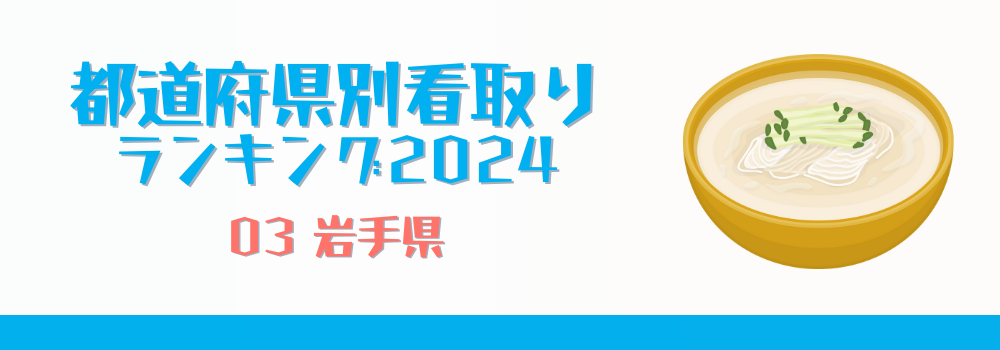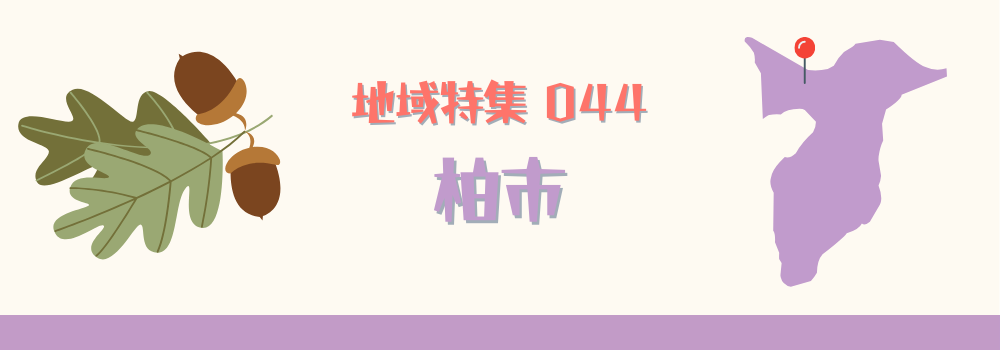名古屋市|通院できない方の在宅医療ならごうホームクリニック:脳卒中・パーキンソン病・ALSにも対応 伊藤剛院長 最終更新日:2025/12/30
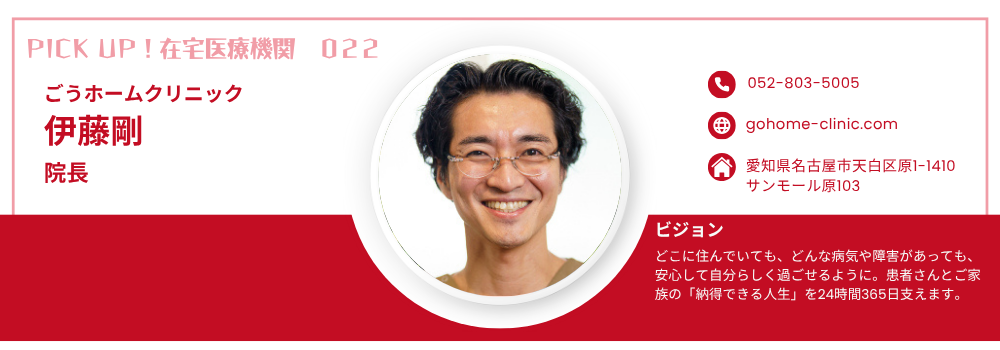
ごうホームクリニックは、名古屋市を中心に「通院できない」方を対象とした在宅医療に特化したクリニックです。脳卒中後遺症、パーキンソン病、ALS、認知症、精神疾患など、身体的・精神的ケアを総合的に診療できる点が大きな特徴です。看護師を中心に多職種が連携し、ご自宅で安心して過ごし続けられるよう、24時間365日体制で支援しています。「納得できる人生と安心できる生活を支える」ことを理念に、地域の医療・介護と密接に連携しながら、一人ひとりの暮らしに寄り添った在宅医療を提供しています。
名古屋市で“通院できない”患者を支える医師の歩みと在宅医療への道
— まず、医師を目指されたきっかけについてお聞かせください。
一番大きなきっかけは、5歳年上の姉の存在ですね。姉が先に医療の道に進んでいたので、その姿が私にとっての自然なロールモデルになっていました。また、子どもの頃にテレビで見た救急医療のドキュメンタリー番組に感銘を受けたり、自身がアトピー性皮膚炎で皮膚科に通っていた経験も、医療という世界を身近に感じるきっかけになったと思います。

— 医師としてのキャリアは、どのような領域からスタートされたのでしょうか。
大学を卒業後、初期研修では整形外科に興味を持ちました。外傷を治療する姿に、漠然とした医師のイメージを抱いていたんです。しかし、実際に現場で向き合うのは高齢者の骨折が多く、少し自分の思っていたイメージと相違があったと感じました。
次に進んだのが循環器内科です。カテーテル治療など、ダイナミックな医療に面白さを感じていましたが、その一方で「この検査は本当に全員に必要なのだろうか」という疑問も感じていました。年齢や状態に関わらず画一的な治療方針になりがちな点に、少し違和感を覚えたんです。
— その後、小児科、そして精神科へと専門を深めていかれたそうですが、その経緯について詳しくお聞かせください。
循環器内科での経験から、より患者さん一人ひとりの人生に寄り添う医療への関心が強まりました。そんな時に心に浮かんだのが小児科です。実家が学習塾を経営していたため、常に子どもたちの声が聞こえる環境で育ちました。そのため、子どもはもちろん、その親後さんたちと話すことにも慣れていましたし、全く抵抗がありませんでした。何より、新生児という人生の始まりから関われる小児科の仕事に惹かれ、そこからJA愛知厚生連 豊田厚生病院の小児科で医師としてのキャリアを本格的にスタートさせました。
一方で、研修で経験した精神科の面白さがずっと心に残っていました。「人の人生を丸裸にする」ような深い関わりの中から治療が生まれていく。その奥深さに心が奪われました。また、小児科が「新生児から」であるのに対し、精神科は「全年齢」を対象にしている点にも大きな魅力を感じていたんです。その研修当時に感じた思いを捨てきれず、その後愛知医科大学病院の精神神経科に移り、専門性を高めていきました。
— そこから、どのようにして在宅医療の道に進まれたのでしょうか。
精神科医としてのキャリアを積む中で、後輩から在宅医療のアルバイトを紹介され、2013年から週に一度、在宅医療の世界に足を踏み入れました。最初は入院患者さんを診る感覚で、個人個人のニーズを汲み取れていなかったと思います。しかし、在宅では患者さんの生活そのものが医療の対象です。その方の生き方や物事の感じ方にまで寄り添う必要があるのだと現場で学んでいきました。
そして2016年、とくしげ在宅クリニックみかわの院長に就任し、本格的に在宅医療に携わることになります。しかし、そこでは自分の目指す医療と組織の方針との間に少しずれを感じるようになりました。もっと患者さんや地域の多職種の方々と深く関わりたいという思いが強くなる一方で、組織の制約に窮屈さを感じるようになったんです。その経験から「自分に裁量権がなければ、理想の医療は実現できない」と痛感しました。

想いと繋がりが「めぐる」、ごうホームクリニック設立へ
— 2019年に「ごうホームクリニック」を設立されましたが、そのきっかけは何だったのでしょうか。
前職での経験から、一度は在宅医療の現場を離れることも考えましたが、そんな私を思いとどまらせてくれたのが、地域の仲間たちの存在でした。これまで一緒に仕事をしてきた訪問看護師さんをはじめ、多くの方々が「先生と一緒にやりたい」と温かい声をかけてくださったんです。その言葉に強く背中を押され、「自分で理想のクリニックを創ろう」と独立を決意するに至りました。
— 設立時の体制や、特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
はじめは、看護師1名、事務長1名、医療事務2名、そして私の合計5名という体制でスタートしました。驚いたことに、前のクリニックで担当していた多くの患者様が「先生に続けて診てもらいたい」と当院についてきてくださったんです。本当にありがたいことでしたが、おかげで開業初日からトップスピードで、クリニックのルールを整備する時間もないほど忙しかったのを覚えています。

— 法人名の「めぐる」には、どのような想いが込められているのでしょうか。
クリニックの名前を考えるとき、自分の名前や地名ではなく、私たちの活動のコンセプトを表現したいと考えました。訪問診療をしていると、まるでゲームの世界のように、ケアマネジャーさん、ヘルパーさん、薬剤師さんといった様々な職種の「仲間」がどんどん増えていくんです。
患者さんを中心に、たくさんの人の想いや専門性、そして繋がりが「めぐる」ことで、より良い医療が生まれる。そんな「好循環」をこの地域で創り出したいという想いを込めて、「めぐる」という名前にしました。平仮名で誰にでも読みやすく、覚えてもらいやすいという点も意識しています。

— クリニックの理念や、診療で大切にされていることを教えてください。
私たちの理念は、「納得できる人生と安心できる生活を支える」ことです。在宅医療では、ご本人やご家族が「納得」できるかどうかが何よりも大切だと考えています。治療の選択肢や予後について正直にお伝えし、共に考える。そうすることで、亡くなるその瞬間だけでなく、残されたご家族が後々振り返った時に「あの時、ああしてよかった」と思えるような、後悔の少ない医療を提供することを目指しています。
通院できない名古屋市の患者が“自宅で過ごす”ための在宅医療体制と支援の特徴
— 貴院の特長についてお聞かせください。
一つは、内科診療をはじめ内科疾患を要する精神疾患など、身体的な疾患と精神的な症状の両方を抱える患者さんを包括的に診られる点です。また、幅広い処置に対応できるよう、医療デバイスも豊富に揃えています。

当院の最大の強みは、看護師を中心とした手厚い支援体制にあります。現在、医師は常勤換算で2.4名、看護師は6名が在籍しており、訪問看護ステーションの看護師と当院看護師が共通言語で密接に連携できる体制を構築しています。
さらに、栄養士やケアマネジャー、総務、医療事務、ドライバーなど、多職種を含む19名のスタッフが在籍。加えて「看護事務」という専門職を設けることで、看護師の業務をサポートし、より専門的なケアに専念できる環境を整えています。
診療地域は、クリニックから半径7〜8㎞圏内が中心ですが、名古屋高速道路が近いという地の利を活かし、ご依頼があれば16㎞ほど離れた地域まで伺うこともあります。
— 診療されている患者さんの疾患には、どのような傾向がありますか?
やはり私が認知症専門医ということもあるので、認知症の患者さんが圧倒的に多いですね。次いで、脳血管障害の後遺症やパーキンソン病などの神経難病の方が続きます。もちろん、がんの終末期の患者さんも一定数いらっしゃいます。また、精神疾患を合併されている方からのご依頼も多いです。
— 診療にあたり、特に重要視されている指標はありますか?
指標の数字自体を追い求めるというよりは、私たちの医療の質を測る一つの目安として、「入院率の低さ」と「在宅での看取り率の高さ」を重視しています。私たちの介入によって、患者さんが可能な限り住み慣れた場所で過ごし続けられるよう、入院を回避し、穏やかな最期を迎えられることを目指していきたいですね。結果として、当院の入院率は毎月3%前後と低く、在宅での看取り率は80〜90%を維持しています。

名古屋市の在宅医療を底上げする取り組み──脳卒中・神経難病・ALS患者への支援強化
— 現在感じていらっしゃる、在宅医療全体の課題について教えてください。
一番は、患者さんやご家族が「在宅医療」という選択肢や、数あるクリニックの中から自分たちに合った場所を選ぶための情報が、まだまだ少ないことですね。多くの場合は、ケアマネジャーさんや病院の連携室からの紹介で初めて知ることになります。しかし、各クリニックがどのような特徴や強みを持っているのか、判断する材料が乏しいのが現状です。
また、24時間365日の対応が求められるため、担い手となる医師が増えにくいという構造的な課題もあります。
— そうした課題に対し、今後どのように取り組んでいきたいとお考えですか?
当院が分院展開などで規模を拡大するのではなく、今あるこの場所で、地域全体の医療の質を「底上げ」していくような役割を担いたいと考えています。
具体的には、病院の連携室の方々と合同でカンファレンスを開催するなどして、病院側に在宅医療への解像度を高めてもらう取り組みを進めたいです。退院後の生活を見据えた上で、「この患者さんなら、在宅でこんな風に過ごせる」という共通認識を持つことが、スムーズな連携には不可欠だと感じています。
— 目指す「理想の在宅医療」とは、どのようなものでしょうか。
患者さんご本人にとっても、そのご家族にとっても、「このクリニックに頼んでよかった」と、心から思っていただける医療です。それは、単に病気を治すだけでなく、その方の人生やご家族と寄り添い、記憶に残るような関わりの中から生まれるものだと信じています。そういった私たちと患者さんやご家族との気持ちの循環が、私たちの法人名にある「めぐる」にも現れているのかなと思います。看取りの後、ご家族がふと私たちのことを思い出し、「あの時、良い時間を過ごせたな」と少しでも温かい気持ちになってくれる。そんな医療を目指していきたいですね。
— 最後に、地域の住民の方々へメッセージをお願いします。
在宅医療クリニックを選ぶ際には、ぜひ「繋がり方の質」に注目してみてください。例えば、休日や夜間でもスムーズに連絡が取れるか、LINEやメールといった多様な手段でコミュニケーションが取れるか。そういった細やかな対応が、いざという時の安心感に繋がります。また、どのような医療処置に対応できるかも大切なポイントです。
私たちは、幅広いデバイスと専門知識で、様々なご要望にお応えできる体制を整えています。また、ご家族が集まりやすいように、土日の初診相談も受け付けています。
何かお困りのことがあれば、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談いただければと思っています。皆さんが納得できる人生と、安心できる生活を送るためのお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。

医療法人めぐる ごうホームクリニック──名古屋市の通院困難者・神経難病を支える在宅医療拠点

診療科
・内科/小児科/精神科
対応エリア
対象となる方の例
・通院が困難な方、移動手段がなく外出が難しい方
・寝たきりの方、または寝たきりに準じる状態の方
・緩和ケアや末期がんの治療を、ご自宅や施設で希望される方
・入院をせず、ご自宅での療養生活を希望される方、または退院後の療養に不安を感じている方
・人工呼吸器、胃ろう、カテーテルなどの医学的管理を、ご自宅や施設で必要とされる方
・外来通院は継続したいが、日々の小さな体調変化に都度受診することが負担になってきている方
・寝たきりの方、または寝たきりに準じる状態の方
・緩和ケアや末期がんの治療を、ご自宅や施設で希望される方
・入院をせず、ご自宅での療養生活を希望される方、または退院後の療養に不安を感じている方
・人工呼吸器、胃ろう、カテーテルなどの医学的管理を、ご自宅や施設で必要とされる方
・外来通院は継続したいが、日々の小さな体調変化に都度受診することが負担になってきている方
診療内容
・血液検査、尿検査、心電図検査、エコー、細菌検査など
・在宅輸血療法(赤血球・血小板)
・胸腔穿刺/腹腔穿刺
・癌、非癌患者の苦痛緩和治療(PCA管理)
・糖尿病患者のインスリン調整
・中心静脈栄養
・経管栄養(胃ろう交換、経鼻胃管交換)
・自己導尿、膀胱留置カテーテル、腎瘻交換
・各種ドレーン管理(腹腔、胆のうなど)
・人工呼吸器、在宅酸素
・重度褥瘡のデブリードメント
・嚥下内視鏡
・人工肛門(ストーマ)管理
・関節内注射(ヒアルロン酸注射など)
・ボトックス筋注(上肢下肢痙縮)
・持効性抗精神病剤筋注(コンスタ・ゼプリオンなど)
・在宅輸血療法(赤血球・血小板)
・胸腔穿刺/腹腔穿刺
・癌、非癌患者の苦痛緩和治療(PCA管理)
・糖尿病患者のインスリン調整
・中心静脈栄養
・経管栄養(胃ろう交換、経鼻胃管交換)
・自己導尿、膀胱留置カテーテル、腎瘻交換
・各種ドレーン管理(腹腔、胆のうなど)
・人工呼吸器、在宅酸素
・重度褥瘡のデブリードメント
・嚥下内視鏡
・人工肛門(ストーマ)管理
・関節内注射(ヒアルロン酸注射など)
・ボトックス筋注(上肢下肢痙縮)
・持効性抗精神病剤筋注(コンスタ・ゼプリオンなど)
診療実績(直近1年間※)
・診療患者数合計 790
・看取り件数 128
・訪問診療等の合計回数 12,464
往診 603
訪問診療 11,861
・在宅医療を担当する常勤の医師数 1
・連携する保険医療機関数 5
❏ さらに詳しい診療内容・実績はこちら
❏ 愛知県の在宅看取り件数ランキング2024年版
・看取り件数 128
・訪問診療等の合計回数 12,464
往診 603
訪問診療 11,861
・在宅医療を担当する常勤の医師数 1
・連携する保険医療機関数 5
❏ さらに詳しい診療内容・実績はこちら
❏ 愛知県の在宅看取り件数ランキング2024年版
※在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書に基づく
訪問診療のご相談・お問い合わせ
〒468-0015
名古屋市天白区原1-1410 サンモール原103
お電話でのご相談
TEL:052-803-5005
お電話受付時間:9.00~17:00
https://gohome-clinic.com/
名古屋市天白区原1-1410 サンモール原103
お電話でのご相談
TEL:052-803-5005
お電話受付時間:9.00~17:00
https://gohome-clinic.com/
伊藤剛院長プロフィール

経歴:
2007年 信州大学医学部医学科 卒業
2007年 JA愛知厚生連 豊田厚生病院 小児科
2011年 愛知医科大学病院 精神神経科
2015年 医療法人福智会 福智クリニック(精神科・心療内科)
2016年 医療法人とくしげ会 とくしげ在宅クリニックみかわ 院長
2019年 ごうホームクリニック 開院
現在に至る
2007年 JA愛知厚生連 豊田厚生病院 小児科
2011年 愛知医科大学病院 精神神経科
2015年 医療法人福智会 福智クリニック(精神科・心療内科)
2016年 医療法人とくしげ会 とくしげ在宅クリニックみかわ 院長
2019年 ごうホームクリニック 開院
現在に至る
資格:
医学博士
臨床研修指導医
医師会認定産業医
小児慢性特定疾病指定医
リビングウィル受容協力医師
日本小児精神神経学会 認定医
日本認知症学会 専門医・指導医
日本老年精神医学会 専門医・指導医
緩和ケア/精神腫瘍基本教育指導者(PEACE指導者)
発達障害児マッチングサービスBranch公認メンター
全英自閉症協会(The National Autistic Society)認定 DISCOユーザー
難病指定医
認知症サポート医
看護師特定行為指導者
子どものこころ専門医
自閉症スペクトラム支援士
愛知県公安委員会指定医(認知症)
日本精神神経学会 専門医・指導医
日本褥瘡学会認定 在宅褥瘡予防・管理師
身体障害者福祉法15条指定医(肢体不自由)
エンドオブライフ・ケア協会認定ファシリテーター
折れない心を育てるいのちの授業 認定講師
臨床研修指導医
医師会認定産業医
小児慢性特定疾病指定医
リビングウィル受容協力医師
日本小児精神神経学会 認定医
日本認知症学会 専門医・指導医
日本老年精神医学会 専門医・指導医
緩和ケア/精神腫瘍基本教育指導者(PEACE指導者)
発達障害児マッチングサービスBranch公認メンター
全英自閉症協会(The National Autistic Society)認定 DISCOユーザー
難病指定医
認知症サポート医
看護師特定行為指導者
子どものこころ専門医
自閉症スペクトラム支援士
愛知県公安委員会指定医(認知症)
日本精神神経学会 専門医・指導医
日本褥瘡学会認定 在宅褥瘡予防・管理師
身体障害者福祉法15条指定医(肢体不自由)
エンドオブライフ・ケア協会認定ファシリテーター
折れない心を育てるいのちの授業 認定講師
渡邉博行医師プロフィール

自己紹介文:
これまで病院でさまざまな診療を経験し、高齢の方の体調変化や日常生活に寄り添う医療の大切さを感じ、訪問診療に携わるようになりました。発熱や感染症、持病の悪化、転倒や骨折後のケアなど、ご自宅で起こる不安な症状に幅広く対応してきました。検査や治療だけでなく、「今の生活で無理がないか」「ご本人やご家族が安心できるか」を大切にしています。これからも気軽に相談していただける身近な医師として、安心して在宅で過ごせる毎日をお手伝いしていきたいと思っています。
経歴:
2004年 名古屋大学医学部医学科 卒業
2004年 社会保険中京病院初期臨床研修医
2006年 同病院外科後期研修医
2009年 同病院外科医師
2009年 JA愛知厚生連豊田厚生病院外科
2012年 名古屋大学医学部医科学研究科腫瘍外科
2015年 名古屋大学医学部医科学研究科腫瘍外科学 卒業
2015年 名古屋第二赤十字病院一般消化器外科
2018年 常滑市民病院外科(現 知多半島りんくう病院)
2025年 ごうホームクリニック
現在に至る
2004年 社会保険中京病院初期臨床研修医
2006年 同病院外科後期研修医
2009年 同病院外科医師
2009年 JA愛知厚生連豊田厚生病院外科
2012年 名古屋大学医学部医科学研究科腫瘍外科
2015年 名古屋大学医学部医科学研究科腫瘍外科学 卒業
2015年 名古屋第二赤十字病院一般消化器外科
2018年 常滑市民病院外科(現 知多半島りんくう病院)
2025年 ごうホームクリニック
現在に至る
資格:
医学博士
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
消化器がん外科治療認定医
難病指定医
臨床研修指導医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
消化器がん外科治療認定医
難病指定医
臨床研修指導医
認知症、脳卒中後遺症、パーキンソン病、ALS、精神疾患など在宅診療に関するよくある質問
Q1. 通院が難しい場合でも診療を受けられますか?
A. はい。当院は「通院できない」方を対象とした在宅医療専門クリニックです。医師・看護師がご自宅に訪問し、内科疾患はもちろん、認知症、脳卒中後遺症、パーキンソン病、ALS、精神疾患など幅広い疾患に対応します。ご家族やケアマネジャーとも連携し、生活全体を見据えた診療を行います。
Q2.脳卒中・パーキンソン病・ALSなどの神経難病にも対応していますか?
A. はい。脳血管障害の後遺症、パーキンソン病、ALS を含む神経難病の患者さんが多く在籍しています。医師・看護師・訪問看護師が密に連携し、症状変化に応じた診療、栄養管理、デバイス管理、生活支援を包括的に行っています。
Q3.名古屋市以外でも訪問診療は可能ですか?
A. 診療の中心はクリニックから半径7〜8㎞ですが、名古屋高速道路の利便性を活かし、16㎞ほど離れたエリアの訪問にも対応しています。訪問可能かどうかは、住所をお伺いしたうえで個別にご案内しています。
Q4.認知症や精神疾患を抱える方も診てもらえますか?
A. はい。当院の院長は認知症専門医であり、精神科の診療経験も豊富です。身体疾患と精神症状の両方を抱える方、行動・心理症状(BPSD)がある方も安心してご相談いただけます。
Q5.初めて利用する際の流れを教えてください。
A. まずはお電話またはメール・LINEでご連絡ください。ご家族やケアマネジャーと日程を調整し、ご自宅へ伺って面談・初回診療の内容をご説明します。土日の初診相談にも対応しており、ご家族が揃いやすい環境で相談いただけます。
関連リンク: