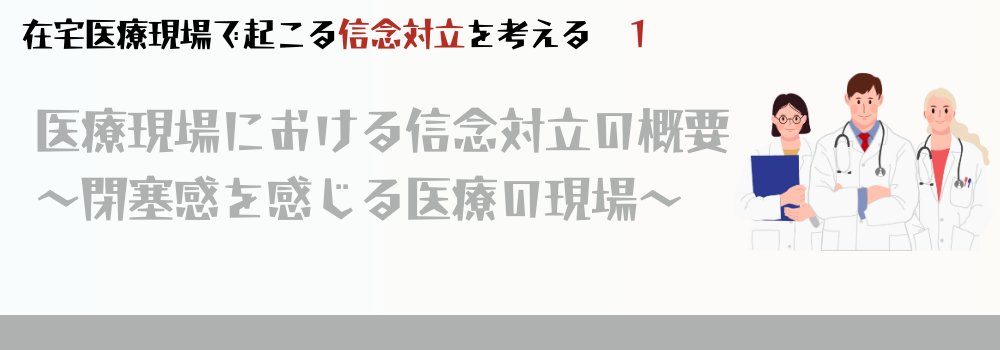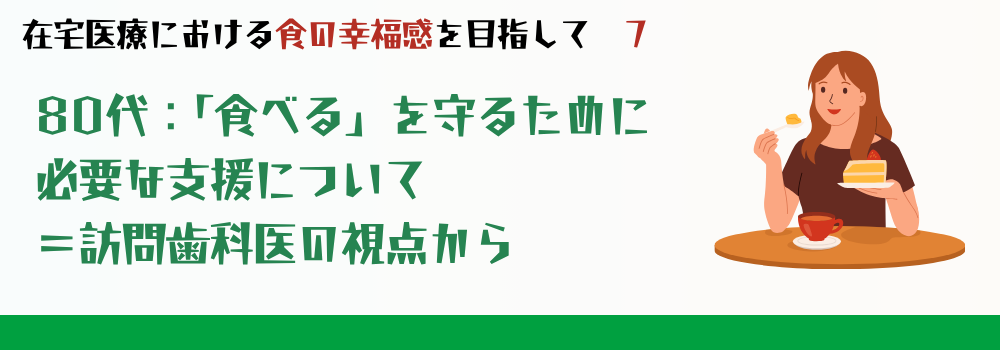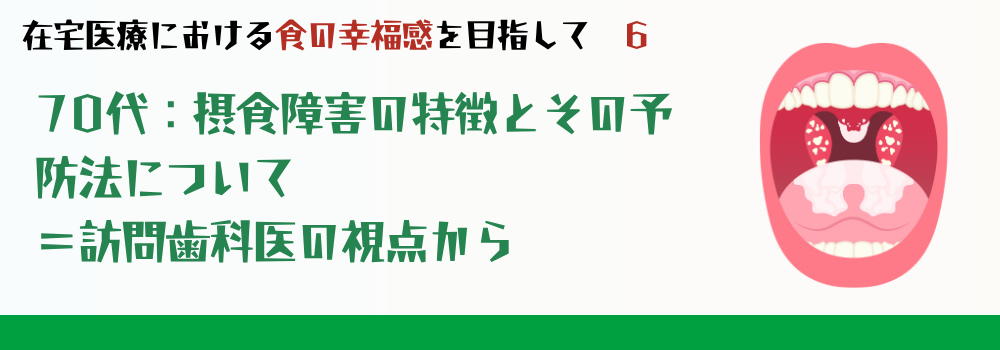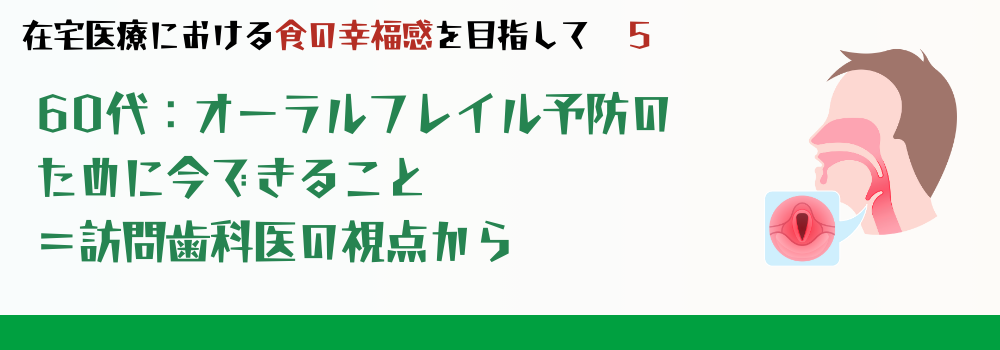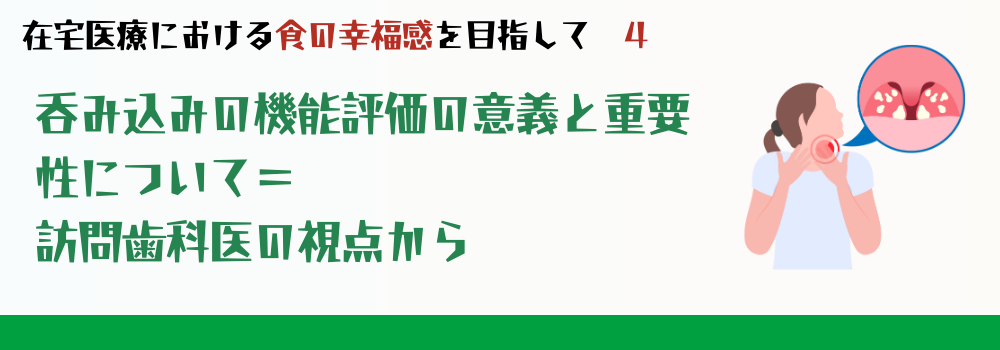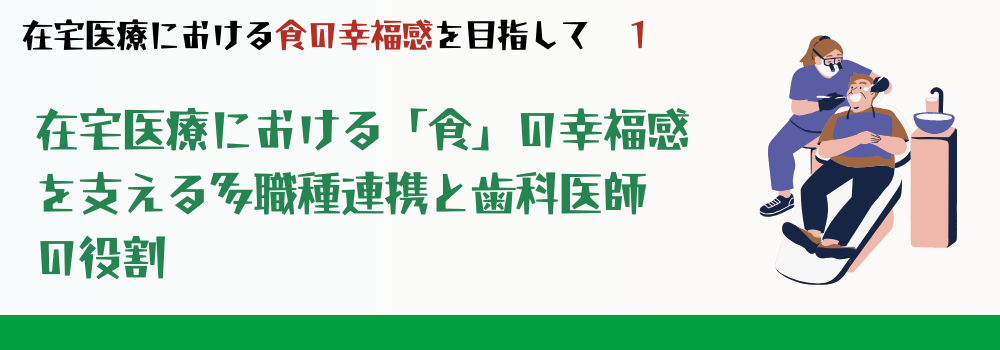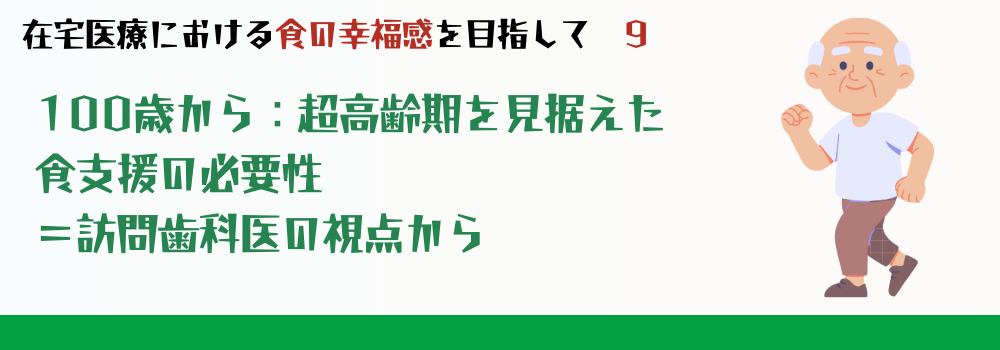信念対立の食支援への活用 最終更新日:2025/11/26
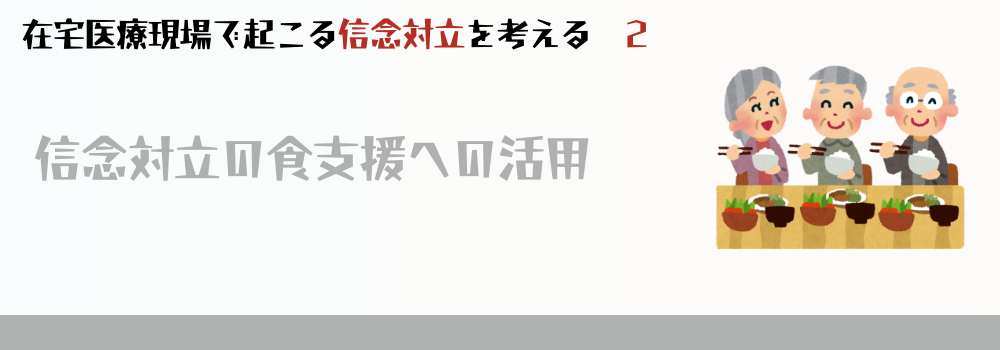
前回は医療者と患者側の間で起こる信念対立と呼ばれる見解の相違について解説をしました。今回第二回目は食支援の現場で起こる葛藤について信念対立という観点から考えてみることにします。
まず最初に前回のおさらいをしながら食支援の場ではどんな問題点が起こってくるかを列挙してみます。
まず最初に前回のおさらいをしながら食支援の場ではどんな問題点が起こってくるかを列挙してみます。
1. 摂食嚥下の信念対立とは何か(前回のおさらい)
(1) 信念対立とは何か
摂食嚥下の現場で起こる信念対立とは、事実認識・価値観・役割の期待・制度上の制約が少しずつずれ、そのずれが重なることで意思決定が止まりやすくなる状態を指します。食支援では、安全(誤嚥や窒息の回避)とQOL(食の楽しみや自立)が拮抗しやすく、「ゼロリスク」を求める姿勢と「許容可能なリスク」で前進する姿勢がぶつかります。関与者が多いことに加え、現場の負担や法的責任が緊張を高め、合意形成に至る難易度が上がります。
(2) 関与者ごとの“典型的な信念セット”
当事者はそれぞれ固有の正当性を持っています。本人は食べる喜びと自律を守りたいと望みます。家族は安全や延命を重く見つつ、看取りの価値や介護負担の現実にも揺れます。医師は医療安全と合併症管理、法的リスクの最小化を重視します。歯科は口腔機能の可塑性を信頼し、口腔ケアや義歯調整の効果を評価します。言語聴覚士は評価と訓練、そして適合した食形態の設定を柱に据えます。管理栄養士は必要量の達成と経口維持の両立を設計課題とします。看護・介護は誤嚥や窒息への恐れと、現場で守れるシンプルな運用性を求めます。経営や管理部門は事故ゼロの方針と記録・説明責任を徹底します。
(3) 争点が集中するテーマ
論点は一定の箇所に集まりやすいです。栄養経路では、経口再開の可否や時期、試行期間の設定が揉めます。食形態では、嚥下調整食の段階やとろみの要否・強度、パンや生野菜、水分の扱いが難所になります。介助条件では、姿勢・一口量・ペース・声かけの組み立てが問われます。口腔ケアの優先度と頻度は不顕性誤嚥による誤嚥性肺炎の予防と直結し、目標設定では延命、QOL、自宅復帰、看取りの優先度の配列が様々な分岐を生みます。終末期では、快適さを優先する経口(comfort feeding)の位置づけが最重要になります。
(4) 対立を増幅する心理・組織メカニズム
判断は心理学的な偏りと組織の構造で増幅します。過去の窒息や肺炎の経験が強く想起されると、可用性ヒューリスティックでリスク評価が過度に厳しくなります。用語の不一致も混乱を招きます。誤嚥、不顕性誤嚥、窒息、むせの区別が曖昧だと議論は噛み合いません。評価所見やリスクの見える化が乏しいと、情報の非対称性がお互いの不信を生みます。合意形成の旗振り役が無責任で曖昧なままだと責任に対する不安が増し、さらに病院や施設の慣行が個別性を奪って硬直を招きます。
(5) 代表的な発生シナリオ
施設入所では、直近の診療情報提供書、看護サマリーに禁食と記されていても、本人は経口を強く希望することがあります。施設は事故ゼロを掲げて慎重になり、家族は早期の経口摂取再開を求めます。三者の期待が微妙にずれることで信頼関係は緊張します。在宅では、家族が通常食を続けたいと願い、訪問看護は水分の稠度も含めた嚥下調整食の必要を主張します。歯科は義歯調整と口腔ケアで経口拡大の可能性を示し、医師は肺炎再発の確率から慎重姿勢を崩しません。それぞれの立場の違いがそのまま判断の差として現れます。
(6) 放置した場合の影響
対立を放置すると、不要な禁食が長引き、低栄養や抑うつを招きます。回避したはずのリスクが別の経路から高まることもあります。不本意ですがチームは分断され、直接介助する現場は疲弊し、クレームや事故対応に人的資源が消費させられます。学びと改善の循環も滞ります。
(7) 予防と解決の実践フレーム
まず、ゴールを二層で設計します。守るべき安全閾値と伸ばしたいQOL目標を同時に置き、二〜四週間の時限目標と再評価日を最初から合意します。次に、最小限の共有データを整えます。嚥下機能の所見(姿勢、反射、一口量、液体・固形の段階)、口腔内の状態(義歯適合、残渣、衛生)、栄養・水分の指標(体重、摂取量、脱水徴候)、既往と増悪因子(感染、薬剤、せん妄)、そして本人・家族の価値観を可視化します。用語は定義を合わせ、誤嚥=気道侵入、窒息=気道閉塞、むせ=防御反応として共有します。リスクは絶対・相対を区別して提示し、各選択肢の便益と不利益を並列で示します。「ゼロリスクはない」を前提に、許容可能なリスクと具体策を組で提案します。
背景:専門性の深化がもたらす“見え方”の差
医療は高度に専門分化しており、同じデータに向き合っても見る軸が異なります。内科は安全と予後を核に置き、看護は実装性と運用の確実さを重視します。リハや言語聴覚士、歯科は機能回復と残存機能の活用、そして食の喜びを主要な到達点に据えます。管理栄養士は必要量の達成と受容性、摂取効率の最適化を求めます。本人と家族は、生活史に根ざした意味と尊厳を判断の基盤にします。価値の序列や時間軸(いま守る安全か、将来の回復か)が少しずつ違うため、各自の「正しさ」がすれ違い、信念対立が生まれやすくなります。
医療は高度に専門分化しており、同じデータに向き合っても見る軸が異なります。内科は安全と予後を核に置き、看護は実装性と運用の確実さを重視します。リハや言語聴覚士、歯科は機能回復と残存機能の活用、そして食の喜びを主要な到達点に据えます。管理栄養士は必要量の達成と受容性、摂取効率の最適化を求めます。本人と家族は、生活史に根ざした意味と尊厳を判断の基盤にします。価値の序列や時間軸(いま守る安全か、将来の回復か)が少しずつ違うため、各自の「正しさ」がすれ違い、信念対立が生まれやすくなります。
2. 専門職が多い摂食嚥下現場で信念対立が起こる理由
多職種連携では、それぞれの専門職が「患者にとって最善」と信じる価値観を持ち寄ります。しかし、評価基準やリスク許容度、制度制約などが異なるため、意見が対立しやすくなります。
・評価指標の非互換性
死亡率、誤嚥率、必要栄養量、患者満足度など、測る指標や評価のタイミングが異なる。
死亡率、誤嚥率、必要栄養量、患者満足度など、測る指標や評価のタイミングが異なる。
・リスク許容度の差
医師は「低頻度でも重篤なリスク」に敏感。リハ職は「反復練習による機能回復」の利益を重視する傾向。
医師は「低頻度でも重篤なリスク」に敏感。リハ職は「反復練習による機能回復」の利益を重視する傾向。
・役割境界の防衛
責任の所在に不安があると、自分の領域を守ろうとする心理が強まり、越境提案への抵抗が生まれる。
責任の所在に不安があると、自分の領域を守ろうとする心理が強まり、越境提案への抵抗が生まれる。
・制度・資源制約
加算要件、スタッフ配置、機材や施設体制などが価値実現の可否に影響する。
加算要件、スタッフ配置、機材や施設体制などが価値実現の可否に影響する。
・用語とフレーミングの齟齬
「安全」「改善」「無益性」などの定義が職種によって異なり、誤解を招く。
「安全」「改善」「無益性」などの定義が職種によって異なり、誤解を招く。
・時間限定性の誤解
「時間限定トライアル」の提案が、「恒久的に続ける」と誤解されることがある。
「時間限定トライアル」の提案が、「恒久的に続ける」と誤解されることがある。
・感情とアイデンティティの影響
専門性は自己価値と直結しやすく、意見への反論を「自分の否定」と捉えやすい。
専門性は自己価値と直結しやすく、意見への反論を「自分の否定」と捉えやすい。
3. 摂食嚥下支援で起こる典型的な信念対立パターン
現場では、価値観や目標の優先順位が異なることで対立が起こりやすくなります。
・安全 vs 自律・喜び
誤嚥リスクなどの「安全性」を最優先する立場と、体験価値や自律を重視する立場の衝突。
誤嚥リスクなどの「安全性」を最優先する立場と、体験価値や自律を重視する立場の衝突。
・短期リスク回避 vs 長期回復
一時的な制限で安定を図るか、機能低下を防ぐため早期挑戦を優先するかで意見が分かれる。
一時的な制限で安定を図るか、機能低下を防ぐため早期挑戦を優先するかで意見が分かれる。
・“普通”の意味の違い
家族の価値観や文化的背景と、医療的調整(とろみ・形態変更など)が衝突することがある。
家族の価値観や文化的背景と、医療的調整(とろみ・形態変更など)が衝突することがある。
4. 信念対立が悪化・長期化するメカニズムと要因
信念対立は、適切に対話がなされないと深刻化しやすくなります。
・立場の固定化(Position Talk)
表面的な主張だけがぶつかり、根底にある本当の関心(Interest)が語られない。
表面的な主張だけがぶつかり、根底にある本当の関心(Interest)が語られない。
・属性化・道徳化
「相手は非倫理的だ」とラベリングし、対話そのものが断絶する。
「相手は非倫理的だ」とラベリングし、対話そのものが断絶する。
・モラルディストレス
自分の倫理観を超えた実践を強いられることで、心理的負担が増し、離職や燃え尽きにつながる。
自分の倫理観を超えた実践を強いられることで、心理的負担が増し、離職や燃え尽きにつながる。
5. 摂食嚥下現場で信念対立が続くと起こる影響
信念対立が解消されないまま進むと、現場や患者ケアに深刻な影響を与えます。
・合意形成の遅延
→ 方針が定まらず、患者安全の低下を招く。
→ 方針が定まらず、患者安全の低下を招く。
・実装の不統一
→ スタッフ間で対応がばらつき、観察データの比較が困難になる。
→ スタッフ間で対応がばらつき、観察データの比較が困難になる。
・感情疲労・離職意向の増加
→ モラルディストレスが蓄積し、ケアの継続性が損なわれる。
→ モラルディストレスが蓄積し、ケアの継続性が損なわれる。
6. 信念対立を解消するための原則と多職種連携のポイント
信念対立を建設的に解消するためには、共通の視点と合意形成の枠組みが必要です。
・事実と価値の分離
データ(例:体重、バイタル、誤嚥率)と価値観(尊厳、生活の質)を別レイヤーで整理する。
データ(例:体重、バイタル、誤嚥率)と価値観(尊厳、生活の質)を別レイヤーで整理する。
・共通ゴールの再定義
「Goal-Concordant Care」=「本人の価値観に沿った安全最大化」をチームで共有する。
「Goal-Concordant Care」=「本人の価値観に沿った安全最大化」をチームで共有する。
・可逆性の高い実装から始める
時間限定トライアルと観察指標を設定し、小さな合意から進める。
時間限定トライアルと観察指標を設定し、小さな合意から進める。
・レッドラインの合意
中止基準やエスカレーション条件をあらかじめ数値で明確化する。
中止基準やエスカレーション条件をあらかじめ数値で明確化する。
・役割と責任の明確化
誰が説明し、誰が観察し、誰が最終判断するかを合意しておく。
誰が説明し、誰が観察し、誰が最終判断するかを合意しておく。
・言語の統一
「安全」「改善」「無益性」「同意」など、用語の定義をチーム内で共有する。
「安全」「改善」「無益性」「同意」など、用語の定義をチーム内で共有する。
7. 現場で使える信念対立解消ミニプロトコル
多職種間の信念対立を解消するための実践的なステップの一例です。
(1) エシックス・タイムアウトの宣言
「価値と事実を切り分けて検討します」と明示して会議を開始。
(2) 4分割法で整理
医学的適応/患者意向/QOL/周囲状況を色分けし、事実と価値を区別。
(3) オプション設計
A案(安全重視)〜C案(QOL重視)を可逆性順に提示。
(4) 観察指標と閾値の設定
バイタル、機能評価、負担スコアなど、事前に中止基準を合意。
(5) 期限付き合意とレビュー
例:2週間後に見直し、再協議のトリガー条件を明確化。
(6) Teach-backで理解確認
本人や家族に要点を要約してもらい、認識齟齬を防ぐ。
(7) 反対意見の記録
少数意見も記録に残し、後日の再評価時に活用する。
摂食嚥下の信念対立まとめと次回予告
・専門性が深いほど評価軸・リスク許容・時間軸がズレ、信念対立は“自然発生”する。
・事実と価値を分け、共通ゴール+可逆的トライアル+数値指標+レッドラインで合意形成を進める。
・4分割法は論点の可視化と役割明確化を助け、実装可能な折衷案を患者価値に沿って設計できる。
・文書化と定期レビューが、対立の再燃を防ぎ、学習サイクルを回す土台となる。
次回最終回第三回目では、4分割法を詳しく解説することでより理解を深めたいと思います。私自身膠着した局面の時など、まずは手を動かして思考をまとめるため、整理するチームメンバーみんなに記入してもらい思わぬ視点に気が付くなどの効果を実感していますので、ぜひご覧ください。
摂食嚥下と食支援の信念対立Q&A
Q1. 摂食嚥下の現場で「信念対立」とは何ですか?
A. 事実認識や価値観、役割期待、制度制約がずれて意思決定が止まりやすくなる状態です。安全を重視する姿勢と、許容可能なリスクで食の喜びを守りたい姿勢が衝突しやすいのが特徴です。
Q2. なぜ多職種が関わるほど信念対立が起こりやすいのですか?
A. 専門職ごとに評価指標やリスク許容度、制度上の制約が異なるためです。医師は安全や法的責任、リハ職や言語聴覚士は機能回復、家族は食の喜びや生活の質などを重視するため、価値観が食い違います。
Q3. 典型的な信念対立の例には何がありますか?
A. 「安全vs自律・喜び」「短期リスク回避vs長期回復」「普通食へのこだわり」などが代表例です。とろみの要否や経口再開の時期など、具体的な食形態・介助条件をめぐる対立も多く見られます。
Q4. 信念対立が放置されるとどのような影響がありますか?
A. 不必要な禁食による低栄養や抑うつ、現場スタッフの感情疲労、モラルディストレスによる離職意向の増加、ケア方針の不統一など、患者とチーム双方に深刻な影響を及ぼします。
Q5. 信念対立を解消するにはどうすればよいですか?
A. 事実と価値を切り分けて整理し、本人の価値観を尊重した共通ゴールを再定義します。時間限定トライアルや観察指標、レッドライン合意、言語の統一などを取り入れた多職種連携が有効です。
関連リンク:
執筆:

本シリーズは全3回で、医療現場で起こる「信念対立」を多角的に解説します。
第1回では、多職種が協働する中で意見が衝突しやすい背景やメカニズムを整理し、対話の出発点となる基本構造を学びます。
第2回では、治療方針の決定や療養形態の選択、多職種カンファレンスなど、実際の医療現場で信念対立がどのように発生し、どのような影響を及ぼすかを具体的に掘り下げます。
最終回となる第3回では、事実と価値を切り分け、共通ゴールを再定義し、柔軟な合意形成を実現するための対話技法やツールを紹介。より良いチーム医療の実践を支援します。
第1回では、多職種が協働する中で意見が衝突しやすい背景やメカニズムを整理し、対話の出発点となる基本構造を学びます。
第2回では、治療方針の決定や療養形態の選択、多職種カンファレンスなど、実際の医療現場で信念対立がどのように発生し、どのような影響を及ぼすかを具体的に掘り下げます。
最終回となる第3回では、事実と価値を切り分け、共通ゴールを再定義し、柔軟な合意形成を実現するための対話技法やツールを紹介。より良いチーム医療の実践を支援します。