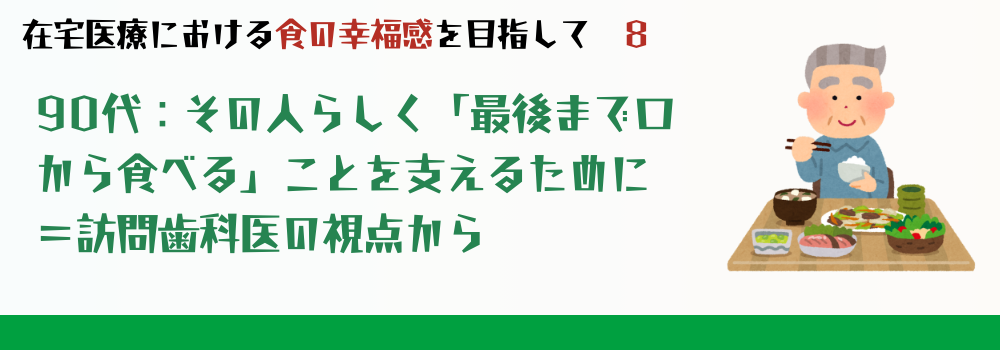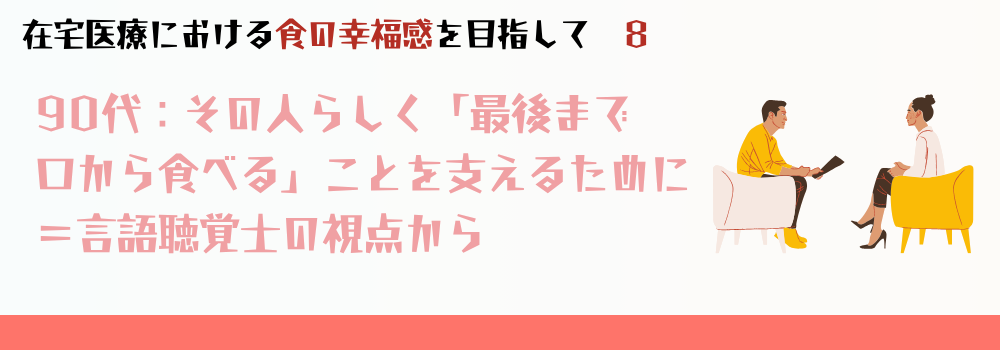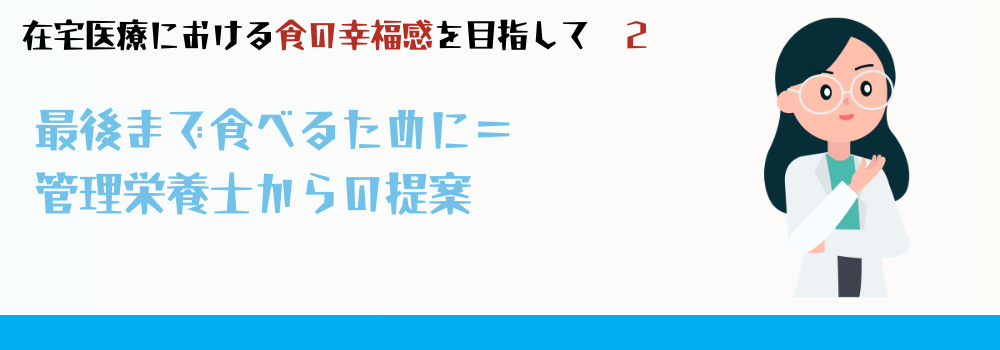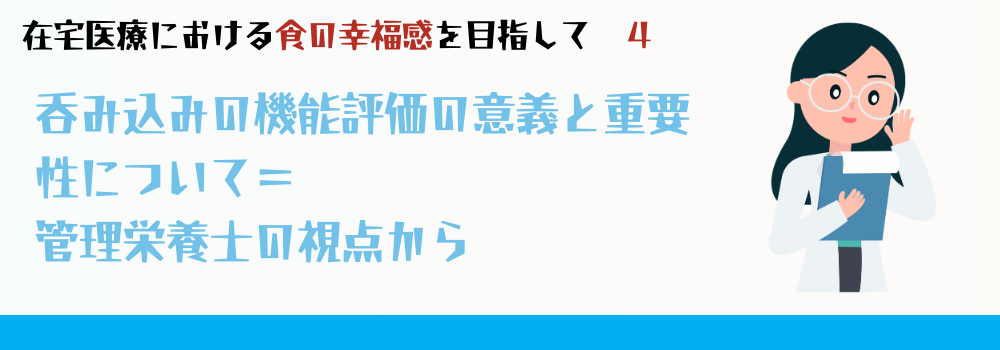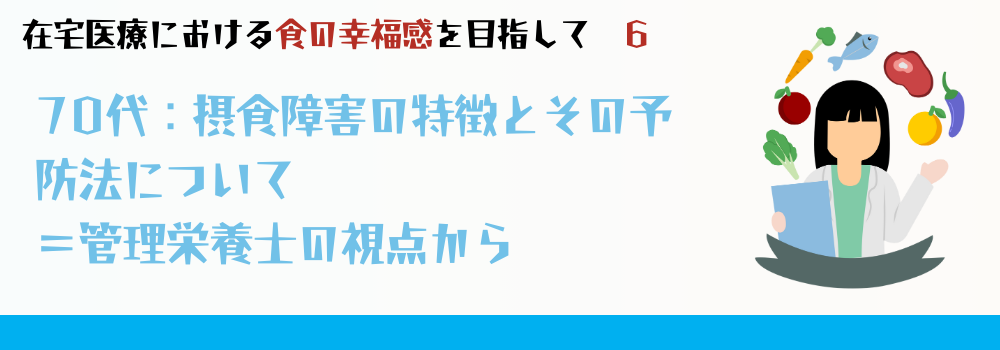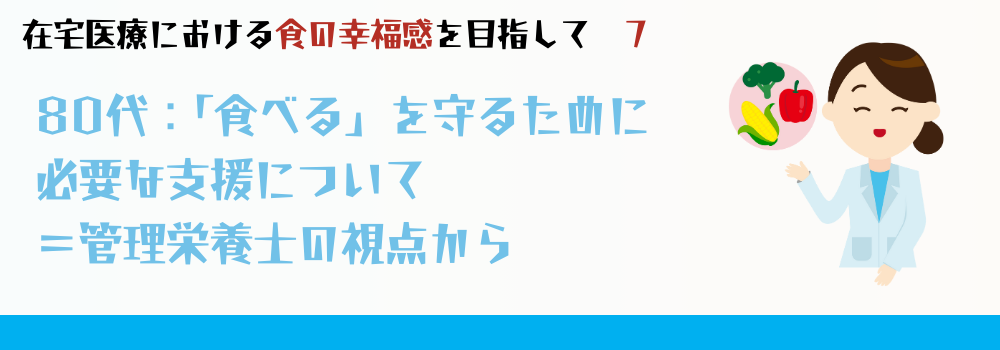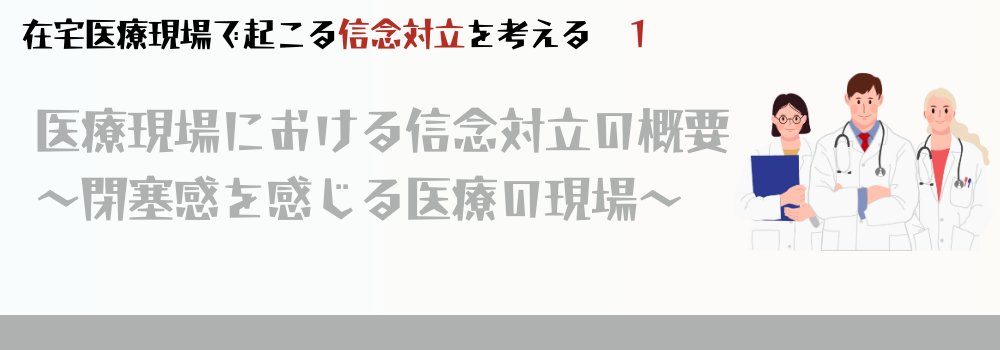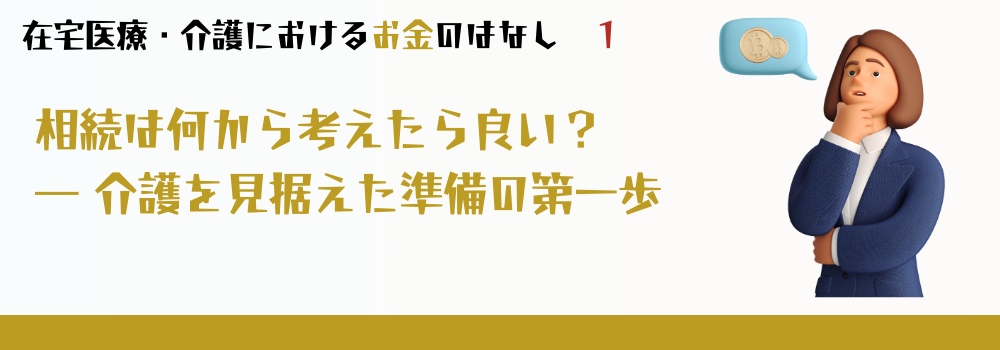【管理栄養士執筆】90代の嚥下障害を支える管理栄養士の実践|在宅で「その人らしく食べる」ための栄養支援 最終更新日:2025/11/26
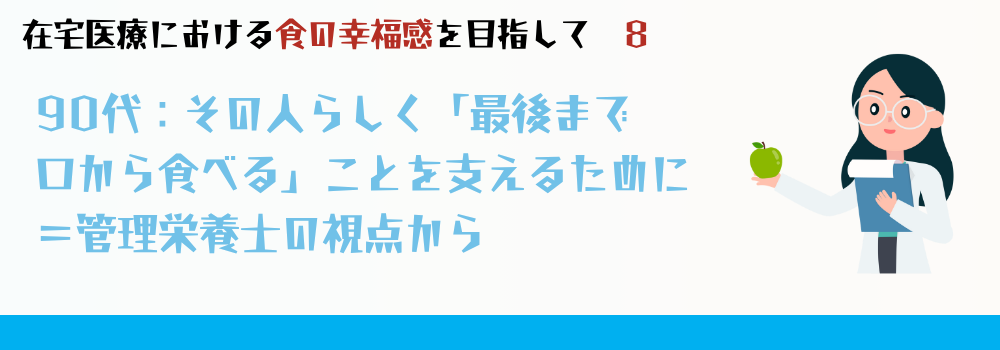
90代の嚥下障害に対して、在宅でどのように「その人らしく食べる」ことを支えられるのか。管理栄養士が行った訪問栄養指導の実例を通して、低栄養・褥瘡・誤嚥リスクの改善、そして家族支援までを詳しく紹介します。最期まで“食べる喜び”を守るための考え方と実践ポイントをまとめました。
1. はじめに──90代の摂食嚥下障害と管理栄養士の支援の意義
90代において『最期まで口から食べる』ということを叶えるのは、その人の最期のあり方を決めるということに直結すると考えます。その人らしく最期を迎えるために実際の事例を用いて管理栄養士の役割を考察します。
2. 事例:90代女性の在宅食支援から学ぶこと

90代女性
低栄養 認知症 嚥下障害
低栄養 認知症 嚥下障害
2-1 訪問栄養指導に至る背景と課題
ご家族と暮らしており、月1回ショートステイを利用している方。ショートでは食事が食べられるものの、自宅に帰ると摂取ができないというお話。低栄養、軽度の嚥下障害、褥瘡を起こすことがあり、訪問栄養食事指導の依頼があった。
2-2 初回介入時の観察と食環境の課題
同居のご家族からお話を伺うと、徐々に食べられなくなってしまい、認知症から食べる際の集中もできず、椅子に座る時間が短くなるというお話あり。以前好きだったものなどを出しても食べられず、たまにむせ込みが見られるとのこと。また介護負担が多く、ご家族が調理する時間がないとのこと。
2-3 長期目標:嚥下障害を防ぎ「口から食べる」生活を維持
褥瘡を起こさないようにし、嚥下障害なく食事ができるようにする
2-4 短期目標:食事量・形態・間食の工夫による改善策
・一回の食事量を少なくし、食事時間の短縮を行う。代わりに間食を取り入れる。
・褥瘡ができそうな場合のみ栄養補助食品を取り入れる。
・現在の食事形態でむせ込みやすい食材を避け、市販の介護食も取り入れる。
その後、上記のアドバイスをもとに生活をしていただきました。
2-5 結果:栄養改善・褥瘡予防・誤嚥性肺炎ゼロの実現
・褥瘡を起こすことはなかった、患部が赤くなってきた時には褥瘡管理に必要な栄養素を含む栄養補助食品のゼリーを召し上がっていただいた。
・たんぱく質、エネルギー量の摂取量が改善された。
・食形態にあった食材を使用することができ、また市販の介護食を使ったアレンジメニューを作ることができた。最期まで誤嚥性肺炎は起こさず過ごされた。
3. 症例を通して考える「その人らしく」を叶える3つの視点
訪問栄養食事指導の介入にあたり、下記のような視点を持って支援を行いました。
3-1 身体的要因を探るアセスメントの重要性
アセスメントの際には、身体的な問題でその人らしさを妨げている要因を探します。例えば痛みや動かしづらさ、姿勢のとりづらさ、義歯の状態、口腔内の状況などが挙げられます。
今回の場合、褥瘡を起こすことがあるということで、患部が赤くなってきた際には、可能な限り栄養補助食品を食べていただくようにしました。褥瘡を起こさず、痛みが起こるのを防ぐ目的がありました。
同じように義歯の状況や口腔内の状態、姿勢などから咀嚼障害、嚥下障害が起きている場合もあります。こうした問題を取り除くのも『その人らしく最期を迎える』ためになるべく取り除いておきたいポイントです。
3-2 栄養管理と『最後の食事』のバランスを考える
一方で注意をしたいのは、栄養管理という形にとらわれすぎないことです。褥瘡や低栄養があって、そのための栄養管理がたとえ必要だったとしても、栄養量の確保を第一の目標にしてしまうことはその人らしさを妨げる要因にもなりかねません。そのため今回は栄養補助食品を毎日使用するのはなく、必要時のみとし、通常の間食はカステラやプリンなどにしました。
特に人生の最期を迎えるような場面では、『最後の食事』を意識しながら、どのような食事ならその人にとって好ましいか、ご本人様はどんなものを食べたいか、家族は食べてほしいのかを考えていきます。その際、どこまでなら提供が可能か言語聴覚士や歯科医師と連携していくことが求められます。

3-3 家族支援と多職種連携で支える在宅ケア
90代の介護には家族支援も重要な側面を持っていると考えます。今回もご家族様の介護負担が問題として挙がりました。
『その人らしく』を叶えるためには家族が介護に対してどのような思いを持っているか、家族はどこまで医療・介護職からの支援を求めているか、実際に家族がどこまで介護に介入できるのか、介入していきたいのか、を確認する必要があります。介護する家族の思いに寄り添いながら、無理のない形で「食べること」を支える工夫が求められます。
また90代の方の介護をされる方がご高齢の場合もあり、ご家族自身もご病気を抱えていたり、体が不自由な場合もあります。この場合、毎日の食事は誰がどこまで準備できるのか、ということが重要になります。
よく聞かれるのは、嚥下障害があっても、手作りの食事を召し上がっていただきたいという思いもあり、一方で調理にかける時間があまりとれないという声です。実際に、ミキサーを使った毎食の調理は、工程が多く調理時間が長くなります。また一方で、摂食嚥下障害があるからといって食事をすべてミキサーにかけると、加水をする必要があることから食事量が増えすぎてしまい、摂取量が低下する可能性もあります。
そのため、実際の栄養指導ではミキサーの使い方の指導の他に、市販の介護食やそのアレンジレシピや、1工程でできる加熱を必要としないメニュー(マグロのたたきに山芋をかける、市販の乾燥マッシュポテトを使うなど)の提案を行っています。
この際、ポイントになるのは、どこで、どの商品が、どのように買えるのか、までを提案することです。単にメニューの提案だけでは行動に移すことは難しいため『●●のスーパーの●●コーナーの横にある●●という商品』とお伝えするようにしています。これは介護食だけではなく、冷凍食品やチルド食品を使う際にも、同様にお伝えしています。スーパーの種類ごとに置いている介護食品や冷凍食品の種類は違いがあります。
4. おわりに──90代の「食べる喜び」を守る在宅医療の未来
「食べること」は生きることそのものです。90代の方が最期まで口から食べることを支えるには、栄養だけでなく、環境や心のケアも欠かせません。管理栄養士として、本人と家族の思いに寄り添いながら、その人らしい食のあり方を共に考えていきたいと思います。

管理栄養士が教える高齢者の食支援術
Q1. 高齢者が嚥下障害になる主な原因は何ですか?
A. 嚥下障害の多くは、加齢による筋力や神経機能の低下が原因です。特に90代では、舌や喉の筋肉の動きが弱まり、飲み込みの反射が遅くなることで誤嚥のリスクが高まります。さらに、義歯の不適合、唾液分泌量の減少、姿勢保持の難しさ、認知症や脳血管疾患による神経障害などが複合的に関係します。また、薬の副作用や脱水も嚥下機能を低下させる要因です。これらを総合的に把握するために、管理栄養士や言語聴覚士など多職種での評価が欠かせません。
Q2. 管理栄養士はどんな支援を行うのですか?
A. 管理栄養士は、嚥下機能や食欲の状態を見極めたうえで、食事形態の調整(刻み食・ミキサー食・ソフト食など)や栄養バランスの再構築を行います。訪問栄養指導では、食べやすい姿勢や環境づくり、補助食品の提案、摂取カロリーと水分量の管理など、在宅での食事が続けられるよう総合的に支援します。また、家族に対しても「無理のない介助方法」や「誤嚥を防ぐ食事介助のポイント」などを具体的にアドバイスし、日常的に安全で楽しい食事時間を実現できるよう伴走します。
Q3. 褥瘡や低栄養はどのように予防できますか?
A. まず基本は、十分なエネルギーとタンパク質を摂取することです。特に90代では筋肉量が減少しやすいため、魚・卵・豆腐など消化吸収のよいタンパク質を意識的に取り入れます。食欲が落ちている場合は、間食や栄養補助食品を少量ずつ頻回に摂る工夫が有効です。また、水分摂取量を確保することで血流が保たれ、褥瘡の発生を防ぎます。管理栄養士は、食事記録や体重変化、血清アルブミン値などをモニタリングしながら、必要に応じて栄養計画を修正します。食事だけでなく、寝具や体位変換など介護環境との連携も重要です。
Q4. 「最後の食事」をどう考えればよいですか?
A. 栄養管理だけでなく、「その人が何を食べたいのか」という気持ちを尊重することが何より大切です。終末期では、無理にカロリーを補給するよりも、本人が安心して食べられる“心の栄養”を優先します。例えば「小さなひとくちの果物」や「昔から好きな味噌汁」など、ほんの少しの食事でも大きな満足につながります。管理栄養士は医師や看護師と連携し、嚥下機能や全身状態を確認しながら、本人と家族が納得できる形で“最後の食事”を迎えられるよう支援します。これは単なる栄養指導ではなく、尊厳ある生き方を支えるケアの一部です。
Q5. 家族はどのようにサポートすればよいですか?
A. 家族の役割は、食事を「義務」ではなく「楽しみ」として支えることです。嚥下障害があっても、焦らずゆっくり食事を進める環境をつくることが大切です。例えば、テレビを消して静かな空間を整えたり、姿勢を少し前かがみに保ったりするだけでも誤嚥リスクを減らせます。さらに、本人が疲れやすい場合は一度の食事量を減らし、複数回に分ける工夫も有効です。介護者が孤立しないよう、訪問栄養指導や地域包括支援センターと連携し、専門職と協力しながら負担を軽減することも重要です。
関連リンク:
執筆:

井上美穂(いのうえみほ)
ふれあい歯科ごとう 管理栄養士
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-11-13せらび新宿1階
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
介護や医療イベントにて食事の大切さを伝えるキッチンカーを運営中
『食の相談室おむすび』
『食の相談室おむすび』