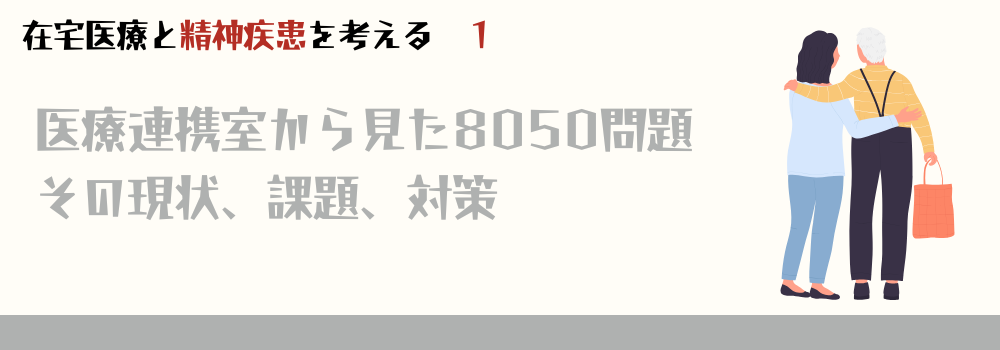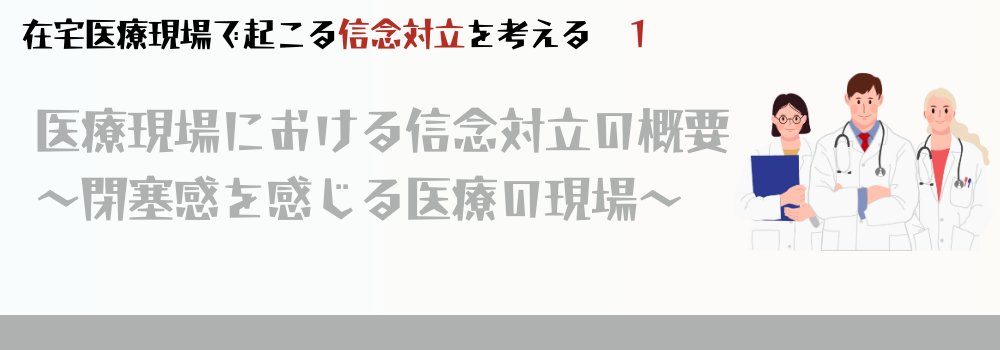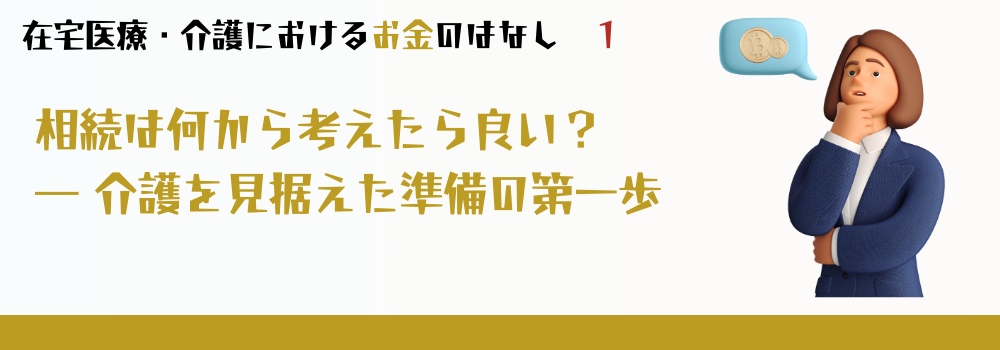看護師から見た8050問題~その現状、課題、対策 最終更新日:2025/02/03
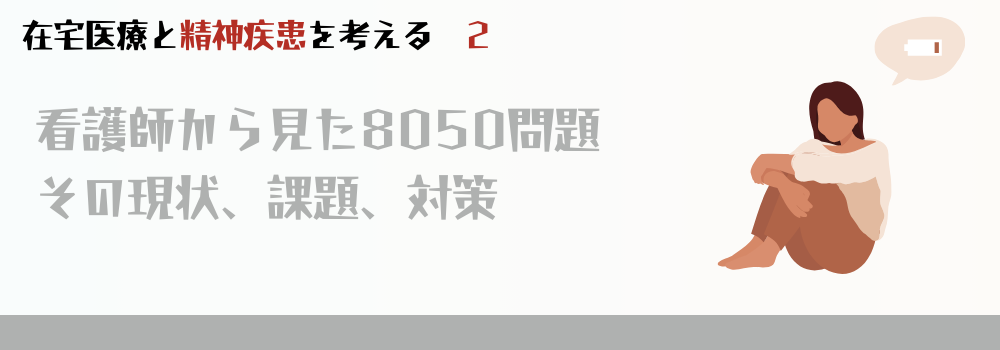
在宅医療と精神疾患を考えるシリーズの第一弾。
80代の親が50代の子どもの生活を支えるために経済的にも精神的にも強い負担を請け負う社会問題「8050問題」をテーマとしてその現状、課題、対策を考えます。第2回目は、看護師の視点から、吉見聖伸氏(成仁病院 看護次長/一般社団法人日本心理FT協会代表理事)により解説いただきました。
80代の親が50代の子どもの生活を支えるために経済的にも精神的にも強い負担を請け負う社会問題「8050問題」をテーマとしてその現状、課題、対策を考えます。第2回目は、看護師の視点から、吉見聖伸氏(成仁病院 看護次長/一般社団法人日本心理FT協会代表理事)により解説いただきました。
はじめに
日本社会では、経済的停滞や高齢化が複雑に絡み合い、「8050問題」が大きな社会問題となっています。この問題は、80代の親が50代の子どもを支える状況を指し、高齢の親に介護や金銭的負担がのしかかる現実を浮き彫りにしています。精神科急性期病棟で看護師として勤務する中、この問題は患者や家族との関わりの中で頻繁に目にします。8050問題は、個々の家庭だけでなく、社会全体に多大な影響を及ぼす複雑な問題であり、早急な対応が求められる課題です。本稿では、精神科急性期病棟での看護師の視点から、8050問題の現状、課題、そして解決に向けた方策を詳述します。
1. 精神科急性期病棟における8050問題の現状
1-1.高齢の親が抱える負担
50代以上の患者には、社会復帰できず親に依存するケースが多く見られます。高齢の親は介護や健康問題を抱えながら、子どもの支援を続けることで、身体的・精神的な負担が増しています。この負担は、親自身の健康状態を悪化させるだけでなく、家庭全体の安定を脅かす要因ともなります。加えて、長期化する支援関係が親子双方の心身に負担を蓄積させる現状も見逃せません。
1-2.支援の途切れと孤立
親子ともに高齢化する中、社会資源へのアクセス不足や地域とのつながりが希薄で、孤立が進む家庭が増えています。特に親が病気や高齢による衰えで支援能力を失った場合、50代の子どもが一人で生活を維持することが困難になりやすいです。この孤立は家庭内だけでなく地域社会とも断絶した状態を招き、支援が届かないまま生活基盤がさらに不安定になる要因となっています。

1-3.コロナ禍による影響
新型コロナウイルス感染症の影響で経済的困窮が深刻化し、8050問題はさらに複雑化しました。コロナ禍では、非正規雇用の減少や社会活動の制限により、ひきこもりや家庭内ストレスが増加しました。これにより、精神的負担が悪化し、入院患者の増加にもつながっています。
2. 看護の視点から見る主な課題
2-1.家族サポート体制の脆弱さ
退院後の生活基盤を親に依存せざるを得ないケースが多く見られますが、親自身が高齢化によって支援の限界を迎えています。親が持つ負担感や疲弊は深刻で、家庭全体が崩壊するリスクを高めています。また、親の健康問題や高齢者特有の精神疾患が重なり、支援体制がますます不安定になるケースも少なくありません。
2-2.社会資源の活用不足
地域包括支援センターや障害福祉サービスなど、社会資源の存在を知らない、または活用方法がわからない家庭が多いです。特に精神疾患を抱える患者は外出や他者との関わりを避ける傾向があり、結果として地域支援ネットワークへのアクセスが限定される現状があります。

2-3.疾患理解とケアの困難さ
精神疾患の再発や併存疾患に対応するための知識が不足している家庭では、対応が困難を極めます。また、親が高齢化による認知機能の低下や身体的制約を抱えている場合、子どものケアに集中する余裕がなくなることが課題として挙げられます。
3. 精神科急性期病棟から見た対策の方向性
3-1.多職種連携による包括的支援
入院時から退院後の生活を見据え、多職種が連携して家族支援や社会資源の活用を進めることが重要です。医師、看護師だけでなく、心理師やソーシャルワーカーが一体となることで、より包括的な支援が可能となります。
3-2.地域との連携強化
地域包括支援センターや就労支援施設と連携し、患者や家族の孤立を防ぐ仕組みづくりが必要です。地域社会との密接な協力により、患者の生活基盤を支えるための環境を整えます。
3-3.親世代への介護・医療サービス
訪問介護やデイサービスの利用支援を通じて、親の負担を軽減する取り組みが効果的です。さらに、介護保険の申請支援やケアマネージャーとの連携も重要です。

3-4.患者本人へのセルフケア支援
セルフケア能力や社会適応力を高める教育やリカバリー支援を進め、患者の自立を促します。特に作業療法や認知行動療法を活用することで、社会復帰への具体的なステップを支援します。
3-5.ピアサポートの活用
ピアサポートとは、同じ経験を持つ者同士が支え合い、互いの回復や社会参加を助ける取り組みを指します。この手法は、精神疾患を持つ患者に特に有効であり、孤立を防ぐだけでなく、自己肯定感や生きがいの向上にも寄与します。
近年では、地域ごとに設置される当事者会やリカバリーカフェなどが普及しつつあります。これらの場では、患者同士が日常的な困りごとや回復へのステップを共有し、互いに励まし合うことができます。
4. 今後に向けて
ここで注目したいのが「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(通称:にも包括)」の概念です。この概念は、既存の支援体制に柔軟性を持たせ、多様な問題に対応できる包括的なアプローチを指します。「にも包括」とは、当事者だけでなく、当事者を取り巻く環境や支援者の立場も考慮し、多方面からのアプローチを可能にする視点を指します。
さらに、家族全体を対象とした教育プログラムを導入することで、8050問題への包括的なアプローチが可能となります。このプログラムでは、家族が利用可能な社会資源や適切なケア方法を学ぶ機会を提供し、家庭内での支援体制を強化します。同時に、地域社会や行政機関が積極的に関与することで、8050問題の解決に向けた広範な支援の実現を目指します。

おわりに
精神科急性期病棟では、患者の急性症状を安定させるだけでなく、退院後の生活を見据えた支援が求められます。看護師は、緊急対応だけでなく、地域や多職種と協力し、社会資源を活用した支援調整を行う重要な役割を担っています。退院後も継続的な支援を提供することで、親子が安心して暮らせる環境の実現を目指し、社会全体で8050問題を解決するための努力が求められます。
関連リンク:
執筆:
吉見聖伸(よしみまさのぶ)
経歴:
2000年 医療法人大徳会桜ヶ丘病院 看護主任
2003年 飯沼病院 急性期病棟看護主任、看護副師長
2007年 成仁病院 看護師長
2013年 成仁病院 主任研究員
2013年 専門学校 首都医校 実践看護学科Ⅱ学科長
2020年 成仁病院 看護次長
2000年 医療法人大徳会桜ヶ丘病院 看護主任
2003年 飯沼病院 急性期病棟看護主任、看護副師長
2007年 成仁病院 看護師長
2013年 成仁病院 主任研究員
2013年 専門学校 首都医校 実践看護学科Ⅱ学科長
2020年 成仁病院 看護次長
資格:
公認心理師
看護師
精神保健福祉士
キャリアコンサルタント
公認心理師
看護師
精神保健福祉士
キャリアコンサルタント