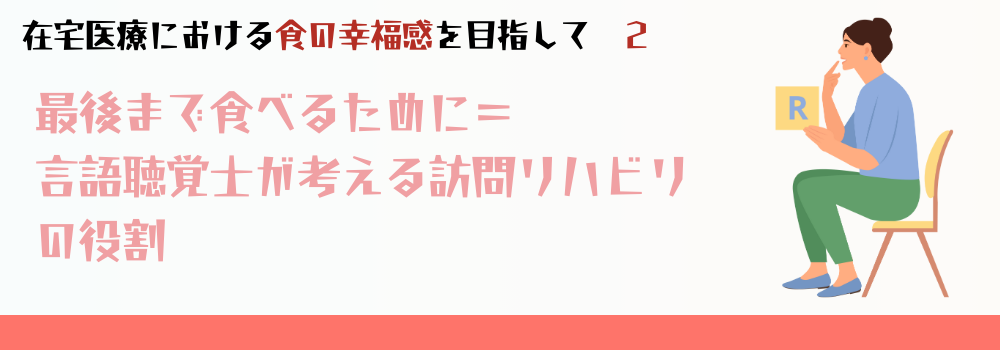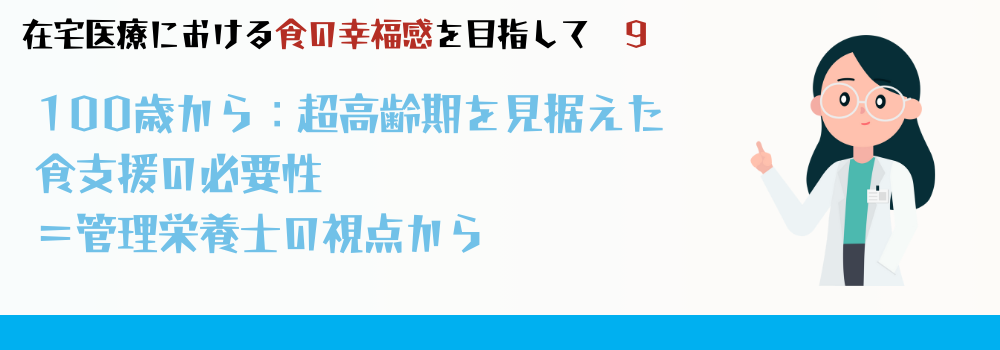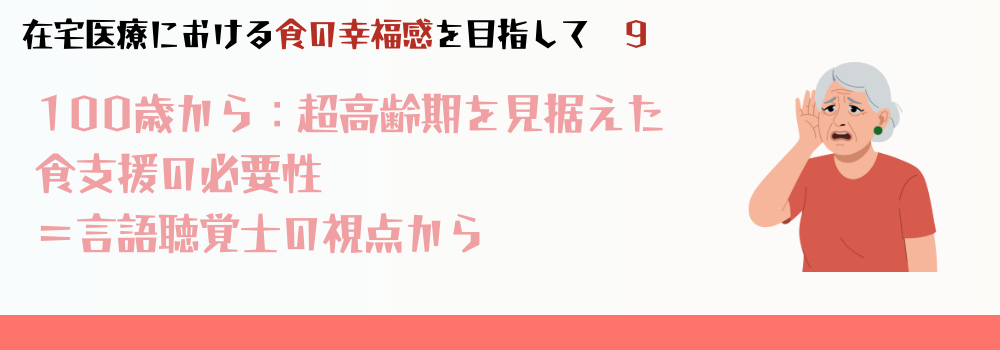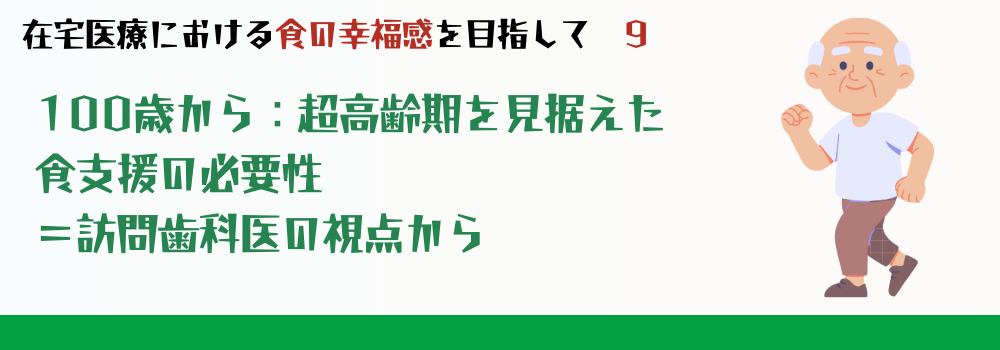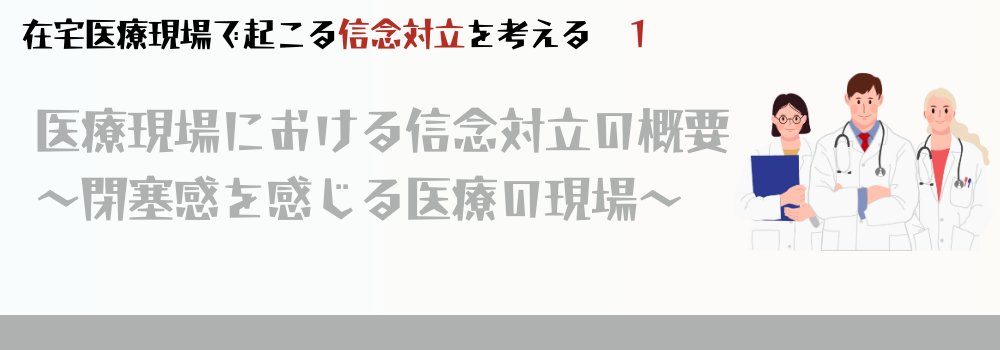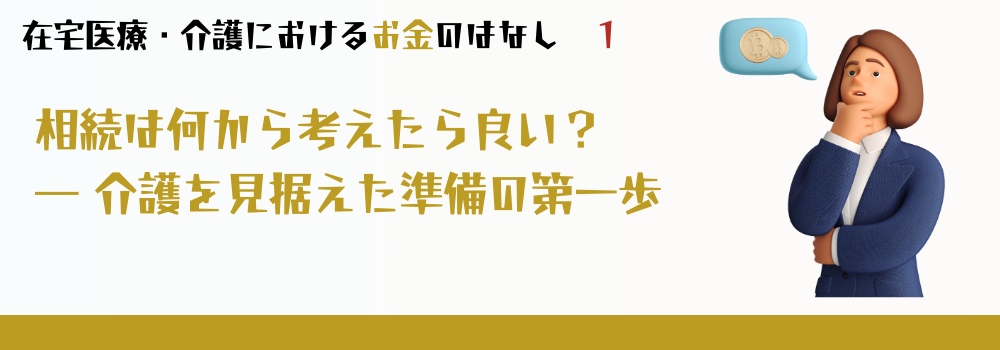摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために=言語聴覚士の視点から 最終更新日:2025/03/24
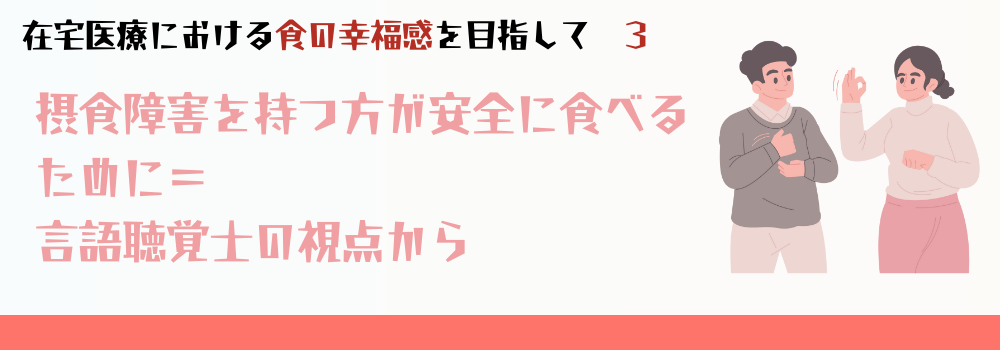
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
3つ目のテーマは「摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために」と題して、言語聴覚士の立場として、後藤茉利奈言語聴覚士により解説いただきました。
3つ目のテーマは「摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために」と題して、言語聴覚士の立場として、後藤茉利奈言語聴覚士により解説いただきました。
はじめに
「食べること」は、栄養を摂るだけでなく、楽しみや人とのつながりを生む重要な行為です。しかし、加齢や病気によって嚥下機能が低下すると、誤嚥や窒息のリスクが高まり、安全に食事をすることが難しくなります。
摂食嚥下障害を持つ方が最後まで安全に食べるためには、本人の努力だけでなく、家族や介護者が正しい知識を持ち、適切な支援を行うことが不可欠です。
この記事では「安全に食べるために、周囲の人ができること」 を言語聴覚士(ST)の視点から、具体的な方法や実例を交えて詳しく解説していきます。

1. 摂食嚥下障害とは? ~なぜ支援が必要なのか~
摂食嚥下障害とは、「食べ物を口に運び、咀嚼し、飲み込む」 一連の動作がスムーズに行えない状態を指します。
障害がある方は、次のような問題を抱えることが多くあります。
障害がある方は、次のような問題を抱えることが多くあります。
・食事中によくむせる
・食べ物が口に残る、飲み込みに時間がかかる
・食後に痰が増える、声がかすれる(湿性嗄声)
・体重が減少している(低栄養のリスク)
しかし、これらの症状があっても本人が気づかないことも多く、「年のせい」「仕方がない」と放置してしまうことも少なくありません。ここで重要なのは、「本人が気づかなくても、周囲が気づいて支援すること」 です。

2. 安全に食べるために周囲ができる5つの具体的な支援
2-1. 姿勢を整える(誤嚥を防ぐ基本)
姿勢を整えるだけで誤嚥のリスクが減ることは意外と知られていません。
正しい食事姿勢のポイント
・椅子に座る場合 → 背筋を伸ばし、足の裏を床につける。顎を少し引く。
・ベッド上の場合 → 背もたれの高さを適正な高さに調整する。足元や、脇の下などにクッションを入れて姿勢を安定させる。
・頸部が後ろに倒れやすい方 → 首枕を使って顎を引きやすくする。
実例A:ベッド上での誤嚥リスクが減ったケース
Aさんは、脳卒中後にベッド上での食事が続いていました。以前は仰向けに近い姿勢で食べており、むせ込みが頻繁に見られました。
言語聴覚士が介入した際、背もたれを本人にあった角度に調整し、クッションを入れて姿勢を安定させる工夫をしました。その結果、むせ込みが減り、食事中のむせ込みがが少なくなったとご家族も安心されました。
言語聴覚士が介入した際、背もたれを本人にあった角度に調整し、クッションを入れて姿勢を安定させる工夫をしました。その結果、むせ込みが減り、食事中のむせ込みがが少なくなったとご家族も安心されました。
2-2. 食事形態を調整する(食べやすい食事にする)
食事の形態を変えるだけで、誤嚥や窒息のリスクが減ることも多いです。
食べやすくするためのポイント
・とろみをつける → 水やお茶はとろみをつけて流れをゆるやかにする。
・軟らかい食事にする → 舌でつぶせるほどの柔らかさに調整する。
実例B:食事形態の調整で誤嚥が改善したケース
Bさんは、トロミなしで水分を取っていましたが、飲むたびにむせていました。そこで、言語聴覚士が、とろみの提案をし、適切な濃度のトロミをつけたところ、ムセが減りました。本人も、ストレスなく飲み込めるようになり、喜ばれていました。
2-3. 食事中の声かけと見守り
「一口ずつゆっくり」「よく噛んでね」 という声かけは、誤嚥を防ぐうえで非常に重要です。
声かけのポイント
・「急がなくて大丈夫」 → 早食いを防ぐ
・「しっかり噛んでからゴックンしてね」 → しっかり咀嚼を促す
・「飲み込んだか確認しようね」 → 次の一口を入れる前に確認
実例C:声かけで食事ペースを改善したケース
Cさんは、食事中に急いで食べる癖があり、よくむせていました。家族に「急がないで、しっかり嚙んでから飲み込もうね」と伝えたところ、食事のスピードが落ち、むせる回数が減りました。

2-4. 誤嚥のサインを見逃さない
誤嚥は、食事中だけでなく食後にも起こります。
食後の誤嚥サイン
・ゴロゴロした湿った声になる
・食後に咳や痰が増える
・翌朝、微熱が出る(誤嚥性肺炎の可能性)
これらの症状が続く場合は、すぐに医師や言語聴覚士に相談しましょう。
2-5. 口腔ケアを徹底する(誤嚥性肺炎を防ぐ)
「口の中が不潔だと、誤嚥したときに肺炎のリスクが上がる」ことが分かっています。
具体的なケア方法
・食後の歯磨き・うがいを習慣化する
・舌の汚れをふき取る(舌ブラシを使用)
・口が乾燥しやすい方は保湿ジェルを使用する
実例D:口腔ケアで誤嚥性肺炎を予防できたケース
Dさんは、以前に誤嚥性肺炎を繰り返していました。言語聴覚士がはじめて介入した際、食後の歯磨き習慣がなかったため、口の中に食べ物が残っている状態でした。食後の口腔ケアの重要性を説明し、口腔ケアの方法を指導。その後、肺炎の再発がなくなり、家族も安心して食事を提供できるようになりました。
2-6. 食事環境を整える
食事の際の環境が適切でないと、注意が散漫になったり、不安定な姿勢になったりして、誤嚥のリスクが高まります。
食べやすい環境をつくるためのポイント
・落ち着いた場所で食べる→ テレビやラジオの音を小さくする、周囲の話し声が大きすぎないようにする
・食卓を整理する→ 机におくものを減らし集中しやすくなるように環境を整える
・適切な照明を確保する→ 部屋が暗いと食べ物の認識がしづらくなり、食事に集中しにくくなる
実例E:環境調整で食事がスムーズになったケース
Eさんは、家族と一緒に食事をしていたが、周囲がにぎやかで食事に集中できず、誤嚥しやすい状態だった。そこで、家族と相談し、食事中はテレビを消し、落ち着いて食べられるよう配慮したところ、むせる回数が減り、食事の時間を楽しめるようになった。
2-7. 食べる前の準備運動
食事の前に軽い準備運動をすることで、嚥下機能を高め、安全に食べやすくなります。
食事前にできる簡単な嚥下準備運動
・唾液腺マッサージ(耳の下、顎の下を優しくマッサージして唾液の分泌を促す)
・発声練習(「パタカラ体操」)(口や舌の動きを活性化する)
・深呼吸と嚥下リズムを整える(ゆっくり深呼吸し、リラックスして食事を始める)
実例F:嚥下準備運動の導入で誤嚥が減少したケース
Fさんは、朝食時にむせることが多く、特にパンを食べるのが苦手だった。食事前に「パタカラ体操」と唾液腺マッサージを5分ほど行うようにしたところ、口の動きがスムーズになり、食事中のむせ込みが減った。
おわりに ~支援の輪を広げよう~
摂食嚥下障害のある方が「安全に食べる」ためには、ご本人だけでなく、家族や介護者、医療・介護職の協力が欠かせません。
「食べること」は、単なる栄養摂取ではなく、生活の質(QOL)に深く関わる大切な活動です。
言語聴覚士は、一人ひとりに合った支援を考え、「食べる喜び」を守るお手伝いをします。
周囲の人が正しい知識を持ち、少しの工夫をするだけで、「最後まで安全に食べる」ことは十分に可能です。
この記事を通じて、摂食嚥下障害の支援について考えるきっかけになれば幸いです。
「安全に食べる」を実現するために、一緒に支援の輪を広げていきましょう!
「食べること」は、単なる栄養摂取ではなく、生活の質(QOL)に深く関わる大切な活動です。
言語聴覚士は、一人ひとりに合った支援を考え、「食べる喜び」を守るお手伝いをします。
周囲の人が正しい知識を持ち、少しの工夫をするだけで、「最後まで安全に食べる」ことは十分に可能です。
この記事を通じて、摂食嚥下障害の支援について考えるきっかけになれば幸いです。
「安全に食べる」を実現するために、一緒に支援の輪を広げていきましょう!

関連リンク:
執筆:

後藤茉利奈(ごとうまりな)
言語聴覚士
経歴:
北里大学医療衛生学部言語聴覚療法学専攻を卒業後、回復期・慢性期病院、老人健康保健施設で言語聴覚士として勤務。
出産、育児をきっかけに小児分野へ転向。
児童発達支援での経験を経て、現在は訪問看護リハビリステーションさんぽに所属。
北里大学医療衛生学部言語聴覚療法学専攻を卒業後、回復期・慢性期病院、老人健康保健施設で言語聴覚士として勤務。
出産、育児をきっかけに小児分野へ転向。
児童発達支援での経験を経て、現在は訪問看護リハビリステーションさんぽに所属。