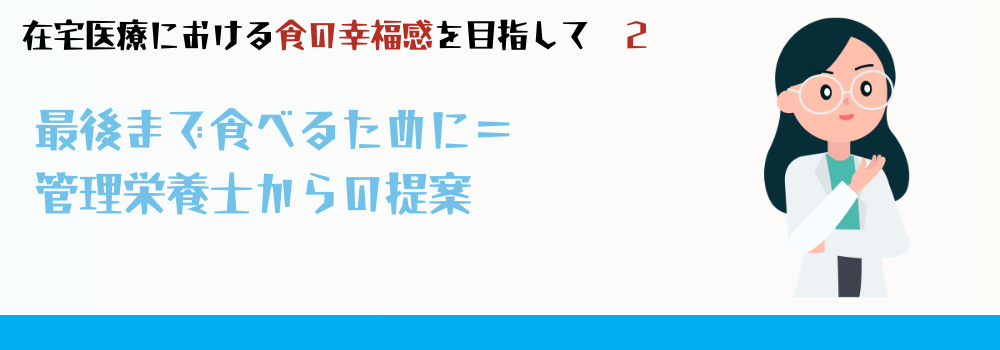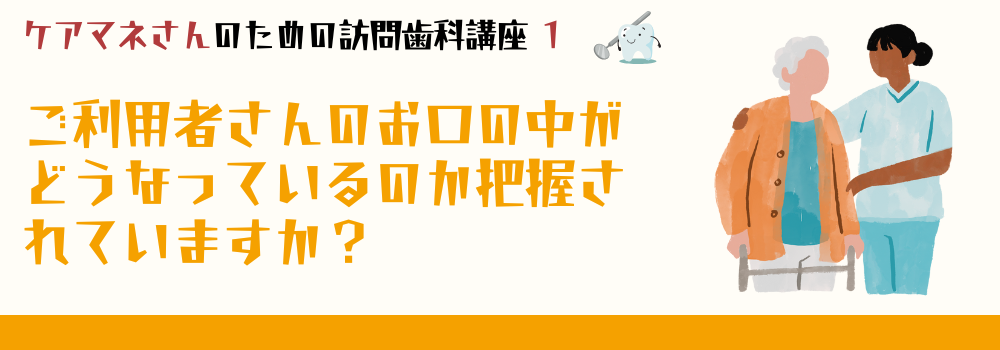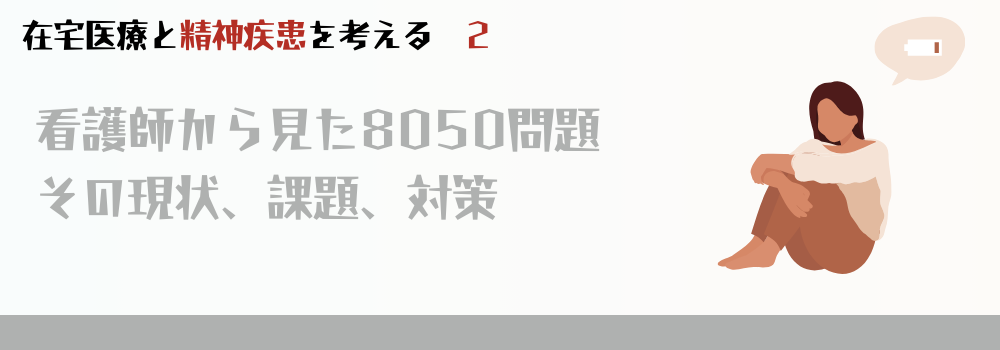最後まで食べるために=言語聴覚士が考える訪問リハビリの役割 最終更新日:2025/03/23
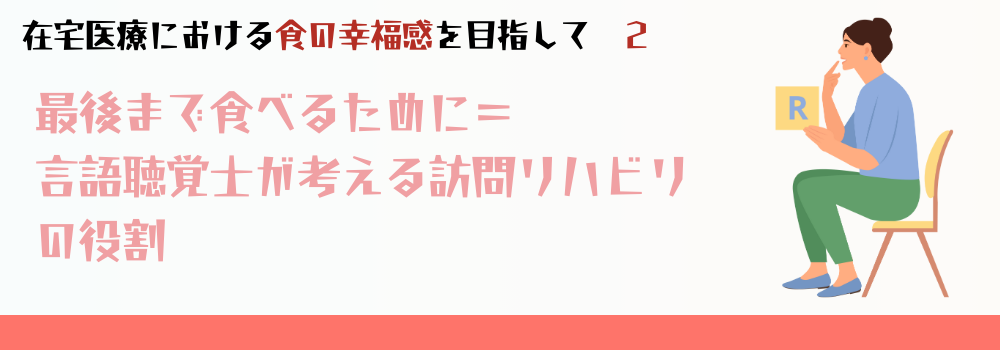
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
2つ目のテーマは「最後まで食べるために」と題して、言語聴覚士の立場として、國谷侑岐言語聴覚士により解説いただきました。
2つ目のテーマは「最後まで食べるために」と題して、言語聴覚士の立場として、國谷侑岐言語聴覚士により解説いただきました。
はじめに
高齢になっても「おいしく食べる」ことは、心と体の健康を維持するためにとても大切です。しかし、加齢や病気によって、食事がしづらくなる方も少なくありません。特に、嚥下(飲み込み)機能が低下すると、誤嚥性肺炎のリスクが高まり、「食べる」こと自体が危険になってしまうこともあります。
そこで、「最後まで食べる力」を支えるプロフェッショナルが、言語聴覚士(ST:Speech-Language-Hearing Therapist)です。本記事では、訪問言語聴覚士の役割や、実際に行なっている摂食・嚥下領域での支援についてご説明します。

1. 摂食・嚥下障害とは?
摂食・嚥下障害とは、「食べ物を口に運び、噛み、飲み込むまでの一連の動作」に困難が生じる状態を指します。原因はさまざまで、以下のようなものがあります。
・加齢による口腔器官の運動性低下
・脳卒中・パーキンソン病・認知症など、嚥下障害を併発する疾患
・歯の欠損や義歯の不適合
・全身の筋力低下による食べる動作の不安定さ
これらの問題を放置することが、栄養不足や誤嚥性肺炎、食事への意欲低下につながります。そのため、嚥下機能の低下がある方は人生の楽しみである「おいしく食べる」ために、言語聴覚士による早期のリハビリ介入がとても重要です。
2. 「最後までおいしく食べる」ために言語聴覚士ができること
2-1. 摂食・嚥下リハビリテーション:嚥下機能を維持・向上するためトレーニング
特に高齢者は嚥下機能が徐々に低下するため、安全に食事を続け誤嚥性肺炎を防ぐためのトレーニングが必要です。
・口腔機能訓練:口周りの筋力を鍛える
・舌・頬・喉の運動・ストレッチ:嚥下に関連した筋群、器官の運動の動きを改善し、食塊形成や嚥下をスムーズにする
・嚥下筋群のトレーニング:食べ物を飲み込む力を強くすることで誤嚥を予防する
・呼吸訓練:咳嗽力を強化し、誤嚥を予防する
・発声訓練:声帯の閉鎖を強化し、誤嚥を予防する
これらを定期的に継続することで、嚥下機能を維持し、「食事の楽しみ」を長く続けることができます。

2-2. 義歯・口腔状態の評価と歯科医師との連携
食べることには、歯の状態や口腔状態も密接に関わっています。
・歯牙欠損や義歯が合わないことで食べ物をうまく噛めず、飲み込みにくくなる
・噛む力が弱まると、食塊がまとまらず、誤嚥のリスクが上がる
・口腔状態が悪いと食事を苦痛に感じ、食欲が落ちる
言語聴覚士は、患者の口腔機能を評価し、歯科医師と連携しながら適切な義歯の調整や適切な口腔ケアを実施します。
2-3. 嚥下障害のある人への食形態の調整
介護、医療の現場では「食べにくいから刻み食」と思われがちですが、刻み食はかえって誤嚥を引き起こすこともあります。言語聴覚士は、以下のような工夫を提案します。
・適切な食事形態の選定(例:とろみをつける、ゼリー状にする)
・水分摂取の工夫(ゼリー飲料・とろみ付きの水など)
・一口の量や食べるスピードの調整
食事の形態を調整することで、安全に食べることができ、誤嚥のリスクを軽減できます。
2-4. 嚥下障害がある方への食事環境の調整
嚥下障害ある方の誤嚥のリスクを軽減し、安全に食事を行うため、以下のような食事環境の調整を行います。
1. 姿勢の安定化
・椅子や車椅子の高さを調整し、足底が床につくようにする
・クッションやタオルでの体感や首の安定を補助
2. 食具や道具の工夫
・スプーン・フォーク:持ちやすいグリップや深めのスプーンを使用。また一口量を考慮した食具の選定
・コップ:とろみがついた飲み物用にすい飲み等の飲み口が細いものを選ぶ
・食器の配置:無理なく手が届く位置に食器を配置し、食事に集中できるようにする。ワンプレートでの配膳
3. 食事環境の配備
・静かで落ち着いた環境を作り、注意散漫を防ぐ
・適切な照明で食事の視認性を高める。
・食事のタイミングや量を体調や疲労度に合わせて調整する。
4. 個別に適した姿勢や嚥下方法の検討
・うなずき嚥下:咽頭への食物残留の軽減し誤嚥を防ぐ
・頚部回旋嚥下:片側の喉頭の動きが低下している場合、嚥下しやすい方向に首を回し食塊の通貨を促す
・完全側臥位法:重度の嚥下障害がある場合、食塊が誤嚥しにくい方向に流れるよう調整
3. 実際のケース:訪問リハビリでの支援例
ケース1:誤嚥性肺炎を繰り返していた80代男性
この方は口腔内の衛生状態が悪く、嚥下機能も著しく低下していたため、誤嚥性肺炎を繰り返していました。訪問言語聴覚士リハビリでは歯科医師と連携し、まず義歯の調整を行い、噛み合わせを改善。次に、口腔内の清潔を保つために毎日の口腔ケアを徹底し、細菌の繁殖を防ぐようにしました。また、言語聴覚士による嚥下トレーニングを継続的に実施し、舌や喉の筋力を強化しながら、安全に飲み込む力を養いました。さらに、食事中の姿勢や食事形態の調整も並行して行い、誤嚥のリスクを最小限に抑える工夫をしました。その結果、誤嚥性肺炎の発症頻度が大幅に減少し、安心して食事ができるようになり、全体的な体調や生活の質も向上しました。
ケース2:認知症の進行により食事拒否が増えた90代女性
この方は認知症の進行により、食事中に集中できず途中でやめてしまうことが増え、栄養状態が低下していました。訪問言語聴覚士のリハビリでは、まず食事環境を見直し、食器の色をコントラストのはっきりしたものに変更し、視認性を向上させました。また、食事時間を一定にし、安心できるリズムを作るよう工夫。さらに、介助時の声かけを丁寧に行い、食べる意欲を引き出しました。食事のペースも本人の状態に合わせて調整し、焦らずゆっくり食べられる環境を整備。加えて、ゼリー食など食べやすい形態の食事を増やし、摂取量や栄養量を確保しました。その結果、食事の時間が安定し、栄養状態も改善。以前のように途中でやめてしまうことなく、穏やかに食事を楽しめるようになりました。

4. 「最後までおいしく食べる」ために、歯科医師・栄養士との連携が重要!
言語聴覚士だけでなく、歯科医師・管理栄養士と連携することで、より包括的な支援が可能になります。
・歯科医師:口腔ケア・義歯調整・歯の治療
・管理栄養士:適切な栄養摂取と食事形態の調整
・言語聴覚士:嚥下機能の評価・トレーニング
この多職種連携によって、高齢者が最後までおいしく食べるという人生の楽しみを持ち続けることができます。
まとめ
「最後までおいしく食べる」ことは、食物を口にして胃に送るだけではなく、人生の大きな楽しみであり、健康を維持する鍵でもあります。加齢や病気による嚥下障害の多くは多くの高齢者にとって切り離せない問題となっており、特に嚥下障害によって引き起こされる「誤嚥性肺炎」は生命を脅かす大きな問題です。
最後までおいしくたべるためには
・摂食・嚥下機能を維持するリハビリが重要
・義歯や口腔状態の管理が食べる力に影響する
・嚥下機能について詳細は評価を行う
・食形態の調整で「安全に食べる」工夫を行う
・歯科医・栄養士との連携が不可欠
訪問言語聴覚士のリハビリを活用することで、ご家族様や多職種と協力しながら、在宅で「最後まで食べる」喜びを支えていく一助になればいと思います。

関連リンク:
執筆:

國谷侑岐(くにたにゆうき)
言語聴覚士
経歴:
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
出雲医療看護専門学校言語聴覚士学科卒業
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 リハビリテーション室
訪問看護ステーション
株式会社サンショー 訪問看護リハビリステーションさんぽ(2025年4月開業:板橋区)
資格:
言語聴覚士
言語聴覚士