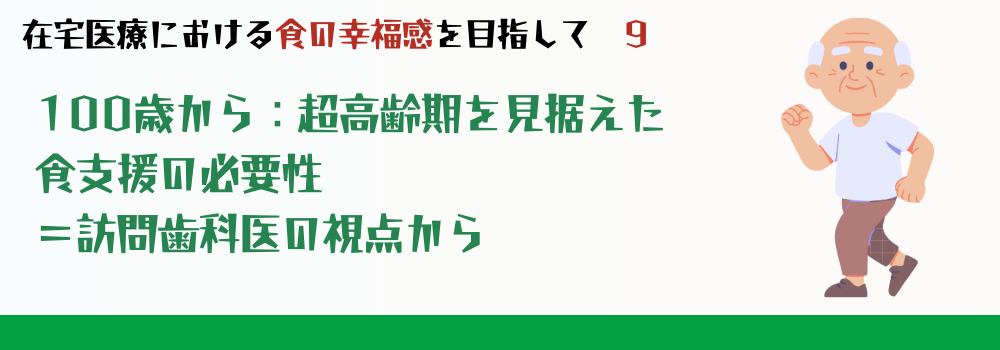排泄ケアの基本とケアマネジャーの役割 最終更新日:2025/04/01
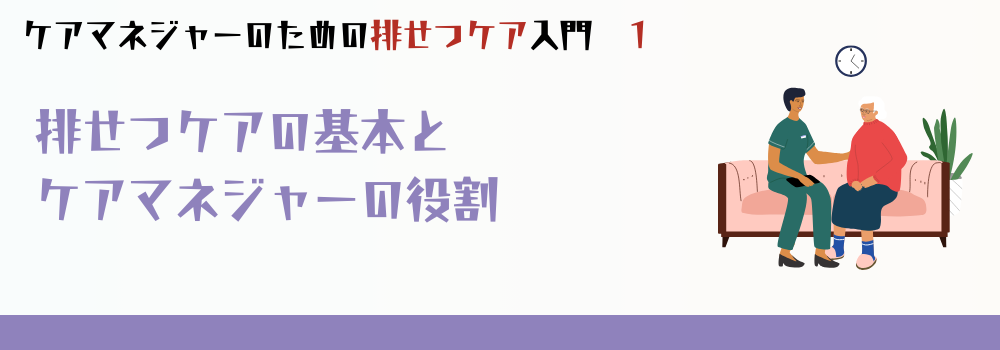
排泄を「ケアの現場で当たり前に起きている日常の営み」としてとらえ、生活全体を支える視点から、その質をどう保ち・高めていくかをケアマネジャーさんと一緒に考えていく新たな企画「ケアマネジャーのための排泄ケア入門 ~生活の質(QOL)を支えるために、いま排泄を見直す~」をスタートします。
皮膚・排泄ケア認定看護師である田村留美氏による10回連載の第1回目は「排泄ケアの基本とケアマネジャーの役割」と題して、排泄ケアの基本について解説しました。
皮膚・排泄ケア認定看護師である田村留美氏による10回連載の第1回目は「排泄ケアの基本とケアマネジャーの役割」と題して、排泄ケアの基本について解説しました。
はじめに:排泄は“生活を守る”中核ケア
排泄は、人が生きるうえで欠かせない営みであり、健康や尊厳、生活の質を大きく左右する重要なテーマです。加齢や疾患、認知機能の低下などにより、排尿・排便のコントロールが難しくなると、日常生活にはさまざまな支障が生じます。
ケアマネジャーが支援する排泄課題は、単なる「失禁」だけではありません。便秘・排尿困難・排泄動作の困難、さらには認知症に起因する排泄の混乱など、多様な“排泄障害”全般が関わってきます。
排泄に関する不安やトラブルは、本人の生活意欲や社会参加、自尊心に大きな影響を与えます。だからこそ、排泄ケアの質こそがQOL(生活の質)を左右する――その重要性を改めて考え直す必要があります。
この連載では復習も兼ねて、排泄ケアを「本人の尊厳と健康、社会参加を支える生活支援」として捉えなおすために、ケアマネジャーの皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

排泄の困りごとは、なぜ見逃されやすいのか
排泄は極めて個人的な営みであり、本人にとっても家族にとっても「恥ずかしさ」や「申し訳なさ」を伴うセンシティブなテーマです。そのため、介護現場でも排泄の困りごとは声に出されにくく、表面的には“問題なし”と見えてしまうことが少なくありません。
また、ケアマネジャーは、モニタリングやアセスメントという限られた機会で排泄の情報を収集しています。本人が「大丈夫」と言っていても、実際には便秘が続いていたり、おむつ内の皮膚トラブルが隠れていたりすることもあります。
このように排泄トラブルは、利用者自身の申告や記録だけでは見えづらく、だからこそ「正常な状態を知っていること」と「違和感に気づける感性」が求められます。「もしかして…」と立ち止まれる視点を持てるかどうかが、ケアの質を左右する第一歩です。

ケアマネの問いかけが現場を変える
ケアマネジャーは、毎日排泄介助をしているわけではありません。だからこそ、第三者の視点で「それって、本当に合ってる?」と問いかけることができます。
たとえば、「このおむつのサイズは合っていますか?」「最近、トイレに行きたがらなくなっていませんか?」「皮膚に赤みは出ていませんか?」といったひと言が、現場のスタッフの気づきを促し、医療や介護職との連携につながることがあります。
“気づく・尋ねる・つなげる”――この流れをつくるのは、まさにケアマネの役割です。小さな違和感に立ち止まり、専門職と共に考える姿勢が、利用者の快適な排泄環境を支える大きな力になります。
排泄ケアが生活に及ぼす多面的な影響
身体的影響
排泄の不安から水分や食事を控える方も多く、これにより脱水・便秘・低栄養・フレイル進行・転倒リスクの増加が引き起こされます。さらに、排尿の我慢による膀胱炎や尿閉、排便時のいきみによる循環器系への負担など、排泄障害は全身の健康に直結します。
また、適切な排泄管理がなされないまま失禁を繰り返すと、失禁関連皮膚炎(IAD)や褥瘡の発生リスクが高まり、感染症の原因にもなります。排泄の問題はQOLを低下させるだけでなく、命に関わる事態にも発展しかねません。
心理的・社会的影響
「漏れたらどうしよう」「においが気になる」といった不安や羞恥心から、外出を控えたり、デイサービスの利用をためらうケースは少なくありません。これが社会的孤立を招き、うつ状態を引き起こすこともあります。
認知症のある方では、排泄トラブルが混乱や不安、苛立ちを増幅し、BPSD(行動・心理症状)の悪化につながります。これが介護負担の増加という悪循環を生み出します。
家族・介護者への影響
排泄ケアは、介護者にとって身体的・心理的に大きな負担となるケアのひとつです。夜間の排泄対応が続けば、家族は慢性的な睡眠不足となり、疲弊してしまいます。また、排泄ケアの知識や情報が不十分なまま対応することで、肌トラブルや漏れ、不快感を繰り返す悪循環を招くこともあります。

事例紹介:実母の排泄ケアから学んだ「気づく力」
私の母は、90歳で膵臓がん末期・要介護5。身長145cm・体重30kg台と小柄で、病院退院後は寝たきり生活が続いていました。定期巡回サービスを1日3回利用しており、使用されていたのはMサイズのテープ式おむつに、朝と昼は6回分、夜間は12回分の吸収パッドという組み合わせでした。製品の吸収目安を合計すると1日あたり4,000mlを超えていましたが、実際に90歳・小柄な女性にそれほどの尿量があるとは考えにくく、実際の必要量との間に大きな乖離がありました。さらに、使用されていたおむつサイズも体格に合っておらず、吸収量の過剰さとサイズ不一致の両面から、明らかに違和感のあるケアが行われていたと感じました。
また体には尾骨部褥瘡を繰り返しした状況と思える複数の瘢痕があり、真菌性皮膚炎によるかゆみや赤みも見られ、本人は常に不快を訴えていたのです。
私が介護に関わるようになってから、おむつの当て方やサイズの見直し、予防的なスキンケアを徹底しました。その結果、皮膚状態は改善し、最期まで大きなトラブルなく穏やかに過ごすことができました。
この事例で痛感したのは、「当たり前」とされていたケアへの疑問を持つことの大切さです。本来なら、訪問看護師が気づいていてもよかったことかもしれません。しかし、それが難しいときこそ、ケアマネジャーが「何かおかしい」と感じて声を上げることが、チームケアの質を左右するのです。
ケアマネジャーに求められる“気づき”と“つなぐ力”
排泄の困りごとは、本人も家族も言い出しにくいものです。「最近、外出を嫌がるようになった」「デイサービスを断るようになった」「トイレの回数が増えている」「おむつが明らかに合っていない」など、行動や生活の小さな変化の背景には、排泄の不安や不快感が隠れていることが少なくありません。
ケアマネジャーには、こうした兆候を見逃さずにアセスメントへとつなげる“気づきの力”が求められます。そして、看護師や介護職、医師、薬剤師、リハビリ職など、多職種と連携しながら、排泄ケアの改善策をケアプランに落とし込む“つなぐ力”が重要です。

ケアプランに排泄ケアを位置づけるには
排泄支援は、ただトイレに誘導したり、おむつを交換するだけの支援ではありません。利用者の排泄機能をできる限り維持・向上させ、自立的な生活をサポートする視点が大切です。
たとえば、
・排泄リズムに合わせたトイレ誘導の工夫
・便秘や排尿困難に対する医療的視点の導入
・サイズ・吸収量・着用方法に配慮したおむつやパッドの選定
・スキンケアの導入による皮膚トラブルの予防
こうした観点を持ちながら、本人や家族の思いをくみ取り、排泄ケアを「生活を整える支援」として具体的なケアプランに反映させていくことが求められます。
まとめ:排泄ケアを“暮らしを守るケア”として捉える
排泄障害は、本人の身体・心・社会との関わりをすべて巻き込み、家族や地域全体にも影響を及ぼす「生活課題」です。そしてケアマネジャーは、その最前線に立つ存在です。
排泄ケアを「誰かがやってくれること」ではなく、「生活の質を支える中核ケア」として主体的に捉えること。小さな違和感を拾い、声をかけ、チームと共有していくこと。その一歩が、利用者と家族の暮らしを守る大きな力になります。
執筆:

田村留美(たむらるみ)
皮膚・排泄ケア認定看護師(WOC:創傷・ストーマ・失禁分野)
経歴:
看護師歴36年。
皮膚・排泄ケア認定看護師として16年の実績を持ち、病院および在宅医療の現場で、創傷・ストーマ・失禁ケアに携わる。
現在は、在宅療養者やその家族、地域の医療・介護職に向けた排泄ケアやスキンケアの支援、講演活動などを行っている。
看護師歴36年。
皮膚・排泄ケア認定看護師として16年の実績を持ち、病院および在宅医療の現場で、創傷・ストーマ・失禁ケアに携わる。
現在は、在宅療養者やその家族、地域の医療・介護職に向けた排泄ケアやスキンケアの支援、講演活動などを行っている。
資格:
看護師
皮膚・排泄ケア認定看護師(WOC:創傷・ストーマ・失禁分野)
特定看護師(創傷管理)
日本コンチネンス協会認定 コンチネンスリーダー
おむつフィッター3級(むつき庵)
リードフォーアクション認定 リーディングファシリテーター
看護師
皮膚・排泄ケア認定看護師(WOC:創傷・ストーマ・失禁分野)
特定看護師(創傷管理)
日本コンチネンス協会認定 コンチネンスリーダー
おむつフィッター3級(むつき庵)
リードフォーアクション認定 リーディングファシリテーター
連載予定:
第1回:排泄ケアの基本とケアマネジャーの役割
第2回:正常な排泄のメカニズム
第3回:褥瘡予防と排泄ケアの関係
第4回:失禁関連皮膚炎(IAD)の予防と対策
第5回:排泄ケア用品の選び方と正しい使い方(パッド・紙おむつ編)
第6回:高齢者の排泄トラブル:排尿編
第7回:高齢者の排泄トラブル:排便編
第8回:排泄ケアと薬剤の影響
第9回:最新の排泄ケア技術とその導入方法
第10回:事例に学ぶ排泄ケアの視点
第1回:排泄ケアの基本とケアマネジャーの役割
第2回:正常な排泄のメカニズム
第3回:褥瘡予防と排泄ケアの関係
第4回:失禁関連皮膚炎(IAD)の予防と対策
第5回:排泄ケア用品の選び方と正しい使い方(パッド・紙おむつ編)
第6回:高齢者の排泄トラブル:排尿編
第7回:高齢者の排泄トラブル:排便編
第8回:排泄ケアと薬剤の影響
第9回:最新の排泄ケア技術とその導入方法
第10回:事例に学ぶ排泄ケアの視点
排泄に関する不安やトラブルは、本人の生活意欲や社会参加、自尊心に大きく影響します。
排泄がうまくいかないことで、「その人らしさ」や生きがいを失ってしまうこともあります。
ケアマネジャーとして、日々多くの利用者さんやご家族と向き合うなかで、排泄ケアにまつわる課題や悩みに直面する場面も多いのではないでしょうか。
この連載では、排泄を「ケアの現場で当たり前に起きている日常の営み」としてとらえ、生活全体を支える視点から、その質をどう保ち・高めていくかを一緒に考えていきます。
スキルや知識だけでなく、「こんなふうに支えてみよう」「こう声をかけてみよう」と思えるヒントを、現場の視点からお届けします。 排泄ケアを通じて、利用者さんの「その人らしい暮らし」を支える一助になれば幸いです。
ケアマネジャーとして、日々多くの利用者さんやご家族と向き合うなかで、排泄ケアにまつわる課題や悩みに直面する場面も多いのではないでしょうか。
この連載では、排泄を「ケアの現場で当たり前に起きている日常の営み」としてとらえ、生活全体を支える視点から、その質をどう保ち・高めていくかを一緒に考えていきます。
スキルや知識だけでなく、「こんなふうに支えてみよう」「こう声をかけてみよう」と思えるヒントを、現場の視点からお届けします。 排泄ケアを通じて、利用者さんの「その人らしい暮らし」を支える一助になれば幸いです。