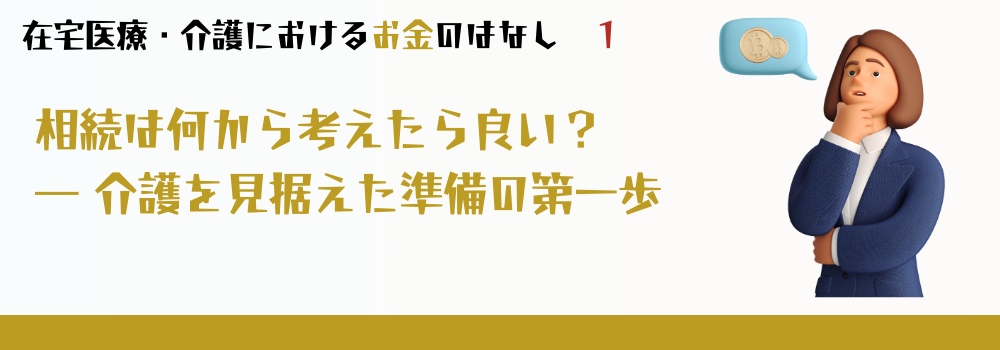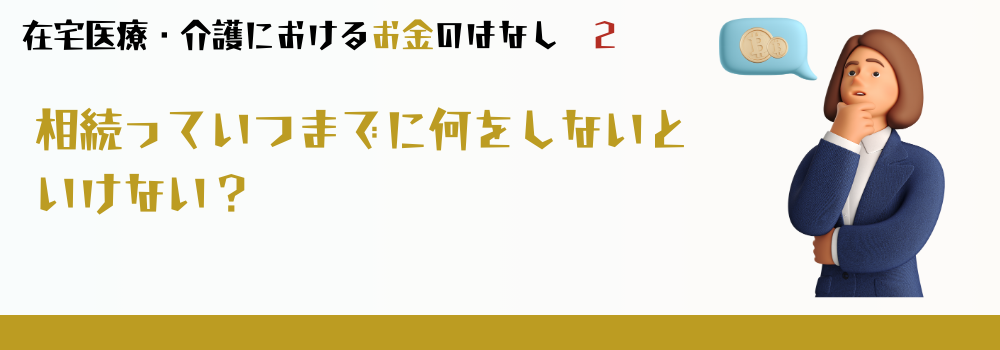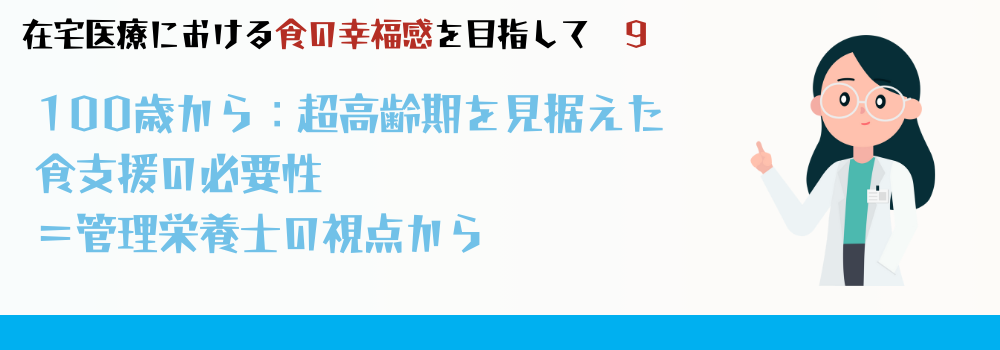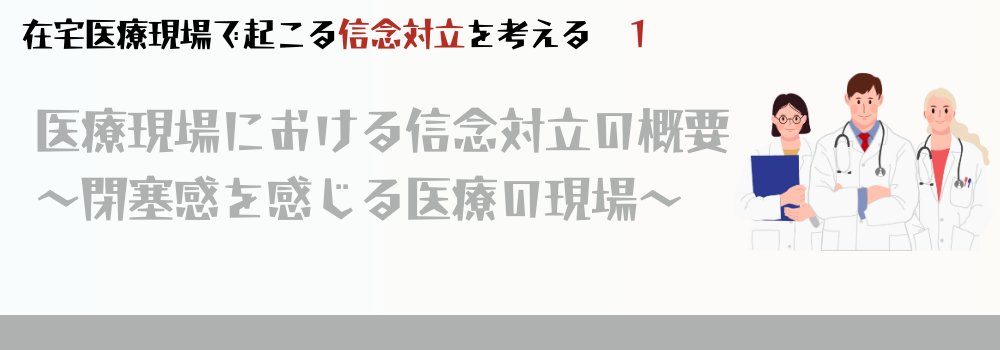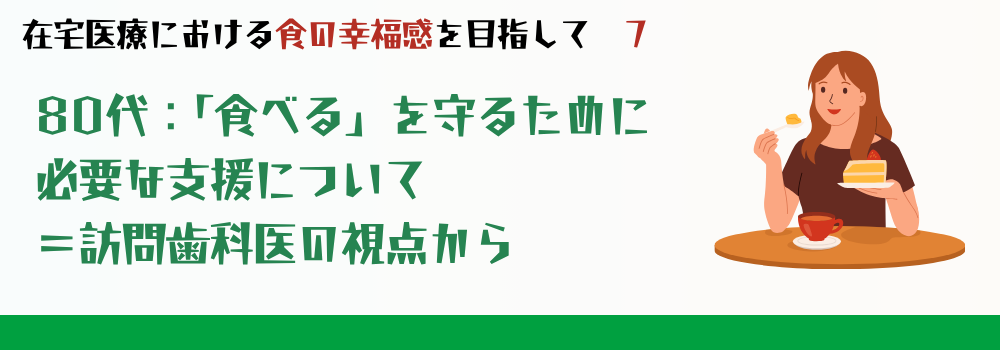贈与税の仕組みと効果的な生前贈与とは? 最終更新日:2025/04/25

「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けする新企画「在宅医療・介護におけるお金のはなし」。
全10回シリーズの第4回は、「贈与税の仕組みと効果的な生前贈与とは?」です。
「財産をできるだけ子どもや孫に残したい」「相続で揉めたくない」 そんな思いから“生前贈与”を考えはじめる方は多いかと思います。特に在宅医療や介護の現場では、ご家族の生活や支援体制を支えるために「今、必要な人に、今のうちに渡したい」という気持ちが高まりやすいものです。
ですが、そこで気になるのが「贈与税」の存在です。今回は、生前贈与の基本的な仕組みや贈与税のルールを整理しつつ、効果的な使い方についてわかりやすく解説していきます。
全10回シリーズの第4回は、「贈与税の仕組みと効果的な生前贈与とは?」です。
「財産をできるだけ子どもや孫に残したい」「相続で揉めたくない」 そんな思いから“生前贈与”を考えはじめる方は多いかと思います。特に在宅医療や介護の現場では、ご家族の生活や支援体制を支えるために「今、必要な人に、今のうちに渡したい」という気持ちが高まりやすいものです。
ですが、そこで気になるのが「贈与税」の存在です。今回は、生前贈与の基本的な仕組みや贈与税のルールを整理しつつ、効果的な使い方についてわかりやすく解説していきます。
1. そもそも贈与税ってどんな税金?
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。対象になるのは現金や預金、不動産、株式など「金銭的な価値があるもの」すべて。相手が親族か他人かに関係なく、もらった人(受贈者)が申告・納税するルールになっています。
2.贈与税の基本ルール
贈与税は「1月1日から12月31日までの1年間」に受け取った財産の合計額に対して課税されます。基礎控除として年間110万円までは非課税ですが、それを超えた分には税率がかかります。
税率は累進課税で、例えば親から子へ300万円を贈与した場合、110万円を差し引いた190万円に対して税率がかかり、納税額は約13万円程度となります(税率10%、控除額10万円)。

3.生前贈与のメリットと注意点
◎メリット①:相続税の節税につながる
相続税は「亡くなった時点の財産」に対して課税されるため、生前に贈与することで相続財産を減らす=節税効果が期待できます。とくに相続税の基礎控除を超えるような財産がある方にとっては、計画的な生前贈与が相続税額を大きく減らす手段になります。
例えば、子どもや孫に毎年110万円ずつ贈与し続けることで、10年間で1,100万円を非課税で移転できます。このように、長期的かつ計画的に取り組むことで、税負担を抑えつつ円満な財産移転が実現できます。
ただし「亡くなる前7年以内の贈与分」は相続財産に戻される(加算される)ので、早めに取り組むのがポイントです。2024年から、3年以内加算が「7年以内」に延びているので、注意が必要です。
◎メリット②:必要な人に、必要なタイミングで渡せる
たとえば、お子さんやお孫さんが住宅を購入するとき、教育資金が必要なときなど、“今渡したい”タイミングでサポートできるのも生前贈与の大きな魅力です。
また、介護を支えてくれているお子さんやご家族に対して「感謝の気持ち」として財産を分けておくことで、相続時の不公平感やトラブルを防ぐことにもつながります。家族関係が良好なうちに、意思表示をはっきりさせられるのも、生前贈与ならではの利点です。
◎メリット③:家族間の信頼を築きやすい
贈与を通じて財産のあり方を共有することは、家族間での対話の機会にもつながります。事前に話し合いを重ねておくことで、相続時の不信感や疑念を未然に防ぐことができる点も、生前贈与の大きな効果です。

△注意点①:贈与の証拠を残そう
口座振込の記録や贈与契約書など、贈与の「意思と実態」がわかるようにしておくと安心です。特に現金で渡す場合や、ご家族間でのやり取りでは「もらった/あげた」が曖昧になりやすく、後から「これは貸しただけ」と争いになるケースもあります。
トラブルや税務署の調査を防ぐためにも、契約書の作成や、贈与を受けた人が自由に使える状態にあることを確認しましょう。
△注意点②:“つもり贈与”に注意
ときどき、「子どもの口座にお金を移したから、もう贈与したことになる」と誤解している方がいます。しかしその口座を親が管理していたり、子どもが自由に使えない状態であれば、“実質的には贈与されていない”と判断される可能性があります。
贈与したら、そのお金は完全に相手のもの。通帳・印鑑の管理も渡し、「あげたことがわかる」状態にしておくことが大切です。
△注意点③:将来の資金計画に影響することも
贈与は一度実行すると原則として取り消せません。「今は余裕があるから」と大きな金額を渡してしまった結果、将来の介護費用や医療費に困るケースもあります。
そのため、生前贈与はあくまで“自分の生活を守ったうえで”行うことが重要です。贈与の前に、老後資金や医療・介護費用の見通しを立てることが大前提となります。
4.効果的な生前贈与の方法
贈与税には、さまざまな“非課税枠”があります。これらを活用することで、より効率的に財産を移すことが可能です。
① 毎年の110万円贈与をコツコツ続ける(暦年贈与)
もっとも一般的で手軽な方法が、年間110万円以内での贈与です。これを「暦年贈与」といいます。たとえば子ども3人に毎年110万円ずつ贈与すれば、10年間で3,300万円を非課税で移すことができます。
ただし、形式的に「毎年110万円あげるね」と決まっているような場合は、“定期贈与”とみなされて全額に贈与税がかかることも。毎年贈与契約書を作成したり、振込時期をずらすなどして「都度の贈与」であることを明確にしておくとよいでしょう。
また、繰り返しになりますが、7年以内の贈与は相続財産に加算されるので、長期的な計画がカギとなります。
なお、相続財産が多く高い相続税率が見込まれる場合には、あえて110万円を超える贈与を行い、贈与税を支払う戦略も有効です。たとえば相続税率が30%なのに対し、贈与税率が20%で済むのであれば、10%の節税になります。実際の税率や適用控除を確認しつつ、将来の相続時にかかる負担と今支払う贈与税を比較することが大切です。
② 教育資金の一括贈与(非課税枠あり)
祖父母から孫への教育資金は、最大1,500万円まで非課税になる特例制度があります。対象となるのは、学費や塾代、留学費用、習い事の費用などです。
この制度は「信託口座」の活用が前提で、金融機関を通じて贈与を行う必要があります。贈与を受けたお金の使い道には制限があり、使った分を領収書などで証明しなければなりません。
注意点として、孫が30歳を超えたときに使い残しがあると、残額に対して贈与税がかかることがあります。制度の適用期限や手続きの詳細も、事前にしっかり確認しましょう。

③ 住宅取得等資金の贈与
子どもがマイホームを購入する際、一定額まで贈与税がかからない特例があります。「令和6年度 税制改正大綱」によって、2023年末で終了予定だった子や孫への住宅購入のための資金の非課税贈与制度が、2026年末まで延長されることになりました。適用される上限額は、住宅の種類(省エネ住宅など)などによって異なりますが、最大で1,000万円の非課税枠が使える可能性があります。
この制度も、贈与を受けた人が住宅を取得するという“目的”に沿った使い方でなければ非課税とはなりません。住宅購入のタイミングと贈与のタイミングを合わせ、事前に要件を確認することが重要です。
また、贈与後は速やかに住宅取得に使用されることが条件となるため、実行のタイミングには十分な計画が必要です。
④相続時精算課税制度の活用
60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して、2,500万円まで非課税で一括贈与できる制度です。
贈与時には贈与税がかからず、相続時にその贈与分を相続財産に加えて相続税を計算する仕組みなので、住宅購入や事業資金など、早期にまとまった財産を渡したいときに有効です。相続時に持ち戻して計算しても、相続税が掛からないような場合は特に効果を発揮します。
ただし、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与はすべてこの制度が適用され、暦年贈与(年110万円まで非課税)には戻せなくなる点には注意が必要です。
5.まとめ:計画的な贈与で“もめない相続”へ
贈与は「思いやり」の手段でもあり、相続をスムーズにするための“生前の準備”でもあります。ただし税金のルールを知らずにやってしまうと、かえって損をしたり、意図しないトラブルにつながることも。
在宅医療や介護のタイミングで、「これからのお金」「将来への橋渡し」を考える方も多いはずです。
大切なのは、贈与のメリットとリスクを理解し、家族の状況に合わせて柔軟に考えること。 必要に応じて、税理士やファイナンシャルプランナーなど専門家に相談しながら、後悔のない贈与を進めていきましょう。
次回のテーマは、「相続財産の分け方」についてです。相続財産の分け方や決め方のルールについても早めに知っておきましょう。

関連リンク:
執筆:

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。