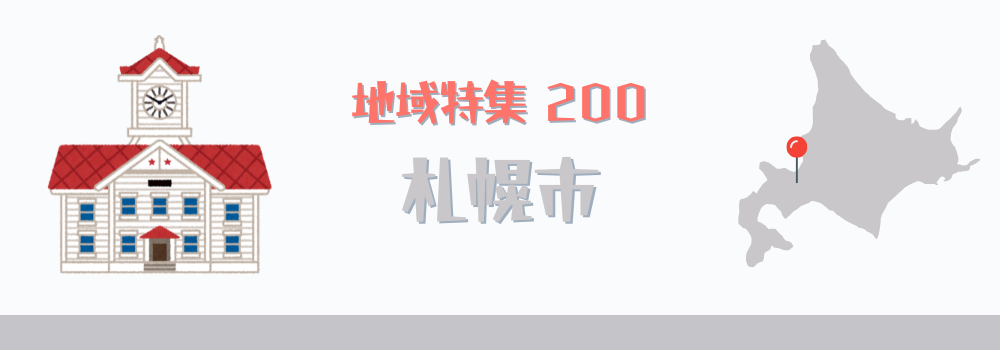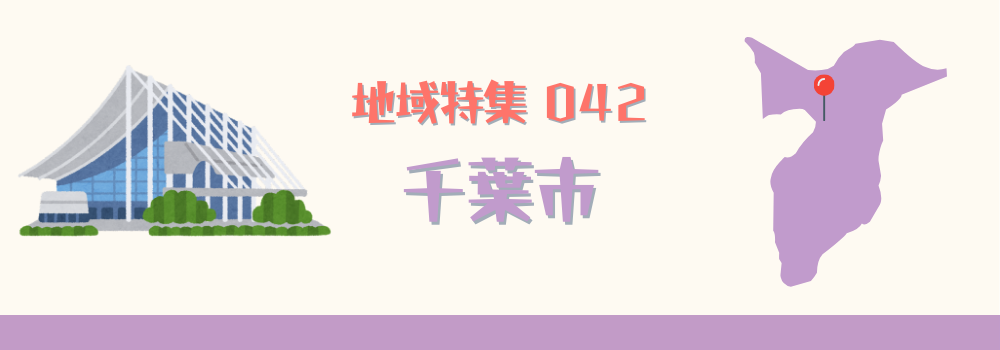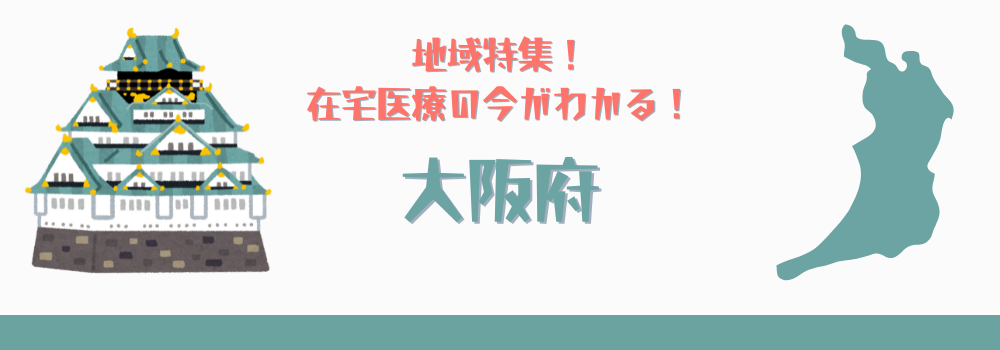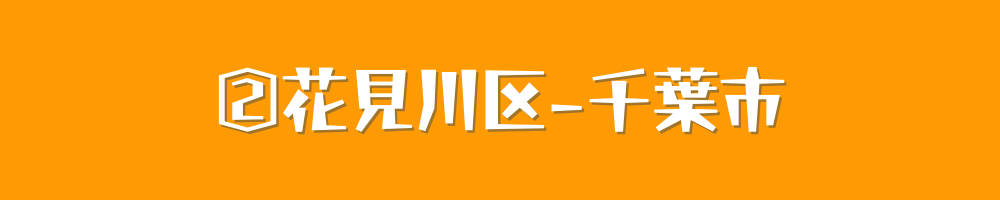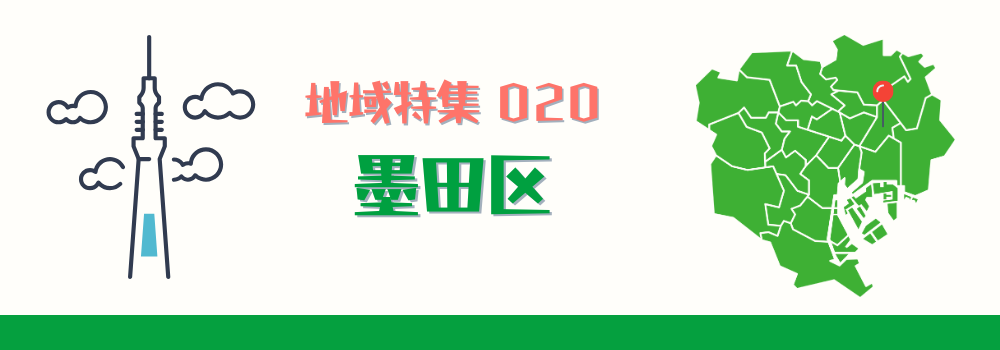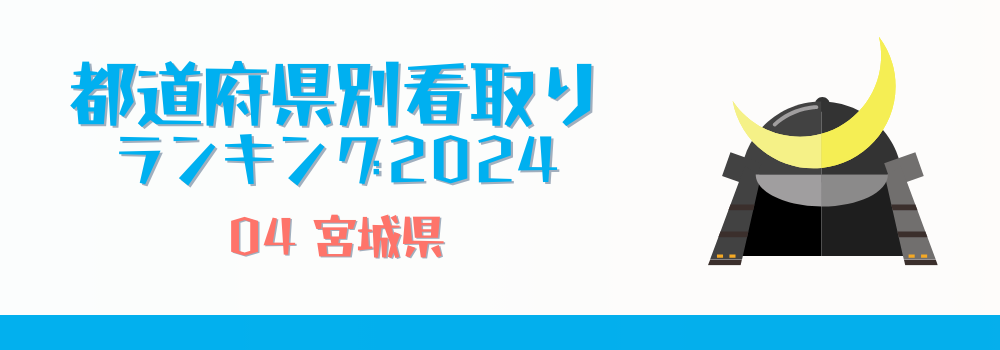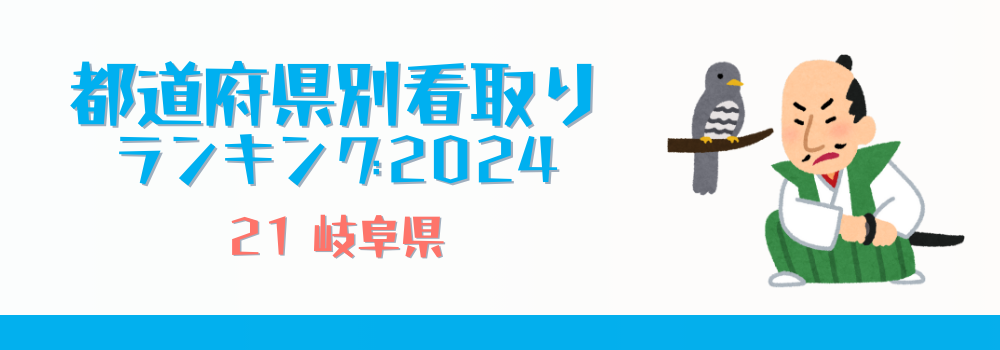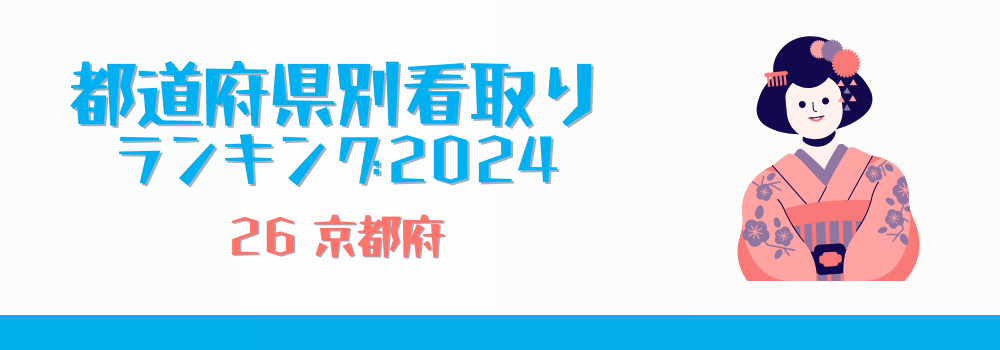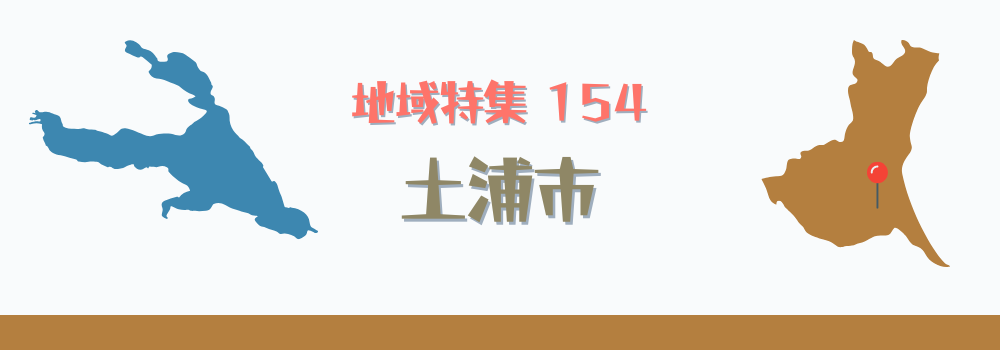訪問診療と緩和ケアの最前線|植松理事長が描く地域包括ケアの未来 最終更新日:2025/09/27
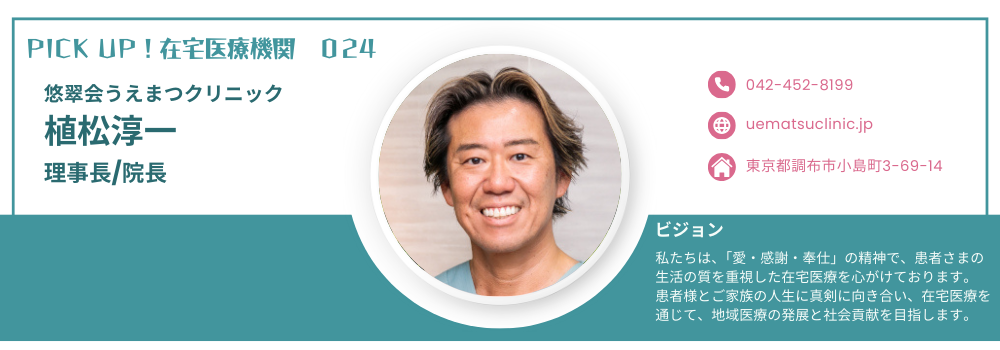
調布市・府中市・三鷹市を拠点に訪問診療を展開する「悠翠会 うえまつクリニック」。消化器内科から在宅医療へ転身した植松理事長は、がん終末期医療や在宅緩和ケアに力を注ぎ、患者と家族の「自宅で過ごしたい」という願いに応え続けています。地域と連携し、24時間365日対応の体制を整えた在宅医療の取り組みと理念を語ります。
医療の世界だけにとどまらない自分の道を探す
— 医師を志したきっかけを教えてください。
子どもの頃から「医者になる」という思いが自然と心にありました。周囲に医師がいたわけでも、強く勧められたわけでもなかったのですが、不思議と他の職業を考えたことはありませんでした。
また、医師としての道を目指していく中で、将来的には独立し、起業したいという思いも抱いていました。医師という職業への憧れと、自分の力で何かを成し遂げたいという気持ちが、自然と重なっていったように思います。

— 研修後に消化器内科に進まれた理由を教えてください。
研修医時代を過ごした東京医科大学病院の消化器内科の医療の質の高さや、世界的にも有名な先生方の存在感に強く惹かれたことが大きかったです。また、内視鏡という手に職をつけることに魅力を感じ、さまざまな科の中で迷いながらも、最終的に消化器内科に進んだことは、今の自分にとって正しい選択だったと感じています。
消化器内科から在宅医療へ、未来を見据えた新たな選択
— 卒業後、どのようなキャリアを歩まれたのですか。
2008年に聖マリアンナ医科大学を卒業後、東京医科大学病院にて初期臨床研修を行い、2010年に消化器内科へ入局しました。消化器疾患全般の診療に従事しつつ内視鏡検査と治療の技術を中心にスキルを高めるべく、国際医療福祉大学三田病院でも経験を積みました。内視鏡技術の習得や専門医の免許を取得し、そろそろ将来の方向性を考えていた頃、先輩から「在宅医療をやってみないか」と声をかけていただきました。
初めは不安もありましたが、新たなことへのチャレンジ精神と人と関わることが好きだったこともあり、まずは挑戦してみようと思い、2013年の1年間は大学病院に籍を置きながら、非常勤医師として在宅医療に関わるようになりました。
— 在宅医療に進まれてみて、いかがでしたか。
在宅医療は患者さまの生活の中に一歩入り、医療を行います。できる医療は限られておりましたが、患者さまとの何気ない日々の会話や、2週間おきに表情を拝見することで、体調の変化や健康状態が、特別な検査や診察をしなくてもわかるようになり、「生活の上に成り立つ医療」というものに非常に興味を持つようになり、自分自身の医療への向き合い方が変わるようになりました。また、患者さまの生活に関わることで、病院以上に“人と人との関係性”が深まる場であることも実感しました。
これからの超高齢社会において、在宅医療は間違いなく必要とされる分野であり、より患者さまに寄り添った医療が実現できると実感し、「今の自分にとって、本当に必要な医療は在宅医療だ!」と強く思うようになり、気づけばその魅力に引き込まれていきました。そうした思いから、消化器内科医から在宅医へ転身すべく、2014年に在宅医療を専門とする医療法人に入職することを決めました。
在宅医療に深く関わる中で見つけたやりがい
— 終末期医療と在宅緩和ケアに注力されるようになったとお聞きしました。詳しく教えてください。
在宅医療の患者さまは通院困難な方を対象としており、疾患や年齢、生活背景も多岐に渡ります。多くは介護保険制度を利用されている高齢者の方が多く、認知症や廃用、サルコペニア、脳血管障害により通院が難しくなった患者さまや、腰椎圧迫骨折や関節リウマチなどの整形疾患の患者さまもたくさんいらっしゃいます。
また、がんの終末期、慢性疾患や老衰による終末期医療をご自宅で過ごされる方も多く、住み慣れたご自宅で大切な家族と一緒に最後を過ごしたいと願う患者さまの思いに寄り添う医療を実現することができます。
私はこの終末期医療と在宅緩和ケアについて非常にやりがいを感じるようになり、自宅で最後まで過ごすことができた患者さまと、そのご家族の人生のドラマに少しでも関わらせていただけることに誇りと感動を覚えるようになりました。
地域全体を在宅医療で支え、在宅医療を通じた社会貢献を実現する
— 開院当初はどのような日々でしたか。
2019年に「うえまつ在宅クリニック」を狛江市に開院しました。ありがたいことに、開院当初から患者数は増え続け、2020年の新型コロナウィルス(COVID-19)の世界的流行は当院にとって逆に追い風となりました。
当院はCOVID-19感染者の自宅療養支援において、地域自治体や医師会と共に協力し、自宅療養者への往診対応も積極的に行いました。その結果、日本の医療情勢としては、新型コロナウィルスの影響で外来受診者数や病院受診者数の減少が問題となりましたが、地域における在宅医療の認知が広まり、訪問診療患者数の増加に繋がりました。
もちろん、通常診療である通院困難な患者さまの訪問診療も行いつつ、地域医療の発展を目指して在宅医療の応報活動や普及活動も行なっていたため、気づけば300人を超える患者さまを一人で診る日々となっておりました。連日深夜のお看取りや日々のオンコールもすべて自分自身で対応し、約2年間はほぼ休みなく走り続けました。
しかし、その後に体調を崩したことをきっかけに「自分が倒れたら誰が患者さまと、このクリニックを支えるのか」と考えるようになり、常勤医師と非常勤医師をお迎えし、「悠翠会うえまつクリニック」を調布に開院すると共に、日々の業務の分担と24時間365日対応のオンコール体制を強化し、随時緊急対応に備えるようにしました。

— 何がそこまで先生を突き動かしたのでしょうか。
「うえまつ在宅クリニック」を開院したのは、緩和ケアを専門とした在宅医療を提供し、自宅で最期を迎えたいという患者さまの思いに応えられる地域をつくり、医療と介護のインフラを充実させたいという思いがあったからです。
当時の調布市や狛江市では、がん患者さまが自宅で看取られるための医療体制が十分に整っておらず、たとえ本人や家族が自宅を希望しても、最終的には自宅療養継続が困難となり病院に戻らざるを得ない実情がありました。
実際に、厚生労働省の調査結果では、7割以上の国民が自宅で最後を迎えたいと希望している一方で、実際に「がん」患者の自宅死亡率は1割に満たないのが現状であると言われております。
私は、この在宅緩和ケアの普及は非常に重要かつ必要なことであり、自分の提供できる医療により、望まれる患者さまが、ご自宅で最後まで過ごすことができる、そんな地域に変えていくことこそが、自分の医師としての使命であり、社会への貢献であると感じるようになりました。
— 実際に先生が在宅医療をする上で大切にされていることを教えてください。
私が実践している在宅医療は、病気そのものだけではなく、生活の質(QOL)や人生の質に焦点をあてた医療を提供することを信念とし、同じ病気であっても異なる生活背景やご家族の生活状況に合わせた、一人ひとりの生活ともに歩む医療を大切にしております。
特に在宅緩和ケアや終末期医療において、“正解”というものは存在しません。
人の人生は様々であり、最期も一人ひとり異なります。終末期医療を提供する中で、自然な最後を迎えられる方もいれば、最後まで点滴や経管栄養などの医療機器を使用して最後を迎えられる方もおります。時に、私自身の中でも「この医療は本当に正しいのか」と、疑問を抱くことや、さまざまな感情が交差しますが、残された時間と1分1秒向き合っている目の前の患者さまとご家族の思いに寄り添い、「もし自分や自分の家族だったら」と常に置き換えながら、全力で支援をさせていただいております。
患者さま自身やご家族の思い、人生観、死生観はそれぞれ異なり、そこにはそれぞれのドラマがあります。
私自身にも信念や価値観がある中で、時に迷いや葛藤を感じることもありますが、 それでも患者さまとご家族の思いを尊重し、必要に応じて軌道修正をしながら、 その人らしい終着点に辿り着かせてあげることが、私の医師としての使命であると信じております。

地域に根ざし、多様な社会の変化に応えるクリニックへ
— クリニックの特徴を教えてください。
うえまつ在宅クリニックには狛江院と調布院があります。
対象地域は調布院は調布市・府中市・三鷹市、狛江院は狛江市・世田谷区・稲城市の一部が中心です。現在は常勤6名を含む複数の医師が在籍し、非常勤医師や精神科往診や皮膚科往診を含む、医師が毎日それぞれのスケジュールを担当して訪問診療を行っております。
対象地域は調布院は調布市・府中市・三鷹市、狛江院は狛江市・世田谷区・稲城市の一部が中心です。現在は常勤6名を含む複数の医師が在籍し、非常勤医師や精神科往診や皮膚科往診を含む、医師が毎日それぞれのスケジュールを担当して訪問診療を行っております。
特徴としては、やはりがん末期の患者さま、終末期医療を必要とする重症患者さまや医療依存度の高い患者さまの割合がこの地域において、他院に比べ多いといえます。
また最近の変化としては、神経内科専門医の入職と、訪問リハビリ事業の立ち上げに伴い、指定難病や神経難病の患者さまのご紹介の増加。
若くして精神疾患を抱え通院できない患者さま、重度身体障害の患者さまや、若年がんや小児の患者さまのご相談も増えており、在宅医療の社会的ニーズの多様性を強く感じております。

— クリニックとして大切にしていること、指標や目標などはありますか。
私たち、悠翠会の根幹にある理念は「愛・感謝・奉仕」です。
全ての患者さま、そのご家族に対し愛情を持って接し、家族の愛や親子の愛など、愛に満ちた生活の支援を大切にしております。
全ての患者さま、そのご家族に対し愛情を持って接し、家族の愛や親子の愛など、愛に満ちた生活の支援を大切にしております。
また、日々のいかなることにも感謝の気持ちを忘れず、どんなに困難な症例であっても当院で在宅医療を任せていただけることに感謝して向き合います。
私たちは見返りを求めず、困っている人たちがいるからこそ、自分たちが生かされて、誰かのため、地域のために行動をする。
それこそが、私たちにできる在宅医療を通した社会貢献であると考えております。
ゆえに、私たちは、病気そのものだけではなく、生活の質(QOL)や人生の質に焦点をあてた医療を提供することを信念とし、同じ病気であっても異なる生活背景やご家族の生活状況に合わせた、一人ひとりの生活ともに歩む医療を目標としております。
— 在宅医療のニーズの拡大とは。
在宅医療の社会的ニーズは確実に拡大していると思います。
当院の傾向としては、従来の通院困難な高齢の患者さまをはじめ、がんの終末期医療や医療依存度の高い難病の患者さまのご紹介が非常に増えております。在宅医療で実施できる医療の質や幅が拡大していることも大きな理由であると思いますが、何よりも地域全体が在宅医療を認知し、インフラが整備され、在宅医療を活性化させようとする熱意ある医療介護従事者が増加しているおかげであると考えます。
当院の傾向としては、従来の通院困難な高齢の患者さまをはじめ、がんの終末期医療や医療依存度の高い難病の患者さまのご紹介が非常に増えております。在宅医療で実施できる医療の質や幅が拡大していることも大きな理由であると思いますが、何よりも地域全体が在宅医療を認知し、インフラが整備され、在宅医療を活性化させようとする熱意ある医療介護従事者が増加しているおかげであると考えます。
当院では調布市、狛江市の消防署の救急隊や救急医療機関と連携し、不必要な救急搬送や救急医療の減少を目指しております。実際に、狛江市と調布市において、この数年で大幅な救急搬送数の減少を達成しております。
また、最近では身寄りがいない方、経済的理由や引きこもりなどで地域社会や医療から社会的孤立をした方々に対し、市や行政からの依頼を受け、訪問診療による医療的介入をきっかけに社会とのつながりを進める医療と社会福祉の連携ケースも増えております。

最期まで“自分らしく”を支えるために、地域とつながる在宅医療のかたち
— 今後の在宅医療の課題についてどのように感じていますか。
在宅医療のニーズが拡大していく中で、今後の課題としては、「在宅医療に取り組む医療機関のハードルを下げること」であると考えております。
私たちの地域においても、これまで外来で診てきた先生方が、かかりつけの患者さまの最期にまで関わることが難しく、通院が困難になった患者さまは、我々のような在宅医療専門の医療機関が引き継いで診療に携わる形が増えてきております。
そこには、在宅医療のハードルである、24時間オンコール体制や深夜の緊急往診など通常の外来診察を行なっている先生方には物理的に難しい壁が存在します。
しかし、出来ることならば、長く診療してきた先生が最期まで患者さまに寄り添える体制の構築が理想的だと考えており、当院では東京都在宅医療推進強化事業の一環として、調布市医師会と連携し、夜間・緊急時のオンコール連携基盤として外来診療をされながら在宅医療に従事してくださる先生方のご負担を軽減できるような取り組みをさせていただいております。
もちろん、がんの緩和ケアや終末期医療など医療的に対応が難しいケースは、私たち在宅医療専門機関がしっかりと引き継ぎをさせていただき、ご支援させていただくことで、患者さまやご家族、そして医療者にとっても、より良い地域医療の形が実現できると信じております。
— 先生の目指す在宅医療、そして将来の展望を教えてください。
2025年8月にうえまつ在宅クリニックは開院から7年目を迎えました。
たくさんのスタッフと、地域で支えてくださる医療介護事業所の皆さまの愛と情熱に支えられ、いまがあると思い、心から感謝しております。
たくさんのスタッフと、地域で支えてくださる医療介護事業所の皆さまの愛と情熱に支えられ、いまがあると思い、心から感謝しております。
僕たちの医療は、患者さま一人ひとりに対する深い敬意と感謝の気持ちから始まります。そして、ご家族の心にも寄り添いながら、その方にとって最良の人生を共に考え、医療を提供していきたいと考えております。
つまり、悠翠会の根幹の理念である、「愛・感謝・奉仕の精神」です。
自分のためではなく、誰かのために生きる。
それは、世のため、人のため、社会のためになり、そして必ず自分のためになるはずです。
自分のためではなく、誰かのために生きる。
それは、世のため、人のため、社会のためになり、そして必ず自分のためになるはずです。
いつ、いかなる時も僕の信念は変わらず、
「皆が幸せであるように!」
そんな組織と環境、そして社会を作っていくことであります。
「皆が幸せであるように!」
そんな組織と環境、そして社会を作っていくことであります。
これからもこの信念と誇りをもって在宅医療に取り組み、社会へ貢献する組織に皆んなと共に成長できればと思っております。

— 最後に地域のみなさまへメッセージをお願いします。
私たちは、どんな状況の方でも地域で安心して暮らせるよう、医療の“最後の砦”として責任をもって在宅医療で皆さまを支えていきます。
「本当に自宅で過ごせるのだろうか」「在宅医療って自分たちにも必要なのかな」と思ったときにはぜひ相談してください。
人生最期の時間を、「どこで・誰と・どうやって過ごしたいか」。
あなたの想いに寄り添い、あなたらしい人生を叶える在宅医療でお手伝いをさせていただきます。
「本当に自宅で過ごせるのだろうか」「在宅医療って自分たちにも必要なのかな」と思ったときにはぜひ相談してください。
人生最期の時間を、「どこで・誰と・どうやって過ごしたいか」。
あなたの想いに寄り添い、あなたらしい人生を叶える在宅医療でお手伝いをさせていただきます。
悠翠会うえまつクリニック

診療科
・内科
・消化器内科
・脳神経内科
・循環器内科
・リウマチ膠原病内科
・緩和ケア内科
・皮膚科
※ 皮膚科往診のみも受け付けております
・形成外科
・外科
・呼吸器内科
・心臓血管外科
・腎臓内科
・腫瘍内科
・高齢診療科
・精神科
・リハビリテーション科
・消化器内科
・脳神経内科
・循環器内科
・リウマチ膠原病内科
・緩和ケア内科
・皮膚科
※ 皮膚科往診のみも受け付けております
・形成外科
・外科
・呼吸器内科
・心臓血管外科
・腎臓内科
・腫瘍内科
・高齢診療科
・精神科
・リハビリテーション科
診療時間
平日:9:00~12:00、13:00~18:00
※ 外来診療は完全予約制となります。
※ 電話によるご相談も上記時間に受け付けております。
※ 土曜日、日曜日、祝日は緊急往診のみとなります。
※ 外来診療は完全予約制となります。
※ 電話によるご相談も上記時間に受け付けております。
※ 土曜日、日曜日、祝日は緊急往診のみとなります。
対応エリア
調布市・府中市・三鷹市
❏ さらに詳しい調布市の在宅医療はこちら
❏ さらに詳しい調布市の在宅医療はこちら
訪問診療の対象となる方の例
ひとりで通院ができなくなった方であれば、どなたでもご利用いただけます。
寝たきりや歩行困難で通院困難な方、病院から退院し住み慣れたご自宅で療養生活を送りたい方、がん末期で残りの人生をご自宅で自分らしく過ごしたいとお考えの方など、様々な理由でご自宅での療養を希望される方を私たちはサポートさせていただいております。
基本的には病院と変わらない診療を受けていただけます。
・通院が困難、外来の待ち時間が長くて大変な方
・ご家族の通院付き添いが大変な方
・入院せずに、ご自宅で治療を受けたい方
・ご自宅での終末期医療、緩和ケアを望む方
・退院後のご自宅での療養が不安な方
・いつでも気軽に相談できるかかりつけ医をお探しの方
・独居高齢者の安否確認が必要な方
寝たきりや歩行困難で通院困難な方、病院から退院し住み慣れたご自宅で療養生活を送りたい方、がん末期で残りの人生をご自宅で自分らしく過ごしたいとお考えの方など、様々な理由でご自宅での療養を希望される方を私たちはサポートさせていただいております。
基本的には病院と変わらない診療を受けていただけます。
・通院が困難、外来の待ち時間が長くて大変な方
・ご家族の通院付き添いが大変な方
・入院せずに、ご自宅で治療を受けたい方
・ご自宅での終末期医療、緩和ケアを望む方
・退院後のご自宅での療養が不安な方
・いつでも気軽に相談できるかかりつけ医をお探しの方
・独居高齢者の安否確認が必要な方
診療内容
基本的には病院と変わらない診療を受けられます。
・訪問診療および緊急往診(24時間365日対応)
・がんや心不全などの終末期医療(緩和ケア、お看取り)
・糖尿病、高血圧などの生活習慣病の予防と治療
・痛みのケア、医療用麻薬の管理、治療(腰痛、関節痛、がんなど)
・脳血管障害後(脳出血・脳梗塞)の治療、リハビリ指導
・褥瘡(じょくそう)の管理、皮膚科往診
・認知症、精神疾患に対する精神科往診
・糖尿病患者様の自己注射指導、血糖管理
・腹部エコー検査、腹水穿刺、胸水穿刺
・心エコー検査、ポータブル心電図、ホルター心電図検査
・酸素吸入、人工呼吸器、在宅酸素療法(HOT)の管理
・睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査、CPAP療法の管理
・経管栄養(胃ろう、経鼻カテーテル)の管理、交換
・点滴治療、中心静脈栄養、高カロリー輸液
・痛みに対するトリガーポイント注射
・関節腔内注射、関節液穿刺
・連携病院、医療機関への紹介、入院
・薬局との連携による薬の配達、服薬指導
・訪問診療および緊急往診(24時間365日対応)
・がんや心不全などの終末期医療(緩和ケア、お看取り)
・糖尿病、高血圧などの生活習慣病の予防と治療
・痛みのケア、医療用麻薬の管理、治療(腰痛、関節痛、がんなど)
・脳血管障害後(脳出血・脳梗塞)の治療、リハビリ指導
・褥瘡(じょくそう)の管理、皮膚科往診
・認知症、精神疾患に対する精神科往診
・糖尿病患者様の自己注射指導、血糖管理
・腹部エコー検査、腹水穿刺、胸水穿刺
・心エコー検査、ポータブル心電図、ホルター心電図検査
・酸素吸入、人工呼吸器、在宅酸素療法(HOT)の管理
・睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査、CPAP療法の管理
・経管栄養(胃ろう、経鼻カテーテル)の管理、交換
・点滴治療、中心静脈栄養、高カロリー輸液
・痛みに対するトリガーポイント注射
・関節腔内注射、関節液穿刺
・連携病院、医療機関への紹介、入院
・薬局との連携による薬の配達、服薬指導
訪問診療実績(直近1年間※)
・診療患者数合計 52
・看取り件数 24
・訪問診療等の合計回数 597
往診 128
訪問診療 469
・在宅医療を担当する常勤の医師数 5
・連携する保険医療機関数 5
❏ さらに詳しい診療内容・実績はこちら
❏ 東京都の在宅看取り件数ランキング2024年版
・看取り件数 24
・訪問診療等の合計回数 597
往診 128
訪問診療 469
・在宅医療を担当する常勤の医師数 5
・連携する保険医療機関数 5
❏ さらに詳しい診療内容・実績はこちら
❏ 東京都の在宅看取り件数ランキング2024年版
※在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書に基づく
訪問診療のご相談・お問い合わせ
〒182-0026 東京都調布市小島町3-69-14第2荒井麗峰ビル4F・5F
TEL:042-452-8199/FAX:042-452-8189
お問い合わせはこちら
https://www.uematsuclinic.jp/contact/
TEL:042-452-8199/FAX:042-452-8189
お問い合わせはこちら
https://www.uematsuclinic.jp/contact/
植松淳一理事長/院長のプロフィール
経歴:
2008年 聖マリアンナ医科大学 医学部卒業
2008年 東京医科大学病院卒後臨床研修センター 初期初期研修医として勤務
2010年 東京医科大学病院消化器内科学分野 臨床研究医として勤務
2011年 国際医療福祉大学三田病院消化器センター医員として出向
2015年 医療法人社団ARCWELL 入職 在宅医療に従事
2019年 うえまつ在宅クリニック開設
2020年 医療法人社団悠翠会を設立し、理事長に就任、東京医科大学地域医療指導教授に就任
2021年 医療法人社団悠翠会 悠翠会うえまつクリニック開設
2023年 医療法人社団悠翠会 ゆうすい会訪問看護ステーション開設
2025年 東京医科大学病院高齢総合医学分野客員講師に就任
2008年 東京医科大学病院卒後臨床研修センター 初期初期研修医として勤務
2010年 東京医科大学病院消化器内科学分野 臨床研究医として勤務
2011年 国際医療福祉大学三田病院消化器センター医員として出向
2015年 医療法人社団ARCWELL 入職 在宅医療に従事
2019年 うえまつ在宅クリニック開設
2020年 医療法人社団悠翠会を設立し、理事長に就任、東京医科大学地域医療指導教授に就任
2021年 医療法人社団悠翠会 悠翠会うえまつクリニック開設
2023年 医療法人社団悠翠会 ゆうすい会訪問看護ステーション開設
2025年 東京医科大学病院高齢総合医学分野客員講師に就任
資格:
医学博士
日本内科学会内科認定医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本消化管学会胃腸科専門医
厚生労働省緩和ケア研修会修了
東京都難病指定医
身体障害者福祉法指定医(肢体不自由、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害の診断)
日本内科学会内科認定医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本消化管学会胃腸科専門医
厚生労働省緩和ケア研修会修了
東京都難病指定医
身体障害者福祉法指定医(肢体不自由、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害の診断)