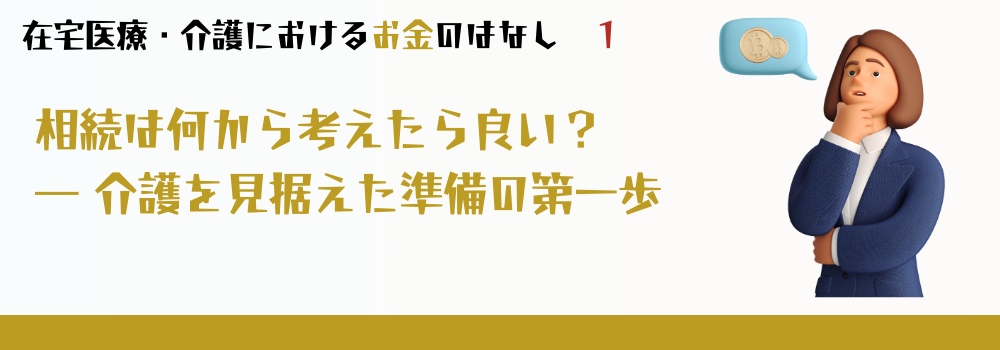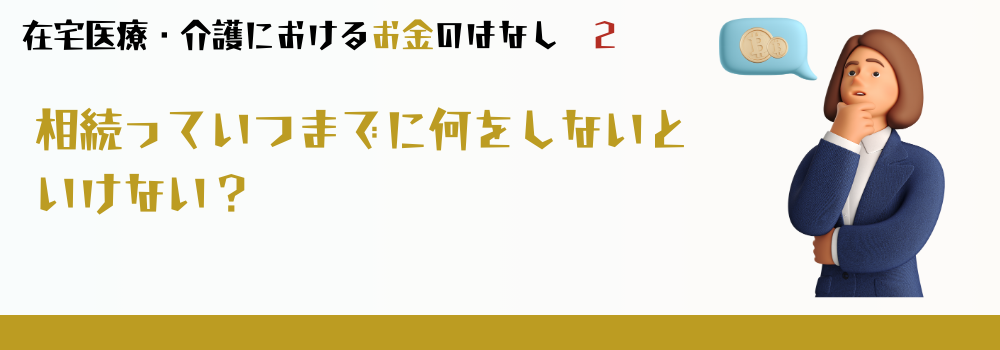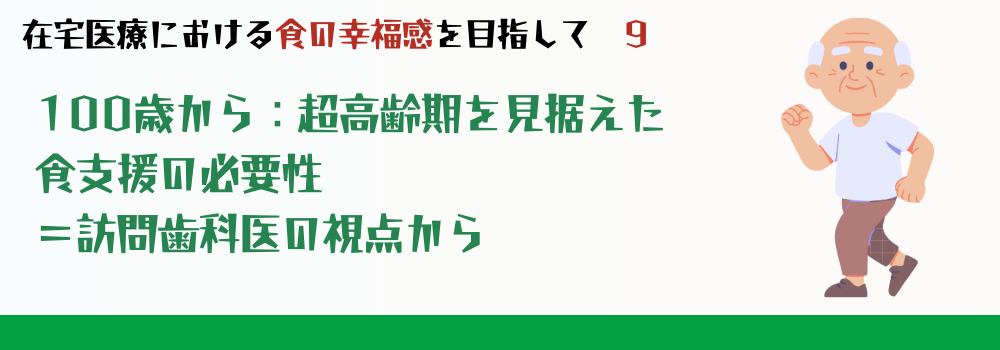認知症になった時のお金のリスクとは? 最終更新日:2025/07/05
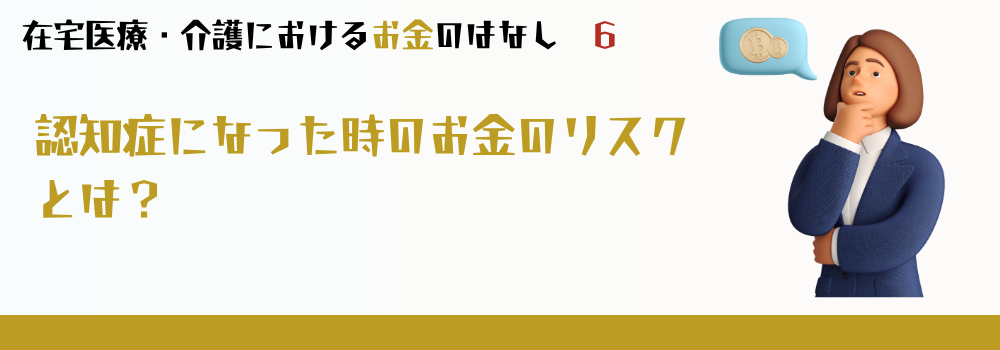
「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けする新企画「在宅医療・介護におけるお金のはなし」。
全10回シリーズの第6回は、「認知症になった時のお金のリスクとは?」です。
「もし親が認知症になったら…」「自分自身が将来そうなったら…」そんな不安を感じたことはありませんか?
介護が必要になったときの心配ごとの一つが“お金”です。特に認知症は、本人に判断力がなくなることから、資産の管理や使い道に大きな制約が出てくる点が特徴です。
今回は、認知症になったときに直面する可能性のあるお金のリスクと、その備え方についてお伝えします。
全10回シリーズの第6回は、「認知症になった時のお金のリスクとは?」です。
「もし親が認知症になったら…」「自分自身が将来そうなったら…」そんな不安を感じたことはありませんか?
介護が必要になったときの心配ごとの一つが“お金”です。特に認知症は、本人に判断力がなくなることから、資産の管理や使い道に大きな制約が出てくる点が特徴です。
今回は、認知症になったときに直面する可能性のあるお金のリスクと、その備え方についてお伝えします。
判断力がなくなると、財産管理ができない
まず最も大きな問題は、本人が自分の財産を管理できなくなることです。
認知症の進行によって判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却、契約の締結など、重要なお金の手続きが一切できなくなります。
たとえば、親名義の自宅を売って施設の入所資金に充てたいと思っても、本人が認知症と診断されていて意思確認ができなければ、売却することはできません。家族が代わりに手続きしようとしても、法律上はできないのです。
加えて、金融機関では認知症の疑いがある場合、たとえ家族であっても取引に応じないケースがほとんどです。預金口座の名義人本人以外が手続きを行うには、後見制度を利用して家庭裁判所の手続きを経る必要があります。手続きには時間と費用がかかるため、急な出費に対応できない状況も起こり得ます。
その結果、資産があるのに使えないという“凍結状態”に陥る可能性があります。これは想像以上に深刻な問題です。たとえば、入所先の初期費用が支払えず入居が遅れたり、急な医療費の支払いができなかったりと、生活に大きな支障が出るケースもあります。

詐欺や悪質な契約のリスクが高まる
また、認知症になると詐欺や悪質な勧誘による被害にも遭いやすくなります。
「優しいお兄さんが何度も来るからつい契約してしまった」「気づかないうちに高額な買い物をしていた」など、本人は悪気がなくても、結果として高額の出費をしてしまうケースが少なくありません。
特に高齢者を狙った訪問販売や電話勧誘などは、認知症の進行とともに判断力が落ちることで、契約の意味を十分に理解せずにサインしてしまうリスクが高まります。不要な健康食品の定期購入や、意味のわからないサービスへの加入、さらには「家を売って投資しませんか」といった詐欺まがいの勧誘まで多種多様です。
こうした事態を防ぐには、日頃から見守る体制を整えておくことが大切です。定期的に通帳やクレジットカードの利用履歴を確認する、信頼できる第三者を交えてお金の管理をしておく、家族間でお金の使い道を可視化する、などの工夫が有効です。地域包括支援センターや成年後見制度の活用も視野に入れておくとよいでしょう。

長期的な介護費用の負担も
認知症は、身体的には元気な状態が長く続くケースも多いため、介護期間が長期化する傾向があります。介護が必要な状態が10年以上続くことも珍しくありません。その間に必要となる費用は、在宅介護か施設介護かによっても異なりますが、月々5万円〜15万円程度が目安とされています。
在宅介護の場合は、介護サービスの自己負担分に加えて、住宅のバリアフリー化、通院や買い物の付き添い交通費、ヘルパーの手配費用などが掛かります。さらに、介護者(多くは家族)が仕事をセーブする必要が出てくると、世帯収入そのものが減少し、家計に二重の負担がのしかかることもあります。
施設介護に切り替える場合、特別養護老人ホーム(特養)では月額7万円~15万円程度ですが、民間の有料老人ホームの場合は月額20万円以上40万円近く掛かることもあります。初期費用として数百万円~数千万円の一時金が必要な施設もあり、認知症に掛かる総費用はトータルで数百万円から1,000万円を超えることも十分に考えられます。
早めの備えがリスク回避のカギ
認知症に備えるためには、リスクを知るだけでなく、具体的な準備を「元気なうちに」「家族と一緒に」進めていくことが不可欠です。ここでは、現実的かつ実行しやすい備えの方法をさらに詳しくご紹介します。
では、こうしたリスクに対してどのように備えればよいのでしょうか?以下のような対策が考えられます。
1. 任意後見制度の活用
認知症になる前に、自分の意思で信頼できる人を後見人として選んでおく制度です。判断力が低下したときに、あらかじめ決めておいた人が自分の代わりに財産を管理・契約できるようになります。任意後見契約は公証役場で手続きを行い、発効には医師の診断書と家庭裁判所の関与が必要です。特に一人暮らしの方や、遠方に住む子どもがいる家庭では、有効な手段の一つになりますが、費用が掛かり続けることや、死後事務は依頼出来ないなど、注意点も多くあります。
2. 家族信託の活用
自分の資産を家族に託して、あらかじめ決めたルールに従って管理・運用してもらう仕組みです。不動産や預金の管理に柔軟に対応でき、将来的な資産凍結のリスクを回避しやすくなります。たとえば、収益を生む不動産を信託することで、家族が収益を活用して介護費用に充てるといった設計も可能です。最近では、家族信託を専門に扱う司法書士なども増えており、制度設計の自由度が高いことが特徴です。

3. 介護費用のシミュレーションと積立
いざというときにどのくらい費用がかかるのかを把握しておくことも重要です。収入や貯蓄と照らし合わせて、どの程度まで自費で対応できるかを確認しておきましょう。自宅を売却するか、持ち家を活用したリバースモーゲージを検討する選択肢もあります。さらに、日々の生活費とは別に「介護準備資金」として一定額を積み立てておくことも有効です。特定口座を設けて分けて管理するだけでも、いざというときの安心感が違います。
4. 保険や公的支援制度の確認と活用
民間の認知症保険や介護保険(民間・公的)に加入しておくことも、一つの備えになります。近年は、認知症と診断された時点で一時金が支払われるタイプの保険商品も登場しています。月々の保険料と保障内容をよく比較し、必要に応じて加入を検討しましょう。
一方、公的制度では「高額介護サービス費」や「介護保険負担限度額認定証」など、自己負担を軽減できる仕組みがあります。自治体によって利用方法や条件が異なるため、早めに情報収集をしておくことが大切です。ケアマネジャーや地域包括支援センター、かかりつけ医など外部の専門家との連携も事前に準備しておくと、いざというときに的確な支援を受けやすくなります。
「もし認知症になったらどうしたいか」を、元気なうちに家族と話し合っておくことも大切です。本人の意思を尊重したケアと資産活用のためには、事前の共有が欠かせません。話しにくいテーマではありますが、早めに方針をすり合わせておくことが、トラブルや混乱の予防につながります。
また、誰が金銭管理を担うか、通院や見守りをどう分担するかなど、家族間で役割を明確にしておくと、実際に介護が始まったときにスムーズに動けます。可能であれば、定期的に「家族会議」を開き、状況の変化に応じて計画を見直していく体制を作っておきましょう。
おわりに
認知症とお金の問題は、誰にでも起こりうる身近なリスクです。特に資産がある人ほど、「使いたいときに使えない」状態になると、家族にも大きな負担をかけることになります。
また、認知症の症状が出てから対策を講じようとしても、すでに判断力が不十分な状態ではできることが限られてしまいます。将来の不安を軽減するためには、早めの準備が何よりも重要です。「まだ元気だから大丈夫」と思わずに、今できることから一歩ずつ備えていきましょう。

次回のテーマは、「国の介護保険でカバーされる範囲とは?」です。公的な介護保険でカバーされる範囲を把握して、効果的な準備をしていきましょう。
関連リンク:
執筆:

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。