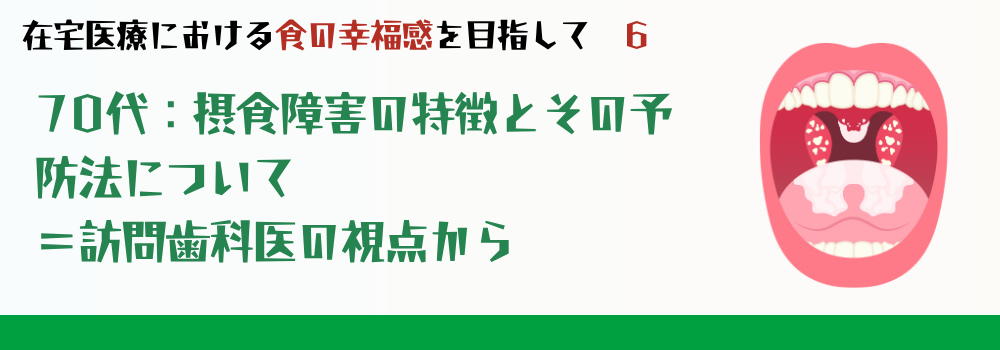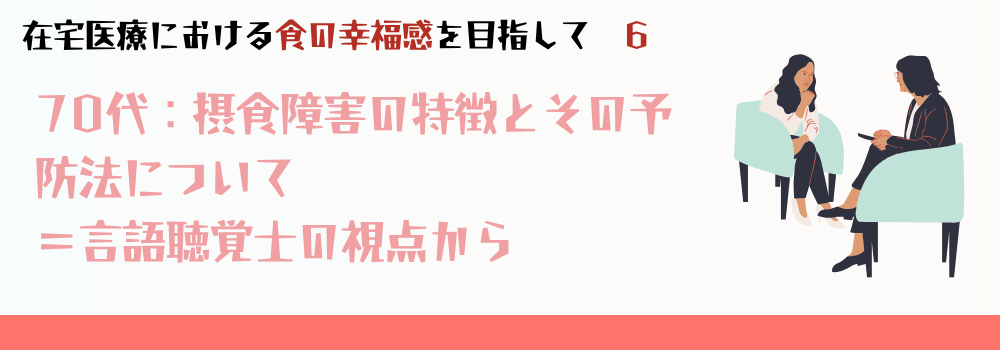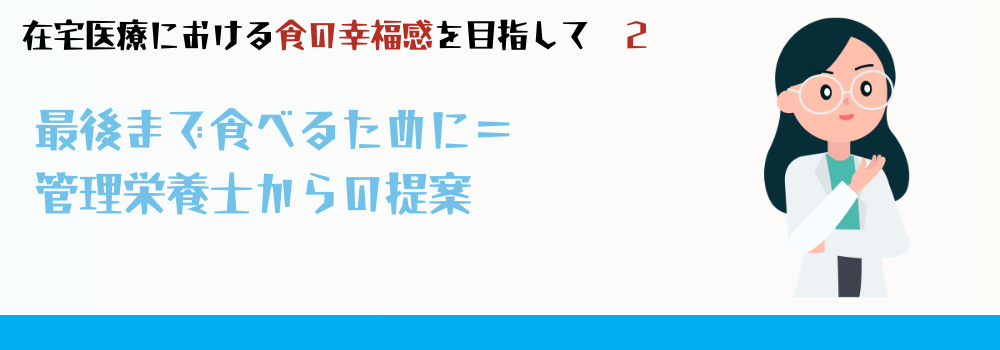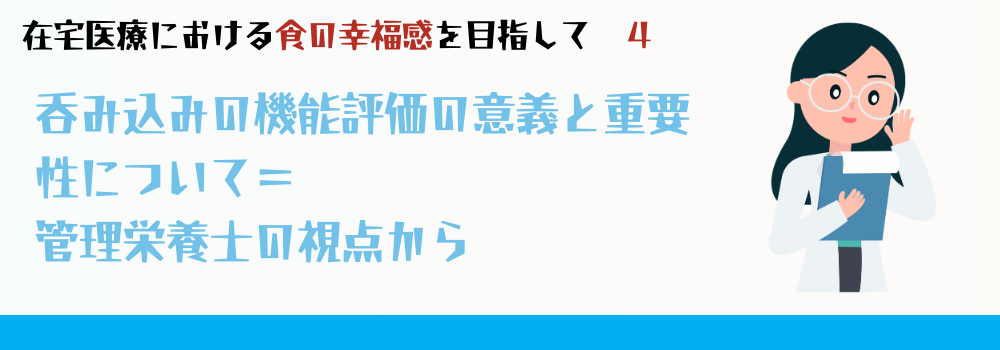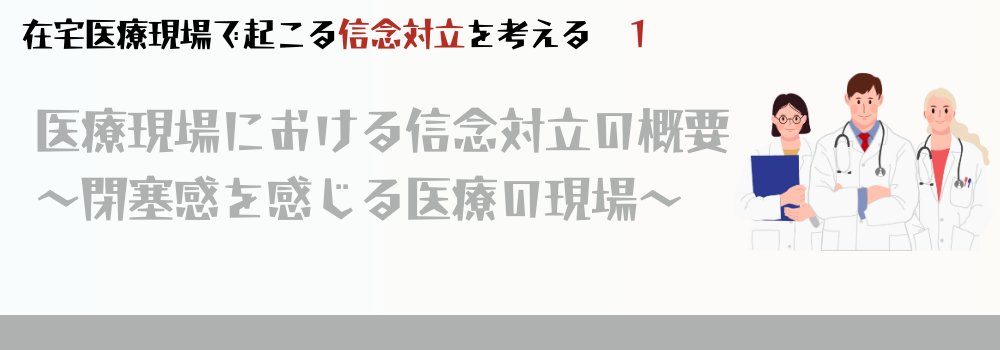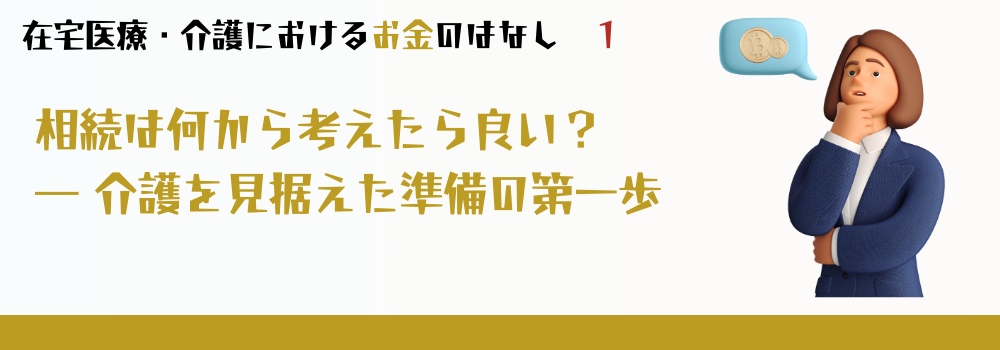摂食・嚥下障害への予防と早期の対応が重要!70代からの“口の老い”に向き合う=管理栄養士の視点から 最終更新日:2025/07/12
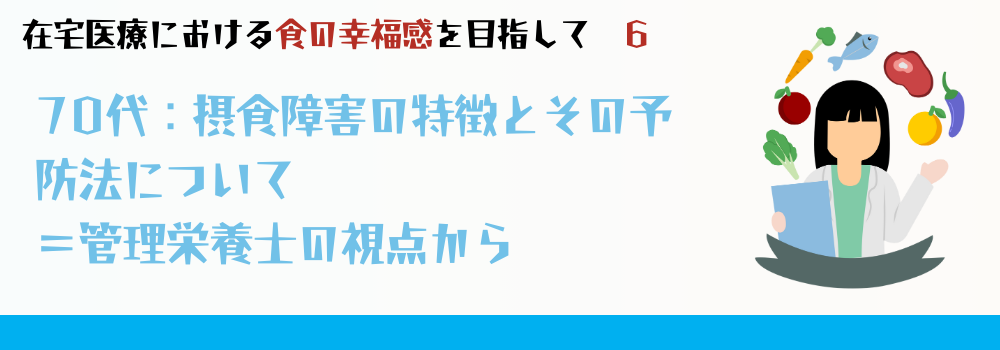
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
前回から年代別の予防について配信、6回目の今回は70代を対象に「70代からの“口の老い”に向き合う」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
前回から年代別の予防について配信、6回目の今回は70代を対象に「70代からの“口の老い”に向き合う」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
はじめに
70代は、身体機能や筋力、認知機能などの低下が顕著に現れる年代であり、その影響は日常生活、とりわけ食生活にも及びます。特に摂食・嚥下機能の衰えは、誤嚥・低栄養・誤嚥性肺炎といった深刻な健康問題につながることから、予防と早期の対応が重要です。
本稿では、70代における摂食・嚥下障害の特徴を整理し、今日から実践できる予防法をご紹介します。
本稿では、70代における摂食・嚥下障害の特徴を整理し、今日から実践できる予防法をご紹介します。

70代に見られる摂食嚥下障害の特徴
70代に特有の特徴としては、加齢に伴う咀嚼・嚥下機能の低下に加え、以下のような点が挙げられます。
サルコペニア・フレイルの進行
加齢による骨格筋量と筋力の低下により、舌・咽頭・口唇などの運動が制限され、食塊の形成や送り込みに支障をきたします。
歯科的問題
義歯の不適合や残存歯の減少による咀嚼力の低下が影響します。
令和4年「歯科疾患実態調査」によると、75歳以上の約9割が歯を喪失しており、70代の義歯使用率は60代に比べ大きく上昇しています。
令和4年「歯科疾患実態調査」によると、75歳以上の約9割が歯を喪失しており、70代の義歯使用率は60代に比べ大きく上昇しています。
社会的要因
孤食や食への興味の減退により、食事量の減少・低栄養が進むリスクがあります。定年退職やコロナ禍をきっかけに、外出機会や人とのつながりが減ったと感じる方も少なくありません。これらの要因が相互に関連しあって、摂食・嚥下障害の進行を助長します。
予防のためにできること
摂食嚥下機能の維持と改善には、栄養状態を整えることを土台にし、下記に記載するような予防方法が挙げられます。
毎食、主食・主菜・副菜を揃えたバランスの良い食事を
→バランスの取れた食事は 筋肉量を維持し、嚥下に必要な筋力の低下を防ぎます。
特に主菜に含まれるたんぱく質が不足すると筋力の低下が起きやすくなるため、適切な摂取量を確保することが重要です。たんぱく質は肉類、魚類、豆類、卵などに含まれます。一日3食、一食あたり片手に乗るくらいのたんぱく質を摂取しましょう。
特に主菜に含まれるたんぱく質が不足すると筋力の低下が起きやすくなるため、適切な摂取量を確保することが重要です。たんぱく質は肉類、魚類、豆類、卵などに含まれます。一日3食、一食あたり片手に乗るくらいのたんぱく質を摂取しましょう。
よく噛んで食べる習慣をつける
→ 咀嚼筋や舌の筋肉を使うことで、口腔機能の維持につながります。軟らかい食材をとるのではなく、食感があり、よく噛む食材、料理を選びましょう。
さらによく噛むためには、一口30回以上噛むことを意識し、『ながら食べ』を控えて食事に集中することなどが挙げられます。
さらによく噛むためには、一口30回以上噛むことを意識し、『ながら食べ』を控えて食事に集中することなどが挙げられます。
・よく噛む食材(咀嚼回数ランク表 ランク5⁻10より)
肉類:とんてき、牛串カツ、豚ももソテー、焼き鳥 など
魚介・藻類:白エビから揚げ、小魚佃煮、いか焼き、げそ天 など
野菜類:にんじん(生・スティック)、らっきょう、キャベツ(生・千切り)、きんぴらごぼう など
肉類:とんてき、牛串カツ、豚ももソテー、焼き鳥 など
魚介・藻類:白エビから揚げ、小魚佃煮、いか焼き、げそ天 など
野菜類:にんじん(生・スティック)、らっきょう、キャベツ(生・千切り)、きんぴらごぼう など

水分を適切に摂る習慣をもつ
→ 唾液の99%は水分で構成されており、唾液分泌や嚥下の円滑さを保つうえで十分な水分摂取は不可欠です。脱水状態になると、身体は生命維持に必要な臓器(脳・心臓・腎臓など)に水分を優先的に供給し、唾液腺への供給が後回しになります。その結果、唾液の分泌が減少し、口腔内が乾燥(ドライマウス)しやすくなります。口腔内の乾燥は、虫歯・歯周病のリスク増加や、味覚異常から食欲の減退、誤嚥性肺炎のリスクへと繋がります。
一日の水分必要量の求め方
体重×30~40ml
例えば体重50㎏の場合・・・1500ml~2000mlの水分が必要
例えば体重50㎏の場合・・・1500ml~2000mlの水分が必要
飲み方は一度に多い量を摂るのではなく、こまめに摂るようにし、起床時・食事中・入浴後・就寝前など、失いやすいタイミングで意識的に補給するようにしましょう。また唾液の分泌量に関してはガムを噛むことで改善するケースもあります。
食事姿勢に気をつける
→姿勢が安定しないと、食べこぼしや誤嚥のリスクが高まります。
良い姿勢の摂り方
顎を軽く引き、少し前かがみにする
・椅子に深く座って背筋を伸ばす
・テーブルの高さは膝が90度に曲がるくらいの高さにする(足裏が床につくような高さ)
・椅子の高さは肘が90度に曲がるくらいの高さにする
・テーブルと椅子の間はこぶし一個分の隙間を空ける
・椅子に深く座って背筋を伸ばす
・テーブルの高さは膝が90度に曲がるくらいの高さにする(足裏が床につくような高さ)
・椅子の高さは肘が90度に曲がるくらいの高さにする
・テーブルと椅子の間はこぶし一個分の隙間を空ける
悪い姿勢
顎が上に上がっている
・背中が丸まっている(顎が上がる原因になる)
・テーブル、椅子の高さがあっていない
・足が浮いており不安定になっている
・テーブルと椅子の距離が近い、または遠い
・背中が丸まっている(顎が上がる原因になる)
・テーブル、椅子の高さがあっていない
・足が浮いており不安定になっている
・テーブルと椅子の距離が近い、または遠い
口腔体操や「パタカラ体操」を日課にする
→ 唇・舌・喉の筋肉を動かして、嚥下機能を刺激・強化する簡便な方法です。
パタカラ体操の方法
単音発声・・・『パ』『タ』『カ』『ラ』を各10回程度発声する
連続発声・・・『パパパ…』『タタタ…』『カカカ…』『ラララ…』を各5回程度発声する
文の発声・・・『パンダのたからもの』を繰り返し発声する
食事前に行うと嚥下機能が活性化されます。毎日無理のない回数で続けることが大切です。
連続発声・・・『パパパ…』『タタタ…』『カカカ…』『ラララ…』を各5回程度発声する
文の発声・・・『パンダのたからもの』を繰り返し発声する
食事前に行うと嚥下機能が活性化されます。毎日無理のない回数で続けることが大切です。
歯科受診と義歯の定期チェックを怠らない
→ 噛みにくさや食べづらさを感じたら、早期の受診・調整が大切です。前述したように義歯を使う人の割合は70代から増えています。義歯は体型や口腔の変化により時間とともに適合しなくなることもあります。義歯が合わないことで軟らかい食材、料理を選ぶようになり、さらに噛む力が落ちることにも繋がります。
孤食を減らし、「人と食べる」「人と話す」機会を増やす
→ 誰かと楽しく食べることは食欲の維持・口腔筋の刺激・嚥下機能の活性化に役立ちます。会話しながら食べることで 口の筋肉を自然と使い、嚥下機能にも好影響です。定期的に地域のサロンやボランティアなど集いの場所に出向くことがお勧めです。

モデル患者事例
前述に述べた予防方法を行い、摂取栄養量が改善したケースをご紹介します。
74歳男性Aさん
・ご本人からの訴え
葉物野菜が食べづらい
プリンやヨーグルトなどが食べやすいと感じるようになった
固いものが噛みづらい(肉類やせんべいなど)
服薬の際にむせることが増えた
唾液が出づらい、口が渇いている
葉物野菜が食べづらい
プリンやヨーグルトなどが食べやすいと感じるようになった
固いものが噛みづらい(肉類やせんべいなど)
服薬の際にむせることが増えた
唾液が出づらい、口が渇いている
・取り入れた対策
パタカラ体操をリハビリの際に取り入れる
水分摂取を促す
ガムを噛み唾液の分泌を促す
義歯の調整を行う
パタカラ体操をリハビリの際に取り入れる
水分摂取を促す
ガムを噛み唾液の分泌を促す
義歯の調整を行う
これらの対策を取り入れたことにより、口腔内の乾燥に改善がみられ、むせの回数が減り、食事のバリエーションが増えました。以前まで軟らかいものが中心の食事でしたが、から揚げなどのたんぱく質も摂取できるようになり、摂取量の改善がみられました。
(対応前:800kcal→対応後:1300kcal)
(対応前:800kcal→対応後:1300kcal)
おわりに
70代は加齢に伴う身体機能の変化が明確に現れる年代であり、摂食嚥下障害のリスクも高まる時期です。これらの障害は、単に「食べにくさ」だけでなく、栄養状態や生活の質、場合によっては命に関わる重大な課題になります。「食べづらくなってから」ではなく、“今この瞬間から”予防的に取り組むことが、健康寿命の延伸につながります。
日々の生活の中に小さな工夫を取り入れながら、「食べる力」を守り続けましょう。
関連リンク:
執筆:

井上美穂(いのうえみほ)
ふれあい歯科ごとう 管理栄養士
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-11-13せらび新宿1階
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
介護や医療イベントにて食事の大切さを伝えるキッチンカーを運営中
『食の相談室おむすび』
『食の相談室おむすび』