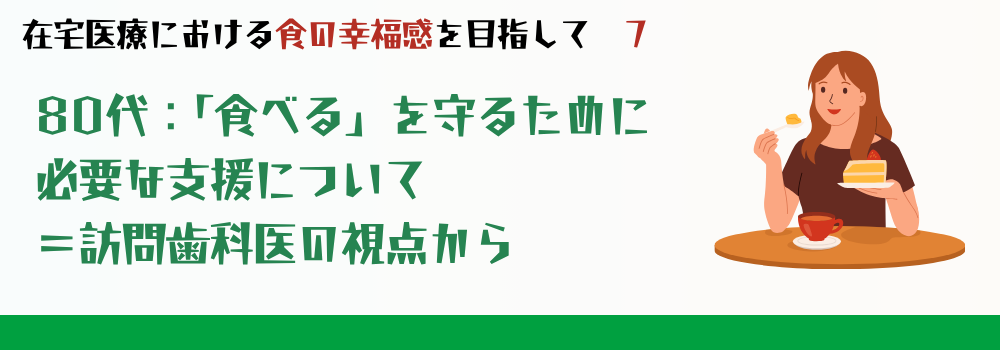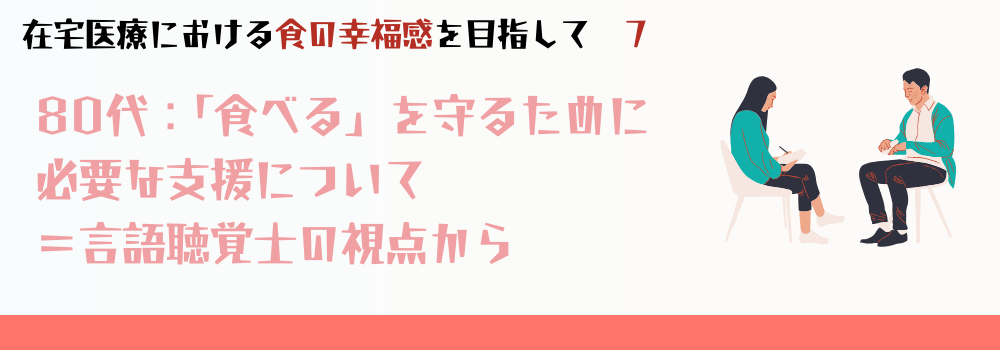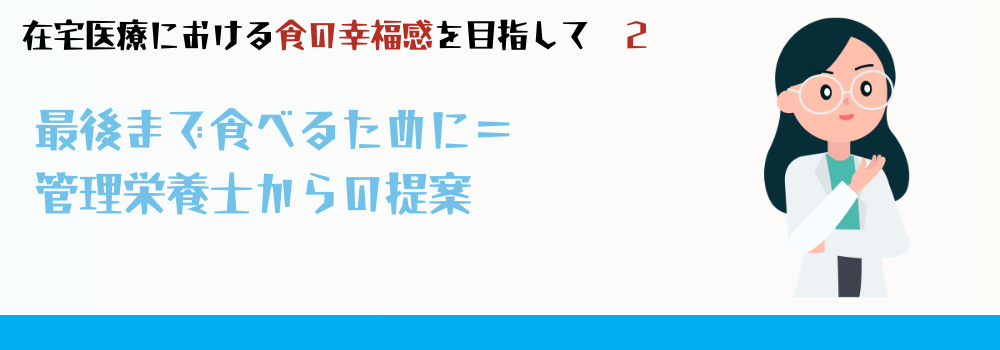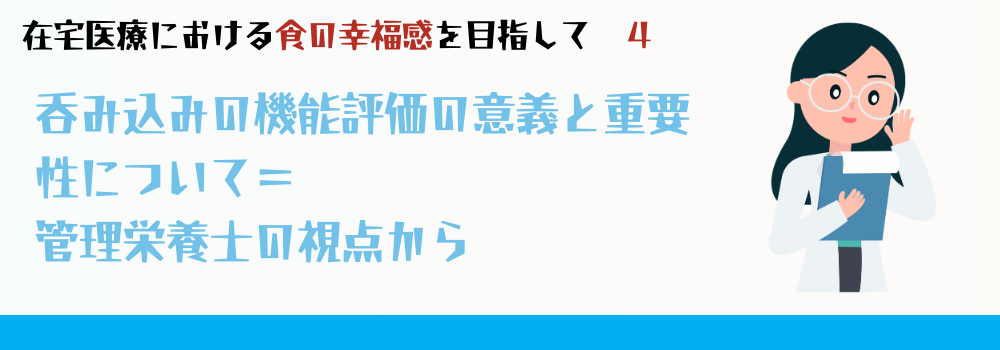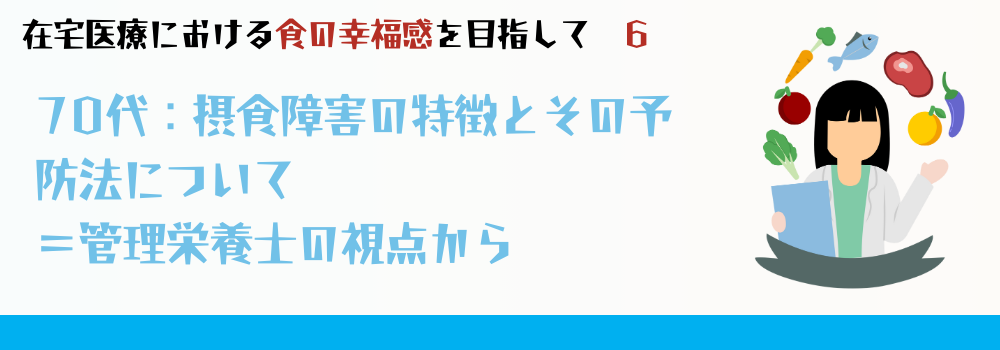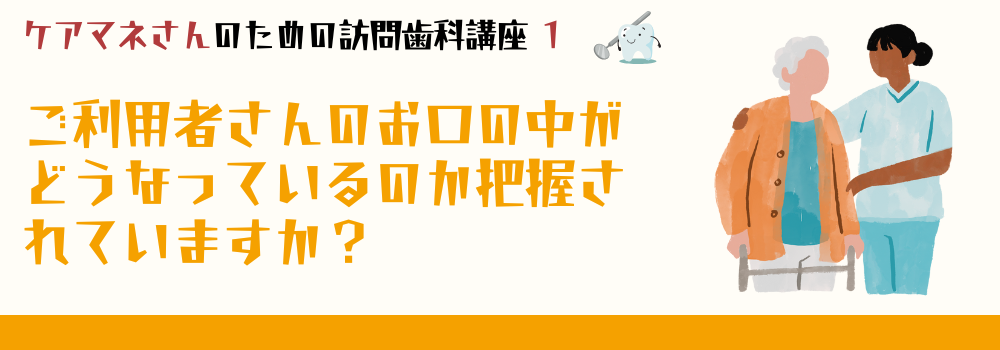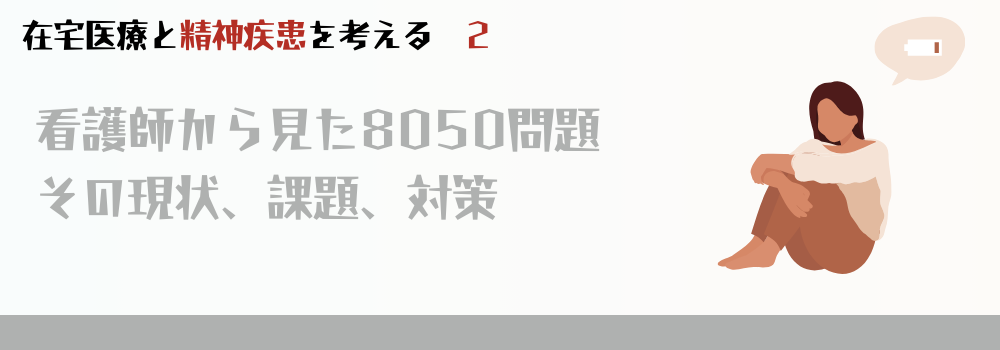「食べる」がこんなにつらいとは思わなかった—80代からの口の支え方=管理栄養士の視点から 最終更新日:2025/08/17
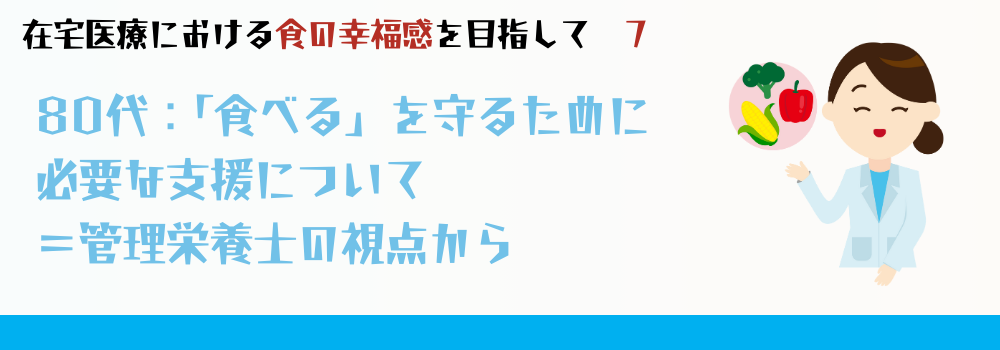
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
7回目の今回は80代を対象に「80代からの口の支え方」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
7回目の今回は80代を対象に「80代からの口の支え方」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
はじめに
80代は加齢に伴う身体・認知・環境の変化により「食べる力」が低下しやすい年代です。 「食べる」ことは栄養を補給するだけでなく、生活の質・尊厳・社会的つながりに直結しています。「口から食べる」を支える意義と、管理栄養士の具体的な関わり方について記述していきます。
「食べる力」の評価
『最近食べられていますか?』という質問に対し、『食べられている』と回答する人の中には、体重が減少したり、むせ込みが多くなっている人もいます。食べられていない原因は身体的機能だけではなく、環境の問題や心理的問題からも考えられます。まず「食べる力」を守るために、まずは正しく評価することが必要です。

栄養状態の評価
・MNA®
MNA®(Mini Nutritional Assessment)は、65歳以上の高齢者の栄養状態を確認するためのツールです。食事摂取量だけでなく、体重変化や歩行、疾患によるストレスや精神的要因などがスクリーニング項目に充てられています。スクリーニングの項目だけでも簡易的に栄養状態を評価することができ(MNA®⁻SF)、下記の様に評価ができます。
12-14 ポイント:栄養状態良好
8-11 ポイント:低栄養のおそれあり (At risk)
0-7 ポイント:低栄養
8-11 ポイント:低栄養のおそれあり (At risk)
0-7 ポイント:低栄養
食欲の評価
・CNAQ-J
高齢者の食欲を簡便かつ信頼性の高い方法で評価できるツールです。質問紙形式のため短時間での実施が可能で、食欲低下についてのチェックリストのため、低栄養の前段階をとらえることができます。食欲の確認に加え、空腹感、食事の味、精神的要因も質問項目に含まれています。評価の点数としては下記の様に評価ができます。体重減少率と併せて評価しても効率的な評価ができるでしょう。
28点以下:6か月以内に少なくとも5%の体重減少のリスク
8点から16点:食欲不振の危険があり,栄養カウンセリングを必要とする
17点から28点:頻繁な再評価を必要とすると判定する
8点から16点:食欲不振の危険があり,栄養カウンセリングを必要とする
17点から28点:頻繁な再評価を必要とすると判定する
簡易嚥下チェックツール
・EAT-10(イートテン)
嚥下の機能をはかるチェック項目として、信頼性と妥当性が検証されています。嚥下時の自覚症状や体重の減少などについて 10 項目の質問で構成されています。
合計点が3点以上の場合は、嚥下障害が疑われ、医師へ相談することが推奨されます。
合計点が3点以上の場合は、嚥下障害が疑われ、医師へ相談することが推奨されます。
「食べる力」を支える対応
スクリーニングなどで食欲の低下や、低栄養状態が疑われるとき、要因に応じた対策が必要です。
味・香りの工夫
食欲が低下している際には嗜好に合わせた食事内容とします。主食、主菜、副菜という形にこだわり過ぎず、可能な限りたんぱく質と炭水化物が摂取でき、脂質で栄養量が確保できるようなものを選ぶと、より良いでしょう。また香りを立たせる方法としては温かいものは温かくすると良いでしょう。
食欲が低下している際にお勧めの料理
香りが良いもの
・味噌汁やスープ類
・焼きおにぎり など
・味噌汁やスープ類
・焼きおにぎり など
のど越しが良いもの
・アイスクリーム
・少量の冷たいうどん
・温泉卵
・茶碗蒸し
・プリン など
・アイスクリーム
・少量の冷たいうどん
・温泉卵
・茶碗蒸し
・プリン など
彩りや盛り付けの工夫
量の工夫
食欲がないと感じる要因の中には、見た目から食べたくないと感じている場合があります。一皿の量が多かったり、品数が多い場合には減らすようにしましょう。少量での盛り付けなら食べられるという体験から食事に対しての拒否感をなくし、成功体験を積むことも大切にしましょう。

料理方法の工夫
食事の見た目から食べる意欲をなくしている場合もあります。例えばミキサー食が茶色になってしまい、中身が何か分からなかったら、食べる意欲は湧きづらいと言えます。彩りがわかるように食材ごとに刻む、ミキサーをかけるのを分ける(煮魚と、付け合わせの人参のミキサーを分ける等)などの工夫があげられます。刻み食やミキサー食の見た目から食欲がわきにくい、という方にはソフト食を使用するという方法もあります。ソフト食はミキサーにかけた食材をゲル化剤でまとめているため、料理にあった形を形成することができます。
食器、食具の工夫
食器の選び方から食事を認識しにくかったり、食事が摂りにくく、食事量が低下しているという場合もあります。例えば白いお茶碗にお粥が入っている場合、認知症の方にとっては認識がしにくいということが起こります。お粥には黒い食器を使う、彩りが多いおかずには白い食器を使うなど、コントラストを付けられるような食器の選び方も工夫ができます。
また身体機能に応じて食器の選び方を変えることも必要です。麻痺がある方などにおいては、食器が滑りやすく食事をすくったり、つかむことが難しいため、滑り止めのついた『自助食器』を使用したり、スプーンの大きさ(柄の長さの調整など)を調整することも必要です。
少量頻回食
食欲低下から一回の食事量を確保できない場合があります。その場合は10時と15時に少量の間食を取り入れることが効果的です。この時、少量で高エネルギーが摂取できるものを選ぶことをお勧めします。時間を特に決めずに、手の届く範囲に間食しやすいものを置いておくという方法もあります。
間食におすすめのもの
・枝豆豆腐
・ポテトサラダ
・アイスクリーム
・プリン
・栄養補助食品
・和菓子(小さいアソートセットなど)
食環境の改善
食環境の整備が不十分で、食事に集中できない場合もあります。テーブルやいすの高さ、位置について確認したり、食事の際はテレビやラジオの音を小さくするまたは消す、自然光を取り入れるためにカーテンを開けるなどの工夫も効果的と言えるでしょう。
食事リズムと心理的サポート
食事の習慣を持てないという方もいらっしゃいます。朝昼夕の食事時間を決め、食事の時間に声かけを行いましょう。孤食をなるべく防ぎ、ご家族や介護スタッフと食卓を囲めることがベストです。また一回の食事が長くなると疲労感を伴います。時間は40分以内にしましょう。
食形態の工夫 嚥下機能低下の場合
嚥下機能が低下している場合には、食形態の調整をしましょう。単に嚥下機能の低下といっても、飲み込みの力が低下している場合もあれば、送り込みができない場合、咀嚼ができない場合と様々です。またミキサーにかける際には加水をするため、栄養量が低下しやすく、味も薄くなりがちです。嚥下調整食3を召し上がる方では、ミキサーにかけるだけではなく、食材や嚥下状態によっては工夫次第で食べられるものもあります。
嚥下調整食3 程度の食事内容
マグロのたたき:出汁や醤油などで味を付けた山芋をかけて混ぜて食べる
南瓜の煮物:皮を取り除き、だし汁を混ぜてペースト状にする
マッシュポテト:いもと牛乳の量を飲み込みやすいように調整する、お湯に溶いてできるインスタントタイプもある
スクランブルエッグ:牛乳、バターをしっかり入れて半熟に仕上げる
パンがゆ:耳なしの食パンを使って調理する
つぶし粥:離水の少ない粥の粒をスプーンなどでつぶす
一方でミキサーを使用する場合はどのような食材を避けるべきか把握をしておく必要があります。
南瓜の煮物:皮を取り除き、だし汁を混ぜてペースト状にする
マッシュポテト:いもと牛乳の量を飲み込みやすいように調整する、お湯に溶いてできるインスタントタイプもある
スクランブルエッグ:牛乳、バターをしっかり入れて半熟に仕上げる
パンがゆ:耳なしの食パンを使って調理する
つぶし粥:離水の少ない粥の粒をスプーンなどでつぶす
一方でミキサーを使用する場合はどのような食材を避けるべきか把握をしておく必要があります。
ミキサーに向かないもの
1. 繊維質が強い野菜・根菜
- セロリ、アスパラガス:長い繊維が残りやすい
- セロリ、アスパラガス:長い繊維が残りやすい
2.海藻類
- わかめ、昆布:均一にミキサーにかけづらい
- わかめ、昆布:均一にミキサーにかけづらい
3. 粒状・種子状のもの
- とうもろこし、枝豆:薄皮や粒の残存が多い
- イチゴ、キウイなどの小さな種:つぶれても舌触りが粗くなる
- とうもろこし、枝豆:薄皮や粒の残存が多い
- イチゴ、キウイなどの小さな種:つぶれても舌触りが粗くなる
4. でんぷんやたんぱくのゲル化しやすい素材
- こんにゃく、寒天:塊になりやすくダマが形成される
- 餃子の皮、春巻きの皮、餅:でんぷん質が分離し、まとまりが悪い
- こんにゃく、寒天:塊になりやすくダマが形成される
- 餃子の皮、春巻きの皮、餅:でんぷん質が分離し、まとまりが悪い
5. 固い食材
- ナッツ類(アーモンド、くるみ):ざらつきが残りやすい、均一にミキサーにかかりにくい
- 鶏の皮、魚の皮:加熱具合により固くなりやすい、均一にミキサーにかかりにくい
- ナッツ類(アーモンド、くるみ):ざらつきが残りやすい、均一にミキサーにかかりにくい
- 鶏の皮、魚の皮:加熱具合により固くなりやすい、均一にミキサーにかかりにくい
症例
80代女性、家族と同居中。娘様が主な介護者。脳出血後遺症から嚥下障害があり食事は全介助。食事量の減少があり、訪問栄養指導を月1回介入。年の瀬に近づき、お正月の料理を食べてもらいたいという思いがあり、訪問時、お雑煮をミキサーにかけたものを摂取され、誤嚥を起こした経験あり。お正月に向けてどんな食材なら摂取がしやすいのか検討を行いました。

おせち
→介護用のおせち(ソフト食)+ あんかけ を作り、ソフト食と混ぜて食べる
お雑煮
→お餅は除き、具材と出汁をミキサーにかけてとろみ調整食品でとろみをつける
お正月を終え、訪問時にはおせちが食べられたという嬉しいご報告を聞くことができました。この時、単に食事は栄養を補給するだけでなく、季節を感じ、日々の喜びを与え、家族の心も軽くするような意義があるのだと感じました。
おわりに
80代において『食べる力』は人それぞれ異なります。管理栄養士が行うべきなのは患者の『食べる』ことをあきらめず、様々なアプローチを行うことです。提案したアプローチの方法ですぐに食事摂取量が改善する場合もあれば、そうでない場合もあります。その方に応じた栄養療法を取り入れ、継続的に栄養の支援をしていくことが80代においての管理栄養士の関わり方といえるでしょう。

関連リンク:
執筆:

井上美穂(いのうえみほ)
ふれあい歯科ごとう 管理栄養士
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-11-13せらび新宿1階
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
介護や医療イベントにて食事の大切さを伝えるキッチンカーを運営中
『食の相談室おむすび』
『食の相談室おむすび』