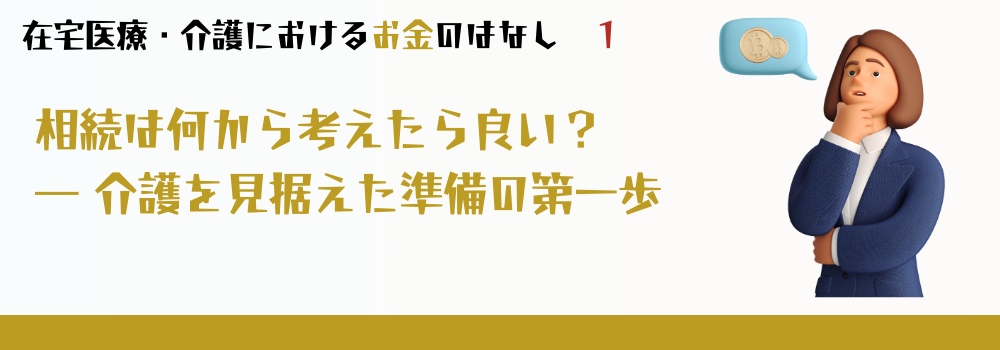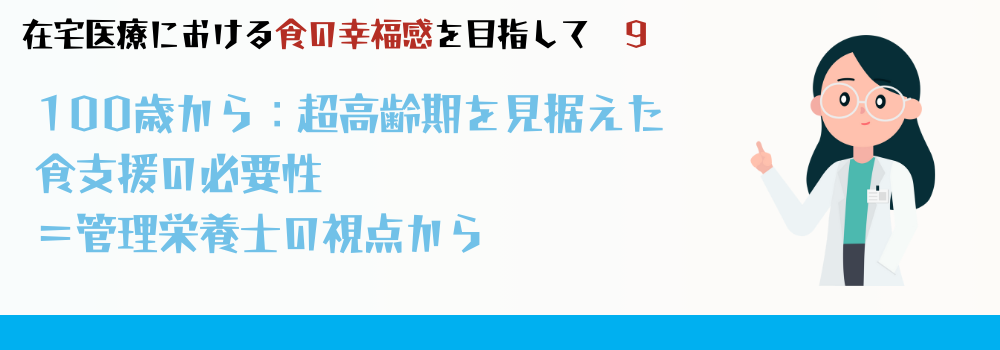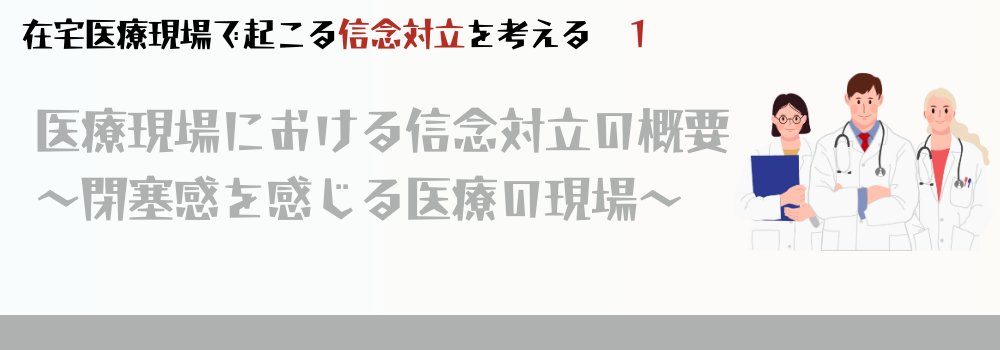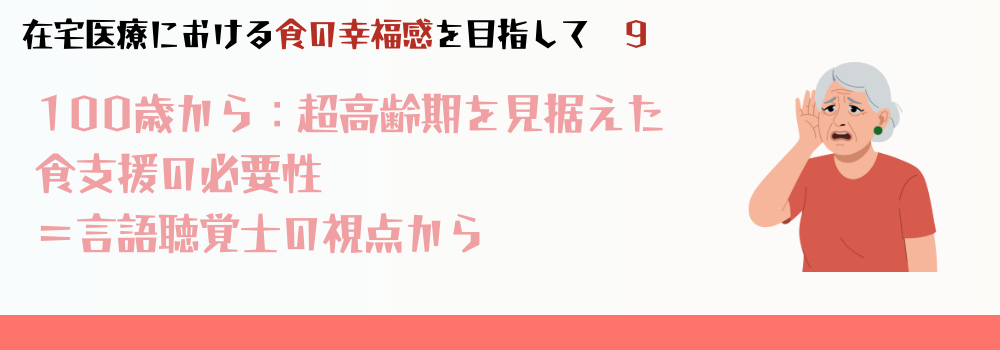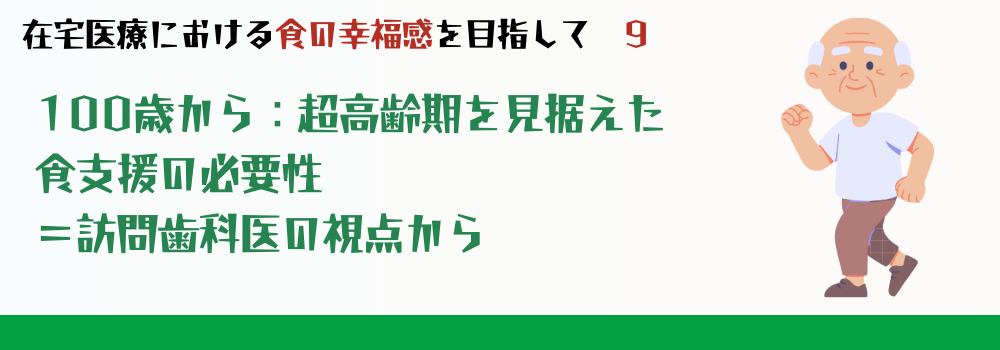相続っていつまでに何をしないといけない? 最終更新日:2025/03/22
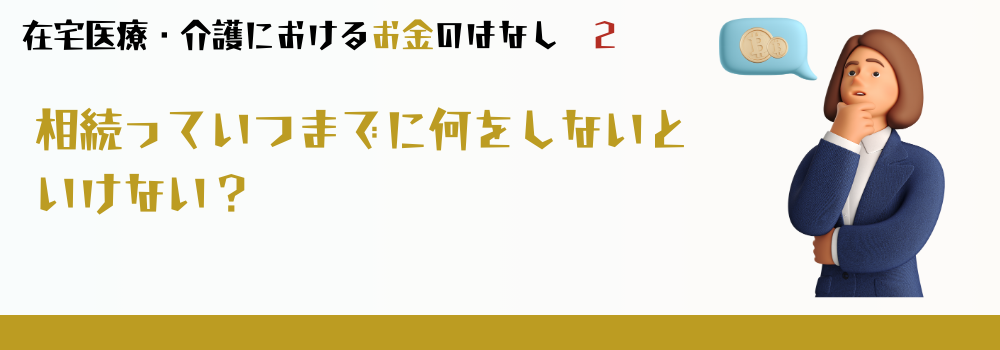
「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けする新企画「在宅医療・介護におけるお金のはなし」。
全10回シリーズの第2回は、「相続っていつまでに何をしないといけないのか?」です。
相続は、突然やってくることが多く、何から手をつければいいのか分からない方も多いでしょう。特に在宅医療や介護をしていた方にとっては、心身ともに負担がかかる中で手続きを進める必要があります。そこで今回は、相続手続きの期限ごとにやるべきことを整理し、スムーズに進めるためのポイントを解説します。
相続がはじまってから慌てて対応するのではなく、どういったことが必要なのか全体像を把握したうえで準備しておくことが大切です。事前に流れを理解しておけば、余計なトラブルを避け、落ち着いて対応することができます。
全10回シリーズの第2回は、「相続っていつまでに何をしないといけないのか?」です。
相続は、突然やってくることが多く、何から手をつければいいのか分からない方も多いでしょう。特に在宅医療や介護をしていた方にとっては、心身ともに負担がかかる中で手続きを進める必要があります。そこで今回は、相続手続きの期限ごとにやるべきことを整理し、スムーズに進めるためのポイントを解説します。
相続がはじまってから慌てて対応するのではなく、どういったことが必要なのか全体像を把握したうえで準備しておくことが大切です。事前に流れを理解しておけば、余計なトラブルを避け、落ち着いて対応することができます。
1. 死亡直後に必要な手続き
(1) 死亡届の提出(7日以内)
死亡の事実を知ってから、7日以内に市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。これは医師の死亡診断書とセットで提出するため、病院で死亡診断書を受け取ったら、速やかに手続きを行いましょう。死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されず、葬儀や火葬ができなくなるため、最優先で対応しましょう。
この手続きは、通常は喪主や親族が行いますが、多くの場合、葬儀社が代行してくれるので、相談してみてください。事前にどこまで対応してくれるのかを確認しておくと、スムーズに進められます。
(2) 年金や健康保険の資格喪失手続き
国民健康保険や介護保険、年金の受給停止手続きも必要です。これを怠ると、後日返還を求められることがあります。特に年金は、死亡後に振り込まれた分を返金しなければならない場合があるため、早めに年金事務所や役所に連絡しましょう。
また、扶養されていた家族の健康保険の切り替えも重要です。会社員の被扶養者だった場合は、国民健康保険への加入が必要になるため、忘れずに手続きを進めましょう。
手続きの期限が、健康保険や年金の種類によって異なるために、注意が必要です。
・健康保険の資格喪失届(5日まだは14日以内)
・介護保険資格喪失届(14日以内)
・年金受給停止(10日または14日以内)
・勤務先への健康保険の資格喪失届(5日以内)

2. 相続の選択
(3) 相続放棄・限定承認の申請(3ヶ月以内)
相続財産には、プラスの資産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの資産(借金・未払い金など)も含まれます。借金が多い場合は、「相続放棄」または「限定承認」を家庭裁判所に申請する必要があります。
・相続放棄:相続権を完全に放棄する。
・限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を返済する。
これらは原則3ヶ月以内に行わないと、自動的に相続を承認したことになります。特に債務の確認には時間がかかるため、早めに専門家に相談し、財産状況を把握することが重要です。
相続放棄を検討する際は、銀行の口座を勝手に触らないように注意しましょう。一度でも引き出してしまうと、「単純承認」とみなされてしまうこともあります。
「単純承認」とは、被相続人(亡くなった人)のすべての財産を相続することになります。預貯金・株式・不動産などのプラスの財産から、借金や滞納税金のようなマイナスの財産まで全て相続をします。相続放棄をしたかったのに、死亡後に銀行に連絡せず預金を引き出してしまったことで、相続放棄ができないという状況は避けましょう。
3. 税務手続き
(4) 準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が確定申告が必要な立場だった場合、相続人が代わりに確定申告を行う「準確定申告」が必要です。これは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行わなければなりません。特に不動産収入や個人事業を営んでいた場合、申告漏れがないよう慎重に対応しましょう。
医療費控除や未払いの税金の精算なども関係するため、税理士に相談するのが安心です。
4. 財産の分割と相続税
(5) 遺産分割協議(期限なしだが早めに)
相続人同士で財産の分け方を決める話し合い“遺産分割協議”が必要になります。話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が署名・押印することで、正式な分割が確定します。
トラブルを避けるためには、専門家を交えて公正証書にすることも検討しましょう。

(6) 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。
5. 生前にできる相続対策
(7) 遺言書の作成
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。特に「特定の人に多く財産を残したい」「事業承継を円滑にしたい」といったケースでは、遺言書が効果を発揮します。
遺言書には、“付言事項”という法的効力を与えることを目的としない記載事項を入れる事ができます。付言事項は、自由に文章を書けるので、遺言者の家族に対する感謝の気持ちや想いを伝える事ができます。
例えば、介護で親身にサポートしてくれた長男に対して、多めの財産を残してあげたいなど、家族で均等にならない配分にしたいこともあるかと思います。その場合、配分が少ない相続人に不満が生じやすくなりますが、付言事項になぜそのような割り合いにしたのかの経緯や想いを伝えることで、相続人の不満が解消され、不要な争いにならないようにすることに繋がります。また、葬儀や納骨の方法に関して記載しておくことで、希望が明確になり、進めやすくなるなどの効果もあります。
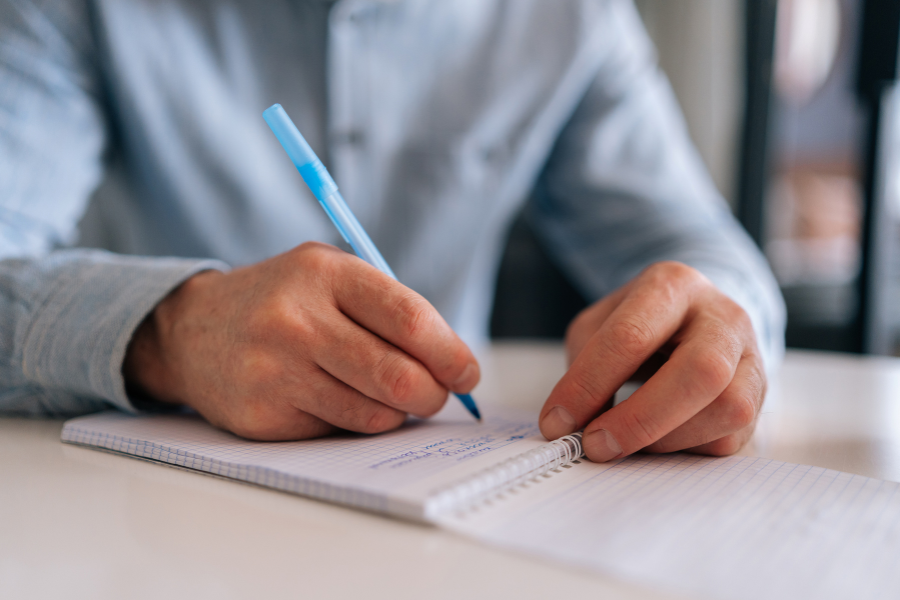
(8) 生前贈与の活用
生前贈与をうまく活用すると、相続税の軽減につながります。例えば、「暦年贈与」を利用すれば、年間110万円まで非課税で贈与が可能です。
なお、相続税には生前贈与加算というルールがあり、2023年末までは死亡前3年以内の贈与に関して、その分は相続財産に加算しなければいけないというものでしたが、2024年1月1日以降の贈与については、対象期間が7年以内に延長されました。
相続対策として、生前贈与を検討される場合は、早めの対策が必須となり、相続財産の規模によっては、あえて贈与税の掛かる年間110万を超える金額を贈与したほうが、相続税の軽減に効果的なケースもあるので、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に早めに相談しましょう。
(9) 家族信託の活用
認知症などで判断能力が低下すると、財産管理が難しくなります。家族信託を活用すれば、財産を信頼できる家族に託し、適切に管理してもらうことができます。
おわりに
相続手続きには、期限が決まっているものが多く、期限を過ぎると不利益を被ることがあります。特に、相続放棄の期限(3ヶ月以内)や相続税の申告期限(10ヶ月以内)には注意が必要です。
また、相続が発生してから慌てないためにも、生前からできる準備を進めておくことが大切です。遺言書の作成や生前贈与、家族信託などを活用することで、相続人の負担を軽減し、スムーズな財産承継が可能になります。
専門家と相談しながら計画的に進めて、大切な財産を適切に管理しましょう。

次回のテーマは、「相続税ってどのくらいかかるの?」です。相続対策というと、相続税の軽減対策をイメージされる方も多いですが、実際に相続税はどれくらい掛かるものなのでしょうか。ご自身の財産と照らし合わせて考えられるようにしていきましょう。
関連リンク:
執筆:

渡邊裕介(わたなべゆうすけ)
(株)N&Bファイナンシャル・コンサルティング 執行役員
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
経歴:
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
2003年慶應義塾大学環境情報学部卒。大学卒業後、飲食の店舗マネージメントに携わる。
社会人生活の中で、自身のおカネの知識のなさを痛感したことをきっかけに2006年FPに転身。個人の貯蓄計画や住宅購入相談・老後資金準備、相続相談などライフプラン作成を中心に、企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。
ファイナンシャルプランニングを通じて、「安心の提供」と「人生の価値向上」に貢献する。
資格・役職:
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
CFP
1級FP技能士
東海大学 非常勤講師
10回にわたって、「相続」と「介護」をテーマに、お金にまつわる知識をお届けします。介護や相続は誰にとっても避けて通れないテーマですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。
このコラムでは、在宅介護にかかる費用の考え方や、相続の基本的な仕組み、そして具体的な準備の進め方を分かりやすく解説します。読んでいただくことで、将来に向けた備えや計画を安心して進めるためのヒントを得ていただければと思います。