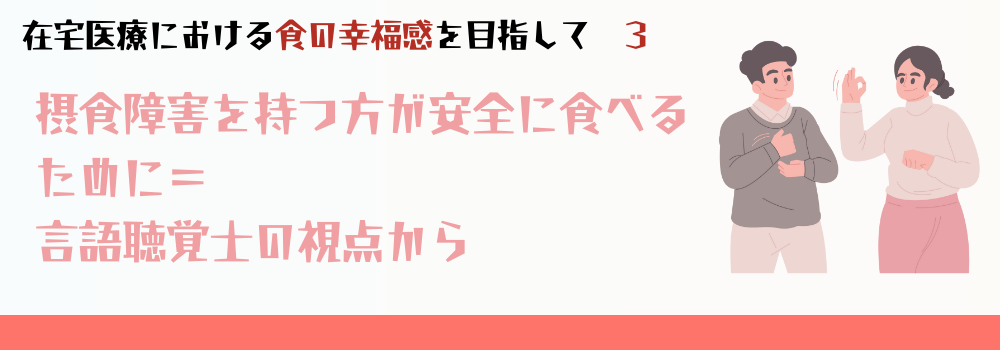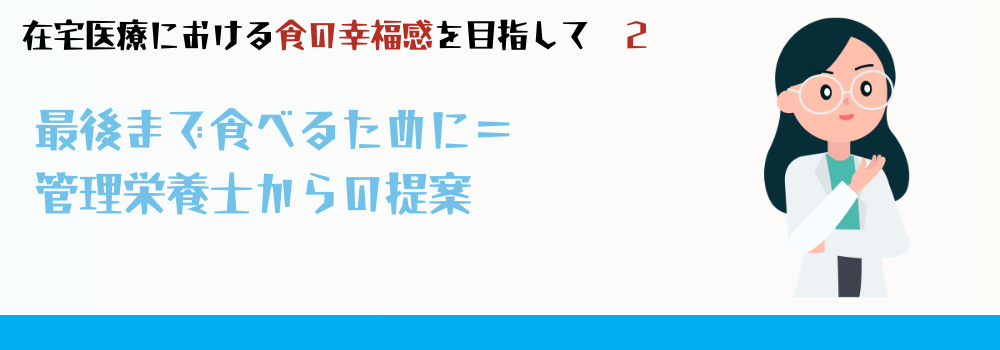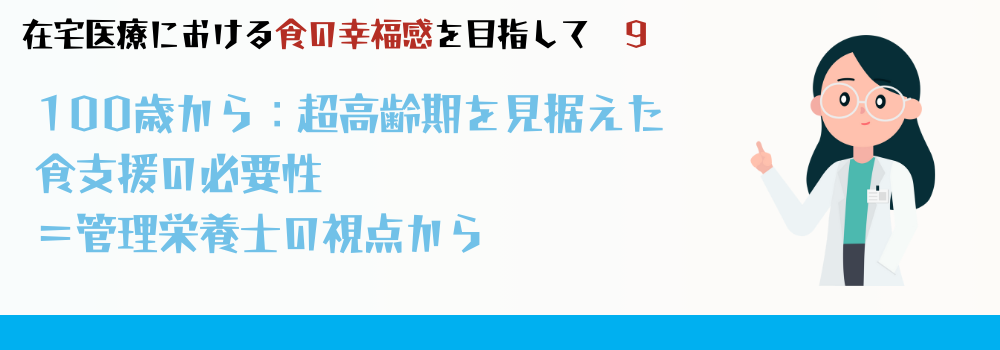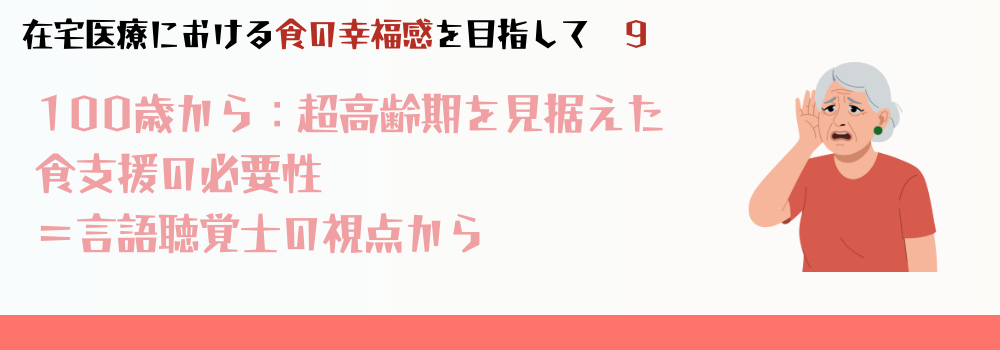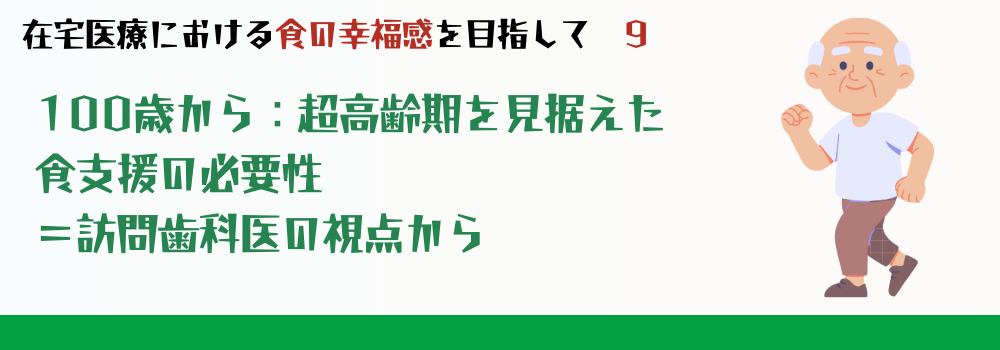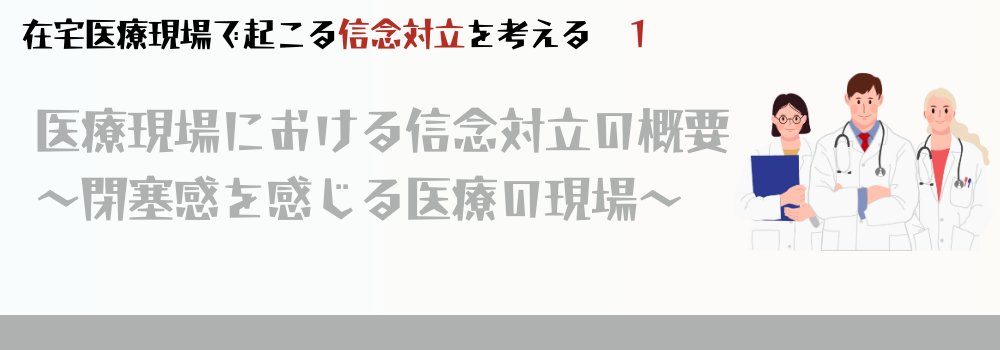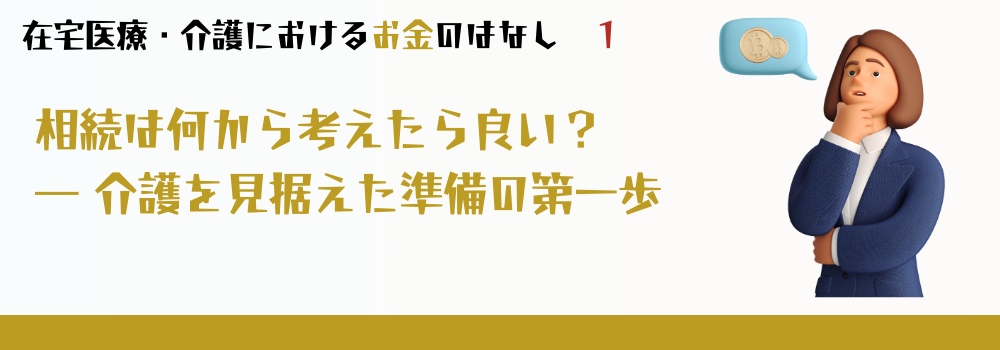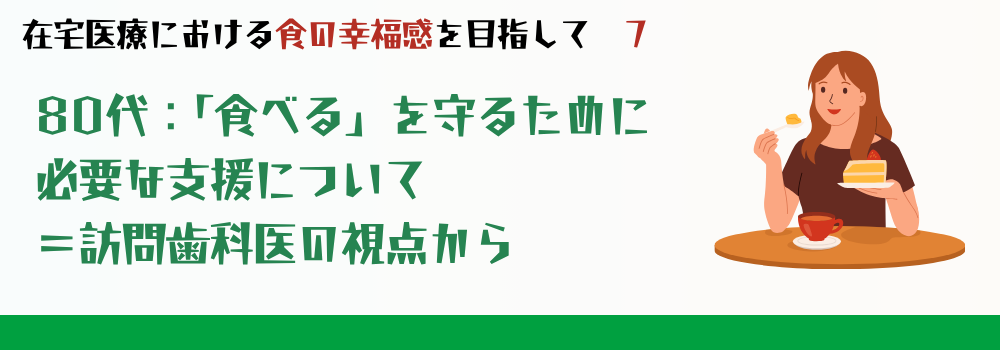摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために=管理栄養士の視点から 最終更新日:2025/03/16

「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
3つ目のテーマは「摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために=管理栄養士の視点から」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
3つ目のテーマは「摂食嚥下障害を持つ方が安全に食べるために=管理栄養士の視点から」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
はじめに
嚥下障害がある方において、誤嚥を起こさずに食事を続けていくことは、療養を続けていく上で重要な課題になっていきます。食べることが困難にならないよう、食形態や食事姿勢、口腔ケア、食事介助の方法など、様々な工夫の仕方があります。嚥下障害が起きてからも適切なケアを行えば、最期まで食事をとることも可能です。

1. 嚥下機能の評価
嚥下障害の状態は人により異なります。まず歯科医師や、言語聴覚士により嚥下機能の評価をしていただきます。どの食事が摂取可能なのかは、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021など(以下:学会分類2021)を用いて多職種間で共有をします。この時、食形態に合わせて、水分のとろみの具合も確認いただきます。嚥下機能に応じて、どの食材、料理、商品がその人にとって適したものなのかを管理栄養士が指導します。この時、学会分類を頼りに指導をしていきますが、すべてがこの通りではなく、人それぞれに、食べられる食材、そうでない食材は違ってきます。学会分類を参考にしながら食べられる食材を確認していきます。
■ 学会分類2021
・嚥下訓練食品0j(ゼリーなど)
・嚥下訓練食品0t(プリン、ムースなど)
・嚥下調整食1j(とろみ付き飲料など)
・嚥下調整食2-1(野菜のピューレ、とろろなど)
・嚥下調整食2-2(パンがゆ、マグロのたたきなど)
・嚥下調整食3(アボカド、温泉卵、スクランブルエッグなど)
・嚥下調整食4(ハンバーグ、カボチャの煮物、皮のとった煮魚など)
■ 学会分類2021(とろみ)
・薄いとろみ(ストローで容易に吸うことができる、スプーンを傾けるとすっと流れ落ちる)
・中間のとろみ(ストローで吸うのは抵抗がある、スプーンを傾けるととろとろと流れる)
・濃いとろみ(ストローで吸うことは困難、スプーンで傾けても、形状がある程度保たれ、流れにくい)

2. 嚥下食
嚥下食においては、食材を選ぶ際にポイントがあります。
・かたいもの、ばらけるもの、張り付くもの、ぱさつくもの、べたつくものを避ける
例:かたいもの ▶ 繊維質の野菜(ごぼう、たけのこ)、ナッツ類など
ばらけるもの ▶ かまぼこ、茹で卵など
張り付くもの ▶ 海苔、わかめ、レタスなど
ぱさつくもの ▶ パン、蒸したイモ類
べたつくもの ▶ 餅など
例:かたいもの ▶ 繊維質の野菜(ごぼう、たけのこ)、ナッツ類など
ばらけるもの ▶ かまぼこ、茹で卵など
張り付くもの ▶ 海苔、わかめ、レタスなど
ぱさつくもの ▶ パン、蒸したイモ類
べたつくもの ▶ 餅など
・野菜の皮は剥く、または厚めに剥く
例:トマト、かぼちゃ、ナスなど
例:トマト、かぼちゃ、ナスなど
・野菜は軟らかくなるまで加熱する
例:葉物野菜、ブロッコリー、カブ、大根、人参など
例:葉物野菜、ブロッコリー、カブ、大根、人参など
・油分を用いてなめらかにし、栄養量をUPさせる
例:マヨネーズやバター、練りごまなど
例:マヨネーズやバター、練りごまなど
・さらさらした水分にはとろみを付ける
・たんぱく質は筋を避け、脂質の多く軟らかいものを選ぶ
・適度に加水をして飲み込みやすくする
また嚥下機能に合わせて、ペースト状やムース状にする必要があり、必要な際にはミキサーを使用します。この時、ペースト状にする場合はとろみ調整食品、ムース状にする場合はゲル化剤などを用いると離水やべたつきを防ぎ物性が安定します。

3. 市販の介護食の使用
嚥下食を手作りすることは、介護をする方への一つのハードルになることがあります。その場合は市販の介護食を用いていただき、どの介護食が適しているのかを管理栄養士が相談に乗ります。
最近はドラックストアでも様々な介護食品が購入可能になっています。また介護食専用の通販などでも購入が可能なため、購入経路の確認も必要です。市販の介護食を使用する場合、ご本人やご家族へは、ユニバーサルデザインフードを用いてご説明することもあります。理由としては市販の介護食にこのユニバーサルデザインフードの記載が多く載っているためです。
嚥下が容易にできる順としては、『かまなくてよい』⇒『舌でつぶせる』⇒『歯茎でつぶせる』⇒『容易に噛める』の順となっています。嚥下状態に応じて、どの段階にするか決定をしていきます。
4. 栄養補助食品の利用
嚥下障害がある方にとって課題なのが十分な栄養量の確保です。理由としてはペースト状などにする際、なめらかにするために加水が必要であり、全体の食事量が増えてしまうこと、そのために一食分の食事をとることが難しいことがあげられます。
そのため、栄養量が確保できない場合は栄養補助食品や栄養剤を使用することも必要となります。栄養量の確保を行うことが低栄養を防ぐことにつながります。
4-1 食事に添加するもの
・MCTオイル
小匙1杯からお粥などに混ぜて摂取。吸収の速い脂質のため、エネルギー源に使われる 小匙1杯(4.6g)=41.4kcal
小匙1杯からお粥などに混ぜて摂取。吸収の速い脂質のため、エネルギー源に使われる 小匙1杯(4.6g)=41.4kcal
・プロテインパウダー
副食などに混ぜて摂取 メーカーにより栄養量は様々、たんぱく質の補給に使われる
副食などに混ぜて摂取 メーカーにより栄養量は様々、たんぱく質の補給に使われる
・粉飴
炭水化物の摂取に使用。お粥やデザート類に混ぜて使用、砂糖の1/5の甘さのため、炭水化物の補給に使われる 13g=50kcal
炭水化物の摂取に使用。お粥やデザート類に混ぜて使用、砂糖の1/5の甘さのため、炭水化物の補給に使われる 13g=50kcal

4-2 デザートなどで補給するもの
ゼリータイプや、クラッシュゼリーのタイプ、アイスやヨーグルト状のものなど様々なタイプがあります。嚥下機能の状態に合わせて選びます。間食の代わりに摂取したり、食後のデザートにします。
4-3 ドリンクタイプで摂取するもの
とろみがついたドリンクタイプの栄養補助食品や、とろみがついていない栄養補助食品、栄養剤があります。ドリンクタイプの栄養補助食品、栄養剤にとろみをつける際には、通常のとろみ剤ではとろみがつきにくいため、栄養補助食品、栄養剤専用のとろみ剤を用いてとろみをつけます。
4-4 副食の代わりに摂取するもの
甘いものが苦手な方へは、しょっぱい味付けの栄養補助食品もあります。こちらは副食の一品として摂取をおすすめします。
5. エネルギー量確保のために食事回数の工夫
一度で食事量が多く摂れない方には、食事回数を増やす方法があります。
三食の他に間食(10時・15時)を取り入れたり、エネルギーの多い飲み物などを飲んだりすることもおすすめです。
三食の他に間食(10時・15時)を取り入れたり、エネルギーの多い飲み物などを飲んだりすることもおすすめです。
結論
嚥下障害の方において、誤嚥を起こさないことは重要な課題ですが、それだけではなく、誤嚥を起こさずに栄養量が確保できる食事をすることが重要です。また、嚥下食においても食の楽しみ、幸福感を大切にした食事を続けられるようなケアが必要となります。
関連リンク:
執筆:

井上美穂(いのうえみほ)
ふれあい歯科ごとう 管理栄養士
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-11-13せらび新宿1階
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
介護や医療イベントにて食事の大切さを伝えるキッチンカーを運営中
『食の相談室おむすび』
『食の相談室おむすび』