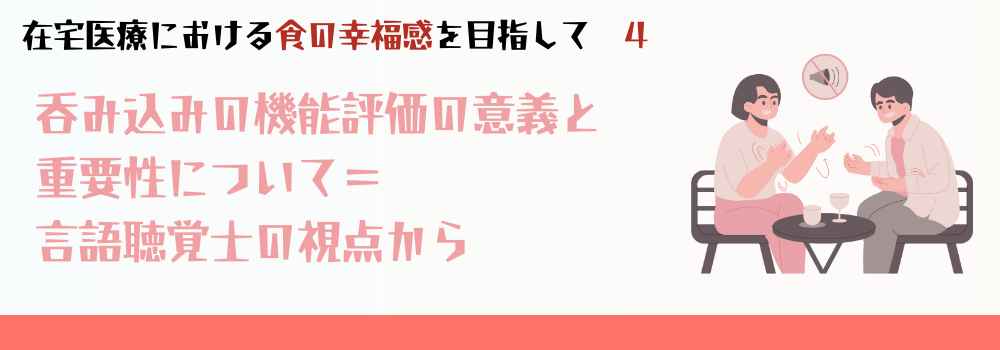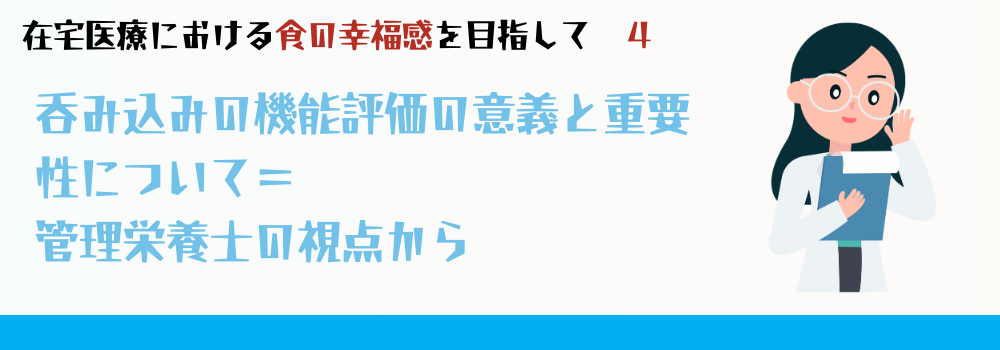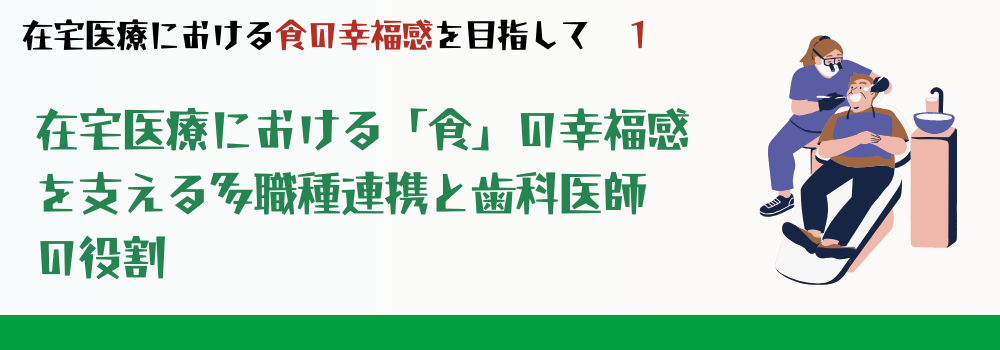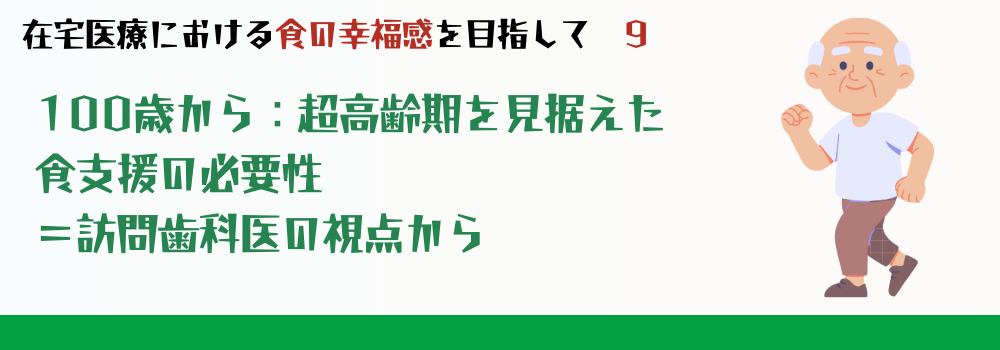嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について=訪問歯科医の視点から 最終更新日:2025/04/29
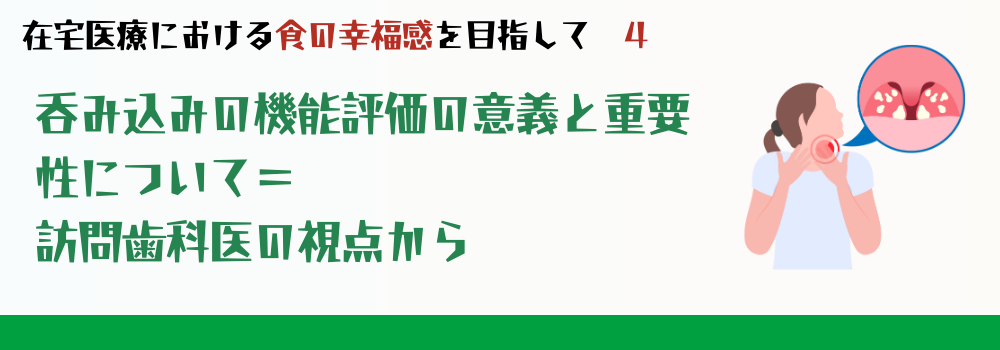
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
4つ目のテーマとして「嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
4つ目のテーマとして「嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について」と題して、歯科医の立場として、澁谷英介先生(澁谷歯科医院院長)により解説いただきました。
はじめに
嚥下機能評価を行うという説明があると患者や家族は「呑み込みの検査なんかしてしまったらその結果がもし悪かったら今後一生口から食べられなくなってしまう」と思い込み、検査やその後のリハビリまでも拒否してしまう場合があります。
今回は「嚥下機能評価は安全に食べるために注意すべきことをみんなで探す。」という大前提を確認するとともにどのように嚥下評価を行っていくかを説明しようと思います。

嚥下機能評価について
嚥下機能評価は、高齢者や障害を持つ患者に対して、口腔機能と栄養摂取、さらには生命予後に深く関わる重要な医療行為である。特に訪問診療の現場では、患者の生活の質(QOL)を支えるうえで、嚥下障害への早期発見・早期対応が求められる。
嚥下機能が低下した状態をそのままにしておくと、広義の誤嚥性肺炎や低栄養状態、水分摂取量の低下による脱水、食事中の窒息といった深刻な事態を引き起こしやすく、最終的にはADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の低下や寝たきりの原因にもなり得る。
嚥下機能評価の意義
嚥下機能評価の意義は、大きく3つに分類できる。
第一に、誤嚥や窒息などのリスクを回避するための「安全確保」である。
第二に、口から食べるという人間らしい営みを支える「生活の質の向上」である。
そして第三に、嚥下障害に対するリハビリテーションや栄養支援といった「介入の方針の決定」となる点である。
第二に、口から食べるという人間らしい営みを支える「生活の質の向上」である。
そして第三に、嚥下障害に対するリハビリテーションや栄養支援といった「介入の方針の決定」となる点である。
嚥下障害は、加齢だけでなく、脳血管障害、神経変性疾患、悪性腫瘍、外科的処置などさまざまな要因で引き起こされるため、評価には多面的な視点が不可欠である。
具体的な嚥下機能評価法
具体的な嚥下機能評価法には、大きく分けて
「問診・視診・触診などの観察的評価」と、
「嚥下造影検査(VF)」「嚥下内視鏡検査(VE)」といった機器を用いた評価がある。
「問診・視診・触診などの観察的評価」と、
「嚥下造影検査(VF)」「嚥下内視鏡検査(VE)」といった機器を用いた評価がある。
訪問診療の場では、機器を用いた検査が制限されることが多いため、まずはスクリーニングを主とした観察的評価から始め、必要に応じて侵襲的な検査法を取り入れ、総合的に判断することが多い。
問診
まず初めの基本となるのは充分な問診である。既往歴特に脳血管障害、進行性の神経難病、認知症など全身状態の把握、それに応じた服薬歴の聴取、食事の形態、摂食にかかる時間、ムセや咳込みの有無、体重の変化、声の変化などについて、本人および介護者から丁寧に聴取する。
また、嚥下障害を訴えていない場合でも、介護者の「食べるのが遅くなった」「飲み込みづらそう」「口に食べ物が残っている」などの主観的な観察記録にも注意を払う必要がある。
視診と触診
次に視診と触診である。着座姿勢、安静時の表情、口のたたずまい、舌や口唇の運動、歯牙の有無ならびに咬合状態、義歯の適合などを観察する。咀嚼や嚥下に関わる筋肉群(口底部の顎舌骨筋、頸部の胸鎖乳突筋など)の緊張度や、喉頭の相対的位置・可動性、甲状軟骨の挙上の有無を触診も併せて確認する。また、発声(パタカラ発音)、舌圧のチェック、反復唾液嚥下テスト(RSST)、改訂水飲みテスト(MWST)、フードテストなど、簡便かつ信頼性のあるスクリーニング検査も行う。
これらの項目は再現性があるため、経時的にその後何度も行い比較することもまた重要である。
これらの項目は再現性があるため、経時的にその後何度も行い比較することもまた重要である。
特にRSSTは、30秒間に何回唾液嚥下ができるかを測定するテストであり、2回以下の場合は嚥下障害が疑われる。またMWSTは、3mlの水を口腔に含ませて飲んでもらい、むせや湿性嗄声の有無、嚥下のタイミングを評価する方法である。フードテストは、プリンやゼリーなどの食品を使って嚥下を観察し、より食事に近い状況での安全性を確認するのに役立つ。これらの簡便な検査も組み合わせることで、訪問先でも一定の精度をもって嚥下機能を評価できる。
さらに、頸部聴診(頸部に聴診器を当てて嚥下音を確認する)や、咳嗽反射の有無、呼吸状態の観察も重要である。嚥下と呼吸は密接に関連しており、嚥下後の呼気の有無は誤嚥の危険性を推察するうえで大きな手がかりとなる。嚥下聴診は嚥下音のみを聴取してむせているかどうかを判別するのではなく、前後の呼吸音の変化を観察することで、外表からであっても咽頭内部の動態を類推することが可能になる。
嚥下造影検査(VF)・嚥下内視鏡検査(VE)
これらの結果からVFやVEといった機器検査が必要であると判断された場合は患者に負担を強いる検査であることを十分説明し、それを行うことでどのような結果が得られ、さらにどのような支援が可能になるのかまでを事前に説明しておかなければ歯科医師自身が検査をする場合も高次医療機関に紹介する際にも必要である。

嚥下機能評価での注意点
嚥下機能評価において、特に注意すべき点は次のように整理される。
第一に、評価時の「姿勢の確保」である。頭部前屈位(頸部屈曲位)を基本とし、座位が取れない場合には半座位や側臥位などを用いて、誤嚥リスクを最小限にする姿勢を工夫する。
第二に、評価に使用する「食品や液体の選択」である。とろみ水、プリン、ゼリー、きざみ食、常食など、形態ごとに嚥下動態が異なるため、無理のない範囲で段階的に使用しながら評価を行う必要がある。特に液体は誤嚥のリスクが高いため、必ず注意深く行うこと。
第三に、「たとえ評価のためとは言え負荷をかけない」ことである。焦って評価を進めることで誤嚥を誘発してしまっては本末転倒であるため、患者の体調や意欲を見ながら、無理のないスピードで段階的に行うことが肝要である。
第一に、評価時の「姿勢の確保」である。頭部前屈位(頸部屈曲位)を基本とし、座位が取れない場合には半座位や側臥位などを用いて、誤嚥リスクを最小限にする姿勢を工夫する。
第二に、評価に使用する「食品や液体の選択」である。とろみ水、プリン、ゼリー、きざみ食、常食など、形態ごとに嚥下動態が異なるため、無理のない範囲で段階的に使用しながら評価を行う必要がある。特に液体は誤嚥のリスクが高いため、必ず注意深く行うこと。
第三に、「たとえ評価のためとは言え負荷をかけない」ことである。焦って評価を進めることで誤嚥を誘発してしまっては本末転倒であるため、患者の体調や意欲を見ながら、無理のないスピードで段階的に行うことが肝要である。
また、嚥下機能は一過性に変化することがある点にも注意したい。たとえば体調不良時や薬剤の影響による覚醒不良、脱水、疲労、環境の変化によって一時的に機能が低下することがあり、1回の評価だけで「この人はもう口から食べられない」と判断するのは危険である。定期的な再評価と、日内変動を含めた観察が求められる。日内変動については一例を補足すると、神経難病の方でドーパミン製剤を一日に複数回服用している方などは服薬のタイミングとその後身体が動き始めるまでのラグが生じることがある。
さらに、評価結果を記録し、他職種(看護師、管理栄養士、介護職、ケアマネジャーなど)と共有することが極めて重要である。訪問診療においては、多職種との連携が患者の生活を支える基盤となるため、評価の所見だけでなく、「どのような食形態で、どのような姿勢・方法であれば安全に摂取可能か」「今後の訓練方針」なども明記するとよい。
患者本人の意思は最大限に尊重されるべきである。「口から食べたい」「最後まで好きなものを食べたい」という思いがある場合には、それに応えるための方策をチームで模索する必要がある。もちろん最優先すべき安全性とのバランスは必要であるが、「絶対に誤嚥させない」ことが目的ではなく、「なるべく安全に、できるだけ楽しく、食事を続ける」ことを目指す支援していく視点が大切である。
最後に
嚥下機能評価は単なる診断技術ではなく、患者のみならず介護する家族、サポートするスタッフまで支援する重要な医療行為である。評価の積み重ねは、そのまま「食支援」の土台となり、患者とその家族の安心につながる。訪問歯科医師としては、単に依頼されたスクリーニングや内視鏡検査を行うのではなく、食事支援の可能性を広げる視点を持ち、常に柔軟な対応と多職種連携の一員であることを意識することが求められる。

関連リンク:
執筆: