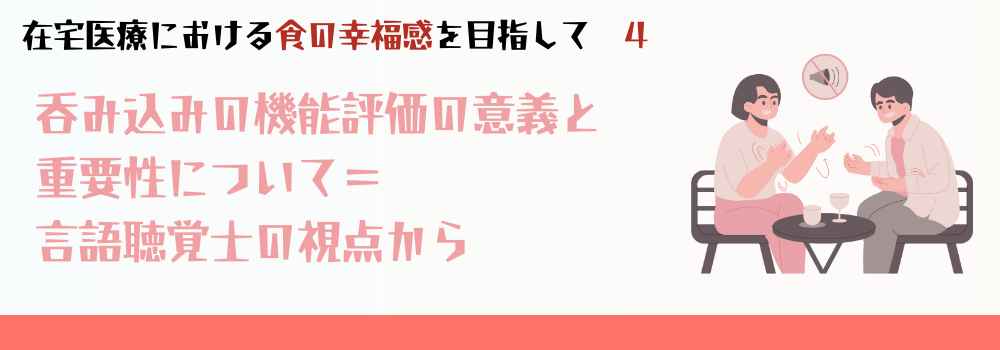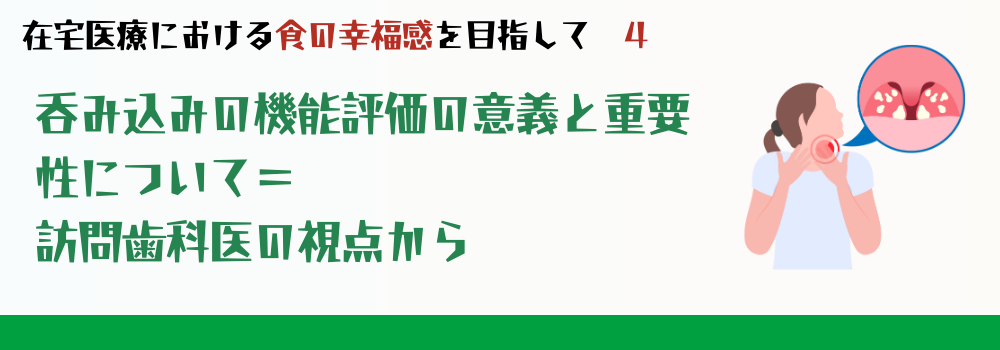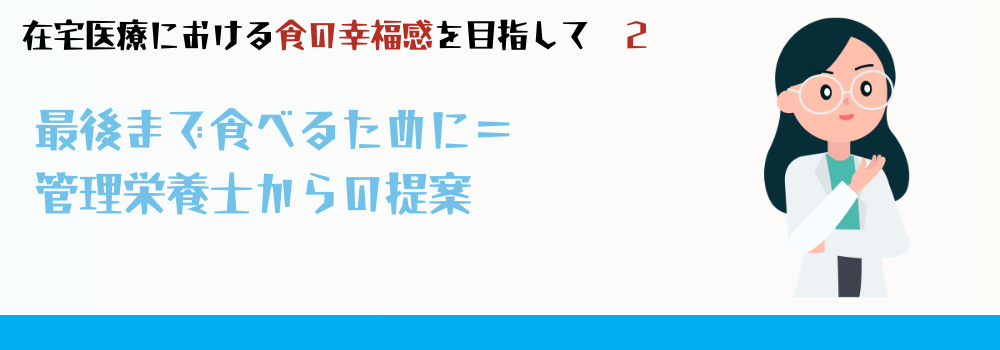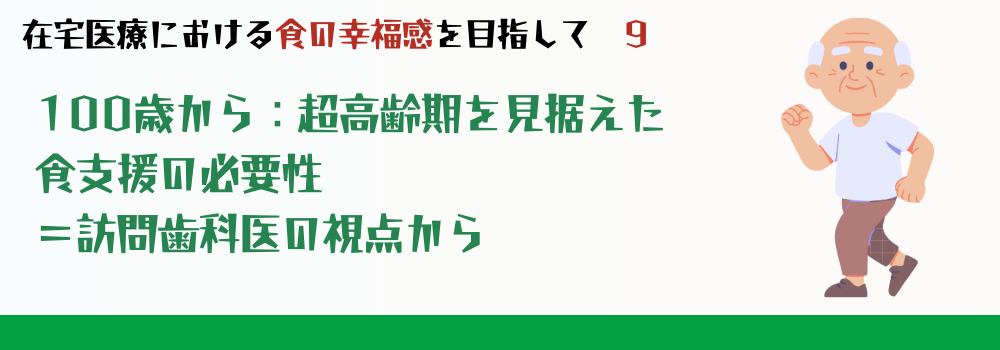嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について=管理栄養士の視点から 最終更新日:2025/04/29
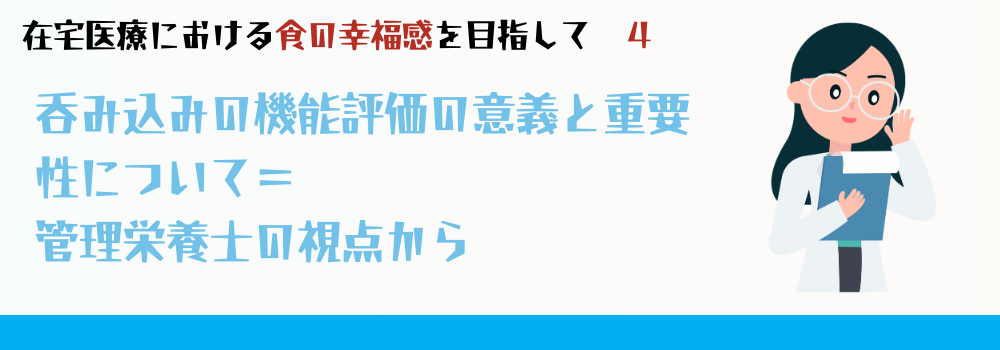
「食」での幸福感の実現、訪問歯科・口腔ケアの普及啓蒙を目的として、1つのテーマに対して、歯科医、管理栄養士、言語聴覚士がそれぞれの立場にて解説する新たな企画「在宅医療における食の幸福感を目指して」。
4つ目のテーマは「嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について=管理栄養士の視点から」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
4つ目のテーマは「嚥下(呑み込み)機能評価の意義と重要性について=管理栄養士の視点から」と題して、管理栄養士の立場として、井上美穂管理栄養士(ふれあい歯科ごとう)により解説いただきました。
はじめに
嚥下機能障害がある方が食事をすることにおいて最初のステップとなるのが嚥下機能評価となります。安全な食形態で食事を行うことは、誤嚥性肺炎や窒息の予防だけでなく、必要栄養量の確保、そして「食べる」ことを叶え、QOLを維持・向上させる役割を持っています。
1. 嚥下機能評価の目的
栄養ケアにおける嚥下機能評価を行う目的は以下の通りです。
①安全な食形態の提案
嚥下機能に応じた食形態を提供することで、誤嚥や窒息のリスクを軽減します。安全な食形態が選択できると、実際の食事内容の具体的な提案や、調理方法の提案を行うことができます。
②栄養状態の改善
適切な食形態を選択することで、食事摂取量を改善し、低栄養状態の予防、改善を行います。食形態が曖昧なままだと、食べるものが偏り、栄養素のバランスが偏りやすくなります。結果的に低栄養状態や体重減少を起こすことにも繋がります。
③QOLの維持・向上
「食べる」ことを叶え患者の食事に対する意識を向上させ、心身の健康を支援します。また家族にとっても「食べる」ことを叶えることは重要な役割を持っています。
このような目的から嚥下機能評価は栄養ケアにおいて栄養改善のために必要なプロセスだと言えます。
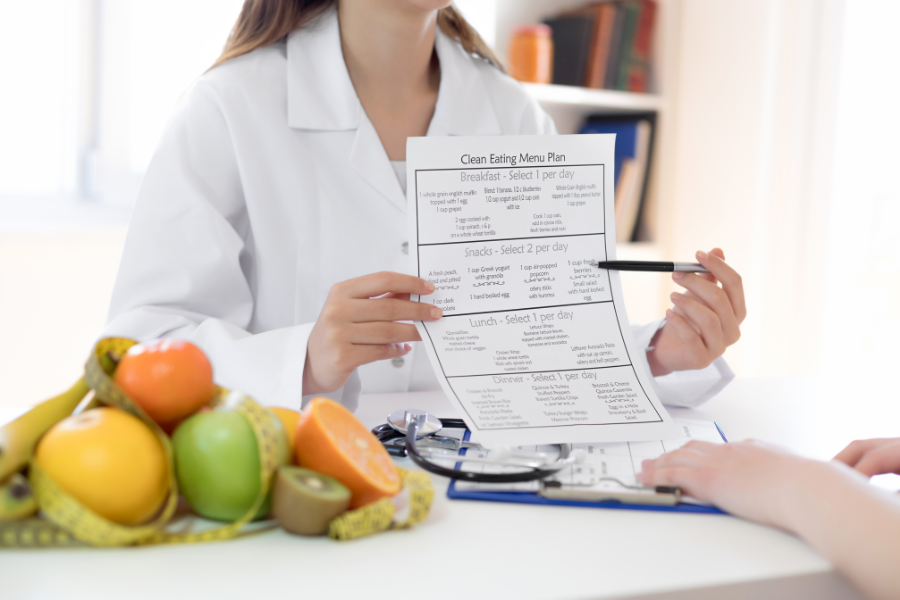
2. 嚥下造影検査(VF)・嚥下内視鏡検査(VE) の際に管理栄養士ができること
実際に検査には携わることは少ないものの、管理栄養士の視点での事前の情報共有は可能だと考えています。日常の食事内容や、摂取栄養量、充足率、姿勢や食事スピードなどをまとめて情報提供を行い、嚥下機能評価の前に共有をするようにしています。特に診ていただきたいポイントなどを添えると、評価後の栄養指導の内容にも反映がしやすいと言えるでしょう。また評価の場面に実際に同行すると、より情報提供をスムーズに行うことができます。
3. 嚥下機能評価による理解促進
嚥下機能評価は患者やその家族、介護者、またケアに関わる多職種にも嚥下障害や適切な食形態について理解することに繋がります。評価の結果を通じて内容を説明することで自宅での食事提供がスムーズになります。また患者やその家族、介護者の不安を軽減することにも繋がります。
また自宅だけではなく、デイサービスなどの通所介護の際にも嚥下機能評価の結果が重要視されます。施設での食形態や水分のとろみ具合が自宅と異なる場合、どちらかにおいて誤嚥を起こすことがあります。同じ食形態のものがどの場面でも提供できるよう結果の共有を行うことが大切です。
4. 嚥下機能評価の結果と管理栄養士が持つべき視点
嚥下機能評価は、主に歯科医師や言語聴覚士が行い、管理栄養士はその結果を共有いただき指導内容に反映させていきます。評価内容はその日、その場所での評価の内容となるため、日常の嚥下状態を確認していく必要があります。特に管理栄養士は食事時間に訪問をすることが多いため、下記のような状態を食事の際に確認するようにしています。
・頸部聴診にて嚥下音や呼吸の確認
・咳込みの有無
・食後の声の変化
・食事中の疲労感
・摂取スピード
・食事介助の有無、スピード など
このように日常的な食事場面から読み取れる情報は多くあります。訪問栄養指導の際に、患者の食べる様子を実際に見ることができるのは、管理栄養士ならではの強みだと考えています。この強みを活かして、日々の実際の嚥下状態を多職種に共有することが重要です。

5. 嚥下機能について多職種連携の意義
嚥下機能の内容を共有しておくことは、患者のケアの方向性を一本化することにも繋がります。主治医やケアマネージャーはもちろん、歯科医師、言語聴覚士、看護師、ヘルパー、そして管理栄養士が同じ認識を持って患者に接することで機能の低下が起きた際にもいち早く気が付くことができます。また逆に嚥下機能評価で評価された食形態ではない食事をすることを防ぐことにも繋がります。
実際に患者家族が食べさせたいという思いで食形態と違ったものを提供してしまい、誤嚥を起こしたという場面に遭遇したことがあります。どの場面でそういったことが起こるかは予想ができないため、共通の認識を持っておくことが重要です。
また嚥下機能障害といっても、すべての方がミキサー食、というわけではなく、ムース食が摂取可能な方、形があっても軟らかければ食べられる方、あんかけがかかっていれば食べられる方、など状況は様々です。共通認識として食形態を把握するためには、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021を理解しておくことも必要だと言えます。
■学会分類2021
・嚥下訓練食品0j(ゼリーなど)
・嚥下訓練食品0t(プリン、ムースなど)
・嚥下調整食1j(とろみ付き飲料など)
・嚥下調整食2-1(野菜のピューレ、とろろなど)
・嚥下調整食2-2(パンがゆ、マグロのたたきなど)
・嚥下調整食3(アボカド、温泉卵、スクランブルエッグなど)
・嚥下調整食4(ハンバーグ、カボチャの煮物、皮のとった煮魚など)
■学会分類2021(とろみ)
・薄いとろみ(ストローで容易に吸うことができる、スプーンを傾けるとすっと流れ落ちる)
・中間のとろみ(ストローで吸うのは抵抗がある、スプーンを傾けるととろとろと流れる)
・濃いとろみ(ストローで吸うことは困難、スプーンで傾けても、形状がある程度保たれ、流れにくい)

終わりに
嚥下機能評価は安全な食事を摂るためだけではなく、栄養状態の改善や、患者、その家族、介護者の不安感の軽減、QOLの向上、多職種での共通認識を持つことにも繋がります。患者が自分らしく自宅で過ごすために、「食べる」を叶えることは、私たち管理栄養士が大切にすべき視点の一つです。
嚥下機能評価を適切に行うことで、患者個々の嚥下状態を把握し、最善のケアを提供する基盤が築かれます。評価結果を活用し、患者一人ひとりの嚥下状態、そしてライフスタイルに合わせたケアを提供し続けることが大切です。
関連リンク:
執筆:

井上美穂(いのうえみほ)
ふれあい歯科ごとう 管理栄養士
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-11-13せらび新宿1階
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
TEL:03-5338-8817/FAX:03-5338-8837
介護や医療イベントにて食事の大切さを伝えるキッチンカーを運営中
『食の相談室おむすび』
『食の相談室おむすび』